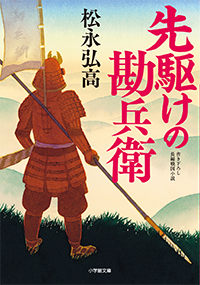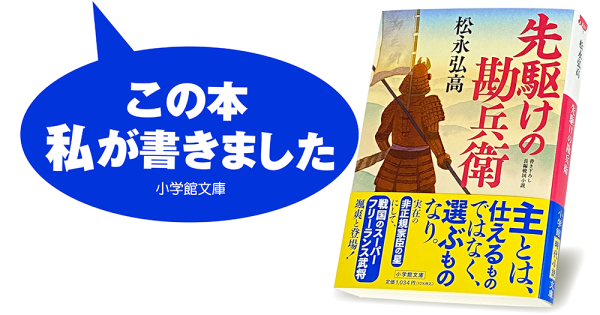松永弘高『先駆けの勘兵衛』
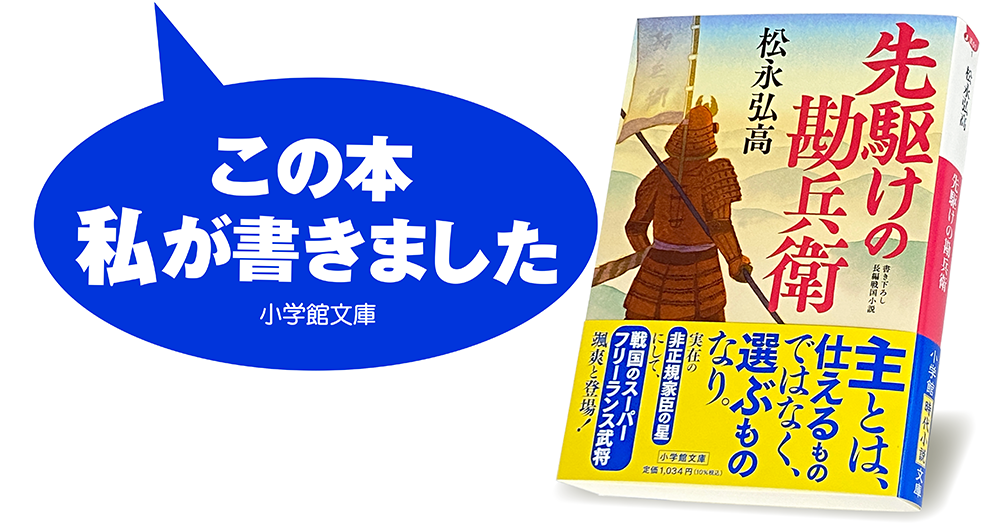
七度主君を変えねば、武士とは言えぬ
表題のフレーズをご存じだろうか?
戦国武将藤堂高虎のことばとして流布されてきた。実際には、高虎が言ったことばではないらしい。
高虎は、生涯で10人以上の主君に仕え、その間に大名に成り上がった。豊臣秀吉の没後、徳川家康の信頼を得て、天下人の側近として重きをなす。続く秀忠、家光、ふたりの将軍の時代にも大きな存在感を示し、世を去った。
いかにも、こんなことを言いそうな人物ととらえられてきたわけだ。
戦国時代末期、手柄を上げ、己の「市場価値」を高め、好待遇を示す主君のもとを渡り歩く武士たちがいた。高虎はそういう生き方をした武士の典型とされる。
その高虎を5人目の主君とし、武功を上げ、藤堂家を去った男がいる。
『先駆けの勘兵衛』の主人公、渡辺勘兵衛だ。
ふたりには共通点が多い。同郷の人でもある。琵琶湖の畔に生をうけた。
「湖?海でしょ!」
大津の遊覧船乗り場から、初めて琵琶湖を眺めた私の感想だ。
大津からだと、西岸の南端から琵琶湖を見ることになる。北岸の方角には水平線があるばかりだ。離島で生まれ、太平洋の水平線を眺めて育った私ですら、その広さに脱帽した。
――この「海」を囲む土地にはどんな暮らしがあるか?
海に囲まれて育った私は、そこに興味を持った。本作の出発点と言っていいだろう。
琵琶湖を取り巻く地域は、かつて近江国と呼ばれた。滋賀県がそれに相当する。
戦国時代においては、浅井氏三代、京極高次・高知兄弟、石田三成、増田長盛、茶々・初・江の浅井三姉妹など、織田信長から秀吉を経て、家康に至る天下統一の流れに関わる人物を多く輩出した。
西に京の都が位置し、琵琶湖を抱える近江は物流の中心、水運の国だった。
琵琶湖の水面には、日本海沿岸各地、北陸、東国から京へ向かう荷を乗せた船が多く行きかっていただろう。京からの荷を乗せた船も同様だったはずだ。
京を制し、天下に号令せんとする者は、近江を制し、琵琶湖の物流を守らなければならない。信長が安土城を築き、琵琶湖を取り巻くように重臣たちの居城を配置したのは、近江の重要性を理解していたからだろう。
近江出身の人々はおのずと天下統一の流れに巻き込まれていく。勘兵衛、高虎もこの流れのなかで輝いた。
『先駆けの勘兵衛』は、この騒がしい国に生まれた青年、勘兵衛が時代の激流に飛び込み、揉まれ、やがて自力で泳ぎ出すまでを描いている。
是非、手に取って頂き、物語の世界に飛び込んで頂きたい!
松永弘高(まつなが・ひろたか)
1976年、東京都生まれ。明治大学卒業。2014年「泰平に蠢く」(刊行時に『決戦! 熊本城 肥後加藤家改易始末』と改題)が、第6回朝日時代小説大賞優秀作となる。著作に『戦旗 大坂の陣 最後の二日間』『奥羽関ヶ原 政宗の謀、兼続の知、義光の勇』『決戦! 広島城 天下大乱の火種を消すべし』などがある。