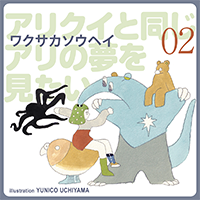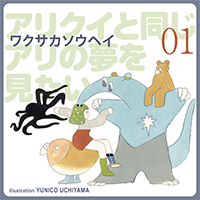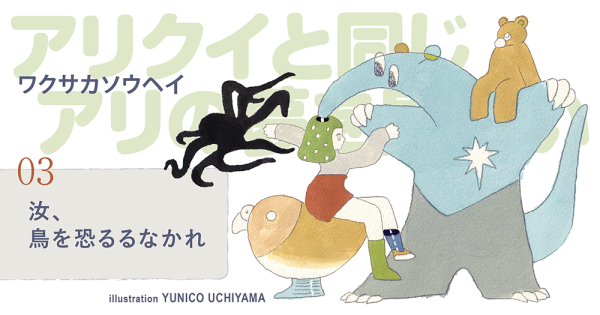ワクサカソウヘイ「アリクイと同じアリの夢を見たい」#03
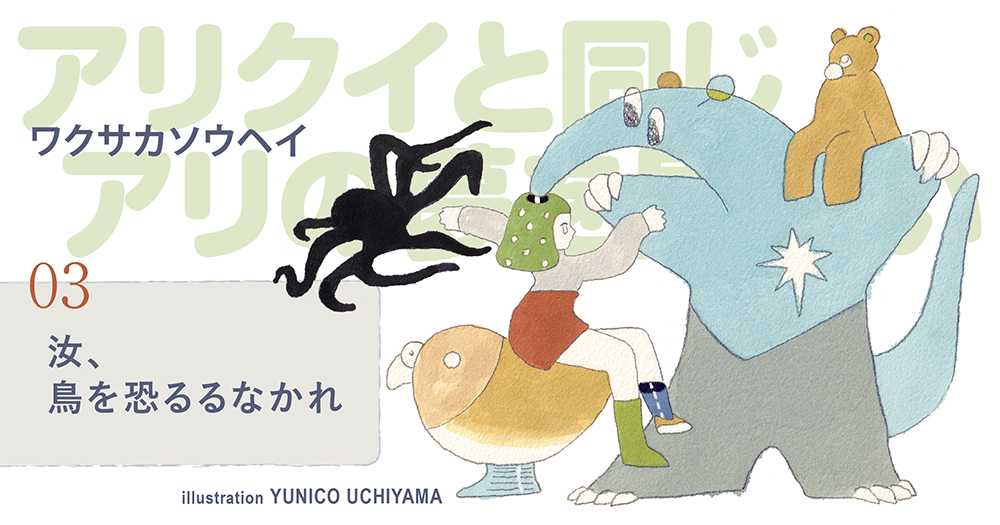
03 汝、鳥を恐るるなかれ
鳥とはいつか、和解しなければならない。
そんな課題が、常に纏わりついていた。
私は、鳥が怖かった。
不意に出会う恐怖。それは生きているかぎり、避けては通れないイベントである。
留守録に残っていた、非通知の無言電話。
夜中のアパートに響く、隣人の奇声。
満員電車、背後から聞こえてきた不穏な舌打ち。
どこに地雷があるのかわからない、威圧的な職場の上司。
話が通じない。コミュニケーションが成立しない。そうした自分とは違う「心」は突如として目の前に現れる。そして気の弱い私はすぐさまそれを恐怖に変換し、全身のセンサーを警戒モードへと切り替えて、そこに漂う不協和音から一目散に逃避する。
非通知の無言電話の記録は削除して、なかったことに。
更新月を待たずして、物騒なアパートからクイックで引っ越し。
舌打ちが聞こえたら、次の駅にて猛然と下車。
理不尽な上司と対峙することもせずに、職場からすみやかに離脱。
危機的な状況に対する処理として、逃げるという行為は確実に機能する。これまで私は恐怖に直面したら、逃げて逃げて、とにかく逃げて、なんとかここまで生きさらばえてきた。
しかし、逃避の有効性というのは、そう長く続くものではなかったりもする。
背中を向けて、一心不乱にそこから足を遠ざける。ようやく安心の場所に辿り着き、一息を吐く。そして、しばらくしてから、ハッと気がつく。
恐怖はこちらの背中を追って、いまだにぬめぬめとした視線を遠くから送ってきているのだということに。
それと目を合わせないようにしながら未来を手繰っていくというのは、なかなかにライフゲージを消耗するものだ。
悪夢めいた思い出しかない、かつての勤務先。その近くの路を歩かなければならない場面と遭遇すると、いまでも私の胸はざわざわと騒ぎ、緊張が走る。あの上司が、退職届も提出せずに逃げ去った私のことを、この街のどこかからじっと睨んでいるのではないか。そんな疑心暗鬼の念が泡立ち、うっすらとした居心地の悪さを味わう。遠くに置き去りにしたはずの恐怖は、恐怖のままに保存されていて、いつまでもこちらの足を引っ張ってくる。
当たり前だが、調子よく生きたいのであれば、恐れをこちらに抱かせるような存在との出会いは少ないほうがいい。
鳥に大いなる恐怖を抱くきっかけができたのは、小学三年生の時だ。
近所の神社で縁日が開催され、お小遣いを握りしめて同級生たちと鳥居をくぐった。
綿あめ、タコ焼き、射的、金魚すくい、りんご飴。そこには華やかで艶やかな祭りの景色が広がっている。なにを買おうか、なにを食べようか。仲間たちと相談しながら境内をウロウロしていると、一角にある物珍しい屋台が目に入った。
「ヒヨコ二百円」
そんなベニヤ板の看板に近づいてみると、そこには箱の中でピヨピヨといじらしい鳴き声を重唱する黄色いヒヨコたちの姿があった。私たちはその生まれたばかりの雛鳥の無垢なる可愛らしさに見惚れ、ため息を吐いた。そして「買います」「僕も」「私も」と、そこにいた全員が百円玉二枚を差し出し、それをヒヨコと交換した。
私の手の中に収まった小さな羽毛玉は、かよわい体温を宿していた。
一生かけてこの子を守ろうと決意し、帰宅する。軽薄に命をテイクアウトして戻って来た私に対して、両親はうんざりとした表情を浮かべ、小言をいくつか漏らしたが、「しっかり自分で世話をするんだよ」と最後は段ボールで飼育箱をしつらえてくれた。
私はそのヒヨコに「ピッピ」と名前を付け、慈愛を注ぎ込んだ。毎朝毎晩、餌を与え、水を替え、飼育箱を掃除する。私のことを純真に見つめてくるピッピ。ああ、なんと抱きしめたくなるような存在なのか。
しかし、ヒヨコが醸す可愛らしさというのは、初回ログインボーナスのようなものである。
ピッピは、あれよあれよという間に、ヒヨコの姿を脱ぎ捨てていった。頭上に鶏冠を生やし始め、体軀は筋肉質なものとなり、鋭い爪を脚にそなえ、数か月も経つと立派なニワトリへと成長を遂げてしまった。そして夜明けのたびに、「ピッピ」の名残など微塵も感じさせない、しゃがれた鳴き声を天に向かって上げるようになっていた。
私は、狼狽えた。ここにいるニワトリは、どんぐりのような眼を浮かべていた、あのピッピなのか。その目つきは、この世のすべてをえぐるような鋭さである。屈強な脚で飼育箱から飛び出し、ナイフのごとき嘴でリビングの障子紙を突いては破る。この暴れる生き物を、一体どのように世話したらいいというのか。家族で途方に暮れ、父親が仕方なしに狭い庭に日曜大工で飼育小屋を設置してくれた。
動揺していたのは、我が家だけではない。近所の同級生たちも、あの縁日でヒヨコを購入していたのだ。猛々しい成長を果たしたニワトリたちが、町内一帯に現れていた。
まず早朝の四時に私の家のピッピが口開けの鳴き叫びを近隣に轟かせる。その五分後には大武くんの家のニワトリが鳴き、さらにその五分後には多田さんの家のニワトリが鳴き、辻くんの家のニワトリも、小宮さんの家のニワトリも、永末くんの家のニワトリも、朝日の昇りきらない薄闇の空を切り裂くような甲高い声を続いて一斉に上げる。誰も止めることのできない、地獄のスヌーズ機能である。
気づけば我が町内は、ニワトリの鳴き声に侵食されていた。ヒッチコックのサスペンス映画『鳥』にも似た、おぞましい光景だ。同級生たちは、誰もがげっそりとした表情を浮かべるようになっていた。
それでも私は、ピッピの世話を毎日務めた。
小屋の窓を開け、さっと餌と水を入れ替える。その作業を急いでやらなければならないのは、隙あらばピッピはこちらの手の甲を突いてくるからだ。私はもう何度も、嘴によって傷を負わされていた。
緊張するのは、小屋掃除のタイミングである。抜け落ちた羽毛や食べこぼしなどを定期的に取り除いてやらなければならないわけだが、その瞬間はどうしても密室の中でピッピとふたりきりの状況になる。
箒を手に、ピッピに背中を向けながら、目を合わさないように清掃作業をする。ピッピは「コッ、コッ、コッ……」と苛立っているような呟きを漏らしながら、こちらの様子を窺っている。一触即発のムードが、そこには張りつめている。
ある日の清掃作業の時のことだ。箒を手から滑らせ、それを拾い上げようとしたら、あろうことかピッピと目を合わせてしまった。
しまった、と思う間すらなく。ピッピは逞しい両脚で地面を蹴り上げるやいなや、まっしぐらに私の右目を狙って嘴を突き刺そうとしてきたではないか。
「ぎゃ……」
私は小さく呻き、その場にうずくまった。眼球自体はなんとか無傷で済んだが、しかしシャッターの役目を果たしてくれた瞼の上には血が滲んでいた。顔を手で覆っている私の周りを、ピッピは首を上下に動かしながら歩き回っている。二の矢を放つタイミングをうかがっているとでもいうのか。
そして私は、ピッピに根源的な恐怖を抱くようになった。
なぜこのニワトリは、私に理不尽とも取れる攻撃をしかけてくるのか。その理由は、どんなに考えたってきっと分からない。ピッピと私の「心」の有様は、はっきりと異なっているからだ。このニワトリには言葉が通じず、そしてコミュニケーションを取ることもできない。その現実に私は慄き、輪郭の伴った震えを得てしまった。怖い、私はピッピが、怖い。
それから両親に泣きついて、ピッピの世話役を代わってもらうことにした。そう、私は恐怖から、逃げることにしたのだ。父と母は腕を傷だらけにしながらも、献身的にニワトリ小屋の清掃や餌替えを行ってくれた。
数年後、私が中学生になってしばらくした頃に、ピッピは寿命を迎えて小屋の中で静かに息を引き取った。父は庭を掘って、墓を作ってくれた。
土の中に消えていくピッピを見て、両親は涙ぐんでいたが、私は少しだけ安堵していた。「もう、怯えを傍らに置いた生活を送らなくてもいいんだな」
そして、そんな思いを浮かべている無責任な自分に、つくづく幻滅した。
それから私は、一羽のニワトリの世話さえも満足にできなかった過去を持つというのに、さらなる無責任さを発揮して、自然の生き物を愛好する大人へと成長していった。
野山で昆虫採集をして、海や川で魚を観察し、金と暇ができたら外国の僻地まで遠征して珍しい動物たちの姿をその目に焼き付ける。
晴れやかな気分を胸いっぱいに広げながら、自然と触れ合う自分。
しかし、そこには、一点の曇りがあった。
ある種の鳥だけが、どうしても怖い。
小鳥なら、平気だ。タカやフクロウなどの猛禽類も、怖くはない。むしろ、愛しい。
しかし、あのニワトリと同じサイズ感の、たとえばカラスなどの野鳥と出くわすと、ぞわっとしたものが背中に走る。路上や電柱にいる彼らと目が合えば、嘴で突かれるのではないのかとつい体を縮めてしまう。
それは確実に、ピッピがあの日に私へと与えてきた恐怖と連なっているものであった。
小学三年生の日に、ニワトリに対する怯えから逃げたつもりになっていたが、ピッピはいまも私の背後からこちらに嘴を鋭く向けていたのである。
ニワトリ自体は家畜の鳥なので基本的に野生には生息していないのがせめてもの救いであったが、しかし自然の世界に一歩足を踏み出せば、ニワトリサイズの野鳥は、木々の枝のあちらこちらにいくらでも留まっている。それを目の端に捉えた瞬間、ヒヤリとしたものを湧き立たせているようでは、自然観察行動の調子が崩れる。というか、この世界には人類の五倍もの数の鳥が生息していると言われているのだ。鳥にいちいち怯えていては、身心がすり減ってしまう。
いつまでも、この恐怖に晒されているわけにはいかない。
鳥と、決着を付けなければならない。ピッピから逃げた過去を、きちんと清算しなければならない。
ある日、私は鳥としっかり向き合うことを決心した。このざわめきや後ろめたさを解消して、堂々と自然を愛好する者になるのだ。
私はあの時、ピッピの中に自分とは違う「心」が存在していると認識し、慄くに至った。その鳥の「心」をもっと理解し、分かり合えるための糸口がどこかにないか、探ろうではないか。
それから鳥類に関する図鑑や資料を読み漁り、また鳥の識者を訪ねて学びを得るなどし、ずんずんと羽毛を纏う者たちのゾーンに肉薄していった。
その世界は、私の知らない知見に溢れていた。
「鳥は、恐竜の子孫と言って差し支えのない存在である」
「この地球上には、かつて『恐鳥(きょうちょう)』と呼ばれる大型の鳥が跋扈している時代があった」
「ムクドリは害鳥として、『世界の侵略的外来種ワースト100』に選定されている」
困ったことに、鳥にまつわる「恐」とか「害」とかのワードについ反応してしまう自分がいた。鳥に対してネガティブな心情を抱いていることの顕われなのだろうか。
気持ちをなるべくフラットにして、改めて鳥のことを調べていく。
すると、とある文献に記されていた内容に目が留まり、私は驚愕した。
「この世には、人語を操り、人間との会話を可能とする鳥が存在していた」
まさか、そんなことってあるのか。
そんなことって、あるらしい。
1970年代から2000年代にわたって、アメリカの心理学者が飼育していた大型インコの一種であるヨウム、その名は「アレックス」。彼は飼い主による教育を受けたことで、約百語ものボキャブラリーを獲得し、人間からの質問に的確な発語で答えたり、また自分の要求を人間相手に伝えたりと、ただのオウム返しではない、人語によるコミュニケーションを果たしていた。この世にも稀なる鳥は、色を見分けることや、「ゼロ」の概念を理解することも可能だったという。
アレックスは三十一歳の若さにして急死してしまうのだが、その死の前日、飼い主に最期に残した言葉は「じゃあね、また明日。君を愛しているよ」であったらしい。
怖い。
大型インコが部屋の隅から「愛しているよ」と囁いたなんて、ホラー映画ではないか。私はアレックスの事実を知り、身を凍らせる。
いやいや。
冷静になり、もう一度、考えてみる。
バイアスのない角度から見れば、これは切なくも心が温まる話なのかもしれない。鳥と人間は、たとえ違う「心」を持っていたとしても、方法によっては互いの想いを伝え合うことができるのだ。
これは、鳥に対する恐怖を克服するための重要なヒントだ。
あの時、ピッピとは分かり合えなかったが、アレックスの事例を知ったいまであれば、鳥と心を通わすことは、可能なのではないか。
いつまでも情報だけで鳥に迫っていては、埒が明かない。
実体としての鳥に、向き合おう。
自分と鳥、それぞれの内面に秘めたるものを鉢合わせさせて、疼く過去からの傷に手当てをするのだ。鳥との和解を果たすのだ。
私は、野鳥の楽園として名高い、マレーシア領ボルネオ島を訪れた。
赤道付近に位置するその地域には、広大な熱帯雨林が広がっている。ジャングルの中を分け入れば、ハチクイ、カンムリワシ、ショウビン、タイヨウチョウなどといった多種多様な鳥の姿をいくらでも見ることができる。
チチチチチ……。
ピイピイピイ……。
カカカカカカ……。
鳥たちの鳴き声と湿度に満たされた森の中を、私は複雑な心持ちで歩いていた。
美しい羽色の小鳥や、壮観な翼を持つ猛禽類は、やはり怖くない。彼らの姿は、目を楽しませてくれる。しかし、私はただの愛鳥目的でここに来たのではない。ニワトリサイズの鳥に対する戦慄を終息させるために、いまこうして、鬱蒼とした熱帯雨林の中を漂っているのだ。
どこだ、私が向き合うべき鳥は、私の背筋を震わせる鳥は、どこにいるというのだ。
何泊もロッジに滞在し、朝昼夕と汗をかきながらジャングルの中を歩き続け、私はその時を待った。
そして、滞在最終日。
ギャア、ギャア、ギャア。
突然に、奇怪な鳴き声が耳に響いた。一体なんだ、とその音がする方へと近寄ってみると、樹木の幹の部分に、怪物然とした一羽の鳥が貼り付いていた。
カササギサイチョウである。
私が最も苦手とする、あのニワトリと同じサイズ感。太く羽毛を生やした脚は、太古の恐竜のような様相をたたえている。
なによりも注目すべきは、その奇面だ。サイチョウの仲間は、巨大な角質の鶏冠を頭上に誇る。まるでサイの角のごときで、それが名前の由来にもなっている。
体長、脚、そして鶏冠。
サイチョウとは、私に恐怖を想起させる、ジャストな存在感の鳥であった。
何を考えているのかわからない、真っ黒な瞳。そしてカービングナイフのような、湾曲した嘴。その姿を前にして、脚がすくむ。目を合わせた瞬間、こちらに攻撃をしかけてくるのではないか。目玉をくり抜かれたりするのではないか。
警戒モードが発動し、いますぐにでもこの場から逃げ出したくなる。
いや、目を逸らしてはダメだ。私はこの恐怖と向き合うために、ここまでやってきたのである。決死のバードウォッチングを敢行する千載一遇の機会、逃すわけにはいかない。
じりじりと、サイチョウが警戒しないぎりぎりの距離まで、歩み寄っていく。茂みに上手く隠れることができ、わずか一メートル足らずまで接近することに成功する。心臓がわかりやすくドキドキと動悸を打ち、二の腕に鳥肌が浮かぶ。
サイチョウはこちらに気づくこともなく、幹に脚を留めたまま、嘴を使っての作業に集中している。いったい、何をやっているのだろう。営巣か、それとも採餌か……?
あっ。
そこで思い当たる。
あれは、子育てだ。
そうだ、以前に読んだ資料のどこかに記されていた。
サイチョウは、鳥類世界の中でもかなり独特な育児を行う。メスは卵をお腹に宿すと、木の洞の中に自らを収め、そして入り口を土や木屑やフンなどによって塞いでしまう。天敵から自らと子どもを守るための、安全策としてのセルフ幽閉だ。
その壁に開けられた小さな穴を通して、パートナーであるオスは虫や木の実などの餌をせっせと運ぶ。メスはそれを嘴で受け取り、そして卵から孵った雛にそれを分け与える。
私がいま目にしているのは、まさにオスが洞の中のメスに餌を渡す瞬間なのだ。
自然世界の有様から、勝手に人間目線のドラマを描くというのは、不遜なことである。しかし、そのサイチョウの育児の姿に、私は鳥の世界の「心」の一端を見たような気がした。
それはおそらく、私の持つ「心」とは異なるものだけれども、それに対して恐怖を得る必要は全くないように思えた。目の前にいるのは、血の通っている、ウソのない、そしてまったく理不尽ではない、鳥の姿なのである。
気づけば私は、先ほどまでの恐怖感も忘れて、サイチョウの子育ての姿を夢中になって観察していた。
サイチョウにとっての恐怖とはなにか。
それはやはり、天敵の存在であろう。そしてその天敵の中には、我々人間も含まれる。サイチョウの鶏冠である角は象牙のように重宝され、密猟の対象にされている状況がいまも続いているのだ。サイチョウにとっては、実に理不尽な話でしかない。
子育ての最中、オスのサイチョウが銃弾によって命を落とすこともあるという。そうなれば、木の洞の中にいるメスと雛はあわや餓死の憂き目に遭うわけだが、ここでもサイチョウは独特な安全策を見せる。メスのパートナーであるオスが育児中に亡くなると、それを近くで見ていた別のオスのサイチョウが、シングルマザーとなったメスにせっせと餌を届けるようになるのだ。そうやって、雛の世話は持続される。
そこに思わず友情や隣人愛のドラマを見そうになるが、それはやはり人間の勝手な妄想に過ぎない。精緻に絡まり合う自然の奥行きを単純な物語として消化するのは、横暴でしかない。
それでも、こんな光景を浮かべてしまうことを、許してほしい。
成長したサイチョウの子どもはやがて、洞の壁面を嘴で壊し、大空を見上げる。
そこに広がる世界には、あまたの天敵の恐怖が待ち受けているはずだ。
少しだけ躊躇するが、それでも意を決して大きな羽を広げる。そしてバサバサと大きな音を立てながら、熱帯雨林の樹冠の先へと飛び立っていく。
不安と希望は、いつでも同じ扉の先にあるのだ。
私がピッピを恐れていたように、ピッピもまた、私のことを恐れていたのかもしれない。鳥と人間は、きっと基本的には分かり合えない。
しかし、分かり合えないということを認めたうえで、それでも相手を知ろうとすることを止めなければ、一歩前進なのではないか。その先に待っているのは恐れの痕跡ではなく、解放の景色なのではないか。
サイチョウと向き合い、私はどうやら、鳥に対する恐怖感を幾ばくか薄めることに成功したようだ。日本に戻り、街でハトやカラスを見かけても、以前よりは怯えずに、それを受け入れることができるようになっていた。
いずれは、あの職場がある街でも、胸を張って散歩できるようになればいいな。いつかは、きっと。
恐怖と折り合いを付けながら、これからも自分の世話だけは手放さずに続けていきたい。それがピッピから無責任に逃げた私にできる、唯一の落とし前のつけ方だと思うのだ。
そんなことを心に浮かべながら近所を歩いていたら、目の前の路上に突然、二羽のキジバトが現れた。思わず、ビクッと体を反応させる。
大丈夫、大丈夫。
怖くない、怖くない。
ワクサカソウヘイ
文筆家。1983年東京都生まれ。エッセイから小説、ルポ、脚本など、執筆活動は多岐にわたる。著書に『今日もひとり、ディズニーランドで』『夜の墓場で反省会』『男だけど、』『ふざける力』『出セイカツ記』など多数。また制作業や構成作家として多くの舞台やコントライブ、イベントにも携わっている。