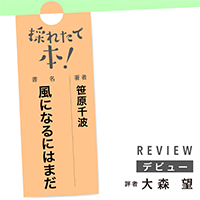笹原千波『風になるにはまだ』◆熱血新刊インタビュー◆
五感すべてを

他者の人生を体験すること。他者の視点や他者の肉体を通じて、世界を感じ直すこと。短編「風になるにはまだ」は、まるで小説を読むという行為そのものを、小説に仕立て上げたような作品だ。
「他人の体に、情報として生きている人が入ってくる、という設定が浮かんだんです。自分とはまったく違う他人の体なのに、借り手はそれが自分のものであると錯覚してしまう。そのニュアンスをどうやったら表現できるかなと考えていく中で、お話ができあがっていきました」
大学3年生の「あたし」は11月のある日、肉体を捨てデータだけの情報人格となって仮想世界で暮らす、42歳の楢山さんに自分の体を貸すことになった。脳に時限的にナノボットを埋め込むことで実現する、1日限りの高額アルバイトだ。「あたし」は楢山さんの指示を受けながら現実世界で身動きし、そこで得た五感の情報全てを楢山さんにリアルタイムで提供する。同期した楢山さんがまず最初に「あたし」に頼んだことは、洋服に触ることだった。その後、楢山さんはこの日の目的である、大学の研究室で出会った友人たちとの特別なパーティーに参加するために、洋服店で「あたし」に似合うドレスを選ぶ。13年ぶりに肉体を得た楢山さんの五感に、生地の触感や色彩が押し寄せる描写が素晴らしい。実は、楢山さんはもともとアパレルデザイナーだったのだ。
「体を持たない人が体をまとう、というイメージからファッションの要素が出てきました。ファッションは自分の体の外にあるもうひとつの輪郭で、他者から認識される自分を少しコントロールするもの。肉体と意識との関係を、より効果的に描けるようになるなとも思いました」
物語は「あたし」と楢山さんの視点をスイッチしながら進んでいく。片方ではなく、双方から五感を描いたからこそ炙り出されるものがあった。
「たとえ誰かと全く同じ出来事を経験できたとしても、それをどう感じるのかは、肉体の違いだけでなくその人の経験とか知識でも規定されるものだと思うんです。アパレルデザイナーで触覚とか視覚に対してすごく鋭敏な楢山に対して、『あたし』はそういったことはほぼ何も知らないし、普段から肉体的感受性もにぶくてぼんやり生きている。そこの落差は、見どころになるかもしれないな、と」
自分の体すらも思い通りにならない
肉体と意識との繫がり。王道とも古典的とも言えるSF的なテーマだが、作家は「応募した当時は、かなりSFには疎かったんです」と苦笑い。このテーマは、友人との雑談から得たものだったという。
「肉体をなくした状態で生きていくとしたらどうだろうという話題で、友達と盛り上がったことがあるんです。そういう、観念的な話をするのが好きな友人がいるんです(笑)。彼女は結構理性、理の人なので、情報だけになってもオーケーという感じだったんですが、肉体がないまま生きるのは私にとっては難しいというか、ちょっと無理そうだなと思ったんですね。もしもそういう状態になった時に、私は私でいられるのかな、と……。そこで浮かんだいろいろな疑問が、このお話の種になったと思います」
肉体への興味や関心、想像力を、作家は実人生の中で育んできた。
「子供の頃と、空白期間を挟んで今も、バレエを習っているんです。踊っていると、自分は一つの不随意な、制御できない肉体であるという感覚になります。自分の体なのに、自分の自由にはならないというところが難しくて面白い。普段はいろいろなことを考えすぎて頭でっかちになっちゃうところがあるんですが、〝自分の体すらも思い通りにならない〟と思えることで、ちょっとラクになれる部分もあるんです」
自分は、この体で生きるしかない。それは諦めではなく、希望になるのだ。
「通っていたのはプロになるような教室ではなかったし、身体的にも自分は恵まれていないし、将来は踊る人になるわけじゃないんだなと気がついて、小学校の終わり頃にバレエを一度やめてしまいました。でも、大人になって再開してみたら純粋に楽しかったんです。ヘタだけど、自分の体を使って踊ること自体に喜びを感じられました」
1編目のラストで、楢山さんが「あたし」の体を愛おしく思ってくれたことにより、「あたし」もまた自分の体や自分の人生を愛おしく感じ始める。そこには、作家自身の実感が形を変えて宿っていたのだ。
「〝自分の体すらも思い通りにならない〟ということを受け入れながらもそれを楽しめている今の自分は、昔よりも人生と折り合いがつけられるようになったのかな、という気がしています」
ルールを恐れて閉じこもるのではなく
デビュー作となる単著を、短編「風になるにはまだ」を含む独立短編集にするという可能性もあったはずだ。しかし、作家自身が、連作短編集にすることを望んだ。
「受賞作の改稿をしている時に、編集の方から設定などについて細かく質問をいただきました。〝私はこういうふうに考えていました〟とか〝そこは考えてなかったけれどこうなんじゃないか〟とお答えしていくうちに、この世界でまだまだ書けそうなことがあるぞ、と。SFって、一個の世界を構築していく創作だと思うんです。せっかく評価していただける面白い世界を一つ作れたのだとしたら、その世界で私ももうちょっと遊びたい(笑)。世界を見るうえで視点は多いほうがより楽しいですから、一編ごとにできるだけ個性が違う登場人物たちを出せたならと思いました」
その段階で、全6編のタイトルを先に決めたそうだ。
「『風になるにはまだ』と同じような、長めで開いた感じのタイトルで全部揃えようと思いました。取り上げたい題材とタイトルを同時に決めて、基本的にはそれに沿う形で物語を書いていったんです。例えば、5編目は『本当は空に住むことさえ』というタイトルで、建築を扱った話です。いろいろな関係性を登場させたいと考えていたので、それまで書いてこなかった高齢の二人組を中心にすることにしました。一人は有名な建築家で、一人は実直な構造設計者。建築については全くの素人で、構造設計者という仕事があることは資料を探している時に知りました。新奇なものを生み出そうとする建築家と、リアルな落とし所を常に考える構造設計者は、協力し合う関係なんだけれども対立する部分もある、という点が小説的にすごく面白いなと思ったんです」
さまざまな事情により生身の肉体を捨て仮想世界を生きることになった人々、という存在によって可能となった、普遍的なテーマへの新たなアプローチも面白い。その一つが、死だ。仮想世界の住人は不死ではなく、「散逸」と呼ばれる死と隣り合わせの状態にある。仮想世界はいくらでも自由が利くからといって、人間らしい営みからは外れた生活をすると、やがてデータの断片になる。
「散逸の設定そのものは、『風になるにはまだ』の段階で決めていました。人間の体が人間の自我を作っているのだとしたら、人間の体のあり方から乖離すればするほど、意識に負担がかかるだろうなと思ったんです。それを回避するために、仮想世界の人たちは、現実世界にいた頃よりも健康で真面目な生活を送るようになるんじゃないかな、と。でも、散逸を恐れて自分に閉じこもっているのは、面白くないって感じる人もいるはずだなと思ったんです。後半は、この世界のルールから逸脱する人たちの話になりました」
死を過剰に恐れていては、生を、今をおそろかにすることになりかねない。リスクを知りながらも楽しむこと、遊ぶことの意義を、全6編の物語は登場人物たちの五感を通して教えてくれている。読み終えると不思議なほどに、生きる力が湧いてくる作品なのだ。
「最近は視聴覚だけでなく、触覚を伝えるインターフェイスなども多少出てきていますが、今のところ五感すべてを体験できる可能性のあるメディアって、小説しかないと思うんです。小説だけが、他人の身体、他人の脳、他人の中から発生する感覚というものを、我がことのように再現することができる。今回の本を作っているときも、私にとってはSFを書くという以前にまず、小説を書いているんだという気持ちが強くあったんです」
病気や障害などの事情で生身の体で生きることが難しくなった人々が、〈情報人格〉として仮想世界で暮らせるようになった近未来。情報人格の小春は、大学時代の同級生が集うパーティに出席するために「一日だけ体を貸し出してくれる」サービスを利用する。体を貸してくれたのは年の離れた大学生だった。ひとつの体を共有して、ふたりは特別な一日を過ごす。第13回創元SF短編賞受賞作を含む瑞々しいデビュー作品集。
笹原千波(ささはら・ちなみ)
1994年生まれ。2020年「翼は空を忘れない」(日吉真波名義)で第204回 Cobalt 短編小説新人賞受賞。2022年「風になるにはまだ」で第13回創元SF短編賞を受賞。他の作品に「宝石さがし」(『アンソロジー 舞台!』)、「夏睡」(『地球へのSF』)がある。