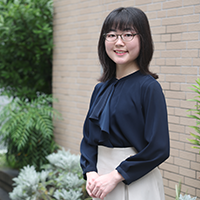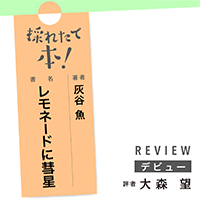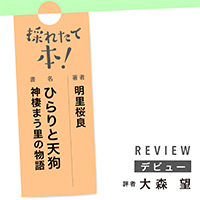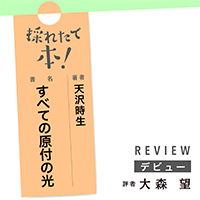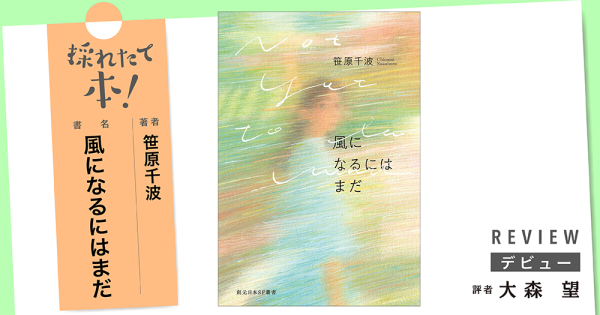採れたて本!【デビュー#33】
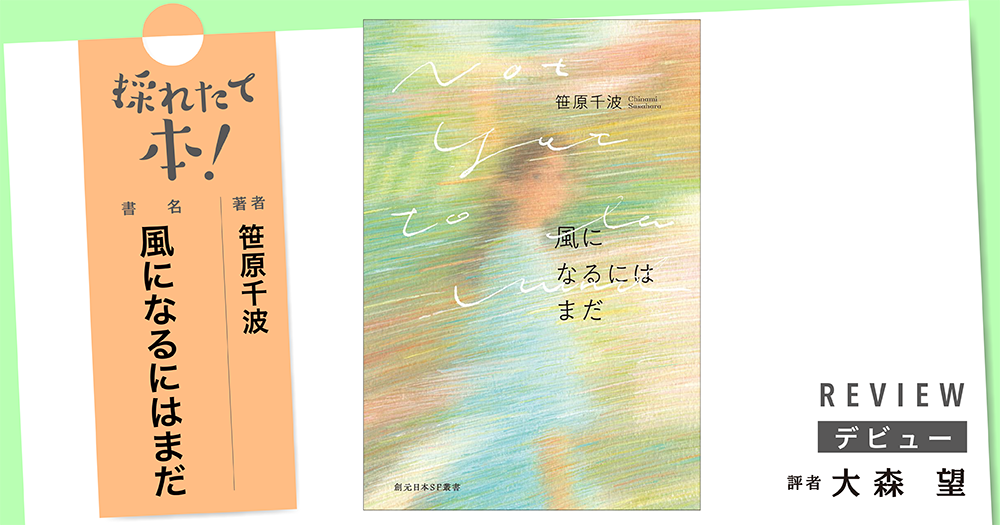
SF作品には当たり前のように出てくるが、現実世界ではなかなか実現しそうにない技術はたくさんある。タイムトラベル、超光速エンジン、テレポート(どこでもドア的なもの)……。
人格のアップロードもそのひとつ。人間の記憶やパーソナリティをすべてデータ化し、そっくりそのままデジタル空間で再現する。仮想空間に移住すれば、土地も食料も衣服も必要なく、コンピュータが稼働する限り、永遠に生き続けられる。そうなるとヒマでしょうがないので、グレッグ・イーガンの『順列都市』の登場人格は、家具職人の人生を選び、何百年だか何千年だか、ひたすら椅子の脚をつくりつづける。そんなことして楽しいのかと思うでしょうが、「椅子の脚をつくることがこの世でいちばん楽しい!」と自分に思わせているので何の問題もない。真の意味での〝永遠の生命〟の恐ろしさと面白さを実感させてくれる小説だ。
一方、笹原千波のデビュー単行本となる本書『風になるにはまだ』では、そうしたデータ人格も不死ではなく、寿命(的なもの)があるという設定が導入されている。情報人格の心身を構成するデータは永遠にそのままではなく、いつか一体性を失いばらばらにほどけて散り散りになってしまう。これが〝散逸〟と呼ばれる現象。それを指して〝風になる〟と表現する人もいる。
そのため、仮想世界にいま〝移住〟するのは、難病にかかっていたり、余命を宣告されていたり、現実世界で長く生きることがむずかしい人々がほとんどだ。
仮想世界でなら、現実離れした途方もないファンタジー空間をつくり、そこで暮らすのも思いのままだが、現実に近い生活を送る方が〝散逸〟を先送りできるとされているため、情報人格も生身の人間と似たような日々を送っている……。
とまあ、そんな時代を背景にした六つの連作短編が本書を構成する。巻頭に置かれた表題作は、第13回創元SF短編賞受賞作。
情報人格は、現実世界にいる家族や友人とも、仮想空間のアバターを介して(もしくは、ビデオ通話や音声通話で)いつでも自由にコミュニケートできるが、直接触れ合うことはむずかしい。そこで、現実世界にいる誰かと同期して、その人物が感じることを情報人格がリアルタイムで経験できるようにする技術が開発された。現実の人間が情報人格のアバターみたいなものになるわけだ。
表題作の語り手は、現実世界にいる大学生の〝あたし〟と、情報人格の楢山小春(わたし)。〝あたし〟は、アルバイトの求人に応募して、小春に体を貸すことに同意する。小春の目的は、大学時代の仲間が集まるパーティに参加すること。小春は13年前、情報人格となった。つまり、現実世界の感触を味わうのは13年ぶりだ。【以下、本文11ページより引用】
同期してすぐ、雪解けに勢いづく大河のように知覚が押し寄せた。汗ばんだ掌、冷えた指、 手の甲にかかるニットの袖。乾いて温かい風が頰にあたる。埃っぽいにおい。座位でも働いている骨格筋、体の下の硬い椅子、身じろぎは衣擦れと皮膚への刺激を同時に生じさせる。不規則に注視点がゆらぐ視界、蛍光灯の微妙なちらつき、ひらいたままのイヤフォンケース、電化製品のうなり、遠くにパトカーのサイレン、肩を上げては下げる呼吸、鼻腔に息が通えば耳にも聞こえる。
こうした細やかで緻密な感覚描写がこの小説のキモ。かつてアパレルデザイナーだった小春は、〝あたし〟を通じて洋服の生地に13年ぶりに触れて、心ゆくまでその感触を味わう。そんなふうにして現実世界を(いわば)再発見していく感動がみずみずしく鮮やかに描かれる。
第2話「手のなかに花なんて」では、第1話と反対に、現実世界に生きる14歳の少女・優花が、仮想世界に移住した祖母のもとを(アバターを使って)訪れる。祖母の家にはほかにもいろんな人が訪ねてくる(第1話の小春もそのひとりとして登場する)。
第3話「限りある夜だとしても」は、高校時代に友人だった中年男性二人の物語。余命3年以内と宣告された三森は、少しでも命を永らえさせるために情報人格となるかどうか悩み、友人の榛原に相談する。
後半の3話はすべて書き下ろし。「その自由な瞳で」は、トオルと映、男女二人が主人公。高校卒業後ひきこもりになった映は、自由にならない体を持つトオルと会うため、約2年ぶりに家を出る……。やがて、トオルとともに情報人格となった映は、いつか彼と一緒に散りたいと願う。
「本当は空に住むことさえ」では、仮想世界に住む著名な建築家・敷島綾女とその手伝いをする構造設計者の古谷誠治に、仮想世界の土地を管理する役所から思わぬ依頼が舞い込む。
巻末の「君の名残の訪れを」は、仮想世界の黎明期に移住してきて、ずっと散ることなく生きている女性・翼が主人公。彼女は自分をこの世界に連れてきてくれた親友の名残を、この世界に吹く風の中にさがしている。
死と別離のモチーフが次第に色濃くなってくるが、仮想空間への移住を経ることで、死は突然の別れではなく、少しずつ遠ざかっていくようなものになる。SF的なテクノロジーを手で触れられるような身近な日常として描く、繊細な連作集だ。ほぼ現代小説なので、ふだんSFを読まない人にこそぜひ読んでほしい。
評者=大森 望