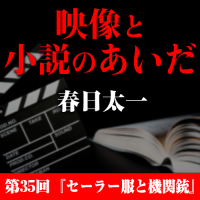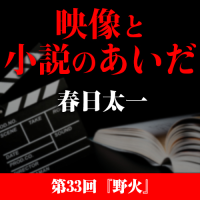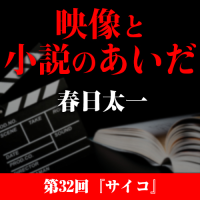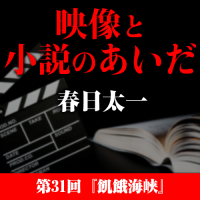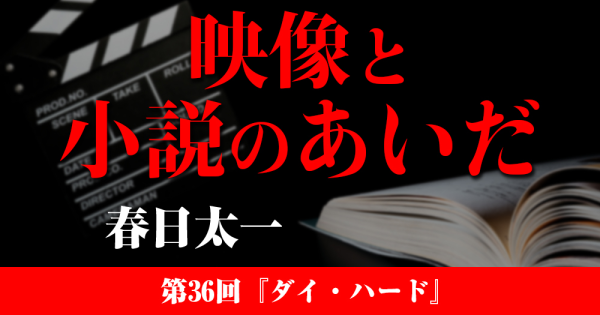連載第36回 「映像と小説のあいだ」 春日太一
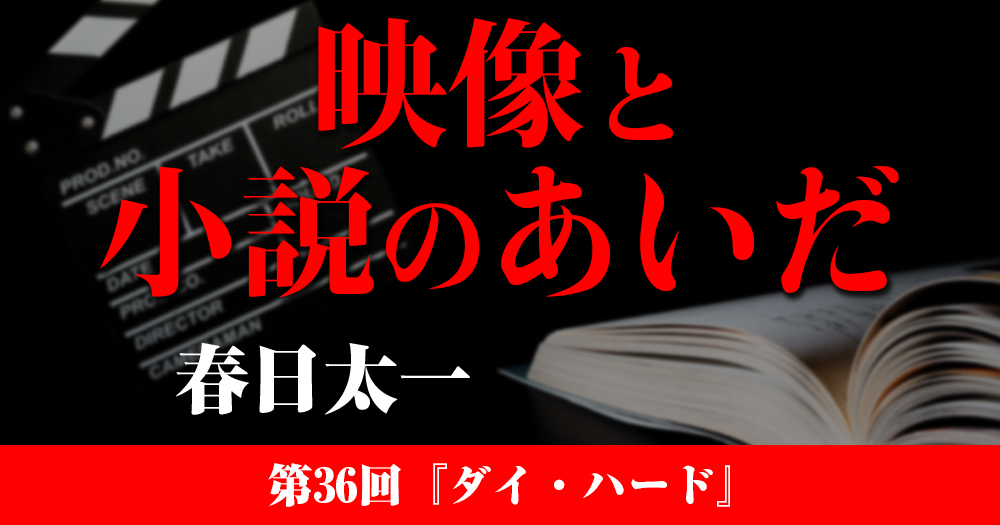
小説を原作にした映画やテレビドラマが成功した場合、「原作/原作者の力」として語られることが多い。
もちろん、原作がゼロから作品世界を生み出したのだから、その力が大きいことには違いない。
ただ一方で、映画やテレビドラマを先に観てから原作を読んだ際に気づくことがある。劇中で大きなインパクトを与えたセリフ、物語展開、登場人物が原作には描かれていない──!
それらは実は、原作から脚色する際に脚本家たちが創作したものだった。
本連載では、そうした見落とされがちな「脚色における創作」に着目しながら、作品の魅力を掘り下げていく。
『ダイ・ハード』
(1988年/原作:ロデリック・ソープ〝Nothing Last Forever〟/脚色:ジェブ・スチュアート、スティーヴン・E・デ・スーザ/監督:ジョン・マクティアナン/制作:ゴードン・カンパニー、シルバー・ピクチャーズ)
〝How the fuck did you get into this shit?〟字幕訳:「何でこんな目にあうんだ?」
ニューヨーク市警のジョン・マクレーン刑事(ブルース・ウィリス)はクリスマスの夜を妻ホリーと過ごすため、彼女の勤めるロサンゼルスの高層ビルを訪ねる。そこでは社員たちがパーティをしていたが、武装したテロ集団に占拠されてしまう。たまたま座を離れていたジョンはたった一人でテロリストたちと戦うことになる――。
アクション映画の金字塔『ダイ・ハード』には、実は映画化される約十年前に書かれた原作があった。そして、マシンガンを支点にしてのエレベーターシャフトの垂直降下、天井裏ダクトでの匍匐前進、裸足でガラス片の上を歩く――といった映画を代表する危機的状況は、原作通りだったりする。また、たまたま近くに居合わせたパウエル巡査(レジナルド・ヴェルジョンソン)と無線を通じて仲間意識を築いていく展開も同じだ。
だが、双方から受ける印象は大きく異なる。というのも、主人公のキャラクターを映画は大幅に変更しているためだ。
原作の主人公はリーランド。既に刑事は退職しているものの、ニューヨーク市警で保安対策の顧問をしている。つまり、テロ対策のプロフェッショナルなのである。そのため、いつも冷静に状況を見つめ、複数の選択肢を想定し、その中から自分の取るべき行動を合理的に選択していく。ビルに入る直前という早い段階で不穏な空気を察し、テロリストが乱入する前から警戒心を持ち続けているし、スペシャリストとしての知識から主犯のハンス(アラン・リックマン)の正体を初期段階から認識している。そのため、これから起きうる悲劇への予測ができていた。生き延び、最悪の事態を防がねばならない。彼はビルから脱出することもできたが、内部からハンスたちに圧力をかけるためビルに居残ることにしたのだ。
つまり、原作のリーランドはこの状況下において、基本的には全て自分の意思で能動的に行動している。それに対し、映画のマクレーンはそうではない。
リーランドの「冷静な分析に基づく的確な行動」と結果的には同じことをしているのだが、そこに至る過程は「突然の状況に右往左往しつつの、強引な突破」としている。その結果、「普通に暮らしていたはずが、いきなり酷い目に遭った」というニュアンスが強くなり、「大変な事件に巻き込まれた哀れな男」としてのツイてないペーソスが強まっている。そのため、全般的にコミカルな色合いになった。
警報装置を鳴らして救援を呼び、消防車の来援を見てはしゃぐ。だが、テロリスト側の機転で引き返してしまいガッカリ。警察に通報するも、コールセンターでは不審者扱いされ、信じてもらえない。原作では協力者だった放送局スタッフが功名心に駆られ迷惑行動に走る。ロス市警の責任者は言い分を信じない上に無能。さらに、新たに来たFBIは傲慢。結果、いずれも被害を広げてしまう。原作でも現場責任者との対立はあったが、あくまで主導権を奪おうとしただけであり、対テロのプロとしての主人公の言い分は聞き入れられていた。さらに人質内にジョンを売る者が出て正体が判明してしまう――。
といった具合に、新たに付け加えられた場面や変更になった場面の大半が、「ツイてない主人公」という面を強めるためのものになっているのだ。そのため、同じようなシチュエーションであっても原作と映画では違った印象となっている。
その最たるところは、クライマックスの屋上のシーンだ。警察(映画ではFBI)は状況を打破すべく、ヘリコプターを屋上へ向かわせ、そこからテロリストの強襲を企んでいた。が、それはハンスに読まれており、彼らの攻撃によりヘリコプターは屋上で爆発。爆風による落下を防ぐため主人公はホースを命綱にして空中にダイブ。下の階のガラス窓を突き破って急死に一生を得る。
この場面は、原作にも映画にもある。ただ、原作はこうなることを主人公は予測しており、ホースの長さをあらかじめ計算しながら調整し、来たるべき時に備えている。一方の映画は地上とのコミュニケーション不全もあり、ジョンはギリギリまでヘリコプターを遠ざけようと努力する。だが、それが通じないとわかった段階で慌ててホースを身体に結び付ける。
この時、重要となってくるのが、主人公のある特質の改変だ。原作の主人公は、第二次大戦の英雄で、戦闘機も操っているし、空挺部隊の経験もある。そのため、空中に我が身を放り出すことに躊躇がない。一方、映画は、旅客機の通路側に座ることにすら怯えるほどの高所恐怖症だと冒頭で示されている。そのため、こんなことは絶対にしたくない。
そして、飛び降りる直前に発せられた愚痴が、冒頭のセリフだ。最も下品なスラングを二つも入れ込んでいるところに、いかにこの状況を厭がっているかが伝わってくる。主人公のトホホ感が極まった場面だ。
ただ、最後の余韻は逆転しており、映画は明るく、原作は苦い。それは、テロリストと人質の関係性の違いによるところが大きい。
映画のテロリストは単なる金目当てであり、人質となる会社員たちの勤める企業は国際的な事業展開を進めているものの劇中では彼らの仕事に落ち度は示されていない。つまり、シンプルな加害者――被害者の関係性にある。そのため、主人公も容赦なくテロリストたちを殺すことができた。
一方、原作の企業は裏では国際法違反の取引をしており、テロリストの目的は金ではなくその悪事の糾弾にあった。つまり、テロリストに正義の倫理があるのだ。しかも、原作では主人公は妻と離婚後に死別しており、人質になっているのは彼の娘。そして、その娘が企業の悪事を主導していると主人公は知ってしまう。そのため、テロリストを一人殺す度に主人公は心に傷を刻んでしまう。
この流れで、終盤に決定的な違いが生じる。追いつめられたハンスは主人公の妻(原作では娘)を楯に対峙する。主人公は隙を見てハンスを射撃。その衝撃でハンスは窓を突き破って外に落下する。この際、ハンスは妻(娘)を道連れにしようとするのだ。そして、映画ではなんとか主人公が妻を救出できたものの、原作では娘はハンスもろとも落下してしまう。慟哭する主人公。「銃の意味など、死以外の何がある」――多くの殺戮の果てに主人公に去来したのは、ただの空しさだった。
映画はリムジンの後部座席で妻と熱いキスを交わすジョンの姿で終わっていく。娯楽作品としては、この上ないラストだ。本作の脚色からは、いかにして【古き良き】ハリウッド映画のエンターテインメント性が構築されているのかがよくわかる。
【執筆者プロフィール】
春日太一(かすが・たいち)
1977年東京都生まれ。時代劇・映画史研究家。日本大学大学院博士後期課程修了。著書に『天才 勝進太郎』(文春新書)、『時代劇は死なず! 完全版 京都太秦の「職人」たち』(河出文庫)、『あかんやつら 東映京都撮影所血風録』(文春文庫)、『役者は一日にしてならず』『すべての道は役者に通ず』(小学館)、『時代劇入門』(角川新書)、『日本の戦争映画』(文春新書)、『時代劇聖地巡礼 関西ディープ編』(ミシマ社)ほか。最新刊として『鬼の筆 戦後最大の脚本家・橋本忍の栄光と挫折』(文藝春秋)がある。この作品で第55回大宅壮一ノンフィクション大賞(2024年)を受賞。