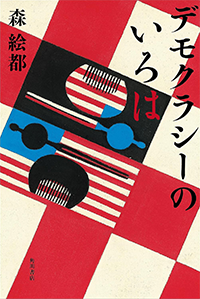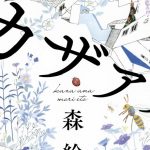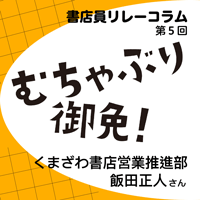森 絵都さん『デモクラシーのいろは』*PickUPインタビュー*

膨大な資料に沈み、浮かんだドラマ
日系2世の通訳官が、民主主義の教師に?
主要人物は日系2世のアメリカ人教師と、決して従順とはいえない日本人女子生徒4人。といってもこれは学園モノではない。森絵都さんの最新小説『デモクラシーのいろは』は、戦後の日本で実験的に民主主義のレッスンが行われる、というユニークな設定の物語だ。現代の自分たちも真剣に考えたい問題を真摯に盛り込みながらもユーモアたっぷり、後半には意外過ぎる展開が待ち受ける極上のエンターテインメント作品である。
「最初は手探りだったんですけれど、日系2世のアメリカ人を先生にすると思いついた段階で、これはいけると感じました」
1946年11月。GHQの主催するランチ会で日本人に民主主義が浸透するかという懸念が話題になったのを機に、モデルケースとして何人かの日本人に一定期間、民主主義教育を受けてもらい結果を見る、という計画が立ち上がる。学び舎と宿泊所となるのは下落合にある、仁藤子爵夫人の別宅。GHQから教師に指名されたのは、巣鴨プリズンで通訳官をしていたリュウ・サクラギだ。本作の視点人物である。
「生徒たちと今の私の間には時代という大きな距離がある。太平洋ほどの距離を隔てて育ったリュウの視点にすれば、自分と同じ距離感で彼女たちを見つめられると思いました。そこから、自分がリュウだったらどんなレッスンをするだろうと考えていきました。民主主義が話の柱となってはいるけれど、説教臭い話には絶対にしたくなかった。それで生徒が自分たちの問題を多数決で決めたり、ディベートで決めたりするなど、なるべくエピソードの中に民主主義の要素を溶かし込むようにしました」

生徒に選ばれたのは、真島美央子(東京出身、元男爵家出身の冷ややかな優等生)、近藤孝子(静岡の農家出身、内気な頑張り屋)、沼田吉乃(横浜出身、学習意欲ゼロ、あっけらかんとした自由人)、宮下ヤエ(青森出身、世間ずれしていて授業中は居眠りが常態)。
「同じ家で一緒に生活することを考えると、生徒の数は4人くらいがいいかな、と。それぞれがどういう戦争を体験して今に至っているのかを書くために、なるべく違うタイプにしようと思いました。なので、一人ひとりの背景に関しては最初に結構詳しく作りました」
しかし彼女たちの個性がバラバラだからこそ、リュウは一人ひとりに向き合いながら、困惑したり、振り回されたり。
「生徒たちを設定した段階で、きっとこれはリュウの受難の物語になるというか(笑)、彼女たちに相当翻弄されるなと予想がついていました。彼にとって生徒たちは、最初は違うカルチャーで育った異質な存在なんですよね。そこからだんだん近づいていって、お互いが作用を及ぼしあっていく部分がこの物語の一番の肝かなと思っていました。リュウはつむじまがりのところがあるけれども、上の人たちに反発しつつ、彼女らを守るところもある。彼らの関係性がどう変わっていくかは、力を入れて作っていきました」
教師がメンター的な存在となるのではなく、教師も生徒も相互理解を深めながら成長していく物語。その過程が時に真摯に、時にコミカルに、時にスリリングに描かれていく。
戦後という不思議な時代を描きたかった
さまざまな切り口の作品を発表してきた森さんだが、今回のこの設定のきっかけは何だったのか。
「出発点は〝時代〟でした。戦時中のことは多くのことが書かれてきたけれど、占領下の時代については私自身、焼け野原という漠然とした一言で捉えていたところがあったんです。でも戦後って、食糧難やハイパーインフレ、住宅不足やチフスなど、あまたの問題を抱えた中で人々が生存競争をしていた時代なんですよね。いかがわしいことも涙ぐましいこともいっぱい起きている。その不思議な時代を背景にドラマが作れないかと思いました」
そこでまず、戦後に関する資料本をランダムに集め、「どこを柱にするか」「どこを切り取るか」を考えながら読み込んだ。100冊(!)ほど読んだところで、浮かび上がるものがあった。
「この時代の大きな特徴は、それまで軍国主義だった日本が民主主義と出会ったところだなと思って。それで民主主義を柱にできないかなと思いました」
そこから今後は民主主義にフォーカスした資料を読み始め、トータルで200冊(!!)ほど読んだところで浮かんだのが、「民主主義のレッスン」だった。
「特に理由も道筋もなく、ふいに民主主義のレッスンをやればいいんだと思って。じゃあ先生はどうしよう、レッスンはどうしよう、生徒はどうしよう、と具体的なことを考えていきました」
作中にも書かれているが、民主主義のありかたは国それぞれ。「これこそが民主主義」と簡潔に説明し実践しうるものがあるわけではない。そんなものについてのレッスンを、エンタメ小説に仕立て上げるのは難しかったのではないか。
「実際、調べれば調べるほど民主主義は捉えどころがないなと思いました。でも、あの時代の日本人は、まさに捉えどころのない民主主義に出会って、それを捉えようと一生懸命になっていたんですよね。彼らの気持ちに立って考えていくうちに、結果的に捉えどころのなさを書くという方向になっていきました」
著者を悩ませた〝出口問題〟
生徒たちに翻弄され、なにかと口出ししてくる高慢な家主の仁藤子爵夫人に辟易し、意外な出来事(トラブルともいう)に直面しながら業務を遂行するリュウ。自由研究や実践授業などの授業の内容も楽しく興味深いが、やはり生徒たちとリュウとの信頼関係の変化が楽しい。やがてリュウは、みんなで出かけた先で、日本において女性がどれだけ見下げられているかを知り愕然とする。
「アメリカでも女性差別がないわけではないですが、あのあからさまな様子は、アメリカ育ちのリュウにしてみれば青天の霹靂だったと思います」

当時の日本の女性の地位の低さは、リュウだけでなく、著者自身をも悩ませた。
「最初は民主主義のレッスンを受けて卒業していく、とだけ考えていたんです。でも彼女たちが卒業した後を考えると、現実では絶対壁にぶつかるんです。当時の社会では女性が意見をすれば生意気だと嫌われたし、せっかく新しい生き方を見つけたのに彼女たちにはその使い道がない。じゃあどうするのかがなかなか見えなくて、編集部の人たちと〝出口問題〟と呼んでいました。それでも、自分たちの力で新しい人生をつかみ取ってほしいなと考えているうちに、ある仕掛けを思いついたんです」
というように、後半にはまさかの、そしてなんとも痛快なサプライズが待っている。
「ただ、資料を読むほどに実感したのが、みんなどれだけ大変な目に遭ってきたのかということでした。あの時代には幸せになった人がいないんです。でもだからこそ、今回は一種のファンタジーとして、せめて小説の中だけでも、彼女たちを幸せにしてあげたかったし、ある意味、現実に仕返しをさせたかった気持ちがあります」
現実は重い。また戦争について書くと思う
人それぞれの戦争体験、元華族たちの変化、財産没収、戦災孤児、軍の物資の横領、スパイの存在、加害者であったかもしれない苦悩……戦後のさまざまな景色が見えてくる本作。
「それが書きたかったことのひとつなんです。今回調べてみて私も発見が多かったので、もっと戦後の時代の解像度が上がればいいな、と考えながら書いていました。戦後を書くということは、戦争を書くということでもあるんですよね。だから、執筆期間中は戦争から自分を切り離さずにいようと思い、ずっと資料は読み続けていました。書き上げた時に数えてみたら最終的に450冊くらい読んでいました」
通読したのがその数で、一部だけ当たった本を含めればさらに冊数は増えるという。もともと森さんは研究熱心な方という印象があるが、それにしてもどれだけ資料読みに時間を費やしたのか。
「やはり特定の時代を書くとなると、少しでも知っていることが多いほうがいいので。今回は戦争が絡むため緊張感も高かったです。小説は前向きな終わり方にしましたが、やはり現実はすごく重いものがあって、自分の中で消化できないまま残っている感じがあります。いつになるか分からないけれど、また戦争について書く時に、それが繫がっていくのかなと感じます。もともといつか海外の戦場を舞台にしたものを書きたいと思っていたので」

本作を書き上げた今、もし「民主主義とはどういうものか」と聞かれたら、森さんはどう答えるのか。
「私はやはり、暴力による決定や暴力による支配から人を守るためのものだと思います。残忍な虐殺のようなことを起こさせないようにするシステムが民主主義であると捉えています。そのためにディスカッションや多数決、尊重が必要になってくる。ただ、今の時代、民主主義が機能しているのかもわからなくなってきている気もします。なのでこの小説が民主主義とはどういうものか考えるきっかけになってくれるといいな、というのがあります。もちろん、エンターテインメントとして楽しんでもらえることが大事なんですけれど」
自分にとっての民主主義とはどういうものか、さらには自分にとって望ましい社会とはどういうものか。楽しませながらも、心の中の漠然としたものに、なにかしらの輪郭を与えてくれる長篇だ。
森 絵都(もり・えと)
1968年生まれ。91年『リズム』で講談社児童文学新人賞を受賞しデビュー。95年『宇宙のみなしご』で野間児童文芸新人賞、産経児童出版文化賞ニッポン放送賞、98年『つきのふね』で野間児童文芸賞、99年『カラフル』で産経児童出版文化賞、2003年『DIVE!!』で小学館児童出版文化賞、06年『風に舞いあがるビニールシート』で直木賞、17年『みかづき』で中央公論文芸賞を受賞。