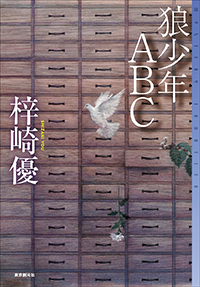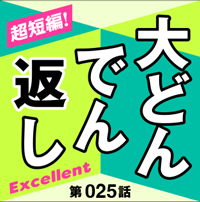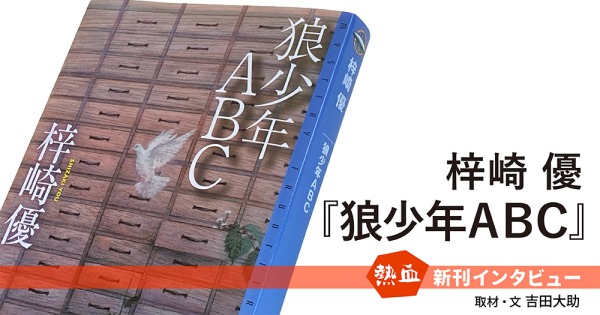梓崎 優『狼少年ABC』◆熱血新刊インタビュー◆
謎を解いたという経験が
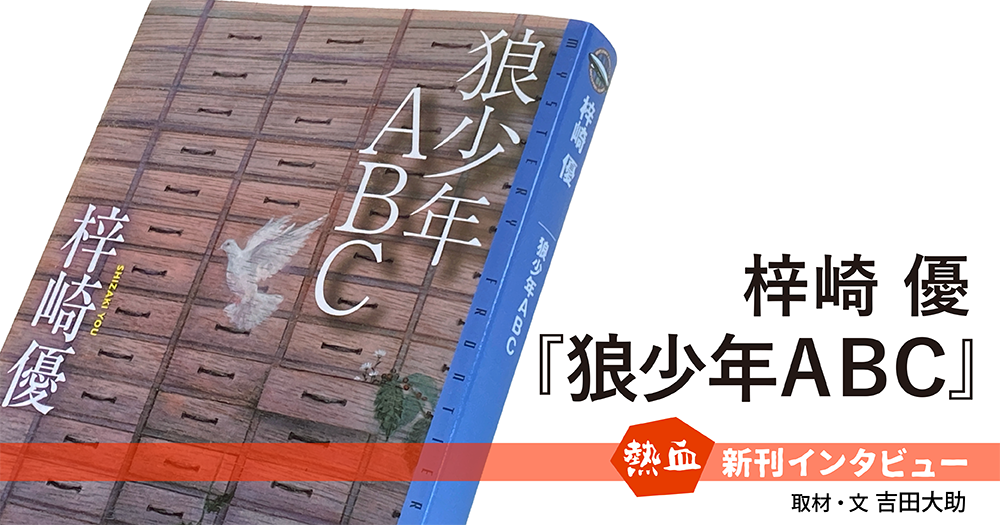
もはや存在自体が伝説となりつつあった作家に、何はさておき真っ先に伺わなければいけないことがあった。前作から12年ものインターバルが空いたのは何故なのか?
「作品が書けなくなったということではなかったんですが、公私ともに忙しい状況になってしまい、なかなか執筆に割ける時間が確保できなかったんです。作家としての未熟さに直面したことも大きかったですね。『リバーサイド・チルドレン』を文庫化(2021年8月)していただき、帯で新刊の告知を載せた時には今回収録した4つのお話のプロトタイプはできていたんですが、どの原稿も相当なブラッシュアップが必要でした。編集者さんにフィードバックをもらいながら手を入れ続けているうちに、こんなに時間が経ってしまいまして。本当にすみません」
作品集を編むきっかけとなったのは、ラストに収録されている「スプリング・ハズ・カム」だ。1冊目の単行本を出した直後、学園ミステリーのアンソロジー『放課後探偵団』(2010年刊)のために書き下ろした短編だった。33歳の主人公が、高校時代の同窓会に出席する。会の途中で、15年前に埋めたタイムカプセルに収められていた無記名の手紙が朗読される。
「『三十三歳の私は宣言する。あの事件の犯人は、私だ』」
卒業式の日、放送室がジャックされる事件が起こったが、犯人は不明のままだったのだ。止まっていた時計の針が動き出し──。
「アンソロジーのタイトルの『放課後』という言葉を広く解釈して、卒業式と同窓会という舞台を扱うことにしました。10代を主人公にするのであれば、10代だから成立する話にしたかったんですよね。犯人の動機や言動は、いわゆる大人になってからだと実現が難しいものだと思うんです」
次に手がけた作品が、冒頭に収録されている「美しい雪の物語」だ。ミステリー専門誌に読み切り掲載された本作の舞台は、ハワイ島の西海岸・コナ。色彩感あふれる風景描写と共に、ボストンから単身でこの地にある叔父の家へとやって来た11歳の少女の五感を通して、この街の美しさがいきいきと活写されていく。一方でハワイには、アメリカにとって第二次大戦の幕開けとなった真珠湾がある。『叫びと祈り』や『リバーサイド・チルドレン』と同じく、日本ではなく外国を舞台にしているからこそ描くことができた物語となっている。
「私は幼稚園の頃から足かけ6年くらい、マレーシアに住んでいました。すぐ近くにジャングルがあるようなところで、その当時目にしていた光景や出会った人々が自分のアイデンティティの一部を形作っています。そのせいか、日本と異なる文化に対しての壁を個人的にあまり感じていなくて、物語を考える時に、日本を舞台にすることが当然の前提ではないんです。『美しい雪の物語』も、〝こういう物語を書きたい〟というイメージに従っていくうちに、ハワイという舞台に辿り着きました」
この物語に関してはまず最初に、謎が生まれたのだという。
「〝日記の続きを知ることはできるのか〟という謎が浮かんだんです。それってどうやって解けるのかな、と想像を膨らませていきました」
少女は叔父の家の書斎で、1冊のノートを見つける。そこには「僕」と「彼女」との運命の出会いがしたためられていて……。
「日記が途切れる理由は何だろうと考えていった先に、戦争という題材が出てきました。私自身の話をすると、2001年にアメリカで起きた同時多発テロ事件が衝撃的だったんです。当時私は学生でしたが、親が取り乱したことをよく覚えているんですよね。学校や友人や受験といった自分を取り巻く狭い世界の外に、大きな世界がある、そこでは本物の戦争が起きているんだということを、親のリアクションを通して肌感覚で気付かされたんです。ずっと自分の中に残っていたその感覚を、主人公に重ねて書いていきました」
戦争というテーマと真正面から向き合うことはともすればシリアス一辺倒になりかねないが、本作には優しさや温かさが入り込んでいる。時間をかけてそこのバランスを探り、初出時から大幅な加筆修正を施したという。
「前の2冊は、ミステリーであることに重きを置いて書いた作品でした。それに比べると今回の作品集は、ミステリー的な演出やロジックも腐心してはいるんですけれども、読んでいる途中で真相が分かってしまったという人は結構出てくるかもしれないという気がしています。それでも、テーマの掘り下げであったり物語としての完成度を高めたりすることが大事な作品集ではないかと考えました」
ミステリーが好きである以前に物語が好き
「『スプリング・ハズ・カム』と『美しい雪の物語』はどちらも学生ないし子供を主人公にしていて、季節が春と夏というくっきりとした違いがある。四季の話で、かつ若い時間を描く物語として4編を束ねたら、一つの作品集が作れるのではないか。その着想を出発点に、秋と冬の物語のイメージを探っていきました」
表題作となった「狼少年ABC」は秋の物語だ。もっともミステリー偏差値が高い一編と言えるが、もっともコミカル。カナダの西部に広がる温帯雨林「グレート・ベア・レインフォレスト」の動物観察小屋(物見台)で、大学3年生の3人が『水曜どうでしょう』のようなダベリを繰り広げる。その過程で、ある人物の過去にまつわる謎の扉が開き、推理合戦が始まる。
「『九マイルは遠すぎる』(ハリイ・ケメルマン)のような、ほんのちょっとした一言からどんどん推理を膨らませていって、最後は思いもよらないところに辿り着くというミステリーを書いてみたかったんです。一方で、自分の若い頃を振り返ると、大学生の時が一番青春らしい時期だったなという思いがあったんですね。他愛もない会話を交わすことや、意味があるかどうかも分からない時間を過ごすことの楽しさを描いてみたい。その2つを念頭に置いたらどういう物語が作れるだろう、と考えていきました」
最後に執筆した「重力と飛翔」はトリック先行型だったという。高校1年生の少年・佐々は、同級生・小原智弘の葬儀に出席する。小原は死の直前、不可思議な写真を撮影していた。雪が重要な小道具として登場する、冬の物語だ。
「この作品集の中で唯一、主人公がリアルタイムで死に直面する話です。昨日まで同じクラスにいた人が死んでしまったという衝撃は、大人になってから直面するさまざまな死とは全く違う。10代の子達にとって、死はなかなか実感が持てないものだと思います。そのリアリティを10代で得てしまった衝撃を、冬の物語として書きたいなと思った時に、今回のトリックを思い付きました。このトリックを語るにはどういう舞台や登場人物が相応しいか、と考えていく中で物語が生まれていったんです」
10代の子供達を主人公に据え、四季を物語の要素に取り入れた全4編は、実はもう一つの大きな共通点がある。
「ただ謎を解いて終わり、謎が解けたことのカタルシスだけで終わりにはしたくありませんでした。謎が解けてから最後の一文に至るまでの展開が、心に残るといいなと思いながら原稿をブラッシュアップしました」
メインとなるトリックが明かされた後に流れる時間こそが、登場人物にとっても読者にとっても重要なのだ。そこにエモーションが宿り、感動が爆ぜる。
「私自身もそうなんですが、過去を振り返った時に、あの時のあれが自分にとってターニングポイントだったな、と思い当たる出来事が誰しもあるのではないでしょうか。この作品集では、謎を解いたという経験が主人公たちの人生にとってのターニングポイントとなる、という作りにしたかったんです。そうすることで、ミステリーであることの意義というか、主人公たちが謎を追う意味が物語の中に生まれるのではないか。ミステリーが好きである以前に物語が好きである自分が書くならば、こういうミステリーでありたいという理想をこの本では追求したかったんです」
本書を読んで、梓崎優という作家の未来への期待感も高まった。
「次の本は、もっと早めにお届けできる予定です(笑)。私の場合、人生の中で触れてきた物語のおかげで今の自分があり、今生きていられています。誰かにとってのそういう物語を、自分が一つでも残せたら本当に嬉しいです」
梓崎 優(しざき・ゆう)
1983年東京都生まれ。慶應義塾大学経済学部卒。2008年、短編「砂漠を走る船の道」で第5回ミステリーズ!新人賞を受賞する。選考委員から激賞された受賞作を第一話に据え連作化した『叫びと祈り』を10年に刊行。同書は《週刊文春》ミステリーベスト10国内部門第2位をはじめ各種年間ミステリ・ランキングの上位を席巻し、2011年本屋大賞にノミネートされた。13年に初長編となる『リバーサイド・チルドレン』を発表し、翌年に第16回大藪春彦賞を受賞。