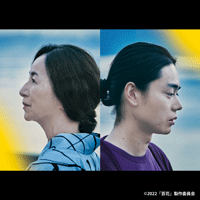川村元気さん『百花』
数々のヒット映画をプロデュースしてきた川村元気氏が、はじめての小説『世界から猫が消えたなら』を発表したのが二〇一二年。それからほぼ二年おきに、コンセプトを明確に打ち出した小説を発表してきた。ただ、四作目となる『百花』は、成り立ちがこれまでとは異なるのだという。そこにこめた思いとは?
新作のテーマは記憶
「今回の本の感想を送ってくれる人が、それぞれ自分の人生についても書いてくるんです。僕にとって良い小説って、物語に没入させるものというより、何か記憶を引きずり出されて自分の人生を照射するもの。今回は特に、それがやりたかったのかなとも思う」
第一作目『世界から猫が消えたなら』では命、二作目『億男』ではお金、三作目『四月になれば彼女は』では恋。人生に欠かせないものをコンセプトに小説を書いてきた川村元気さん。四作目となる『百花』では記憶をテーマに選んだ。ただ、これまでの小説とは成り立ちが少し違う。
「今までは映像を作る人間として、映像ではできないことを紙のメディアでどう書くかトライしてきました。でももう三作書いたし、そろそろ小説家として小説を書くことと向き合うべきだと考えていたんです」
そんな時、母方の祖母の認知症が発覚。
「久しぶりに会ったら、"あなたは誰?"と言われて。ショックだったけれど、同時に興味も湧きました。映画『君の名は。』では、お互いの名前を忘れてしまう話をファンタジーとして作った。そのファンタジーが目の前に現れたんですから。吉田修一さんにその話をしたら、"それなら、認知症の人が見た世界を書くといい"と言われ、それを真に受けて書く気になりました(笑)」
祖母の元に通い、たくさん話をした。
「いろんなことを忘れていく姿が清々しくも見えました。一方僕はといえば、スマホを見るとアドレス帳にはもう誰だか憶えていない人の連絡先がいっぱいある。二度と見返さないだろう写真も沢山保存している。なのにスマホを買い替えるとそれらをクラウドにあげて、ひとつのメモリもこぼさないようにしようとする。結局何が大事な記憶か分からなくなっている」
祖母には、そんなことを憶えているのか、と驚かされたことも。
「物心ついてから憶えていることを記した〈記憶集〉を作り、祖母に"こういうことがあったよね"と答え合わせをしていったんです。ある時、"海で一緒に釣りをしたよね"と言ったら、祖母が"湖だよ"と言う。確かめてみたら本当に湖でした。自分がいかに忘れているか、記憶を改竄しているかに気づいて。それで、忘れていく母親と、思い出していく息子の物語が書けるのではないかと思ったんです」
認知症を患う母と一人息子の物語
実体験から出発することとなった本作。主人公はレコード会社で働く三十代の泉だ。妻が妊娠し、もうすぐ父親になる。そんな折、一人で自分を育ててくれたピアノ教師の母、百合子が六十八歳で認知症を患っていると判明。泉だけでなく百合子の視点も交えながら、改めて向き合う母と息子の物語が展開する。
「認知症を扱った小説といえば、有吉佐和子さんが一九七二年に発表した『恍惚の人』は身内が認知症になったら大変だと思わせる話でした。当時は実際にそういう印象だったんでしょうけれど、今は認知症患者が五百万人いて、もはや日常になっている。現代的なものにアップデートする必要があるとも思いました」
シングルマザーの家庭にしたことにも理由が。
「『恍惚の人』は肉親同士ではなく夫の父親を妻が介護する話で、その家族関係のずらし方が面白いとも思えた。でも今回は、濃い血縁関係で逃げ場がないものにしたかった。血が繋がっている肉親が思い出を忘れて違う人になっていく姿を見るのは耐えられない。母一人息子一人の家族ならなおさら辛いだろうと考えたんです」
そこで、多くのシングルマザーとその子どもに取材した。
「ある男性の話で印象深かったのは、母親に結婚すると伝えて喜んでくれるかと思ったら"やっと親子みたいなことができると思ったのに"と泣かれたそうです。母と息子というより、恋人みたいな感覚だなと思って。息子は息子で、父親の記憶がないからどうやってお父さんになればいいのか分からないという。それはそれで記憶というものに結びつく話だと思いました」
また、子どものエピソードが認知症患者と結びついた瞬間もあった。
「小さい男の子を連れたシングルマザーに取材した時、"大変だ、辛い"、"この子はすぐ迷子になるんですよ"と泣きだして。男の子を見るとずっとうつむいている。その時、あ、この子はわざと迷子になっているんだな、と分かったんです。母親が一生懸命自分を捜している姿を見て愛情を確認しているんでしょうね。それでふと、僕の祖母も認知症になってからよく一人歩きするようになったのも、愛情を確認したかったんじゃないかな、と」
もちろん、認知症の人たちにも多く会った。
「祖母のいるホームだけでなく、他に十か所くらいの介護施設を訪問しました。話しているうちに分かったのは、認知症の人って記憶が並列化しているんですよ。"すごく前の記憶"と"ちょっと前の記憶"が全部、"今"の中に入っている。そう考えると、彼らが一人歩きして迷子になる理由も分かる。買い物に行こうと駅のほうに向かっている途中で学校に遅刻すると思って道を曲がり、そういえば今日は〇〇さんがお茶しに来るって言ってたわ、と思い出した時にはもう知らない場所にいるわけです」
その気づきがあって、認知症ヴィジョンで書ける、という感触を得た。

「思うのは、『恍惚の人』が怖いのは相手がどうしてそんな行動をとるのか分からないから。分からないから怖い、怖いから逃げたい、逃げたいから放っておく。だから状況がどんどんひどくなる。だから、理解するって、大きいんですよ。認知症の人が一人歩きして迷子になることにも、ちゃんと理屈があるんだと分かれば怖くなくなる」
百合子が憶えているのは、大きな、重要な出来事、素敵な体験とは限らない。それはなぜか。
「それこそが書きたかったことだとも言えます。憶えているのはむしろ、残念な体験の思い出だったりしますよね。でも大勢で楽しい経験をしたことよりも、息子と二人で"残念だね"と話した体験のほうが貴重かもしれない。僕はずっと人間にとって何が幸せかを考えて書いてきましたが、記憶における幸福論として、そうした感覚を描きたかった」
また、人は遠い過去のことより近い日のことから忘れていくともよくいわれるが、
「まさにカバー写真がそれなんです」
という。使われている鈴木理策氏の写真は手前がぼやけ、奥には花々が映っている。
「僕は自分が描いた景色をすでに描いている人は絶対にいると思っていて。その答え合わせをするのが好きなので、表紙を撮り下ろしてもらうことはしないんです。それで使用する作品を探していた時にこの写真を見つけて、もう言いたいことを全部言ってくれている、と思った」
花の写真を選んだのは、もちろん『百花』というタイトルに合わせてのこと。
「花って枯れるじゃないですか。僕は造花があまり好きではないし、花は枯れるから美しいと思う。まさに、記憶もそうだなと感じます。それに、人が死ぬ時に持っていける記憶って百くらいしかないんじゃないかと思う。それで、このタイトルにしました」
記憶にまつわるものを盛り込んだ
親子関係の他にも、本作には記憶をモチーフとしたエピソードが多数登場する。たとえば泉の職場では、
「みんなスマホやノートPCを使って仕事をして情報を共有して、何も忘れてはいけないという強迫観念がある。クラウドにあげて共有するのが求められている。それが、あまり幸せそうには見えないんですよね」
天才的な女性歌手発掘の顚末も強烈だ。
「だいたいのシンガーソングライターってピークが短い。それで、"なんで前のようにいい歌が書けないんですか"って乱暴な質問をすると、ほとんどが"あの頃どうやって書いていたか思い出せない"と言うんです」
また、途中で挿入されるのは百合子の日記。過去のある出来事の真相が明かされるが、そこに阪神淡路大震災が関わってくる。
「東日本大震災が起きた時に、これまでの災害が世間的に上書きされた気がして、それが怖かった。僕なりに上書きされたものを掘り起こす作業がしたかった。それに日記ってどこか人に読まれることを意識して書くところがあって小説的。記憶を捏造して書く場でもあると考えると、認知症の人が見ている景色にも繋がると思いました」
日記の内容は、百合子の女としての一面がうかがえるものだ。
「僕は平気なんですが、母親の"女"の部分を見たくないという男性も多い。自分の母親に女というものが内包されているのを目の当たりにして、それでも血縁として離れられない関係の面倒くささと良さを書きたかった。泉の中では、母親に対しての愛情と、許せない気持ち、女としての彼女を見たくない気持ちが全部同じ力で引きあっているんです」
それでも百合子に上品さが漂うのは、著者の頭の中にモデルがいたからかもしれない。
「勝手に吉永小百合さんを当て書きしたんです。僕は吉永さんが好きで十代から現在までのフィルモグラフィも全部観ている。ご本人も少女のような部分と情熱的な女優の部分をどちらも内包されている方だと思うんです。加えて、認知症の方がホールスタッフを務める〈注文をまちがえる料理店〉に行った時、六十代の認知症の女性がピアノを弾いていたんです。その若さで認知症になったためか、もう少女みたいな方で。そのイメージを書いたところもありますね」
では、吉永さん主演で映画化したい?
「映画は観たいです。吉永さんに演じてもらいたいけれど、それは望み過ぎかもしれません」
これまで映像ではできないことを小説で試みてきた著者が、率直に映像化を望むとは意外な気もするが、
「書く前に映画を意識したわけじゃないんです。映画にするなら脚本を書いたほうが早いですから。ただ、今回、映像の人間としてではなく、小説家として書いたからこそ、書き終えた時に素直に映画で観たいな、と思ったんです」
もちろん、本作にいちばん影響を与えた人物といえばお祖母さんだ。彼女からは何かしら反応があったのかと聞くと……。
「発売の二週間前に見本ができたので届けようとしたら、その日に亡くなってしまいました。でもこの二年半、おばあちゃんのことを毎日考えていたので、後悔はないです。お棺に本を入れたのですが、花の表紙だし、百本分の花を入れたことになるのかな、とも思えて。こんなに清々しく亡くなった人を送ったのは、はじめてかもしれません」