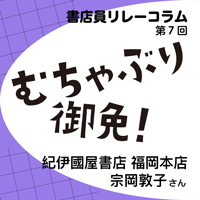私の本 第1回 若松英輔さん ▶︎▷03

新連載「私の本は、あらゆるジャンルでご活躍される方々に、「この本のおかげで、いまの私がある」をテーマに、本のお話をお伺いする企画です。
第1回は、批評家であり、詩人でもある若松英輔さん。貴重なお話を3回に分け、連載しています。最後となる今回は、あらゆる人にとって「書く」ことが重要であるというお話です。その理由とは?
「読む」こと、「書く」こと
「読む」「書く」というのは、人にとって根源的な営みです。
本当の意味で「書く」ことに出会ったのは、大学生の頃でした。
上京してまもなくの頃です。井上洋治神父が、毎週日曜日に自宅で行うミサに参加するのが、そのきっかけです。
そこには、カトリックだけでなくプロテスタントや仏教者、洗礼を受けていない人も集まり、遠藤周作や安岡章太郎の姿もしばしばありました。井上神父と遠藤周作は20代でフランス留学した時からの親友でした。
遠藤周作以外にも福田恆存、河上徹太郎、田村隆一、高橋たか子といった作家たちも時折、彼のもとを訪れていました。
作家が普通に存在している、そうした環境の影響もあって、大学にはほとんど行かず、作家の講演会にばかり足を運ぶようになっていました。
大江健三郎、開高健、井上光晴、佐多稲子などさまざまな作家の話を聞いた。
それにより文学は、生きた人間から生まれるということを実感として知ったのです。
中村光夫の葬儀で大岡昇平の姿を見たのも印象深い記憶になっています。
書物は実在する人間が書いている
若者は作家の姿を見るために、からだを動かしたほうがいいように思います。
言葉なんて交わさなくてもいい。
肝要なのは、書物は実在する人間が書いているというのを、身をもって知っておくことです。

その大学時代、小林秀雄を好んで読んでいました。
ある時、「これをあげる」と井上神父から小林秀雄の著作『常識について』を差し出された。「持っています」と言うと、「いや、この本は持っていないだろう」というのです。
本を開くと、そこには小林秀雄の署名がありました。
「河上徹太郎の葬式の時にもらったんだ。でも、これは君が持っていたほうがいいだろう」と、預けてくれた。
井上神父はもう亡くなられてしまったので、本はそのまま頂いた形になっていますが、当時は――今もそうですが――由来のある小林秀雄の署名は信じられないほどの宝物に感じられました。
その井上神父から、「小林秀雄が好きなら、井筒俊彦を読むといい」と薦められました。
哲学者としてすでに高名だった井筒俊彦の名すら知らなくて、そのまま紀伊國屋書店新宿店へ行き、『意識と本質』と『イスラーム哲学の原像』を買って読みました。
その時は、まったく内容はわかりませんでしたが、やがて井筒は、かけがえのない存在となり、彼に関する本を何冊も書くことになります。
編者として『読むと書く』という井筒俊彦のエッセイ集、そして彼の『全集』も出版しました。
代表作『意識と本質』で井筒は、中東やインド、中国や日本、さらにはヨーロッパなど生まれた国は別々ながら、同時代に「東洋的」視座をもって生きた詩人や哲学者、宗教者たちを描き出しました。
そして万物の根源的エネルギーである「コトバ」をめぐって論じたのです。
「存在はコトバである」と井筒俊彦は書いています。
万物は、言語を超えた意味のうごめき、すなわち、井筒のいう「コトバ」によって成り立っている、というのです。
SNSでつぶやいても、自分を知ることはできない
井筒俊彦は晩年、何を読み、何を書くかということではなく、「読む」あるいは「書く」という営為そのものへの思索を高めていきます。
「読む」「書く」というのは根源的な営みなので、呼吸のように、吸って吐いて、吸って吐いてというのを繰り返すものです。
しかし現代の人々は、吐く=書くことをしなくなり、過呼吸のようになっているのではないでしょうか。
確かに、「読む」よりも「書く」ほうが力が必要なので、うまくいかないことも多い。それで人々は書くことを止めてしまったのでしょう。
今、書く=吐くの代替は、人に話すことか、ブログやツイッターといったSNSがその現場になっています。
SNSも悪くはありませんが、真に書くという行為は、それにより初めて自分が何者かを知ること、つまりは自分の内心と出合うことです。
自分を知るということが、本当は一番大事なのです。
私たちは、SNSを見て誰が何をしているかなど他人のことは知っているけれど、じつは、自分のことを一番よく知らないのではないでしょうか。
書くことは、自分を知ること
ドストエフスキーは生活のためにも物を書きましたが、真の動機は書かざるを得ない、そうしなければ自分を保つことができなかったからです。
それは、私たちも同じです。
遺言を書くのもそのひとつの行為といえます。もしあなたが80歳まで確実に生きるなら、それは79歳のときに書けばいいと思うかもしれない。
しかし、人は今日、書く文章が最後にもなりうる。それが現実です。
だからこそ、書くことは、なるべく早く、今日からでも始めるほうがいい。
東日本大震災が私たちに教えてくれた、もっとも大きな教訓は、死は予期しないときに訪れるという、厳粛なる事実です。
近代は、動かない確かなものを築き上げようとしてきました。
しかし、それは幻想です。
「揺れる」のは地面ばかりではありません。私たちの内面はいつも「揺れている」。
自分のことばかりではなく、一番大事な人が病になったり、その人を喪ったり、親が要介護になることもある。そういった人生の揺れは、しばし、私たちの人生を飲み込んでしまう。
でも、このようにつねに動いていること、「動的」であるということが、生きていることの証しにほかならない。
「読む」はもちろん、「書く」行為は、人生の揺れに備えるためのものでもあります。
「書く」ことは揺れ動いている自分をまざまざと知ることであり、そして同時に揺れ動いている他者をまざまざと感じる営みでもあります。
揺れのなかで生き抜くためにも人は、もう少し、「読む」ことと「書く」ことに時間を費やしてよいように思います。
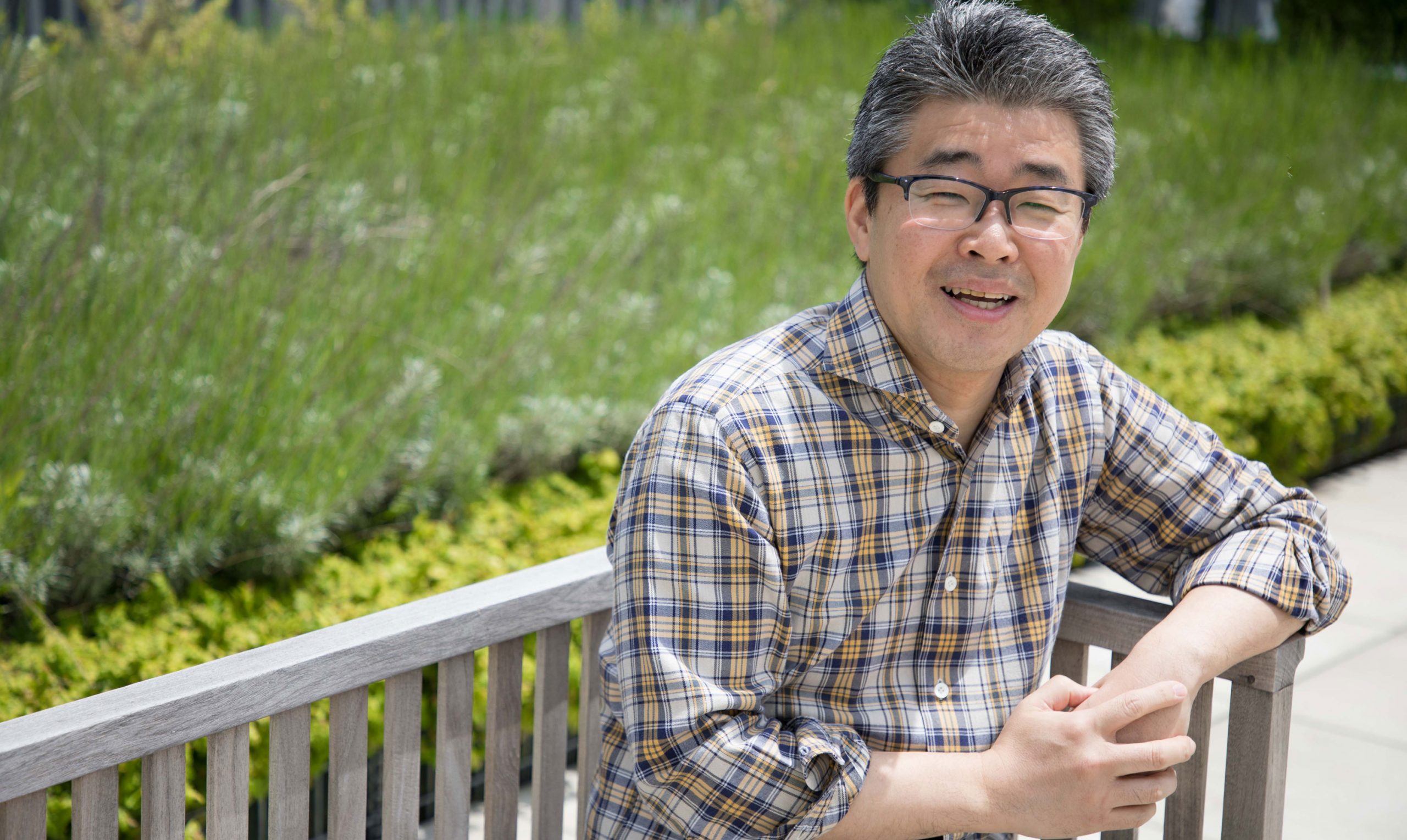
五年ほどまえから「読むと書く」という講座を行っています。
民藝の提唱者である柳宗悦は、博物館に収容されている芸術家の壺は確かに美しいけれど、無名の人が造った、私たちの日常に寄り添う器には、それとは別個の美しさがあるといい、それを「民藝」と呼んだ。
言葉も同じです。
芥川賞や直木賞作家だけでなく、言葉は誰もが持っていて、その言葉と日々暮らしていく。
「言葉の民藝」というべきものの存在を世に知らしめたい。
柳宗悦が器の世界で行ったことを、言葉でやりたいと、切に思っています。
前の記事はこちらからお読みいただけます
若松英輔さん▶︎▷01
若松英輔さん▶︎▷02