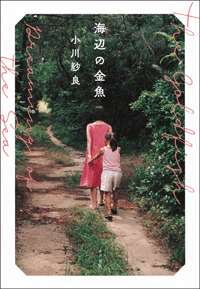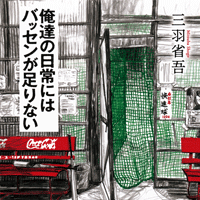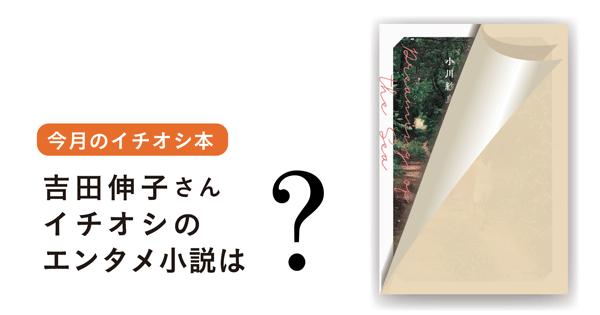今月のイチオシ本【エンタメ小説】
『海辺の金魚』
小川紗良
「星の子の家」、それが本書の主人公・花が暮らす施設の名前だ。「星の子の家」は、「親が病気になってしまった子、経済的な問題で家庭で暮らせなくなった子、身体や精神に深い傷を負った子」たちを預かる施設で、花は8歳の時にやって来た。それから10年、花が18歳の誕生日を迎えた日から、物語は幕を開ける。
その日、施設には新たに一人の少女がやって来る。晴海という、小学校二、三年生くらいのその少女に、花はうっすらと過去の自分を重ね合わせるのだが、晴海は頑なに心を閉ざしたまま、誰とも口をきこうとさえしない。翌日、家に帰ろうとしたのか、施設を抜け出した晴海を最寄駅で保護した花は、以来少しずつ晴海との距離を縮めていく。
花の母親は、ある事件を起こして収監されていた。母親の弁護士からは面会を促されてはいるものの、応じるかどうか、花は心を決めかねている。
花の母親は住んでいた地域の夏祭りで、かき氷に農薬を混入し、人々の命を奪っていた。開発事業に絡んだ土地の問題があったとはいえ、それは、許されることではなかった。
「星の子の家」に預けられている子どもたちの中で最年長の花は、翌春には施設を出て行くことになっている。施設というある意味閉ざされた世界で生きてきた花にとって、社会に出て自立することはなかなかイメージできない。それでもここを出ていくことこそが、自分の人生の第一歩になることを花はわかっている。
擬似家族のような「星の子の家」に暮らす子どもたちの、埋められない寂しさや屈託。花の目を通して描かれる子どもたちの姿に、胸がきゅっとなる。
温もりに満ちた、けれどかりそめの家族と、本物でありながら、心身ともに傷つけられてしまう家族。子供にとって、そのどちらが正解なのか。その答えを描かないところに、作者の誠実さが、ある。
作者の小川さんは、役者であり映像作家でもある方だ。本書は、同タイトルの小川さんの長編初監督作品を、自身で小説化した作品である。佇まいは静かなのに、読む者の心にくっきりと跡を残す。
(文/吉田伸子)
〈「STORY BOX」2021年8月号掲載〉