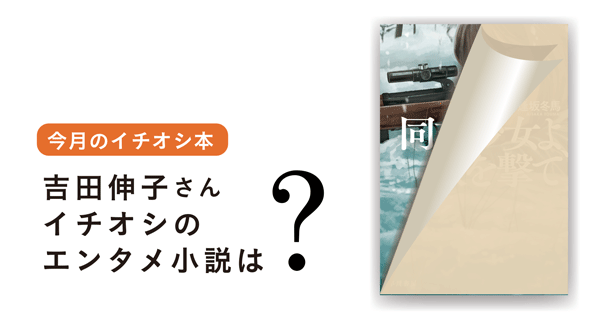今月のイチオシ本【エンタメ小説】
『同志少女よ、敵を撃て』
逢坂冬馬
「史上初、選考委員全員が5点満点」が話題の、第11回アガサ・クリスティー賞受賞作は、独ソ戦さなかの一九四二年、モスクワ近郊にあるイワノフスカヤ村から幕を開ける。
母親のエカチェリーナとともに、狩りをして暮らしていたセラフィマの日常は、ある日突然断ち切られる。ドイツ兵によって、村人は皆殺しにされ、エカチェリーナはセラフィマの目の前で撃ち殺されたのだ。間一髪のところで、赤軍に命を助けられたその日、セラフィマの少女時代は終わりを告げた。
母親と故郷を奪った敵への復讐。その一心でセラフィマは、狙撃兵となるべく中央女性狙撃兵訓練学校の生徒となり、女性だけの狙撃小隊の一員として、独ソ戦の只中に身を投じていく。
ウラヌス作戦、史上最大の市街戦とされたスターリングラード攻防。戦争の最前線での狙撃兵としての、激烈な日々を、セラフィマはくぐり抜けていく。斃れていく仲間たち、敵狙撃兵との心理戦、裏切り……。
どの場面も臨場感に溢れ、張り詰めた緊張感に、読んでいるこちら側まで息が詰まるほど。立ち込める硝煙の匂いまでもがリアルに伝わってきて、これが新人賞応募作とは思えない。その完成度の高さに目を見張る。
けれど、本書が真に素晴らしいのは、迫真の戦闘シーンにあるのではない。狙撃兵として頭角を現していくセラフィマを描くと同時に、もしセラフィマが平和な時代に生まれていたら、と読者に想起させる力があるところだ。
成績優秀で、大学進学を決めていたセラフィマ。ドイツ語に堪能で、「戦争が終わったら、必ず外交官としてドイツとソ連の仲を良くするの」と語っていたセラフィマ。歩めたはずのもう一つの青春が輝けば輝くほど、狙撃兵として生きるしかなかった現実の過酷さが際立つ。
本書を読みながら、スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチの『戦争は女の顔をしていない』を想起される読者も多いと思う。そんな読者には、本書のラストがとりわけ深く胸に残るだろう。
(文/吉田伸子)
〈「STORY BOX」2021年12月号掲載〉