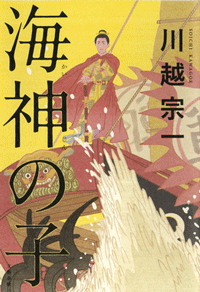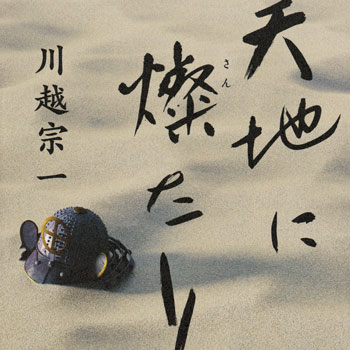川越宗一さん『海神の子』
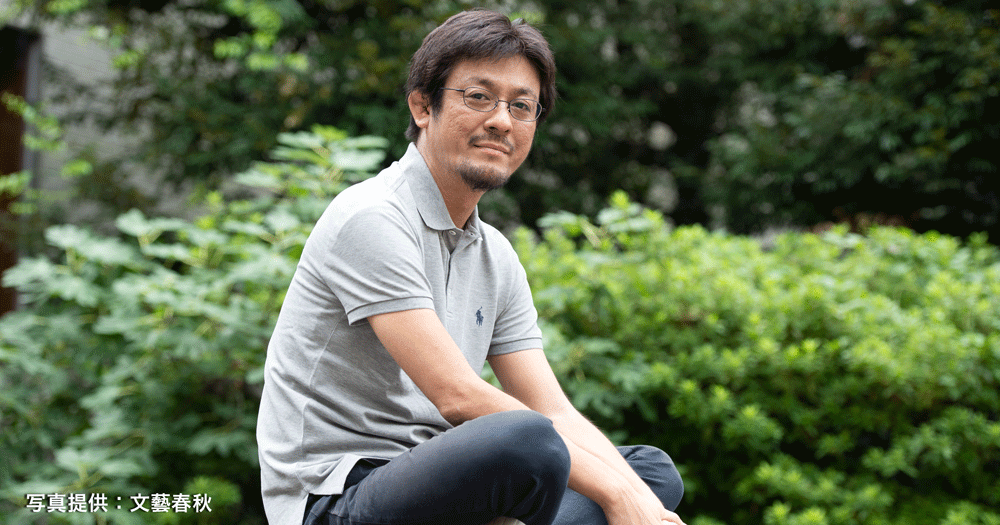
架空のキャラクターであっても〝自分の人生を生きてほしい〟
江戸時代、東シナ海では各国から集まった海賊たちが幅を利かせていた。そこから登場したのは、あの英雄─。川越宗一さんの新作『海神の子』は、台湾鄭氏の祖である鄭成功の生涯を、架空の人物も交えてダイナミックに描く長篇小説。実は最初に興味を引かれたのは、彼ではなく、彼の母だったという。
新作の中心人物は英雄・鄭成功
直木賞受賞作『熱源』で、北の大地を舞台にアイヌとポーランド人の人生が絡まり合う物語を生み出した川越宗一さん。待望の新作『海神の子』の主な舞台は、ぐっと南下し、東シナ海だ。中心となるのは鄭成功。中国が明から清に変わろうとする時代、最後まで抵抗を続けて台湾に渡った人物である。日本では近松門左衛門の浄瑠璃「国性爺合戦」のモデルとしても知られている。
「デビュー作の『天地に燦たり』で最後に沖縄が舞台になるんですが、本当はその時に琉球や中国、日本や東南アジアの人たちが船で行き来していたことを盛り込みたかったんです。あの小説ではそこまで入れられなかったんですが、いろんな人が海で繫がっていた世界は書いてみたかった」
最初はその思いを短篇に反映させた。といっても鄭成功の話ではない。
「ウィキペディアの歴史に関する項目などのリンクを片っ端から見ていくという、趣味とはいえない趣味がありまして(笑)。それで、鄭成功の父親が海賊で、母親は日本人だったと知ったんです。海賊と結婚するなんて、そんな出会いはなかなかないなと思い、鄭成功のお母さんの話を書きました」
その短篇が、本作の冒頭部分になっている。江戸の鎖国の時代、国際貿易港だった平戸。両親のいない松は親戚夫婦の商家でこきつかわれていた。しかしその家は借金の返済が滞っており、松が15歳のある日、雇われた海賊に家が襲われて夫婦は殺される。松は妓楼に売られそうになり抵抗し大暴れ、それを見て気に入った海賊の船頭の思斉は、彼女に陸か海を選べと告げる。松が咄嗟に選んだのは、海だった─という内容だが、そんな史実はない。
「『海神の子』の序章は、はじめての短篇だったので必死に書いているうちに史実から離れたオチになりました。その後に書いた『熱源』で『調べすぎ』だという批判もあり、続きを書くときは史実にとらわれすぎず自由に書こうと心掛けていました。実際の鄭成功の母親のマツについては確定的な史実がないんです。一般的に知られているのは、海賊の鄭芝龍と結婚して子どもを二人産んで平戸で暮らしていたものの、後に鄭成功になった息子から呼ばれて明に行ったら戦に巻き込まれて命を落とした、というストーリーです」
最初は、この松の話を含めた短篇集にするつもりだった。
「鄭成功や周囲の人間を主人公にした短篇をいくつか書くつもりでした。でも鄭成功の話を書き始めたらえらく長くなってしまって。それで、彼を中心とした長篇にすることにして、今の形になったんです」
架空の母親は女海賊
海の上で生きる松は二人の子を産み、子どもたちを平戸の知人に託す。やがて海賊の長となった彼女は、長男の福松を海へと連れていく。ちなみに福松は、鄭成功の幼名だ。そして物語は福松の視点へと移り、鄭成功となり、国姓爺と呼ばれるようになり、清の脅威に屈せず明を復活させようとする彼の冒険と闘いが描かれていく。
海賊集団には出身国も経歴もさまざまな人間がいるが、福松もその一人だ。以前、国や文化の「あわい」に生きる人たちに興味があると語っていた川越さんだが、これはまさにそうした人々の物語。のちに福建で学んで科挙に合格し、明が滅んだ後も復興させようと抵抗し続ける福松は、「あわい」に生きる人たちの居場所を求めて闘っていく。ただ、劣勢になっても抵抗し続ける姿は危うくも感じられる。
「彼が実際にどういう人だったのかは分かりませんが、僕が書いた福松が戦争を続ける理由は、自分の居場所が欲しいという思い。その理想に他人を巻き込んで頑張っている。表面上いい奴に書いてはいますが、それってエゴですよね。それに、そもそも海賊はどこにも居場所のなかった人が集まってできた集団ですから、その人たちに対する受け皿はひとつではないだろう、とも思います。でも、福松がもがいているうちに、同じ思いの人たちが彼についてくるというイメージがありました」
では、女海賊として派手に立ち回る一方、息子に対してそっけないが秘めた母心を持つ松に関してはどのようにイメージしていたのか。
「最初に考えたことがあって。マツは鄭成功に呼ばれて明に行き戦に巻き込まれて死にますが、戦前の本に〝死に様が立派だった。日本婦人の鑑だ〟というような記述があるんです。それが個人的には、あまりしっくりこなかったというか。別に日本婦人の鑑になりたくて海を渡ったわけじゃないだろう、と思うんです。だから、もうちょっと自分の人生を生きている人にしたかった。まあ、派手な話にするために女海賊を出そうという考えもありましたが」
確かに、これは松に限らず、なんとか自分の人生を自分で決めて生きていこうとする人たちの話でもある。たとえ過ちを犯しても「生きて正せ」と諭されるなど、死ぬことが立派だという考えを否定する場面などから、「生きよ」という思いが力強く伝わってくるのだ。
「それは書きながら意識していました。一作目にも二作目にも共通していますが、〝生きる〟とはどういうことかが、僕が考えたいところでもある。物語を書いていると自己犠牲のシーンは書きやすいし感動させやすいと感じますが、いつも思うのは、架空のキャラクターであっても〝自分の人生を生きてほしい〟ということなんです。命を投げ出すことが、命より大事だとは書きたくないという気持ちがあります」
クセがありすぎる登場人物たちの魅力
これは、福松と松、二人の話でもある。だが、成長した福松は、やがて松と意見を違えることに。
「親の視点から始まって子どもの視点に移るので、子離れ、親離れのシーンは話のキーになると思っていました。親子だからといって理解しあえるとも、応援しあうとも限らない。それに、国姓爺という名前をもらったというとポジティブな達成の話に感じますが、この名前を背負う辛さや重さも描きたかった」
海賊や明国の人々の暮らしも丁寧に描写され想像しやすく、合戦の様子なども迫力が伝わってくる本作。たっぷりと創作も盛り込まれるが、鄭成功の闘いの軌跡や当時の世界の状況は史実にのっとっている。たとえば、兵を引き連れて遠征に出かけたものの食糧不足で窮地に陥る、などという経緯は史実通りだが、そこから、その裏に誰のどんな思惑があったのかを想像を膨らませて描き込み、さまざまな陰謀や裏切りが絡まり合うスリリングな展開になっている。
「人物に関して脚色ばかりなので、舞台世界はちゃんとしようと考え、僕なりに調べて書いたつもりです。出版社の人に資料集めを手伝ってもらったり、言葉も詳しい方に監修してもらったりしました」
そもそも、鄭成功の周辺にいた人物については、名前くらいしか残っていない人が多いという。つまり架空の人物はもちろん、実在したと思われる人物についても、想像で人格を形成していくしかなかった。これがみな実に個性豊かで魅力的。たとえば、松の影武者である蛟。架空の人物で、かなりクセのある人間だが、彼が海賊になるまでどんな過酷な人生を辿ってきたかも盛り込まれるため、彼の国に対する怒りと不信感は納得がいく。単なる身勝手な人間とは思えないのだ。
「苦労したキャラクターなのでそう言ってもらえると嬉しいです。今まで、はりきって悪いことをする人をあまり出してこなかったので、書いていて楽しかったです(笑)。背景の説明なく強いキャラクターを作れたらベストなのかもしれませんが、僕はついつい、生い立ちを考えてしまいますね」
クセがあるといえば、福松が科挙を受験するために教えを乞う銭謙益。彼は実在した文人だ。本作では、がめつい上に女遊びが好きだが、実は政治的理念を持っている人物として描かれる。
「彼も、書いていて楽しかったですね。当時の中国って、いろんな人がいたんです。腐敗しきって賄賂だらけの社会の中でそれに染まる人もいれば、命がけの忠誠心を持っていた人もいた。それに、当時は妓楼通いはたしなみだと思われていた面もある。そうした部分を、きゅっと集めた人物になりました」
また、福松の妻となる友も強烈な印象を残す。縁談を持ち込まれて気乗りせずにいる福松に対し、「私と結婚しなさい」と詰め寄るような女性である。
「この人も資料に名前しか残っていなくて。この人を書くにあたって、纏足に触れたかったところがあります。あれは女性にとって大変な風習だったから今はもうないわけですが、当時は美しくなるための手段だといってポジティブにとらえていた女性もいた、ということを研究している人がいて。野蛮な風習だということだけ書けば分かりやすいですが、自ら纏足を選んだ人として書こう、と思いました」
彼女もまた、自分の人生を自分で選び、生きようとした人間として描かれるのだ。
現代を知るために過去を書く
エピローグ的な場面で、「国性爺合戦」に言及される箇所がある。もちろん、浄瑠璃の内容は史実とも本作ともまったく異なるわけだが、だからこそあえて加えたという。
「あの浄瑠璃も、この小説も、さんざん脚色されているんですよね。後に伝わる話って、人が見たいような世界になって語り継がれていくものであって、本当のことは、当時生きていた人しか知らないんだ……という感じのことを入れておきたかったんです」
そうであっても、史実と虚構を織り交ぜてここまで読ませる、壮大なスケールの物語に仕上げる筆力はさすが。
「本当は架空の人物のほうが書きやすい気はするんです。でも僕のいたらないところで、荒唐無稽な話でも〝いや、史実にあるんです〟というと話が通りやすいというか。そこに頼ってしまっているところがあるかもしれません」
現在は、鄭成功の時代の少し前、ローマに渡ってカトリックの神父になったものの、帰国してもキリスト教は禁止されていて……という実在の日本人の話を地方新聞に連載中。やはり今後も、時代小説を書いていくのだろうか。
「時代小説のほうが着想を得やすいのは確かですが、よくよく考えたらそんなにこだわっていません。僕が興味があるのは現代なんです。現代がどうしてこうなったのかを知るために、今は過去を見ているんです」
川越宗一(かわごえ・そういち)
1978年鹿児島県生まれ、大阪府出身。龍谷大学文学部史学科中退。2018年『天地に燦たり』で第25回松本清張賞を受賞。19年刊行の『熱源』で第162回直木賞を受賞。
(文・取材/瀧井朝世)
〈「WEBきらら」2021年9月号掲載〉