著者の窓 第9回 ◈ くどうれいん『氷柱の声』
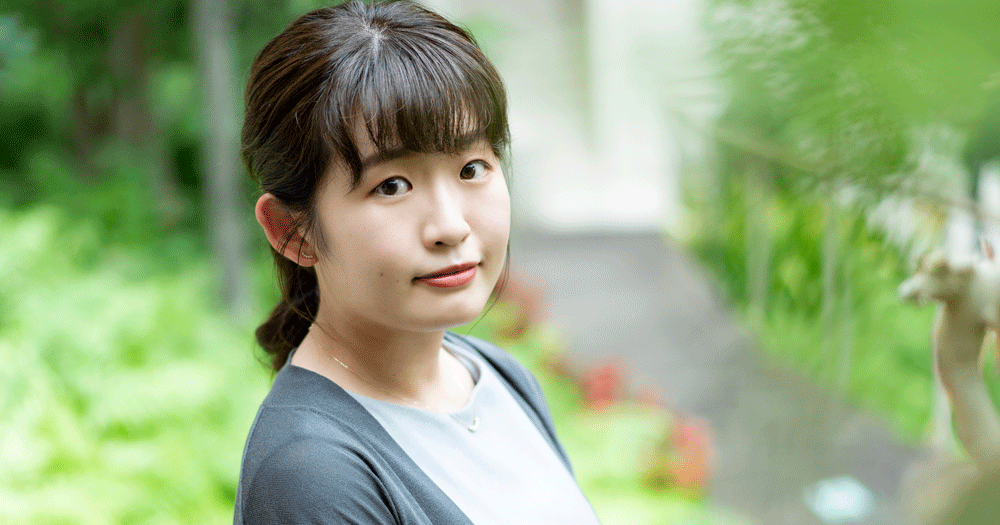
エッセイ集『うたうおばけ』、歌集『水中で口笛』などが話題の作家・くどうれいんさんが、初の小説『氷柱の声』(講談社)を発表しました。東日本大震災発生時、盛岡の高校生だった主人公・伊智花の目を通して、人びとの経験や思いを紡いだ連作小説です。震災報道では触れられることのない、さまざまな葛藤や悩み、苦しみ。語れないと思っていたこと、言葉にできなかったこと──。いくつもの「声」を瑞々しい文体で描き、第一六五回芥川賞候補として話題を呼んだ今作品について、くどうさんにお話をうかがいました。
いつか書こうと思っていた、あの気持ち
──『氷柱の声』は「群像」二〇二一年四月号に掲載された作品です。歌人・エッセイストとして活躍されるくどうさんにとって初の小説ですが、執筆の経緯を教えていただけますか。
「群像」の編集長から「書いてみませんか」と声をかけていただいたのがきっかけです。東日本大震災に関する、エッセイではない二十枚くらいの創作はどうかと。なので最初は五人くらいの同世代の声を架空の日記のような形で並べる短編にしようと考えて書き進めました。ひとつめのパートを書き終えた時点でもう四十枚になっていて。プロットもないまま最後まで書き終えたら中編小説になっていました。どういう形になるのか分からない小説をぎりぎりまで待ってくださった編集部には感謝しかありませんね。
──二〇一一年から二〇二一年までを舞台に、東日本大震災をめぐるさまざま思いや経験を切り取った連作です。震災については高校生の頃から「絶対にいつか書く」と決意されていたそうですね。
わたしは二〇一一年の春、岩手県盛岡の高校一年生でした。大きな揺れに見舞われて、電気や水道が止まったものの、県の沿岸部で大変な思いをされた方々に比べると被害は微々たるものです。この「被災県在住だが被災者とは言えない」という自分の立場が、震災について語るのをためらわせました。関東の人からは大変でしたねと同情される一方、沿岸部の人に対しては、何も失っていなくてごめんなさい、という気持ちになる。いわゆる「震災もの」の作品では描かれることのないもやもやした思いを、自分に書く資格はあるのか、と悩んだり、書きたくなったり、その繰り返しで。そのための機会を「群像」が与えてくれた、という感じです。
──東日本大震災を経験した岩手、宮城、福島の二十代に取材し、その率直な「声」を作品に生かされたそうですね。
震災について「言えなかったこと」「言うほどじゃないと思っていること」を聞かせてくださいとお願いしました。取材といっても一度はお話ししたことがある方ばかりなので、それほどあらたまった雰囲気ではなくて、お互いマグカップを用意して、「元気だった?」とオンラインの Zoom 越しにおしゃべりしたという方が近いですね。登場人物にはモデルになった方がいますし、お話ししてもらったことは作品に取り入れていますが、あくまでフィクションとして発表しているので、書かれていることにはわたしが責任を持ちたいと思っています。
──冒頭の「滝の絵(二〇一一)」という章は、美術部の活動に打ち込む高校生・伊智花の物語。震災当時、盛岡の高校生だったという伊智花のプロフィールはくどうさんと重なります。
伊智花は自分の経験がいちばん投影されているキャラクターですね。特に震災発生直後、彼女が自宅の周辺で目にした光景は、わたしの経験をほぼそのまま書いています。一口に震災体験といっても、あの時どこにいたかで経験したことが変わってくるので、伊智花は盛岡出身ということにしました。ちなみに高校時代、美術部にすごくいい油絵を描く友だちがいて、その子がキャンバスに向かう時、背中から出ていたオーラみたいなものを思い出しながら、伊智花を描きました。何かを作り出す人のすごみ、みたいなものを再現できたらいいなと思いました。
評価されているのは作品か、事実か
──絵で被災地を励ますという企画に、ニセアカシアの絵を出品し、高い評価を得た伊智花。彼女は繰り返される「絆」「がんばろう」というフレーズに違和感を覚えます。
ここは自分でもアンビバレントな気持ちがあるんです。「絆」「がんばろう」なんて白々しいと思う一方で、津波で家族を亡くされた同世代の人が「やっぱり絆が大事なんだ」「毎日感謝して生きよう。前を向いてがんばろう」と言っているのも聞いていますから。絆というメッセージに嘘くささを感じるのは、自分が何も失わなかったからなのかもしれない。そこは今でも揺れています。でも絆や感動は自発的に湧いてくるものであって、外から押しつけるものではないですよね。高校時代、被災地のために何度も千羽鶴を折ることを求められましたが、それよりも被災者のためになることがあるのではないかと疑問に思っていました。

──震災の年に開催された県の絵画コンクール。最優秀賞に選ばれたのは津波で家族を亡くした女子生徒の、瓦礫と双葉を描いた作品でした。渾身の一作を出品しながら優秀賞に留まった伊智花は、言いようのない悔しさを覚えます。
似たようなことは小学校の作文コンクールでもありますよね。文章が上手いかどうかではなく、どれだけ大変で感動的な体験をしたかを競うコンテストになっているような気がします。わたしの小学校時代の担任は「思ったことをなんでも書きなさい」と言ってくださる先生で、わたしは文章を書く楽しさを知りましたが、何度コンクールに出品されても受賞はできませんでした。受賞するのは決まって飼い犬が死んだとか、病気の友だちを助けたといった感動のストーリーで、文章そのものが評価されているわけじゃない。そういう疑問を子どもの頃から感じていました。
──東日本大震災に関する作品では、いっそう悲しいエピソード、感動のドラマが求められているところがある気もします。
石巻出身で歌人仲間の近江瞬さんに「継続的支援が大事と書きながら続けば報道価値はなくなる」という短歌がある。この歌のことをよく考えます。とはいえ誰かを悪者扱いしたいと思っているわけではないんです。わたしもこの作品のための取材をしていて、ついこうあって欲しいというストーリーに当てはめる聞き方をしてしまい、反省したことが何度もあります。人の話をフラットに受け入れるというのは難しいな、とあらためて思います。
〝何も失っていない人〟もまた傷ついている
── やがて伊智花は仙台の大学に進学。二歳年下の医大生・トーミからは「震災という大きな物語」に人生を奪われたという嘆きを、恋人の中鵜からは「何も失っていない」ことへの罪の意識を、ふとした瞬間に聞くことになります。
世の中には他者の痛みを受け流せる人と、それができない人がいます。中鵜のエピソードでは、そういうグラデーションのようなものを描きたいと思いました。他者の痛みをまるで自分のことのように感じ、ボロボロになるまで苦しんでいる人は、果たして何も失っていないことになるんでしょうか。〝失っていないようなものだ〟とは言いますが、決して無傷ではないと思うんです。でも、そういう苦しさを口にする人はあまりいません。
──旅だっていくトーミと食べたザボン、伊智花が職場の先輩セリカと食べた鴨しゃぶなど、それぞれのエピソードには印象的な食べ物が登場します。
美味しいものが好きなんです。全体のプロットは決めずに書いているんですが、ここでザボンが出ます、ここで鴨しゃぶを食べます、といった細部だけはあらかじめ決まっていました。こういうディテールが展開や台詞を連れてきてくれることも多いですね。つらい心情を告白する場面が多いので、せめてここは美味しいものでも食べながら、という思いもありました。お話を聞いた皆さんとご飯が食べられなかった悔しさを、小説の中で叶えたかったんです。
──「エスカレーター(二〇一六)」は、客のいないデパ地下のエスカレーターから、三月十一日の黙祷を連想する、というごく短いエピソード。印象的なシーンをさっと切り取った、短歌のような味わいのある章でした。
まさに、おっしゃるとおりです。わたしは「人がいるかぎり電気があるかぎり永遠にのぼりのエスカレーター」という、三月十一日の黙祷をモチーフにした歌を詠んでいるんですよ。デパートにいた全員が黙祷を捧げている中で、エスカレーターだけが音を立てて動いていました。数日間電気が止まった体験をしていることもあって、忘れがたい光景だったんです。それを静物画のように、連作の中に収めてみました。ちなみに盛岡では三月十一日午後二時四十六分になるとサイレンが鳴って、ほとんどの人が黙祷します。東京でもおんなじだといいんですが。今年は会社の屋上で、海の方を向いて黙祷しました。

──最終章「桜(二〇二一)」は就職した伊智花の転機を描いたエピソード。タイトルにある〝氷柱〟が春の訪れを感じさせる場面とともに、効果的に描かれています。
『氷柱の声』というタイトルだけは早くから決まっていて、そのイメージに導かれるように物語を書き進めました。東北の氷柱は太くて、荒々しくて、かっこいいんです。強さやきらめきみたいなものを感じさせてくれる存在です。東日本大震災を詠んだ短歌のモチーフとして使うことも多いですし、東北への思いを託しやすい言葉でした。単行本の装丁をしてくださったのは同郷の名久井直子さん。氷柱のイメージを見事に形にしてくださって、装丁ってすごいなあと感動しました。
誰もが震災後の日常を生きている
──本作は第一六五回芥川賞候補となりました。初の小説が反響を呼んだことについて、くどうさんはどう受け止めておられますか。
編集部からは「この作品は丁寧に、誠実に届けていきたい」と言っていただきましたし、わたしもそうあってほしいと願っています。なので正直言って、身構えてしまうところはありますね。誤解なく届いてくれるだろうかと。取材をもとに書いた作品ですし、作品をしっかり守るというか、自分が書いた言葉に責任を持ち続けたいとも思っています。もちろん多くの方に届いてほしいので、話題にしていただくのはありがたいです。
──「語れないと思っていたこと」や「言葉にできなかったこと」を綴った本書が、東日本大震災を経験した読者にどう受け止められるのか気になります。
内陸部にお住まいの、わたしと近い境遇の方からは「これまで震災については見ないように、考えないようにしてきたけど、この作品を読んだことで気持ちが変わりました」との感想をいただいて、嬉しく思いました。大きな被害に遭った沿岸部の方は、自分も失ったものについて語りたい、と感じてくださったそうです。それぞれに体験や思いがあり、一口に被災経験といっても一様ではありません。わたしの小説がそれを語り始めるきっかけのひとつになれば嬉しいです。
──そして本書は東北以外の読者にとっても、決して無関係な物語ではありません。本書「あとがき」でお書きになっているように、誰もが震災後の世界を生きているからです。
この小説は高校生のときからずっと抱えてきた感情を、自分で理解し、納得するために書きました。誰かを励まそうとか、救おうと思って書いたわけではないんです。東北在住かどうかにかかわらず、東日本大震災が起こったタイムラインに生きているわけですから、すべての人に関係がある小説だと思いますし、いわゆる「震災もの」ではないとも思っています。そもそも「震災もの」というジャンルは成り立たないのではないでしょうか。すべての作品は震災から今日までずっと続いている、あなたやわたしの日常の物語なんです。
くどうれいん(工藤玲音)
1994年岩手県盛岡市生まれ、同市在住。著書に『わたしを空腹にしないほうがいい』(BOOKNERD)、『うたうおばけ』(書肆侃侃房)、『水中で口笛』(左右社)、『プンスカジャム』(福音館)、共著に『ショートショートの宝箱』(光文社)がある。
(インタビュー/朝宮運河 写真/藤岡雅樹)
〈「本の窓」2021年9・10月合併号掲載〉


