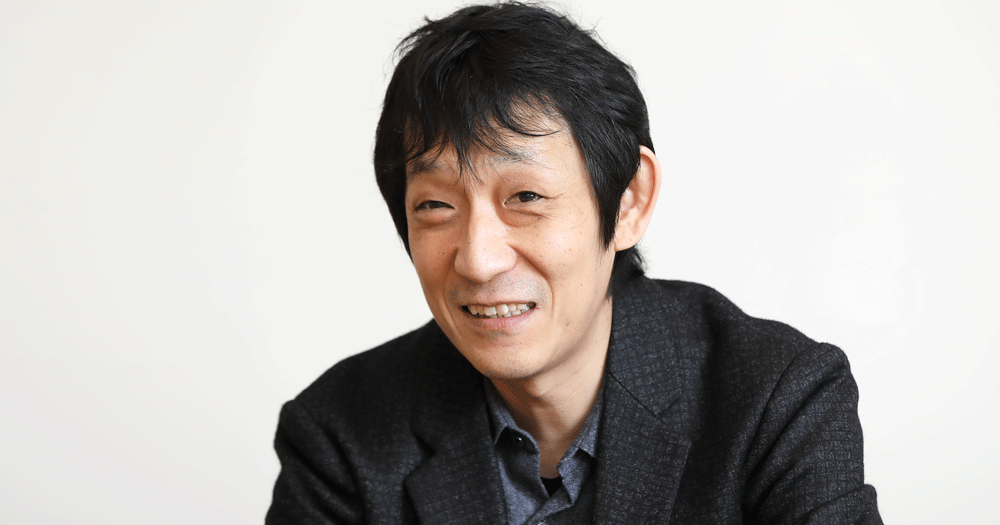薬丸 岳さん『告解』
現代社会における罪と罰のあり方を追求し続けてきた薬丸岳が、最新長編『告解』で新境地へと踏み出した。
ひき逃げ殺人事件を題材にした本作は、二〇〇五年のデビュー以来初めて、加害者本人を主人公に据え、その内面にフォーカスを当てたのだ。執筆中は、苦難の連続だったと言う。
二十歳の大学生・籬翔太が、バイト仲間と居酒屋で痛飲している場面から物語は始まる。雨脚が強まるなか埼玉北部にある実家へ深夜に帰宅すると、恋人の綾香から携帯にメールが届いた。『直接会って話がしたい』。『今から?』。『今すぐに会いに来てくれなければ別れる』。翔太はあえて返信せず、突然アパートを訪問して驚かせようとたくらんで車に乗り込む。飲酒もしており、免許を取ったばかりで雨の日の運転は初めてだったにもかかわらず。すると、ある交差点に差し掛かった時、前方不注意で何かを轢いた。〈雨音をかき消すようなギャーという奇怪な音が耳に響く〉。自分が轢いたのは人だと知りながら、アクセルペダルを踏んだ──。
ひき逃げ死亡事件の加害者である籬翔太と、被害者の配偶者である八十四歳の法輪二三久とその家族、双方の視点をスイッチしながら物語は進んでいく。
「僕がこれまでに書いてきた作品は、事件や犯罪に巻き込まれてしまった被害者側の人々か、あるいは加害者の周囲にいる人々を主人公にしてきました。いつか加害者本人を視点に据えた話が書きたい、きっとそれは勝負作と呼ばれる作品になるだろうという思いは以前からあったんです。ただ、このタイミングでそういう作品を手掛けることになったのは、まったくの偶然でした。ある晩、ベッドに入って眠りかけていたら、突然『告解』のお話のイメージがブワーッと頭の中に流れてきたんです。おおまかなストーリーはもちろん、台詞やシーン、細かい描写なども明け方ぐらいまで流れてきて、それをずーっとメモに取りながら眠れない夜を過ごしました。今年で十五年になる作家人生の中で、初めての体験でした」
驚きの創作秘話だ。薬丸には幾度となく取材をしているが、中心となる事件や犯罪が、現実に起こったとしても決しておかしくないものだと感じられるようになるまで、物語のラフスケッチを何度も何度も引き直す人なのだ。
「もともとは別の作品を書く予定だったんです。そちらの構想を進めていた頃、中軽井沢で一人暮らしをしていた父親がインフルエンザで入院したんですね。持病も進行しており生還は難しい状況で、できるだけ一緒にいられる時間を設けようと、連載以外の仕事は一旦休止しました。三ヶ月ちょっとで亡くなってしまったんですが、父は厳格でありながらも優しい、僕の価値観の多くを培ってくれた尊敬できる人だったので、茫然自失の日々が続いてしまっていた。そんな時に、あの〝ひと晩〟が訪れました。書き殴ったメモを改めて見返すと、これこそ今の自分が書くべきものだと感じられたんです。今まで書いてきた罪と罰の問題に新たな角度から向き合えると思いましたし、僕自身の中に渦巻いて消えずにいた、亡くなった父に対する〝まだいろいろな話がしたかった。あなたのことをほとんど何も知らなかった。もっと自分には何かできることがあった〟という後悔や罪悪感も、作品の中に込められるんじゃないかと思ったんです」
司法では裁かれないような心の中で感じる「罪悪感」
本作の実質的な主人公はひき逃げ死亡事件を起こした籬翔太だが、彼の直接的な「加害」の光景は、プロローグのわずか五ページで描かれるにとどまっている。その後の物語で描かれていくのは、「贖罪」だ。しかし、彼がその心情に辿り着くまでの道のりは平坦ではない。翔太は裁判において、「人間を轢いたとは思わなかった」「こちらは青信号だった」と容疑を一部否認したのだ。裁判ではその主張が退けられ、懲役四年十ヶ月の厳しい判決がくだされる。その一連の経緯を、翔太の心情描写を重視しながらドキュメントしていく。
「今まで僕が書いてきた殺人にまつわる話は、加害者は自分とは違う特別な人間性の持ち主だなとか、自分はここまでの状況にはいかないだろうなと思いながら、いわば別の現実の話としてみなさん読んでいたと思います。ただ、『告解』で描かれた事件に関しては、誰しもがいつ何どき同じような状況に陥ってしまうかわからない。車を運転している人間であれば、誰だって死亡事故の加害者になり得ます。車を持っていなかったとしても、自転車でも十分に起こり得る話ですよね。でも、そのリスクを頭の片隅においてハンドルを握っている人は果たしてどれぐらいいるのか。もし事故が起こっても翔太と同じ言動を自分は絶対にしない、と言い切れる根拠はどこにあるのか」
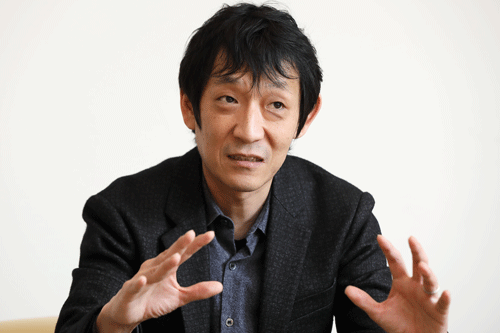
翔太のずるさや身勝手さ、弱さは、彼の中だけにあるものではない。だからこそ、ページをめくる手が止まらない。
「人間は誰しも大なり小なり、何かしらの罪の感覚を持っているんじゃないでしょうか。例えば被害者の夫である法輪二三久は、風邪を引いた自分のために妻がロックアイスを買いに行った、そのせいで妻は事故にあってしまった。翔太の恋人の綾香は、自分がメールをしたせいで翔太に運転させてしまった、と思っている。司法では裁かれないような、自分の心の中で感じる罪悪感と、良心についてのお話になったんじゃないかなと思っています」
物語が真のスタートを切るのは、翔太が刑期を勤めあげて日常に戻ってきたところからだともいえる。綾香と再会し新しい生活を始めた翔太は、過去と向き合うことから逃げているがために、いくつもの壁にぶち当たる。その一方で、事件から五年が経ち八十九歳になった法輪二三久が、翔太のもとへと接近してくる。「やらなければいけないことがあるんだ」と、不吉な言葉を口にしながら……。やがて被害者家族と加害者との間の、いまだかつてない関係性が描かれることとなる。
「刑期をまっとうすることで法律的には〝罪は償った〟とされますが、本当にそうなのでしょうか? 司法うんぬんではない部分での償いの気持ちを持っていなければ、その後の人生を誠実に過ごすことなどできないのではないのか。翔太には試練を与え、法輪二三久の息子である昌輝にはある種の使命を与えました。そして、フィクションだからこそできるやり方で、両者を出会わせてみたいと思ったんです」
最後の二行は初稿から一切手を加えていない
本作のもう一人の主人公である法輪二三久は、認知症を患っている。「認知症者の内面」を書くという試みも、作家にとって初めてのチャレンジだった。
「専門書などは何冊も読みましたが、当たり前ながら、どれもあくまで認知症になった方を外側から見た様子が描かれているんです。この小説では内側から書かなければいけない、そうしなければ法輪二三久の言動に説得力が出せませんでした。創作とはいえ認知症者になり切って書くことは、この病気の辛さを追体験する感覚がありましたね。本人は正しいことを言っているつもりなのに、周囲からすれば明らかに間違っている。そのことを指摘されても、気づけない。その辛さすら、感じることができない」
法輪二三久の息子・昌輝が、父に対して抱く感情や思考には、作家自身が看取った実父に対する思いも込められている。加害者になり切り、認知症者になり切り、自らの人生も込めて書くことで、『告解』は出来上がったのだ。
「大本の原稿は『小説現代』のリニューアル号(二〇二〇年三月号)に一挙掲載されたんですが、単行本化にあたってはここまで変えてしまっていいのかというぐらい、細かく加筆修正しています。ただ、小説を締めくくる最後の二行は、初稿段階から一切手を加えていません。そんなことって、初めてなんじゃないかなと思うんですよ。これまではどの作品でも、最後の一行をどうするかで迷って、本にする直前まで粘りに粘って修正していたんです。実は今回の最後の二行は、物語の全体像が頭に流れ込んできた時点で既にありました。その二行から、『告解』というタイトルも導き出している。振り返ってみればその二行を伝えるために、原稿用紙四百数十枚を費やしたようなものなんです」
物語の終盤では、ミステリー作家としての想像力も大きく花開く。その瞬間、登場人物たちの秘められた感情も爆発する。新たな代表作が完成した。

講談社
飲酒運転で女性をひき逃げしてしまった青年、事故によって生涯の伴侶を突如奪われた遺族男性。加害者と被害者、双方の家族を巻きこみ物語は進んでいく。出所後の青年と、認知症を患った遺族男性に待ち受ける運命とは。