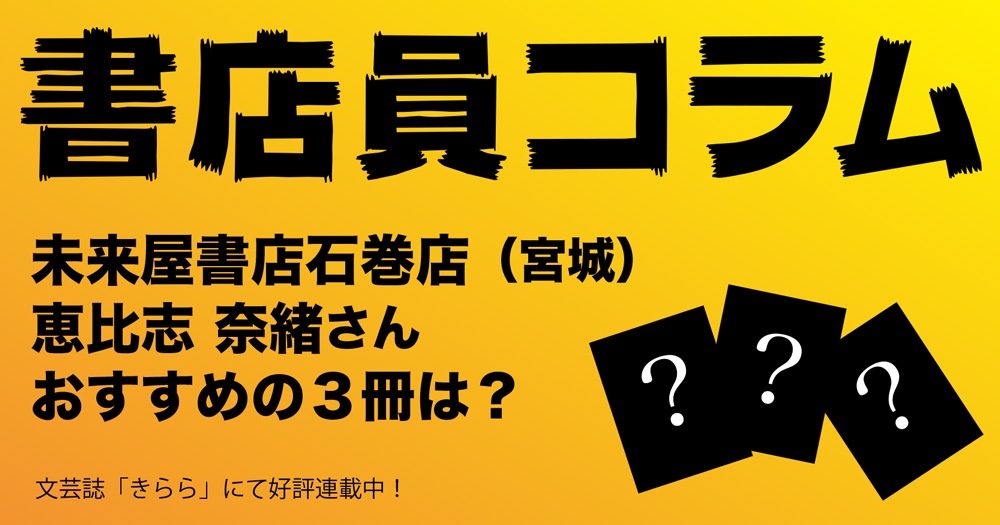からの心を満たすもの
亡霊が、自らの骸を引き摺って歩いている。そんな心境でいた一〇代の頃、拠り所にしていた書店でふと手に取ったのが梶井基次郎の『檸檬』であった。どのような作品かと頁を捲るうち、表題作の一文が目に留まった。それは「私」が幼き日に嘗めてみた硝子のおはじきの味覚、甘美な思い出の吐露であった。「あのびいどろの味程幽かな涼しい味があるものか」。郷愁を感じさせる声音が私の記憶を呼び起こした。座り込んだ畳の古びた色、幼少の悪戯心に伴う昂り、硝子に透ける青や緑や赤の模様。氷とも飴玉とも違う感触が舌によみがえる。いっそこのまま飲み込んでみたら──。それらの享楽を、ああ確かにこの作家も味わったのだ。私はすぐに『檸檬』を買い求めた。文学の中に初めて己を見出した一瞬の体験は、悄然とした魂に訪れた小さな救いの実感であり、作中で「私」の心を慰めたレモンエロウの色彩さながら、今も鮮明な輝きで目を細めさせる、いとおしき残像である。

太平洋戦争の末期、九州帝国大学医学部で米兵捕虜の生体解剖が行われた。遠藤周作の『海と毒薬』はこの実際に起きた事件を題材にした小説である。物語は終戦から二十余年が過ぎた東京の町から始まり、米兵を思わせるマネキンの碧い眼が、読者を過去のある一点へと引きずり込んでゆく。捕虜を生きたまま解剖し死亡させる行為は、たとえ戦場でそれ以上の理不尽な死があるにせよ、紛れもない罪であろう。なぜ医学生や看護婦は関与を拒まなかったか。恥でなければ罪ではないのか。信仰を持たない人間に神はないのか。己の良心の存在を確かめるために事件に加担した医学生・戸田の、少年時代からの罪の告白に、作者の問う声が重なった。

私の本棚にはニコルソン・ベイカーの『中二階』が並んでいる。幅約一センチの痩躯に、感性の爆発が生んだ小宇宙を内包する、おそるべき一冊である。米国のオフィスに勤める男を語り手に、身近な日用品や日常の動作、何気ない会話などの細部への考察が延々と述べられ、日本語訳の言い回しが独特の手触りを加えている。ときに本文を追い越す程に饒舌な注釈は壮観であった。作者の愛ある眼差しとユーモアは惜しみなく万物に降りそそぎ、われら人間の涙ぐましい努力の賜物、大いなるちっぽけな生活を、美しく瞬かせるのだ。