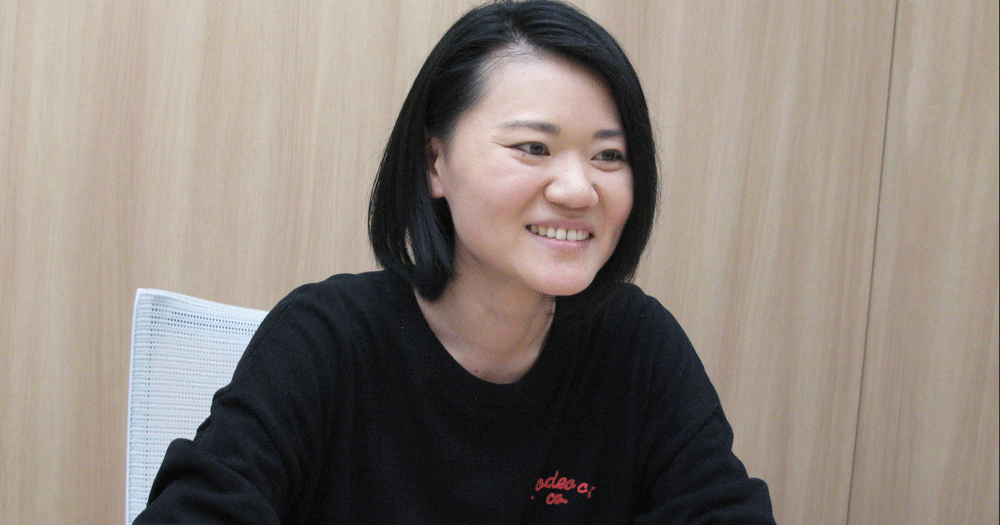翻訳者は語る 大谷瑠璃子さん
ガスライティング──被害者に繰り返し誤った情報を提示し、被害者が自身の認知や感覚、正気を疑うように仕向ける心理的な虐待行為を、映画『ガス燈』にちなんでそう呼びます。最愛の夫を喪い心が不安定な時に、ガスライティングで追い詰められていく女性の心理を描いた米国のスリラー小説『不協和音』。本書が単独翻訳の初作品という大谷瑠璃子さんは、どのように臨んだのでしょうか。
〈後半三分の一でとんでもない話に〉
「想像とは違ってちょっと変わっているけれど、小説として感動できる、すごく好みの作品」。最初に原書を読んだとき、そう感じました。本作は夫を亡くした主人公リリーの「悲嘆」を美しい文章で紡いだもの。スリラーと言うには展開はゆっくりで、プロットの起伏よりも日常のディテールや心理をじっくりと描く純文学風の小説です。特に前半三分の二は、時に断片的なエピソードを繋いでじわじわと物語が進むので、スピーディーな展開を求める王道ミステリーのファンにはじれったく感じられるかもしれません。ところが、後半三分の一でとんでもない話になり(笑)、「やっぱりスリラーだった!」と納得させられ、さらに最後には単なるイヤミスで終わらない、じわっとこみ上げるような感動作でもある。
喪失の悲しみを描く小説でもありますが、悲しみだけでなく、夫に先立たれ、子どもを二人抱えて仕事もしなければならない、そんな中で次々と理不尽な目に遭うリリーの「怒り」もつぶさに描かれ、とてもリアルだと思いました。
舞台となるテネシー州の豊かな自然の描写も魅力的。またリリーは音楽アーキビスト、夫はオペラ歌手という設定なので音楽の要素がふんだんに描かれ、章タイトルに曲名が使用される点など、音楽好きの読者も楽しめる。そんな小説の数々の美点をぜひ伝えたいと思いました。
〈全身全霊で向き合った翻訳〉
刊行が決まったときはとても嬉しかったのですが、その後「しまった」と(笑)。というのも、原文の文章がかなり独特で、読みながら「翻訳するのは大変だろうな」と漠然と思っていたからです。あまり知ったようなことは言えませんが、原文はシンプルで緊密な詩のような印象です。例えば名詞句だけを並べたり、文やセリフの流れが省かれていたり。英語の美しさが生き、豊かなイメージを喚起する文体なのですが、これを日本語に違和感なく移すには、言葉を補うなどの処理が増えてしまう。一文一文の密度が高く、読み手のイメージが豊かに広がる文章、さらに生と死という重いテーマを描いている。そのため、上っ面だけでは訳せない、全身全霊で向き合わないと翻訳出来ないと覚悟を決めました。
とはいえ、文体の雰囲気はなるべく出したいので、翻訳中は常に居住まいを正し背筋を伸ばす気持ちで、詩のようなぶつ切りの文章をいかに日本語に撚り合わせていくかに神経を使いました。
原題の「GRIEVANCE」はネガティブな感情全般を指す広義の言葉で、日本語ではひと言で表すのが難しい。同様に原文も、英語ではひと言で事足りる濃縮された言葉が使われています。翻訳では、濃いカルピスを飲みやすくするようなイメージで、言葉を尽くすようにしました。
〈今の年齢だからこそ訳せる小説〉
翻訳中は、師匠の田口俊樹先生から教わってきた処理の仕方や、「日本の読者に読ませる文章」を大切にする、ということが支えでもありました。師匠がゴリゴリの「原文尊重派」だったら、この作品は訳せなかったかもしれません(笑)。
脳科学者の中野信子さんが書いて下さった解説原稿を読んだときは、感激しました。作中で謎が全て説明されているわけではないので、訳しながら「これでいいのかな」と自信がなくなってくることもありましたが、ガスライティングに詳しく触れた解説を読んで「これで良かったんだ」と安心したり、改めて「リリー、辛かったよね」と同情したり(笑)。
今思うと、三十代という今の年齢でこの作品を訳せて良かったな、と思います。リリーとほぼ同世代で共感することばかりだったのも大きいですが、私自身も家族のことなど様々な問題に直面し悩んだ経験があり、実感をもって訳すことができました。きっと数年前までだったら、途中で白旗を揚げていたかもしれません。
〈ほとんど本を読んで過ごした二年間〉
小学生のとき、二年間ロサンゼルスに住んでいたのですが、その間は外で遊ぶこともあまりなく、家でずっと本を読んでいました。親戚から譲り受けた小学館の『少年少女 世界の名作文学』全五十巻が家にあり、その二年間はほとんどそれを読んで過ごしたほど(笑)。時代も国も関係なく、物語の数だけ世界があることを知りました。振り返ると、このときが一番翻訳小説を読んでいたかも。だから、初めての単独翻訳作が小学館から出ることは本当に嬉しいです。