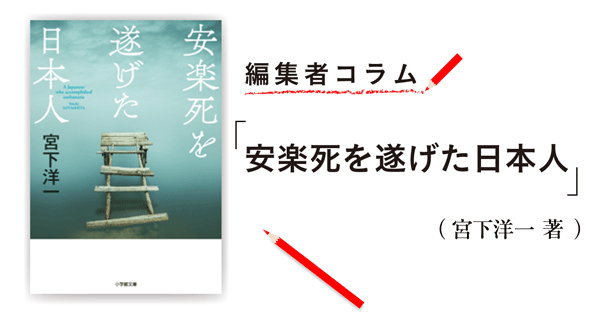◎編集者コラム◎ 『安楽死を遂げた日本人』宮下洋一
◎編集者コラム◎
『安楽死を遂げた日本人』宮下洋一
『安楽死を遂げた日本人』は、宮下洋一氏が世界6カ国の安楽死の現場を訪ねた『安楽死を遂げるまで』の続編です。本作では、前作の重要登場人物であるスイスの安楽死団体代表プライシック氏のもとで、実際に日本人女性が「旅立つ」までが描かれています。彼女は、神経難病で四肢の自由がきかず、「幸福な死」を求めてスイスに渡ったのでした。
単行本は、発売と同時に「NHKスペシャル」でも放映されたことで大きな反響を呼びました。なぜNHKと共同で取材にあたっていたのか。出版後よく聞かれました。実は、日本人女性をNHKに紹介したのは私たちでした(紹介時点では彼女は安楽死の願望を語っていたものの、実現するとは本人も周囲も思っていませんでした)。ジャーナリズムの観点からいえば、社会的な関心を呼び、かつ慎重に扱わなければならないテーマを他社と共有するのは、リスクがあります。それでも踏み切ったのは2つの理由があります。
生前、この女性は安楽死に対する思いを宮下氏に語っていました。ベッドの上で深く、長く考えぬかれた彼女の訴えは、安楽死是非論には収まりきらない切実な響きがありました。その声をたくさんの人びとに届けるため、映像の力を借りたかったというのがひとつ。
ふたつめは、NHKディレクターの姿勢に私たちが感化されたというものです。宮下氏は欧州に拠点を構えています。日本での取材は限定され、むしろプライシック氏が活動するスイス取材に注力しました。一方、日本をカバーしたのがこのディレクターでした。
失礼ながら私はNHKに対し、ヒトやカネに恵まれていることは認めざるを得ずとも、〝お堅い〟放送局という印象を抱いていました。でもこの人は志は高いけれど、腰はあまりに低いジャーナリストでした。女性が住む新潟の病院に何度も通い、カメラも持たずに女性の話に耳を傾けていました。時には女性と衝突したこともあったようです。以下はディレクターが後に明かした、彼女を車椅子に乗せて水族館に行った際のエピソードです。
「カメラケースを肩にさげて持って行ったんです。鞄代わりに使っていたただけで、中には大したものは入っていなかった。でも彼女は、後で病室に戻ったとき『あなたはそうやって誘いながら、絶えず私を撮ろうとしているんでしょ』(中略)僕は楽しむ時間を共有したかっただけなんですけどね。彼女にはそれがアピールに見えたみたいで……彼女に大きなストレスをかけてしまったと思います」(本書より)
正直すぎる告白です。が、ある種の競合関係にあった著者に、〈時間をかけ、信頼関係を築いてから仕事に立ち向かう彼の姿勢からは、効率よく取材を進めようとする私には学ぶべき点が多い〉(本書)と言わしめている点からみても、ディレクターの正直さ、つまりは誠実な姿勢には敬意を示したくなりました。一方の宮下氏も、ディレクターから刺激を受けながら、プライシック氏に肉薄し、安楽死の矛盾についても深く切り込んでいきました。本書がセンセーショナリズムに陥らず、日本人女性やプライシック氏の「人間の物語」になりえたのは、ディレクターの存在が大きかったと思います。
この日本人女性は最期、致死薬を自らの体に注入したのち、同行した家族への感謝に続けて、こんな言葉を口にしています。ディレクターの名前を優しく呼びかけたあと、彼女は笑みを浮かべながらこう語るのです。「私のことをちやほやしてくれてありがとう」
そのシーンはもちろんNHKでは放送されていません。その言葉が持つ意味について、それから2年半、文庫版を出版する今となっても、時折考えることがあります。

──『安楽死を遂げた日本人』担当者より

『安楽死を遂げた日本人』
宮下洋一