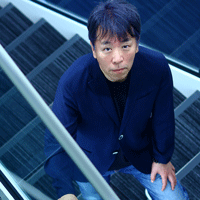白石一文さん『一億円のさようなら』
今の社会のあり方、人間の生き方に疑問を提示するような作品を発表してきた白石一文さん。
新作『一億円のさようなら』は、難解な命題は封印し、エンターテインメントに徹した作品。しかし、その人生観や社会観は、ところどころににじみ出ていて……。
十二年前のメモ書きから生まれた小説
もしも長年連れ添ってきた配偶者が、巨額な資産を隠し持っていると分かったら? そんな現実にはありえなそうな、しかしちょっぴり夢見たくなるような出来事を発端に、意外性に溢れる方向へと話が転がっていく『一億円のさようなら』。白石一文さんの最新長篇である。
「長年にわたって親しくしている徳間書店の崔さんと何年も前から仕事の約束をしていたのですが、なかなか果たせなかったんです。で、結局、知り合って十年以上経ってようやく書き上げたのがこの作品でした。近年は小難しい小説を書くことが多かったんですが、徳間書店で書くことを考えた時、今回は最後まで一気呵成に読めてしまう、ひたすら面白いものを書こうと思いました」
白石さんはいつも、小説のアイデアを書き留めたメモが入った引き出しから、次に書くものを選んでいる。「今回のネタはこれでした」と見せてくれたのは、プリントアウトしたA4の紙2枚にわたる、小説の書きだしのような文章。タイトルには「楽園ゲート」とある。
「"歳をとると涙もろくなる"いう冒頭から始まって、荒川静香が金メダルを獲ったのを観て涙した、と主人公の心境を綴っています。つまり、僕がこの書き出しをメモしたのはトリノオリンピックの頃、2006年だったということですね。すでに主人公の鉄平や妻の夏代という名前は使ってあるし、隠し財産のことや、夏代の"あれは私のお金じゃない"という決め台詞も書かれているんですよね。メモといってもこんなふうに詳しく書いてあるメモもあれば、短いセンテンスだけといったメモもありますが、こうして書き留めたものを"いつか書こう"と思って引き出しにいっぱいとってあるんです。そろそろかなと思った頃に取り出して読み返し、今回は『楽園ゲート』かな、なんて思いながら、書き出し以外のことをメモっておいた別の数枚も併せて眺めて、ぼんやりとイメージを作っていきました。今までの経験上、七、八年経つとメモがようやく熟成されてくるという感じですね。今作の場合は、すでに十年以上が経っているので、きっとメモの枠を超えて頭のどこかで作品を書き進めていたんでしょうね。実際の作業としては、映画の字幕を書き写すような感覚でした。僕自身、話の先がどうなるのかは分からない。でも字幕を書き写すように進めていけば、必ず結末までたどり着く。そんな感じで、途中で筆が止まることは一度もなかったですね」
つまりは十二年前のメモ書きが、今こうして長篇小説として実を結んだわけだ。
妻の巨額の隠し財産が発覚
加能鉄平は五十二歳。理不尽なリストラにあい、地元である九州・福岡に戻って化学製品の総合メーカーに勤務して七年。会社は祖父が創業し、先代社長は叔父、現社長は従兄弟が務めており、親族である鉄平は社長から邪魔者扱いされている。それでも従兄弟のやり方が時流に合致していないと、会社経営に関して危機感を抱くような、真面目な男だ。
ある日自宅で受け取ったのは一本の電話だ。東京の弁護士だという彼は、鉄平も事情を知っていると誤解して、妻の財産について語り始める。夏代はかつて伯母の遺産を相続し、さらにその一部をベンチャー企業に投資したところ成功し、現在の額がなんと──四十八億円になっている、というのだ。妻を問いつめたところ、彼女は「あれは私のお金じゃないのよ」と言う。「きっと誰のお金でもないのよ」「善いことにも悪いことにも、どんなことにも使わないって決めてるのよ」と。鉄平の頭をよぎるのは、自分がリストラにあった時、親の医療費や子どもの学費が必要だった時、マンションを購入した時……。どんなに家計が苦しい時でも、夏代は自分もパート勤めをしながら、隠し資産のことは一切口にしてこなかったのだ。
「小難しい部門」と「面白い部門」
「僕が書くものはいくつかのタイプに分かれているんですが、おおざっぱに二分すると、まずワクワクしながら読めるすごく面白い小説。次に、後世に残すことを考えた、世界にまつわる小難しい理屈を並べ立てた小説。それで今回は"面白い部門"の方を選んだわけです。そうすると、おとぎ話のような、非現実的な物語の方が読んでいて楽しいだろうということになる。若い書き手がよく書いている、たとえば異世界に行って生まれ変わってみたり、好きな人が難病だと分かったり、記憶が続かなかったりといった話も、最初はその突飛な設定に"えっ"となりますけど、読み始めると一気に引き込まれますよね。僕はもう還暦なのでさすがにそういうものは書かないけれど、いかにも現実世界にリンクしていそうな風俗小説っぽいおとぎ話であれば、すごく面白いものが書けるだろうと思ったんです」
ちなみにご本人の過去作品でいうと「小難しい部門」は『この世の全部を敵に回して』を筆頭に、山本周五郎賞受賞作の『この胸に深々と突き刺さる矢を抜け』や『僕のなかの壊れていない部分』『神秘』『記憶の渚にて』、「面白い部門」はというと、直木賞受賞作の『ほかならぬ人へ』や『私という運命について』『心に龍をちりばめて』『彼が通る不思議なコースを私も』『翼』など、とのこと。
もうひとつ、今回試みようと決めていたのは「とにかく長い小説を書く」ということ。実際、本書は単行本で五百四十ページ超ある。
「もともと書くのも読むのも長いものが好きなんです。作家だった父が昔から"長篇が一番楽しいぞ。乗ってくるとエンドレスに書けるぞ"とずっと言っていたから、その刷り込みがあるのかもしれません。そして、長いものを書くとなるとやっぱりどんどん読み進められる面白いものにしなくちゃいけない。そこで、読者には充分な現実感を持たせつつ、それでいて小説のコアの部分は思い切りファンタジックというような作品を作り上げていくんです」

人間不信となった男の決意
妻の隠し財産が四十八億円ということも驚きだが、それをずっと秘していたことも鉄平には衝撃だ。それぞれ他県に進学した長男長女も妻とは仲がよいが自分とは距離がある。会社のトラブルでも不信感が募った鉄平は、次第にすべてのことが信じられなくなっていく。
「夫婦を二十年もやってきたのにこんなことがあった場合、読者たちは"自分ならどうするか"ときっと考えるでしょう。そうした心理の最大公約数を全部入れ込んでいくわけです」
やがて鉄平は、一億円を手に入れて家族を捨てようと決意する。つまりそれは、多くの人の願望でもあるということ?
「それはそうでしょう。父親って、子育てが終わりに近づいても達成感が余りないんですよ。サンタクロースのプレゼントを買うのは自分でも、それを子供たちに配るのはぜんぶ妻だという根っからのひがみもありますから(苦笑)。そういう時に家族から邪険にされたり除け者にされたりすれば、どうしたってやけっぱちになっちゃう。この小説でも、問題を起こして鹿児島に逃げた長男に、家族会議をやるならスカイプにしようと言われて、その瞬間、彼は気持ちがプツンと切れる音を聞いてしまうんです」
ただ、そこからは、最大公約数が予想するような展開にはならない。鉄平はひょんなことをきっかけに、新しいビジネスを試みる。そのきっかけになるのが、金沢ののり巻きの店なのだが、これは実際にモデルとなった店があったのだという。
「金沢のガイドブックには必ず載っているような〈ちくは寿し〉というのり巻きの名店があって、実際に食べてみると非常に美味しいんです。金沢は水もうまいし、隠れた米どころだというのもあったんでしょうね。でもある時、まだ若かったご主人が突然亡くなる不幸があって、お店を閉じてしまった。小説の中にのり巻きのメニューを載せていますが、それは全部、この〈ちくは寿し〉のものです」
こののり巻きに関する展開は非常に痛快、人と人との出会いも重なっていき、間違いなくワクワクするストーリー。
家族という会社の経営者は妻
だが、そうして家族とは別行動を始めた鉄平に対し、夏代も黙っているわけではない。
「妻は、家族という会社の経営者ですから。会社が倒産しそうになったら、そうはさせまいと懸命になるでしょうね。そういう、システムを取り戻そうとする情熱を愛情というんじゃないでしょうか。それを愛情と呼ばないとすれば、じゃあ愛情って何、という話になってしまいますから。そもそも、たいていの男に対して最も有効な女性からの口説き文句は、"あなたの仕事がどうしようもなくなったら、私が食べさせてあげるわ"なんです(笑)。家族というシステムのなかで、好きなことを存分にやって、しかも全肯定してくれるとなれば、これは男はコロッといきますよね。そうやって持ちつ持たれつやっていければ夫婦はうまくいくんでしょうね。そんなことをちろちろ考えながら書き進めていきました」
では、システムを崩壊させようとしている鉄平は、愛情が希薄な人間なのだろうか。
「自分のことを振り返っても、父親というのは、子供に対してべたべたした愛情はあんまり持っていないと思います。ただ、子供への好奇心は強くある。鉄平にとっても子供たちはあくまで関心の対象だったのでしょうね。夏代に対してはやはり特別な愛情を持っていますが、彼は、その妻に激しく裏切られてしまう。そうなると、男としての素の自分がむくむくと湧き上がってきて、まずは独立を目指し、さらには、仕事でのかかわりや世界と繋がっているという感覚を求めるようになる。一番大事なのは家族なんかじゃないって彼は目覚めるわけです」
では、彼らの関係はどんな結末を迎えることになるのか。
もしも一億円が自由に使えたなら?
さきほどの「小難しい部門」の作品では、現代の家族制度を疑うような内容も書いてきた。では、この「面白い部門」で鉄平たちの家族の関係はどのような決着を見せ、鉄平と"世界"との繋がりはどのような形になっていくのか。
スリリングな展開を追ううちに、「十分大人になった後だって、人生新しいことに挑戦してもよいのではないか」という気持ちも湧いてくる。
ではもし、白石さん自身が、一億円をもらって好きにしてよいと言われたら何をするか。
「人間の寿命が延びている時代、長生きすると一億円じゃ足りないでしょうね。二〇四〇年以降に生まれた人はみんな百歳以上生きるといわれているくらいですから、今の定年制度や年金制度はすでにして破綻が目に見えているんです。僕も還暦を迎えましたがまだまだ元気なんですよね。となるとやっぱり、一億円で遊んで暮らそうとは思わない。ただ、いままでのような書き方はしないでしょうね。自分で出版社を作って、自分の作品をネットで公開したりオンデマンドで直送したり、そうした今とは違う方法を探っていくことを考えると思います。加えて僕は自分の小説をもっともっと英語にしたいという気持ちが強い。やっぱり最後はそうやって世界と繋がりたいんですよね」