白石一文『道』刊行記念特別インタビュー

読み手の世界の認識を揺さぶる、壮大なスケールの小説を描いてきた白石一文。このたび最新長編『道』を発表した。中年男性が、かつて失った大切なものを取り戻すため、1枚の絵を手がかりに時空を超える。
タイムリープした先の世界に、想像を超える事実が現れ、物語は未知の領域へ。時間という、定まりのない概念の言語化に、極限まで迫った傑作だ。神秘的な物語にこめた思いを、白石本人に聞いてみた。
何年も醸成したものがつながった『道』
もう一度、あの瞬間からすべて、やり直せたら。歳を重ねれば誰もが抱く思いを、『道』の主人公・功一郎は、50代の半ばを過ぎて実行する。
本作は人生の仕切り直しを試み、遭遇する事態に心をかき乱される男の心象を、丹念に描出した長編だ。功一郎が人生をやり直すとき、鍵になるのは、ロシア出身の画家ニコラ・ド・スタールの絵画作品『道』。キャンバスの真ん中に描かれている白い三角形が、遠くへ延びる道に見えてくる、不思議な抽象画だ。物語の構想は、この実在する絵から想起されたという。
「小説を書くときは、過去に書き留めていたメモの束から、熟れ時のタイミングを見計らい、1枚抜いて構想を練っていきます。今回は『人生をやり直せたら』という大枠のテーマを取り出し、何か掛け合わせるものはないだろうかと考えていました。
そこでスタールの絵を思いついたのです。
スタールを知ったのは、10年ほど前でしょうか。テレビ東京の『美の巨人たち』という番組で紹介されていて、印象に残りました。僕はパブロ・ピカソが世界一優れた画家だと思っているのですが、スタールの才能は、ピカソを超えていた気がします。残念ながらスタールは41歳の若さで夭逝します。短い活動期間でしたけれど、ピカソの円熟期と重なっているんですね。勝手な想像になりますが、ピカソは少しだけ安心したんじゃないかしら。スタールが自分を超える才能かもしれないと、気づいてたはずです。
番組をきっかけにスタールに魅了された僕は、日本で開催された個展の図録を取り寄せ、何度も見返していました。いつか小説に書いてみたいと思いながら……」
小説の構想中に図録をめくるなか、ある作品に目が留まった。気になったのは2作。そのうち、すっと胸に入ってきたのは『道』だったという。
「絵としては、もう1作の方がいいんだけど、『道』は何ていうか本当に天才的なんです。あれは誰にも描けない。具象と抽象の境目を超えています。この1点だけでも、間違いなくピカソに肉薄しています。
メモの束とスタールの絵、何年も前から醸成してきたもの同士がつながり、『道』という小説を書こうと決めました」
このタイトルは、過去に自身が読んだ、名作短編に感じた気持ちも重ねている。
「高校時代に、三浦哲郎さんの芥川賞受賞作『忍ぶ川』を読みました。大人の恋愛の話で、映画化作品がとても評判良かったんですね。童貞ボーイだった僕は、どんな凄い恋愛が描かれているのかと期待して読みだしたのですが、ひどくがっかりしました。つまらないのではなく、『忍ぶ川』って、主人公たちが出会う小料理屋の店名なんですね。物語を象徴する、重い意味を含んだタイトルかと思えば、ただのお店の名前か! と。あのときの僕の落胆を、今回の『道』の読者にも共有してもらえたらと考えました。
悪い意図ではありません。がっかりした気持ちをずっと記憶しているのは、何かの意味があるはず。フォローするわけではないですが『忍ぶ川』は本当に優れた作品ですし、実際に高校時代からずっと覚えています。
凄いとか素晴らしいじゃなくても、心に永く影響する何かを読者の方に届けたいという思いで、このタイトルに決めました」
時空を飛び越える現象はあり得なくもない
どのような仕組みかは不明だが、『道』の絵の前に立った者の身には、功一郎が「あれ」と呼ぶ現象が起き、願った過去の時間に遡ることができる。
かつて高校受験で「あれ」を経験した功一郎は、再び時間遡行に臨んだ。2年半前に事故で亡くした娘・美雨、娘の死以降、心を深く病んでしまった妻の渚を快復させ、渚のケアのために負担をかけている妹の碧を解放するのが目的だった。
人生2度目の「あれ」にも、功一郎は成功する。いったんは大切な家族を取り戻したが、思いがけない問題に直面してしまう。
「渚と碧の関係や、美雨の新事実などは、物語を面白く読んでもらうために手をかけた部分です。七面倒くさい設定でも、まずエンターテインメントであることを第一にしています。一方で、面白いだけじゃなく、僕が持っている世界の認識を小説で表現したいと思いました。
ジャンルで分けると『道』はタイムリープもので、荒唐無稽かもしれない。でも人が時空を飛び越えるのってあり得なくもないでしょう? と考えています。時間って、ほとんどの人は過去から現在、現在から未来へと、飛び石が移るようにイメージしていますが、実はそんな正しい規則性はない。時間から時間へ移動する中間点はとてもぼんやりした、曖昧なものなんです」
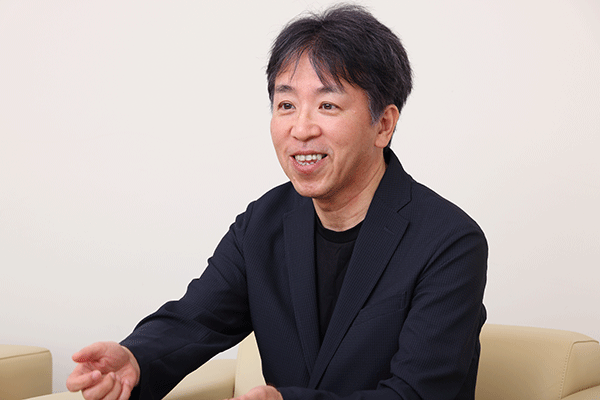
数学や物理学の世界では、更新されていく「いま」を、厳密な意味において正確に予測することはできないという。
「多少の予測はできるかもしれませんが、たまたま次に現れる『いま』は、無限の数の『いま』のひとつでしかない。幸せか不幸せかは、関係ありません。
だから、人生のやり直しには意味がないんです。やり直せたとして、『道』の先が願い通りの人生である保証はないですし、別の辛い事態が起きることもあります。
結局のところ、喪失がすべて満たされるようなやり直しは不可能でしょう。微細なズレを含んだ『道』の反復を無数に繰り返すだけ。功一郎は目先の望みは叶えられたかもしれませんが、やり直しの無為に気づき、時間の隙間で途方に暮れていると思います」
世のなかは、わからないことだらけになっている
物理など理系書を大量に読み、さまざまな思索を重ね、白石は60代半ばを迎えようとしている。この10年ほどの間には、『神秘』『ファウンテンブルーの魔人たち』など、超常的な世界をとらえた意欲作を書き上げた。現実への信頼が、いい意味で薄らぎ、起こり得ない出来事をリアルに描きとることが、作家の主眼になりつつある。
「この世界は数学的な理解と、非数学的な論理展開の複雑な交わりで形成されていて、真の意味で荒唐無稽な現象など、どこにもない。それが真理じゃないでしょうか。
たくさんの他世界が、『いま』と一緒に、同時並列的に存在しています。世界と世界とが、どう接続しているのか、法則はまるでない。ただ、隙間はすごく曖昧で、どろどろしています。その曖昧なところを小説に書いてみたいと思うじゃないですか。
曖昧な隙間をとらえたい気持ちは、僕の作家としての野球のボールの芯です。固い芯に糸を巻いていくように、いろんな小説的技巧を凝らし、ボールの形状に整えて、読者に投げています。芯を投げても届かないですよね。まず、小説として面白くなければいけない。近年はそういう心構えで作品を書いています」
シンクロニシティなど、スピリチュアルな現象を白石は強く信じているという。これまで政治や経済、不倫など多彩な題材で高く評価されているが、すべての作品に共通しているのは精神世界との深い親和性だ。
「最初は封印していたつもりなんですけど、結果的に、にじみ出ていますね。僕は自分が、本当に実感しているものしか小説に書けない。ビジネスとか恋愛とか、いろいろ書いてきましたが、そういうのはめっきり興味が向かなくなってきました。グラウンドに何年も降りないで、試合の勘とか最新のプレースタイルを理解できなくなった野球解説者みたいな状態でしょうか。人間関係で深刻に悩んだり、狂おしい恋愛に身を焦がすようなことは、とんとご無沙汰なので、小説に書く意欲が湧かない。身体を使って野球をしてないのに野球を語ってもピントが外れるだけですからね。
そうならないよう自分の実感に根ざしたものを書くしかないとしたら、やはり最初から実感に根ざして持っているスピリチュアルな精神が顕れてきます。世の中って、わかることだけじゃないから。むしろ、歳を重ねるたびにどんどんわからないことだらけになっていくのが人生というものなんだよ、という僕の解釈を、小説でみんなに伝えたくて書いているんです」
長く寝かせて意味を持ち出す瞬間を書きたい
『道』の物語には、もうひとり重要な人物が登場する。九州の大富豪で、スタールの『道』の所有者である長倉人麻呂。超然とした態度で、功一郎の導師のような人物だが、詳しい素性や目的は不明だ。後半、時間の隘路にはまりこんだ功一郎は、人麻呂の言葉によって、己の人生に秘められた真実に気づいてゆく。
多層化した物語の時間軸にちりばめられた違和感が、見事に回収されていくクライマックスは圧巻だ。読了後すぐに1ページ目から、読み返したくなる。
何が起きたのか、理屈ではわからない。だが確実に、世界の認識が揺さぶられる。タイムリープの精密な構造に、時間の境界の不穏な曖昧さを掛け合わせ、読者を条理の外へ連れ出す驚異の文学小説だ。
「人麻呂を登場させた理由は、自分でも説明できません。わからないんです。思いついたのだから書いたとしか言いようがない。柿本人麻呂から想起した人物なのだろうけど、人麻呂の関連書を読んでも、何だか腑に落ちない。でも選択したというのは、何か意味があると思って、とりあえず書き進めます。
直感に従うというか、後々に生み出されるシンクロニシティを証明したいんですね。わからなかったものが、いつかどこかで何かとつながり、意味を持ちだす瞬間を待ちたい。人麻呂も、書き進めていくとやはり、功一郎の人生との共時性が表れてきました。それは事前に、作者の僕も予想できません。意味を持つかどうかは、彼らの人生が決めることです」
作家として充分なキャリアを重ねたいま、書きたいものをすぐ書くのではなく、あえてテーマやアイディアを寝かし、シンクロニシティの立ち上がる瞬間を待つこともあるという。
「今回の『道』も言ってみれば、形になるまで10年かかっているんです。構成を細かく練り、本格ミステリのように小説を組み立てていく方法も否定はしませんが、僕は向かない。短いものは書けても、それだと長い小説は書けないんです。
僕の場合、樹木そのものではなく、地面の下に隠れている複雑な根っこの絡まりを、小説で表現したい。あるいは、きれいな音を奏でるより、ボールの核に巻いた糸が回り出して、頭の中で鳴る音を楽しみたいんです」
子どものイマジネーションの強さは本物
白石は「いいものを書きたい、だけでは無理。長い小説を書くために、時間がかかっても遠回りをする」と語る。
「僕の親父の白石一郎もそういう考え方だったから、遺伝なのかもしれませんね」
近年は特に、プリミティブな気持ちで、小説を書いているという。
「子どもの頃の希求に従って書いている感じがします。『いま』とは別の世界があって、自分の人生を入れ替えられるとか、子どものときは本気で信じていたわけじゃないですか。また誰か大切な人を失ったとき、『いま』からは消えたけれど、その人はどこかの平行世界でまだ生きていて再会できると感じていたわけじゃないですか。大人になるとみんな分別がついて、そんなのあるわけないじゃん! という態度になりますが、いろんな経験をして歳を取ってくると、いやいやそうでもないよ、と。若い時分のイマジネーションって単なる妄想ではなく、意外に本物だから、馬鹿にはできません。
ユング的な解釈における集合的無意識に通じますが、平行世界が存在するという頭のなかの認識は、空想で片づけられるものではない。すごく強いんです。イマジネーションを現実世界に再現するエネルギーを僕たちは生まれながらに持たされていると思っています」
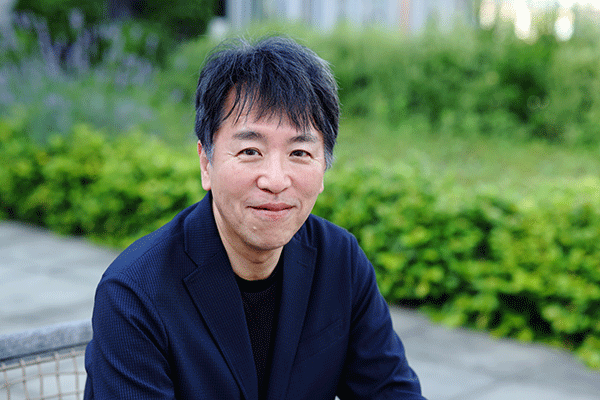
『道』は、第一級のエンターテインメントで、人々に潜在するイマジネーションを再起動させる物語でもある。読者を常識の縛りから解放する、新たな名作の誕生だ。
「僕は10代のとき電車内で、一度タイムリープを経験しています。あれは錯覚でも、思い違いでもない。たしかに現実の出来事でした。『道』の功一郎のような体験は、突飛なフィクションではないし、あり得ない話だとは思っていません。
僕はどの小説でも、嘘は書かないと自負しています。できるだけ面白くするよう努力はしますが、身についた本当の実感だけを書いています。『道』も、嘘はひとつも書いてない。作り物だという先入観を捨てて、是非読んでほしいですね」
白石一文(しらいし・かずふみ)
1958年福岡県生まれ。2000年『一瞬の光』でデビュー。2009年『この胸に深々と突き刺さる矢を抜け』で山本周五郎賞、2010年『ほかならぬ人へ』で直木賞を受賞。近著に『ファウンテンブルーの魔人たち』『我が産声を聞きに』。
(取材・文/浅野智哉 撮影/浅野 剛)







