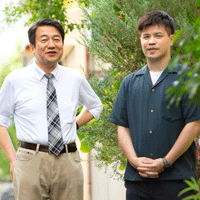今村昌弘さん『魔眼の匣の殺人』
二〇一七年を代表するミステリーの話題作といえば今村昌弘さんの『屍人荘の殺人』でした。二〇一九年の映画公開も決定し、ますます注目が集まっていますが、ついに待望の第二作『魔眼の匣の殺人』が刊行されました。早くも大ヒット中の作品について、お話を伺います。
──年末恒例の各ランキングで首位を独占、さらに本屋大賞でも三位になるなど、『屍人荘の殺人』は新人のデビュー作としては異例のベストセラーになりました。今村さんご自身も、あれほどの反響は予想しておられなかったのでは。
今村 刊行直後、同業の先輩方やミステリーファンが肯定的な感想を広めてくださったのが本当にありがたかったです。潮目が変わったのはランキングの結果が出て「王様のブランチ」で取り上げてもらったあたりで、インタビューでも、ミステリーファン限定ではなくて一般向けの質問が来るようになりました。
──「クローズドサークル(閉鎖状況下の事件)」とか専門用語を言っても伝わらないし。
今村 それどころか、まず誤解を解かなければいけなかったです。「本格」は、ミステリーが大好きな人以外は読んじゃいけないんじゃないか、と身構えさせるみたいで(笑)。そうじゃなくて、謎解きを楽しむミステリーが本格なんですよ、と。自分も決してマニアではなかったんです、そういう人間でも楽しめるのが本格のいいところなんだ、とお話しするようにしました。
やはり広い読者層に向けて書いていきたい
──本が出たあとのインタビューでも、今村さんはこれからミステリーの勉強をしていかないと、とおっしゃっていましたよね。今回、『魔眼の匣の殺人』を書くにあたって、葛藤があったと思うんです。マニアに絶賛された作品でありながら、一般読者にも広く受け入れられた。いったいどの層に向けて書くべきか、悩まれたんじゃないかなと。今、もらったゲラを見てみたら序章の終わりに自分の書き込みがしてあって「リーダビリティよい。才能?」と書いてある。
今村 ありがとうございます(笑)。
──前半がすごく読みやすくて、登場人物たちが事件現場になる魔眼の匣に集められ、最初の事件が起きるまでが非常にスピーディで、かつスリルがある。そして後半に行くにしたがってハードルが上がっていきます。マニアじゃないとついていきにくそうな展開ではあるんだけど、そこまで引き込まれた読者ならば食いついてくるだろう、という計算をして書かれているように見えました。『屍人荘の殺人』で初めてミステリーを読んだ人をどうやって後半まで連れていくか、かなり考えて書かれてますよね。
今村 前作は自分が好きなことを書いたので迷いがなかったんです。今回選んだモチーフは予知能力なんですが、これは書いていくと論理ゲームにならざるを得ないんですね。そうすると、論理の漏れがないことを説明するためには難解なことも書かなければいけない。本格ミステリー好きならば読んでくれると思うんですけど、途中で諦めちゃう読者が出てきそうな気がしました。最後の謎解きだけ読めばいい、途中は飛ばしてもいい、というような。それが作者としては無念で、なんとか途中の理屈も読んでもらいたかったんです。だから何度も書き直して、完成まで時間がかかってしまいました。途中で担当編集者から「もうゲラにしませんか」と言われたんですけど「いや、もっとわかりやすく、どんどん読み進められるようにできる」とわがままを言いまして。とにかく、ミステリーファンではない方に苦しみながら読んでもらいたくはなかったんです。そこをおろそかにするのは、自分をミステリーに引き寄せてくださった先達の苦労を無にするのと同じことですから。
──ネタばらしにならないように言うと、『魔眼の匣の殺人』のおもしろさはプロットにあって、終盤になって初めて、あるミステリーの古典的な型が見えてくるんですよね。私は斬新な試みだと思ったんですけど、そこに辿り着くまでにいくつか山を越さないといけない。
今村 ロジックの組み立てには苦心しました。一つ言い方を変えただけで、すっと論理が入りやすくなったりするんです。それができたときの快感はありますが、やはり苦しい。
キャラクターを魅力的に書くのも仕事の一つ
──物語の構成でいくと『屍人荘の殺人』は消去法に近くて、一人ずつ容疑者が消えていくことで選択肢が狭まっていきました。ところが『魔眼の匣の殺人』はそうではなくて、今言った最終形が見えてくるまで推理の筋道が固まらない。だから読者を立ち止まらせないようにするのが重要だったと思うんです。「早くすかっとさせてくれよ」と騒ぐ人をなだめすかす工夫が(笑)。
今村 『屍人荘の殺人』同様、オカルトをテーマに使っているんですが、予知能力って「それは嘘なの、本当なの」という真偽の判断に引っ張られるんです。これまでの本格ミステリーでもほとんどがそういう作品で「予知に見えた現象はトリックとして合理的に解決できました」という落ちでした。かといって予知能力を使って誰かを呪い殺せるというようなものでもないので、トリックとしても使いづらい。どうあっても結局は論理ゲームになってしまう。もう、絵面が地味なんです。僕は元来、不可能犯罪ものが大好きだから、派手なトリックを仕掛けたいのに(笑)。そういうこともあって、関係者の一人を絵を描く予知能力者にしたわけですが。

──主人公コンビが出会う少女、十色真理絵ですね。彼女が物語の鍵を握っています。
今村 そうですね。だからなのか、初稿では物静かで目立たないキャラクターだったのに編集者から「もっといい子にしてください」と注文がつきました。え、いい子って物静かで何もしないからいい子なんじゃ、と頭を抱えましたよ(笑)。他にも大学教授の師々田を口うるさい男にしてみたり、いろいろ変えています。途中でキャラクターが引っ張ってくれる部分もないと、読みにくいだろうと思ったので。論理がちゃんと合う、というのが第一段階で、そこからキャラクターの個性を出していきました。
──後付けでデフォルメしていったわけですか。たとえば主人公コンビの葉村譲と剣崎比留子と先ほどの真理絵が、ちょっと三角関係っぽくなる展開が途中でありますが。
今村 ああ、後から付け加えた部分です。
──葉村と剣崎のラブコメ的な関係が最初にあるわけじゃないんですね。それが人物設定の核っぽく見えるのに。話をおもしろくするためにキャラクターを後から強化するというのは妙案です。そんな手もあるんですねえ。
おもしろさの鍵は引き算にあり
今村 だって、初稿は自分で読んでもおもしろくないんですもん、くどくど書いていて。これをなんとかおもしろくしないといけない。第一稿が上がったのは(二〇一八年の)四月ごろですが、それを書きながら、おもしろくないなあ、と思っていました(笑)。編集者は「いついつまでに上げてください」と言う。「上げられますけどおもしろくないですよ」と言いながら書いてましたから、ラストはものすごく適当でした。それを夏までに直すことになったんですが、読み返してもやはりおもしろくない。一人死ぬまでが長すぎたんです。「何がおもしろくてこれをみんな読むんだ」と思いました。本来、自分が読者として楽しめるものは、好みがわかっているわけですから本人がいちばん書くことができるはずです。なのにそうではないものが目の前にある。これは我慢のならないことでしたね。
──それはどうやって改稿したんですか。
今村 結構時間がかかりましたが、わかりやすくおもしろくするのはシンプルにすることだと思うんです。たとえばミステリーの謎解きというのは、作者の筆がいちばん乗るところだと思うんですが、第二稿の段階でも書くのが苦痛で仕方なかった。要素の整理ができていなくて、ごちゃごちゃになっていたんです。それでも論理としては筋が通っていたので、編集者にはゲラにすることを勧められたんですけど、待ってもらいました。紙にしてしまうと直すのは大変ですけど、データのままならまだ入れ替えが何度でもできるじゃないですか。そういう部分でも試行錯誤はありました。解決できるのは自分だけで、天から答えは降って来ないんですよね。完成したものはずっとシンプルになっているので、苦労した跡は見えないと思いますが(笑)。
──わかりやすさは引き算なんですね。
今村 はい、ずいぶん手を入れたのでページ数も増えるかと思ったら、逆に減りましたから。
──本作は予知能力というオカルトの題材を扱いながら、ご自分でおっしゃったように「嘘か本当か」という二元論に安住せず踏み込んだのが独自のロジックのおもしろさを引き出すことにつながったと思います。予知能力というアイデアは、いつごろからあったんですか。
今村 二作目を書かなければ、となってからですね。『屍人荘の殺人』はギミックを思いついてからそれを使って何ができるかを後から考えたんですが、本作も同じでした。予知能力があると何ができるんだろう、というパターンを考えていきました。さっきも言ったようにトリックに使うことは難しかったんですが、そこにこだわらず、不思議な超能力として置いたままでもミステリーなら成立するんじゃないか、という結論に達して。
──そのへんが今村さんのクレバーさだと思うんです。『屍人荘の殺人』という成功体験があるのに、それをなぞらないで違った形式の謎解きを書くことを選ばれた。エンターテインメントの作者として大事な資質ですよ。本作は気になる終わり方をしていて、シリーズはまだ続きそうなのですが。
今村 はい。とりあえず第三作を、できれば『魔眼』ほどは時間をかけずにやらないと(笑)。その後も本格ミステリーを続けたいと考えていますが、ちょっと違った形のものを書きたい気持ちもあります。見かけは本格ミステリーではないけど、実はそうなっているというような。たとえば、恋愛小説にしか見えないけど、人の心の謎を解いていく段階は本格ミステリーそのものだ、というような小説ですね。
──小説の外構にはこだわらず、物語の中身をそうしていくということですか。
今村 殺人の道具を使わなくても本格は成立すると思うんです。たとえばラブレターのような恋愛のアイテムも、組み合わせによっては謎解きに使えるはずです。読後感はまったく違うけど本格ミステリーとして成立している。そういう作品も書けたらいいなと思っています。
──なるほど。もともとマニアではなかった今村さんから見て、本格の魅力というのは何でしょう。最後にそれを伺ってもいいですか。
今村 読者が登場人物と一緒になれるのがいいと思っているんです。たとえば超人的なヒーローの作品だと、自分と主人公は絶対に別物です。でも本格ミステリーなら、手がかりは登場人物と同じように見せてもらえるから、自分が主人公になることができる。私もそういう楽しみを提供できる小説を書きたいですね。

『魔眼の匣の殺人』
東京創元社
今村昌弘(いまむら・まさひろ)
1985年長崎県生まれ。岡山大学卒。2017年『屍人荘の殺人』で第27回鮎川哲也賞を受賞しデビュー。同作は『このミステリーがすごい!2018』、『〈週刊文春〉ミステリーベスト10』、『本格ミステリ・ベスト10』で各第1位を獲得し、第18回本格ミステリ大賞[小説部門]を受賞、第15回本屋大賞3位に選ばれるなど、高く評価される。今最も注目される期待の新鋭。