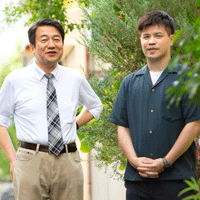思い出の味 ◈ 今村昌弘
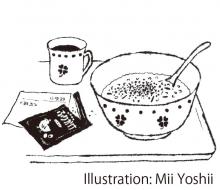
毎年インフルエンザが流行する時期になると両親から、ワクチンは受けたのか、と尋ねられます。というのも、僕はとても体の弱い幼児期を過ごしたのです。別に先天的な疾患を持っていたわけではなく、ただただ病気がちで、すぐ高熱を出しては入院するような子供でした。
そんな僕は、病中の食事のことを強く憶えています。あの頃の僕にとって、熱を出して病院に“泊まる”のはままあることだったのですが、辛かったのは食事でした。当時の病院食は味のしない、子供には物足りないもの。特におかゆなんてベチャベチャしていて、美味しいとは思えなかった。
そこで僕は親にふりかけを買ってきてもらって、それをアテにおかゆを克服したのです。シャリシャリという食感と濃い味がついただけで苦手意識がなくなるのですから、子供というのは単純なものです。これが僕の“病気ご飯”の始まりでした。
僕の病気癖は小学校に上がってからも治らず、一年生時には年間で三十六日も病欠してしまいました。それとともに“病気ご飯”も変化していくことになります。
ある時、僕は喉をひどく腫らしてしまい、親が食事をとらせようとしてもなかなか受け付けませんでした。味の強いものは喉を刺激しますし、かといって白飯だけでは食欲が湧かない。そこで母にこう頼んだのです。
「ご飯にきなこをかけて」
きなこ餅ならぬ、きなこご飯。これなら甘みで喉が刺激されず、すいすいご飯が進みます。親としても素直に食べてくれるのならと、それからは病気のたびに「ご飯には何をのせる?」と聞くのが習慣となりました。ところがある日体調を崩した僕は、こんなリクエストを出したのです。
「鯛の刺身」
可愛くないガキです。鯛の値段を知らず、素直に好きな魚をリクエストしただけなんですけどね。今考えれば料理ですらない食事ですが、あの頃の“病気ご飯”シリーズの味は、静かな部屋の中、賑やかな教室の様子を脳裏に浮かべながら憂えていた情景とともに僕の記憶に焼き付いています。
今は「咳をしても一人」。
(「STORY BOX」2018年2月号掲載)