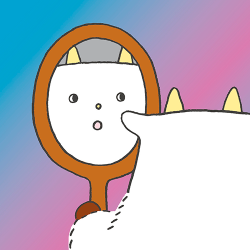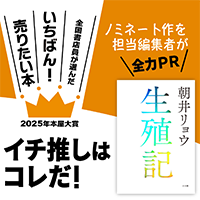朝井リョウさん『死にがいを求めて生きているの』
八組九人の作家が集結し、「対立」を共通のテーマとしてそれぞれが長篇を執筆した「螺旋」プロジェクト。その単行本第一弾が刊行された。朝井リョウさんの『死にがいを求めて生きているの』は、平成を舞台に、二人の対照的な青年の関係が綴られていく。しかし分かりやすいバトルが描かれるわけではない。そこにある、著者の意図とは?
競作プロジェクトの第一弾
「依頼をいただいた時、私からすると、文壇高校の伊坂先輩に呼んでいただいた感覚で、これは応えないわけにはいきませんでした」
と朝井リョウさん。何の話かというと、文芸誌『小説BOC』創刊時から始まった「螺旋」プロジェクトのこと。伊坂幸太郎さんと編集者の雑談のなかで生まれた競作企画で、二人に加え、天野純希、薬丸岳、乾ルカ、澤田瞳子、大森兄弟、吉田篤弘の各氏が、古代から未来にわたるまでの各時代をそれぞれ受け持ち、「対立」をテーマに小説を連載。その単行本第一弾が、平成のパートを受け持った朝井さんの『死にがいを求めて生きているの』だ。
「伊坂さんは"僕は発起人じゃない"と言いつつすごく気にしてくださって、連載中も毎回感想をくださって……今は、伊坂先輩のために最高の卒業式を! みたいな気持ちです」
競作の各作品は、繋がりのある内容になっている。「対立」というテーマだけでなく、海族と山族といった共通のモチーフ、隠れキャラクターなどが盛り込まれている。
「連載がスタートする前は何度も集まって打ち合わせをしましたが、執筆がスタートしてからは割とそれぞれで作業していたと思います。ただ、連載中、薬丸岳さんの作品に出てくる島を自分の小説にも出したいと思い、了解を得るなどのやりとりは個別にありました」
二人の幼馴染みの来し方とは
物語に登場するのは、植物状態となって入院中の青年、智也と、彼を見舞う雄介。幼馴染みで友人同士の彼らだが、性格は正反対。自己顕示欲が強く、運動会でも大学での活動でも、やりがいのあることを見つけてはりきってきた雄介と、そんな彼を冷静な目で見つめてきた智也。いま、なぜ智也は植物状態になっているのか。幼少時代からの彼らの様子が、章が替わるごとに視点人物を替え、第三者の目を通して描かれていく。
当初は、平成の「対立」をテーマに書くといっても、何も浮かばなかったという。
「今なら男女の格差といったテーマが浮かびそうですが、数年前の段階では私の引き出しの中には何もなかったんです。何度かあった連載開始前の全員集合での会議の席でも、いろんな意見が飛び交っているなか、私だけ何も発言することがなくて、縮こまってしまっていました」
日頃から原稿が書けない日は安眠や美食を自分に禁じるなど、"セルフネグレクト"に走る傾向のある朝井さん。会議の席でも、そんなふうに自分を責める心境に陥った。
「自分は無価値で意味がないなと思って。"適当に喋ればいいんだよ"と言われたとしても、どうしてもできない自分がいるんです」
この感覚が、本作のテーマに繋がっていく。
「互いに遠くにあると思っていたふたつの事象が本質的には近くにあると気づいたとき、そこに普遍性が宿ると思っています。その瞬間に小説の大きな構造が生まれる、ということがこれまでも何度かあって、今回もそうでした」
会議で無価値だと感じた自分と結びついたのは、かねてから興味を持っていた事柄。
「平成に起きた事件の中で、私にとって特に記憶に残るニュースといえば、秋葉原通り魔事件や『黒子のバスケ』脅迫事件。最近で言えば、元日の未明に二十一歳の青年が死刑制度廃止を訴えて竹下通りに車で突っ込んだ事件です。犯人の供述書や手記を読むと、共通しているのは"社会にとって自分は無価値である"という思い。たとえば『黒子のバスケ』脅迫事件の犯人は、漫画家として成功している作者に嫉妬したのが動機と思われていたけれど、途中から"そういう設定だった"とカミングアウトするんです。本当は嫉妬による攻撃ではなく、自分が生きていることを実感するための攻撃だった、と。"何もしていない社会的に無価値な自分"から脱するために、犯罪に走っていたわけです」
ふと、これらの犯人たちと、会議で何も発言できない自分が、同じ線の上にいると気づいた。
「私たちはなぜ"自分は無価値"という考え方をしてしまうのか。私は、平成とは"平らかに成る"という字のごとく、個人間の争いを省いて平らかにしていこうと試みた時代だと感じています。小説にも書きましたが、運動会で勝ち負けを決めない、テスト結果の順位は貼りださない、一番を取ろうではなく"個性を大事にしよう"というように。でも"個性"を見つけようとすると、私はやっぱり、人と自分を比べることをやめられなかった。私は二十九年間、一秒もさぼらず他者を気にして、社会の中での自分の立ち位置を把握しようとしてきたんです。ナンバーワンになるために競争して脱落する辛さではなく、オンリーワンになれと言われた先の何もない地獄のほうが、私には心当たりがあるんです」
表向きは競争が存在しないが、自分の価値を確かめるために、心の中で「これはあいつに勝った」「あれはあいつに負けた」と繰り返す日常。
「自分で自分の価値を見つけなければいけない"自分地獄"ですよね。そうすると小さな自己否定が積もっていくんですよ。それは内側から腐っていく感覚。外から殴られたなら痕がつくから"あの人は傷ついている"と分かるけれど、内側から腐っていく痛みは人には見えない」
こうした思いを抱く世代が何に悩んでいるのか分からない人は多いと思う、と朝井さん。
「日本はインフラも整っているし街もきれいだし、二十四時間食べたいものを買えるし、条件だけ抽出すると豊かですよね。だから、他国の人からすると、何がそんなに生きにくいのかと思われるかもしれない。でも、物質的には豊かになったからこそ、洗濯はボタンひとつで乾燥までできたり、生活を営むうえで最低限必要な様々な作業も時短でできるようになり、ただ生きているだけだと時間が余るのかな、と。その結果、これまでは考えなくてもよかったいろんなことを考えてしまうのかもしれないなとも思います。甘えた、贅沢な悩みなのでしょうが、何が悩みなのか見えないまま内側から腐っていくのが今の普遍的な痛みだとするなら、それを書くことによって、平成での『対立』を逆説的に書けると思いました」
章を書き進めていくうちに浮かんできたのは「自滅」という言葉。
「明確に"お前は生きる価値がない"と言われてはいないのに、勝手にはね返しを感じて自滅していく感覚が自分の中にも強くあります。先日、大きな商社に就職した年下の人と話していたら、"(個人の時代といわれるなか)自分は組織で働いていていいのか悩む"と話していて、抱かなくていい罪悪感だなと思いました。彼も何かの"はね返し"を受けているのでしょう」

その息苦しさがよく分かるのが、智也たちの大学生時代を与志樹という学生から描いた章。与志樹も雄介タイプで、意気揚々と社会的活動をしている若者と集まり時事問題を語りあうが、彼は会話についていけない。しかし他の仲間も「議論することが大事」といって、そこで満足している様子が見受けられる。
「最近、同世代で他者貢献に従事する人が増えたと感じるんです。もちろん他者貢献は素晴らしいことだけれど、なかには自分の生活を犠牲にしている人もいて、私はそれに驚いてしまいました。マズローの五大欲求の一番上は自己実現といわれていますが、彼は晩年、その上に自己超越があると発表していますよね。数年前までは自己実現を目指す人が多かったのに、最近はそこをすっ飛ばして、他者貢献することで自己超越を目指す人が増えた気がするんです」
小説内にも、ボランティア活動が行き過ぎて疲弊していく女性が登場する。
「もちろん、他者貢献と自己実現や自己超越がうまく重なっている人もいる。でも、他人のために何かしないと罪悪感をおぼえるから活動している印象の人もいます。その時、"死にがい"という言葉が浮かびました。生きよう、というより、"人生に意味を残して死のう"という感覚のほうが当てはまるというか。生きる、ということを全うするには十分整えられた先進国が必ずぶちあたることですけれど、今の日本も、生きるモチベーションが希薄になって、生きがいというより、死にがいを求める人が増えているのかな、という気持ちに行き着きました」
生きがいや死にがいがなければ生きている意味はない、なんてことはないはず。しかし、短絡的な思考へ走る傾向があるのが今の時代。
「昨年、生産性という言葉に注目が集まりましたが、自分もやっぱり、子だくさんの人や巨額の納税額を公表した人をすごいと思ってしまう。それって、生産性で人を測っているということですよね。本来は、命の価値は数字や論理的なものでとらえられないはず。人間の心理も論理的じゃないから、1+1は2ではないはずなんです。なのに論理的に判断しようとする流れを感じていて、そうしたことへのモヤモヤは今後も描けたらいいなと思っています」
言葉がまだまだ足りない
これまでも朝井さんは『何者』など、自意識や自分の価値探しに縛られる若者を書いてきた。
「今回の小説は集大成というか。これまでの他の小説が地区予選だとしたら、これは全国大会みたいな雰囲気があると思います」
作中人物では自分と重なるのは雄介、という。
「さきほど挙げた事件もそうですが、自滅精神から発生する犯罪って、なぜか犯人が男性なんですよ。だから余計、犯人と自分を重ねてしまうのかもしれません」
しかし、オンリーワンを求められる苦しみを主観的に主張するのではなく、智也という客観的な視点を置いた点に、冷静さを感じる。
「自分が間違った生き物という思いが確固としてあります。"書き手として正しくあれ"という風潮のはね返しを勝手に受けているのかもしれません。今回はじめて、登場人物の偏見のある言葉の部分一行だけ写真に撮られて拡散されたら、作者本人の意見として捉えられて批判されるのかな、なんてことを考えました」
雄介と智也の間の真実が少しずつ明かされていくなか、第六章にはプロジェクト各作品に共通するシークエンスも。
「水か何かがこぼれることをきっかけ描写にして、"対立"とは何なのかという議題で登場人物が対話を繰り広げるシーンがあります」
本作の場合、学生食堂でコーヒーがこぼれるシーンがあり、そこから智也がある考えを与志樹に語るのだが、確かに説得力がある。
今回、書きながら思ったことは、
「世の中にある感情や現象に対して、言葉のほうが少ない、ということです」
それは語彙が足りないということではなく、
「たとえば、アルコールを摂取しても正確な判断ができる状態を表す言葉が"二十歳"であったり、老々介護で七十五歳が九十五歳を殺してしまったことが"殺人罪"と言われたりするようなことですね。小説を書いていて言葉が足りないと今回はじめて感じましたが、だから書くことはなくならないのかなとも思う。言葉の選択肢をできるだけ多くもって、言葉にならないことを言葉にしていく試みを続けたいです」