米澤穂信さん『黒牢城』
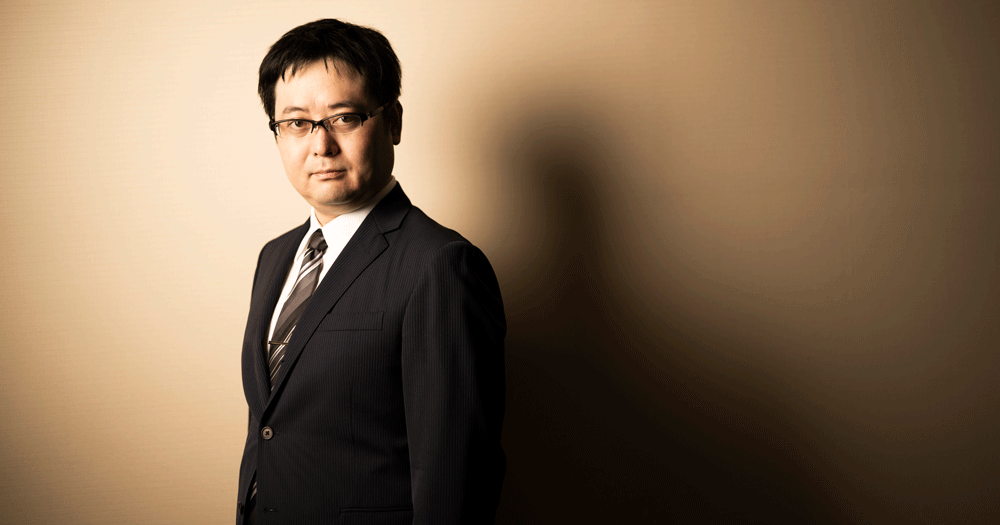
英雄と英雄が戦う話よりも、当時の世界で必死に生き抜いた人の姿が好きでした
なんと、米澤穂信さんが歴史小説を上梓。これまでにも中世ヨーロッパを舞台にした『折れた竜骨』などを発表してきたとはいえ、新作『黒牢城』は荒木村重と黒田官兵衛という、戦国時代に実在した人物が登場する。しかし読めば、これは実に米澤さんらしい本格ミステリ。執筆のきっかけは何だったのか。
雑談から生まれた戦国×本格ミステリ小説
本能寺の変から四年前を舞台にしたミステリ『黒牢城』。これが米澤穂信さんの新作だといえば驚く読者は多いだろう。だがページをめくり、緻密に構築された謎と、そこから浮かび上がる繊細な人間心理を味わいつつ最後の一行までたどり着いた時、この完成度の高さは間違いなく米澤作品だ、と思うはずだ。
執筆のきっかけは、編集者との雑談だったという。
「何の気もなしに〝地下牢に閉じ込められている黒田官兵衛を安楽椅子探偵役にしたミステリを書いてみたいんですよね〟と言ったら、〝米澤さんの小説は倫理観に特徴がある。籠城という閉鎖空間で描くとその倫理観の個性が際立つと思う〟と言っていただいたんです」
籠城する村重、幽閉された官兵衛
天正六年、織田信長に叛逆し有岡城に立てこもった荒木村重は、説得に訪れた織田方の軍師、黒田官兵衛をとらえて土牢に幽閉。その後、城内で不可解な出来事が発生するたびに、村重は秘密裡に土牢を訪れ謎を打ち明ける。だが、敵対している以上、官兵衛は協力的に推理を披露するわけではない。実に遠回しにヒントを出すのだが、その様がなんとも不気味。彼の思惑は何か。二人の関係性が微妙に変化していく様も読みどころ。ちなみに約一年後、村重は城を捨て、官兵衛は救出される。実在の人物を扱う以上、史実は動かせないという難しさはなかったのだろうか。
「歴史ものは〝こういうことがあってこうなった〟と、入口と出口は決まっている。でも、山田風太郎はその間の、書かれていない部分で波乱を仕立て上げるんです。今回は風太郎に倣って、官兵衛が捕まるという入口、村重が城を出るという出口の間に何があったのかを創作しようと考えました」
ちなみに米澤さんは、荒木村重や黒田官兵衛に対して特に好悪の感情を持っていたわけではないという。
「村重の権力基盤は何だったのか、最終的になぜ城を離れたのかには興味がありました。調べていくうちに村重の足元が強固とは言えなかったことが分かりました。本人もそれを自覚しているんですが、それでもリーダーとして持てるカードで精一杯勝負しなければならなかった。そういう状況は現代にも通じるところがありますよね。でも、小説を通じて村重を再評価してほしいという気持ちはありませんし、現在の視点でもって〝こいつは愚かだった〟と断罪するつもりもないんです」
もともと米澤さんは、英雄譚よりも敗者の話に惹かれるという。
「歴史上の人物に限らず、敗れて落ち延びていく人、流されていく人に興味があります。時代小説も英雄と英雄が戦う話よりも、当時の世界で必死に生き抜いた人の姿を読むのが好きでした。勝った人間が何を考えていたのかは、やったことを見ればある程度、分かる。しかし負けた人が本当はどういう思いを抱いていたかは知ることができない。大望破れた後どうやって生きたのか、そこに関心があります。子どもの頃、平安時代の僧侶、俊寛が謀叛を起こして鬼界ヶ島に流刑になった際、一緒に流された二人が許されて都に帰ったのに一人だけ残されたと知り、どういう気持ちで去っていく船を見ていたんだろうと思ったことがありました。その後、芥川龍之介の『俊寛』を読み、こんなふうに人の心を書く方法があったのか、とショックを受けました。そういう意味で、『黒牢城』のきっかけは『俊寛』かもしれませんね」
一方、黒田官兵衛についてはというと、
「面白い人だなあ、という思いがありました。最初は、それこそ地下牢の安楽椅子探偵としてハンニバル・レクターのようなイメージになりそうだと思っていたんです(笑)。でも、地上で戦いが行われているなかでずっと地下に閉じ込められている一年間、一体何を大切にし、何を目的として生き抜いたのかと考えて書いていくうちに、思ったよりも情の深い人間になりました」
この舞台設定だからこその謎を用意
各章のミステリにはバリエーションを持たせた。第一章「雪夜灯籠」では、安部二右衛門が織田側に寝返ったことが判明。その場合、城中に預かっていた人質を殺すのが当時の常識だが、村重は安部の人質を生かしたまま納戸に放り込むよう命じる。しかし翌朝、人質は死体となって発見される。何者かに殺されたと思われるが、納戸の周囲は雪が積もっていたにもかかわらず、誰の足跡も残されていなかった──。
「私のこれまでの読者の方も飲み込みやすいよう、最初は雪密室というミステリの定番にしました」
あるいは第三章「遠雷念仏」では、町屋の外れの庵で極秘の任務についていた僧が殺され、村重は事件前後に庵を訪れた人々の行動を確認していく。これには時代小説ならではの苦労もあったようだ。
「編集者から〝次はアリバイを読んでみたい〟と言われたんですよね(笑)。でも、当時は時計がない。辰の刻、巳の刻などと書いては引っ掛かりが生じてしまうし、かといって地の文で〝午前何時頃〟などと表記すると読者が現実に引き戻されて小説の魔法を破ってしまう。現代の言葉を使わずにどう伝えるかの工夫を考えました」
他にも、言葉や表現については相当な注意を払った。
「うっかりすると〝黒幕〟や〝糸を引く〟といった言葉を使いそうになって、ああ、これは歌舞伎が語源っぽいから戦国時代にはなかったのではないだろうか、と気づいたり。一行一行、辞書を引きながら書いていたので時間がかかりましたが、知識が増えていくことは純粋に楽しかったですし、ハリボテではない小説世界を作るためには必要なことでした。たとえば銀林みのるさんの『鉄塔 武蔵野線』って、名詞の嵐なんです。聞いたことのない名前がたくさん出てきて、ああ、あれはこういう名称なのかと知ることも多くて、それが小説世界を豊かにしていた。名詞は大事なのだなと実感しました。といっても、さかしらに当時の言葉を使うことはせず、適度に馴染ませるようにも考えました。まあ、作者の水の下のバタ足は気にせずに読んでいただけましたら(笑)」

硬質な文体ながら分かりやすく読みやすく、緊張感を保ちながら最後まで書き切った筆力はさすが。また、各章で描かれる評定(会議)の様子や、第二章「花影手柄」で細やかに描写される戦の後の首実検の段取りなど、当時の武家の習慣やルールも興味を抱かせる部分が多い。
「それは今回の裏テーマでした。エリス・ピーターズの『修道士カドフェル』のミステリ・シリーズがそうなんです。容疑者が修道院に駆けこんで祭壇にタッチすると教会の保護下におかれるので逮捕できなくなることや、イングランドとウェールズでは相続法が違うといったことがミステリの一番面白い部分に絡んでくる。歴史の勉強という感じではまったくなく、知識と物語が響き合うのが楽しかった。自分でもそういうことができないかと思いました」
官兵衛、そして側近たちとの心理戦
籠城する村重は次第に追い詰められていく。それが織田側からの軍事的圧力によってというよりも、味方側の心理的な変化によるもので、だからこそ、彼の孤独と不安がじわじわと伝わってくる。
「部下たちは村重を支えるために協力しているのではなく、村重に従えば勝てると思ったからついてきている。だから状況が変われば心は離れていく。それは今もいつの世も変わりませんよね。村重の周囲の人間については、荒木久左衛門など実在の人物も出しましたが、軍記などに登場する人物を膨らませた存在もいます。実際には関わる人間はもっと多いのですが、できるだけ登場人物を絞り、どの人物にどんな役割と思いがあるのか一人一人考えました」
そんな御前衆の面々もさまざまで、織田に対しても「攻めろ」「待て」など意見が異なるが、個々の立場がきちんと描き分けられているためその理由や状況が把握しやすい。それぞれが手柄を主張しあうため、村重が悩む場面も。
「たとえるなら、荒木株式会社が織田ホールディングスと敵対した際に、後ろ盾の本願寺グループから送り込まれた派遣チームの雑賀衆と、かつて共同プロジェクトに取り組んだ高槻衆という同業他社と、どちらに花を持たせるか、ということですよね(笑)。こういうケースは現代でも困るだろうし、当時も困ったでしょうね」
価値観の違いに興味がある
村重、官兵衛、そして周囲の人々が交錯するなか、やがて秘められた意外な思いも見えてくる。そうした複雑な人間模様から浮かび上がってくるのは、それぞれの、少しずつ異なる死生観だ。
「まさに、この小説では死生観の違いを書きたかったんです。生と死のとらえ方は個人によって違いますが、時代や文化圏によっても大きく異なります。実は当時のある死生観について、矛盾しているのではないかと感じていたんです。それをこの小説でも書こうと考えていましたが、当時の人もその矛盾を感じていたのか分からず、後世の人間が断じていいものか、ためらいがありました。でも調べていくと、あの時代でも〝おかしい〟と言っていた人がいると分かったんです。これで大丈夫だ、書ける、と思いました」
当時の価値観について、そして現代のそれとの違いについて考えさせられる面も多い本作。米澤さん自身も、もともとそこに興味があったという。
「現代の自分とは違う価値観に惹かれます。理由はふたつありますね。ひとつは、自分とは別の価値観を持つ時代、文化圏があると知ると、自分の価値観が絶対と思えなくなるから。それは独善を防いでくれる気がします。もうひとつは、自分とはまったく価値観が異なるのに、〝ここだけは分かる〟という、通底するものが見つかる時があるから。そこから、〝不易と流行〟の〝不易〟の部分を知ることができます」
これまでも、中世のヨーロッパを舞台にした『折れた竜骨』や、二〇〇一年のネパールを舞台にした『王とサーカス』など、異なる時代や場所を舞台にしてきた米澤さん。
「『黒牢城』はそれらの作品の系譜といえますね。歴史小説が書きたかったというよりも、あくまでも書きたいものの舞台がたまたま日本の歴史だったという感覚です」
では、他にも、異なる時代や文化圏を舞台にして書きたいアイデアはあるのだろうか。
「興味はいろいろありますね。今も『雨月物語』の再話のような話をあちこちの媒体で書いています。『黒牢城』を書いている最中はこんなにきついことは二度とやるものかと思いましたが、書き終えるとまた、いろんなアイデアが湧いてきますね(笑)」
米澤穂信(よねざわ・ほのぶ)
1978年岐阜県生まれ。2001年『氷菓』で第5回角川学園小説大賞奨励賞(ヤングミステリー&ホラー部門)を受賞しデビュー。11年に『折れた竜骨』で第64回日本推理作家協会賞(長編及び連作短編集部門)、14年に『満願』で第27回山本周五郎賞を受賞。他の著書に『王とサーカス』『いまさら翼といわれても』『Iの悲劇』『巴里マカロンの謎』など多数。
(文・取材/瀧井朝世 撮影/千川修)
〈「WEBきらら」2021年7月号掲載〉



