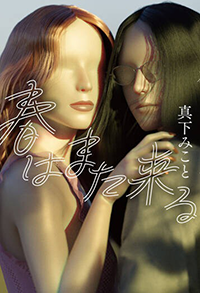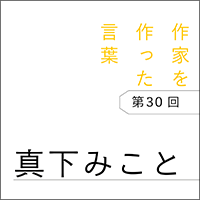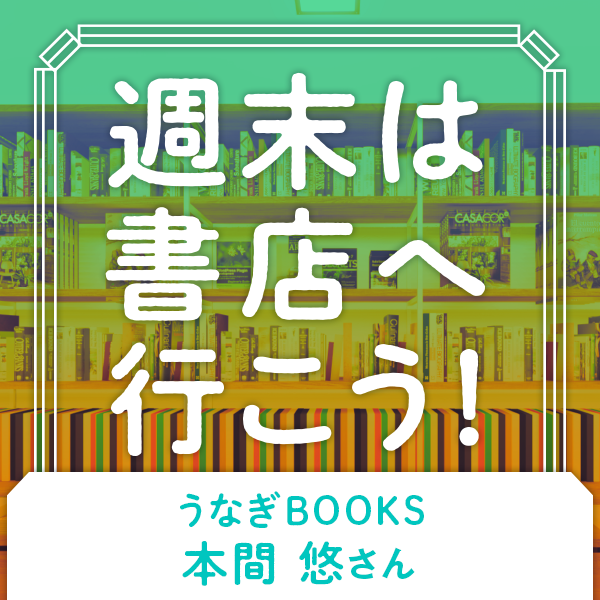真下みことさん『春はまた来る』*PickUPインタビュー*

今の自分だから描けた〝違和感〟
タイプの異なる二人の女子大学生
ひたすら勉強に励む理系の女子大学生と、お洒落が好きで、恋愛への関心が高い女子大の学生。そんな、まったくタイプの異なる女性二人がいた時、あなたは彼女たちが仲良くなれると思うだろうか、それとも? 真下みことさんの新作『春はまた来る』は、女子大に通う友人が性被害に遭ったと知り、相反する思いに葛藤し、やがて彼女なりの相手への復讐方法を考えていく理系の女子大学生の成長物語だ。
「私自身、中高時代のクラスで親しくなかった子と大学に入ったタイミングで仲良くなったことがあったんです。そういうこともあるんだなと思って。それで、高校時代は交友関係が被っていなかった二人が、大学に入ってから出会い直したらどうなるんだろうと考えました。それが出発点です」
地方から東京のW大学の理工学部に進学し、現在二年生の牧瀬順子は勉強に追われる日々を送っている。同級生には女子が少なく、一緒に課題に取り組む班の仲間も男子ばかりだ。ある時、同じ班の男子がインカレサークルで一緒だという女子大の学生を学食に連れてくる。偶然にもそれは、順子と高校時代に同級生だった倉持紗奈だった。高校時代、可愛いともてはやされていた紗奈に対し、順子は男子から「陰キャ」と呼ばれる存在だった。その頃は交流のなかった二人だが、顔を合わせるうちに少しずつ親しくなっていく。
「私が早稲田大学に通っていた頃、同級生の男子が、男子は早稲田、女子は女子大という形のインカレサークルに入っていまして。早稲田の女子は入ってはいけないという仕組みが不思議でした。それとは別に、男子から〝早稲田の女子と女子大の女子ってやっぱり全然違う〟みたいなことを言われたことがあったんです。すごく違和感が残りました。でも、その違和感の正体が分からなくて。そうしたことを小説に書きたかったんですが、当時はそれを小説にできる技術が自分には足りていない気がしていました」

その後、真下さんは大学在学中の二〇一九年に『#柚莉愛とかくれんぼ』でメフィスト賞を受賞、翌年同作を刊行して小説家デビューを果たした。
「二作目の『あさひは失敗しない』を出したあたりで、今ならあの違和感についてプロットをおこせるかもしれないと思って。二〇二二年の春くらいから二年ほど構想を練り、二〇二四年の春くらいから執筆を始めました」
真下さん自身、学生時代に学内でインカレの女子大学生を見かけることはあった。
「学校内で男友達が自分たちとは雰囲気の違う女の子を連れているのを見て、早稲田の女の子同士で〝きっとインカレサークルの子だよね〟と話していました。でも、そういう子に話しかけようとはしなかったんです。もし話しかけていたら、何か違ったんじゃないかなという思いがあります。作中、順子と紗奈はタイプが違い過ぎて仲良くなれないだろうと決めつけている男子が出てきますが、そうした先入観を軽やかに覆してくれる二人になればいいな、と思いながら書きました」
理工学部の授業の進め方や班に分かれての学習の様子も丁寧に描かれる。実験がある日は安全のために服装は長ズボン、靴はスニーカーのように足の甲が覆われたヒールのない靴が義務づけられ、大きなパソコンを入れるためにいつもリュックを背負っているなど、順子がお洒落しづらい環境にいることも分かってくる。
「私自身が理系の出身なんです。これまであまり理系の女子は書いてこなかったのですが、今回は正反対な二人を書きたくて。着飾ることが好きな紗奈に対し、順子はお洒落に興味がないうえ学部的にもそれができない状況にすることで、より対比が作れると思いました」
紗奈はT女子大学で社会コミュニケーション学科に属し、副専攻では女性学・ジェンダーを学んでいる。
「順子が周囲に壁を作って自分を守ろうとする人なので、紗奈はその壁を壊すような、コミュ力の高い人をイメージしました。副専攻については、順子がジェンダー論に明るくないので、それを教えてくれる人がほしくて。それに、ジェンダーやフェミニズムについて学んでいる人でも、いざ自分が性被害に遭った時に自分を責めてしまうことはあると思ったんです。学んできたことと起きたことに対する感情の齟齬が生じるところも描きたかった」
紗奈を可愛くて着飾ることが好きだという女性像にしたのも、順子との対比だけでなく、別の理由がある。
「性被害に遭った女性への二次加害として、〝そんな格好をしていたからだ〟などといった責められ方をしているのをSNSで見かけるので、その反論のような気持ちもあり、あえてそういう人物にしました」
「自業自得」と思ってしまう心理の不思議
ある時、紗奈はW大の近くに住むインカレサークルの先輩男性宅での飲み会に誘わる。男子三人、女子二人で飲むはずが女子の一人がドタキャン。女子一人で参加した紗奈は、そこで性被害に遭ってしまう。
「一緒に参加する予定の女子がドタキャンした時に、自分ならどうするだろうと思って。〝じゃあ私も行きません〟と言ったら自意識過剰と思われそうで嫌だな、と考えて行ってしまう気がしました」
逃げ出した紗奈が助けを求めたのが、近所に住む順子だった。その夜は部屋に連れて帰り、翌朝紗奈から事情を聞いた順子がまず抱いたのが、「自業自得じゃないのか」という思いだ。
「ここはもう、リアルなこととして書こうと思いました。現実の事件について、絶対に加害者が悪いと主張する人でも、心の奥底で、一瞬でも、自業自得かもしれないと全く思わなかったと言い切れる人っていないんじゃないかと感じていて。私の誰にも言えなかった本音がここに書かれていると思ってもらってもいいです。まったく自業自得なんかではないのに、一瞬でもそう思われてしまうのが性被害という犯罪の不思議だなと思います。なので、決して自業自得ではないと理解し、分かり合えるようになる二人を書きたかった」

事件後、紗奈は学校の友人にも被害を相談する。しかし返ってくるのは無理解な言葉ばかり。みな、そんなサークルに入るからだ、そんな飲み会に行くからだ、などと「お前が悪い」と言わんばかりで、紗奈は心の傷を深めていく。暴力事件や殺人事件では、被害者が自業自得と決めつけられることは少ないのに、性被害となるとなぜ、えてしてそう言われてしまうのか。
「実際には、どんな格好をしていようと、宅飲みに行こうと、性加害は許されないことですよね。今回、順子の自業自得と思ってしまうところを書いて感じたのは、何の落ち度もない人が性被害に遭う可能性を考えたくないのかな、ということでした。何か落ち度がある人がそういうことに巻き込まれるのであって、私には落ち度がないから関係ないと思いたいのかな、って」
そんな順子を通して、読者は彼女と一緒に紗奈と向き合っていくこととなる。
「最初は順子の視点と紗奈の視点を交互に書こうとしていたんです。でもそうすると、紗奈が被害に遭う場面も直接描かないといけなくなる。それだと不用意に心の傷をえぐられる読者もいるはず。それは避けたかったので、順子の視点だけにしました。順子の視点だけにしたことで、読者も彼女と同じように、紗奈と深く対話する体験が得られるのかなと思います」
分断を煽られる女性たち
一方、順子と同級生たちの関係も変化していく。特に村井と宮田という、紗奈と同じインカレサークルに入る男子の同級生の言動がリアルで読ませる。
「村井は、女子たちのことを決めつけて見るところがありますよね。宮田はインカレサークルの先輩のことを尊敬していますが、後にそのことを後悔する。どちらが善でどちらが悪ということもないんですが、どこか対比になる二人になればいいなと思いながら書きました」
紗奈と順子は互いと話すうちに、男子たちが女子大の学生に対してはW大の女子の悪口を言い、W大の女子の前では女子大の女子を馬鹿にしていたと知る。その際に、紗奈がこぼす言葉が印象的。
〈あいつらの目的はさ、私たちを分断することだったんじゃないかって、思うわけ〉
「高校時代も男子から可愛い女子と可愛くない女子に分けられ、大学でも女子大の女子とW大の女子に分けられている。そうやって女子同士の分断を煽って、連帯させない仕組みがあるんじゃないかと感じます」
作中、インカレの男子が女子を学年(年齢)で差別するような、あまりにひどい表現があって閉口する。実際には、インカレ内だけで使われていたわけではないという。 「学生時代、特に意識せずともどこからでも耳に入ってくる表現でした。先日早稲田出身の方たちと話す機会があったんですけれど、やはり皆さんこの表現をご存知でした。あまりに違和感のある表現なので、以前、批判的な意味をこめて別の小説に書こうとしたら、編集者に〝言葉が強すぎる〟と言って止められたことがあって。それで、書ける機会を待っていました」
タイトルの意味が二度変わる、希望のあるラスト
やがて順子は、ある行動を起こす。
「警察にも相談できなくて二次加害もあるなかで、これ以上紗奈が傷つかないようにするためには、順子ならどう行動するかを考えました。裁判を起こしたりするわけではないので読む人によっては復讐としては不十分だと思うかもしれませんが、順子にできる最大の復讐ができたかなと思います」
決して泣き寝入りしない展開に救われる思いがする。順子と紗奈の関係からは、女性の連帯というテーマも浮かび上がるが、
「二人がずっと一緒に仲良く暮らしていく話にはしたくなかったですね。それだと紗奈のように恋愛の優先順位が高い人は女性と連帯できないというメッセージを発してしまう懸念がありました。それよりも、ずっと一緒にいなくても、緊急事態が起きた時に女友達がシェルターになることは誰にでも可能なんだよ、というようなことを伝えたかったです」

それにしても、中盤で浮かび上がってくる本書のタイトルの意味が、じつに恐ろしい。
「読む前と後でタイトルの意味が変わって見える小説が好きです。〝春はまた来る〟って一見ポジティブな言葉ですけれど、この小説を読んで、すごく嫌な言葉なんだと驚きを持っていただけたら嬉しいです。ただ、どうしたら最悪の春から逃れられるかという気持ちで書き進めたので、ラストにはまた違った意味が生まれています。タイトルの意味が二度変わる、お得な小説になったのかなと思っています」
これまでに発表した作品のなかには、バッドエンドのものもある。しかし本作は、辛い出来事を描きながらも、希望のあるラストを迎える。
「デビュー前に無理してこの題材で書いていたら、バッドエンドになる可能性が高かった気がします。今このタイミングで書けて、すごくよかった。あの頃、今は書けないかもしれないと思った自分の直感が間違っていませんでした。二年の構想期間で考え尽くしてから書いたので、自信を持ってお送りできると感じています」
これからも、なにかしら自分が違和感を抱いたものについて、書いていきたい、と真摯に語ってくれた。
真下みこと(ました・みこと)
1997年生まれ。早稲田大学大学院修了。2019年『#柚莉愛とかくれんぼ』で第61回メフィスト賞を受賞し、2020年同作でデビュー。その他の著書に『あさひは失敗しない』『茜さす日に噓を隠して』『舞璃花の鬼ごっこ』『わたしの結び目』『かごいっぱいに詰め込んで』等がある。