連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第27話 色川さんと那須の土地
![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第27話 色川さんと那須の土地](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2025/02/secret-story_27_banar.png)
名作誕生の裏には秘話あり。担当編集と作家の間には、作品誕生まで実に様々なドラマがあります。一般読者には知られていない、作家の素顔が垣間見える裏話などをお伝えする連載の第27回目です。今回は、色川武大(麻雀小説は阿佐田哲也として発表)にまつわるエピソード。純文学に始まり、無頼派、エンターテインメント作家としても名を馳せた色川武大に担当編集者として携わった時の秘話を語ります。
私が講談社に入社してすぐ配属になったのが、小説現代編集部だった。新米の編集者が任されたのが、グラビアページと、俳句、短歌、川柳の応募欄、それに天野大三という雀士の1ページコラムだった。
麻雀牌の下半分に、小さな筒子(筒を輪切りにして丸く見えるようなもの)が正方形になるように4つ並んだ上方に、一列に並んだ三つの筒子が左に傾いて並んでいるのをチーピン(7筒)と言った。
ゴルフで、打ったボールが、急激に左に曲がって飛んでいくのを「チーピン」と言うのは、そこから来ている。
どうやら小説現代の編集部員は誰も麻雀をやらないらしくて、図版のチーピンの、上の三つ並んでいる筒子が右に傾いでいるのに誰も気が付かないようだった。
小説現代では、この頃、麻雀の記事に使われる麻雀牌の図版は版下屋さんに頼んで、それを活字の大きさに縮尺して銅版にする方法をとっていた。私は、翌月から、版下屋にチーピンの傾きを訂正してもらうように指示をした。
あるとき、天野さんの原稿がゲラになってきたのを見て、いつもなら空いたままになっているところに、麻雀牌がすでに活字として作られている牌活字が埋まってきたのに驚かされた。「へえ、これなら、版下屋に頼む必要がないや」と思ったのである。
阿佐田哲也さん、小島武夫さん、そして古川凱章さんといったプロの雀士たちの活躍により、「週刊大衆」や「週刊ポスト」などの週刊誌に、麻雀小説やエッセイ、それに誌上麻雀大会の記事が頻繁に載るようになって、世の中は麻雀ブームとなっていた。
![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第27話 色川さんと那須の土地 写真](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2025/02/secret-story_27_image.png)
私が勤めていた講談社のある音羽通りにも何軒のも雀荘が出来て、ゲラを待つと称して、編集者たちが徹夜で卓を囲んでいたものだ。ちなみにいまは麻雀はすっかり廃れてしまって、音羽通りには、雀荘は一軒も無くなってしまったと聞く。
ところで、牌活字はこうした麻雀ブームの中で生み出されてものだが、はじめてこれを使ったのは、やはり阿佐田哲也さんらしい。双葉社から出ている「週刊大衆」に麻雀のコラムをはじめたとき、阿佐田さんの要望で、双葉社から印刷所にその開発を頼んだという説があるのだ。
私は、阿佐田哲也名義で書かれたものは、『麻雀放浪記』をはじめ、あまり読んでいなかった。そうして、当時、人気のあったミニコミ誌「話の特集」に掲載され、1977年に刊行された色川武大名義の『怪しい来客簿』を読んでから、色川さんの作品を読むようになった。
銀座の小さなクラブで半分眠りながらソファに座っている色川さんを深夜遅く送っていくのが日課になったときもあった。
たぶん、1980年の中頃から、色川さんは、四谷の左門町の自宅から、引っ越したいと思うようになったようだ。遊び仲間が押しかけて、仕事にならないとこぼしはじめていた。
ある時、色川さんの奥さんの孝子さんが、「那須に色川武大名義の土地があるはずなの。私の父が、タケは生活能力がないからと言って、土地を残してくれたの」というようなことを言った。
孝子さんは、色川さんの従姉妹なのだ。
色川さんも、それを確かめに行って、よければそこに引越したいということだった。
那須の温泉街に向かう那須街道の交差点の一軒茶屋の近くに、会社の健康保健組合が持っている社員用の寮があって、私は那須に土地勘があった。
当時の小説現代の編集長も同行して、色川夫妻と四人で、私の運転する車で那須まで出かけることになった。
色川さんは東京を脱して、どこか静かなところで、腰を据えて執筆に備えたかったのだ。
ところが、色川さんも孝子さんも、のんびりした性格で、その土地が那須だと聞いただけで、詳しい番地は知らなかった。
一軒茶屋を左折して、山麓道路に面した不動産会社に飛び込んで、仔細を打ち明けて、色川名義の土地を台帳から探してもらうことになった。応対してくれた人は、阿佐田哲也の顔を知っていたらしく、この人のためならとばかり図面を何枚も広げては調べてくれた。
「ありました!」
三十分ばかり経ったころ、叫び声が上がった。
「ほら、ここ」
私たちが地図を覗き込むと、那須温泉神社の裏手、昔ながらの一等地に「色川」とあった。
「こりゃあ、いいところですよ」
と、不動産会社の社員は言った。
さっそく、現地に向かってみる。昔ながらの立派な別荘地に、草がぼうぼうと生えている空き地があって、そこが色川さんの敷地だった。
残念なことに、ここに自由に行き来するには車がないと不便だということになる。色川さん夫妻は運転免許を持ってないので、黒磯駅から温泉街に来るには、1時間に1本しかないバスを使うか、高いタクシーを使うかしか方法がないのだ。黒磯駅は東北本線が停まる駅で、那須温泉街に一番近い駅だ。
どうやら諦めなくてはならないと、しょんぼりした気分で、近くの「山楽」という旅館に投宿した。
そこで1泊してから、黒磯駅の近くに居を構えている、作家の谷恒生さんのお宅を訪ねて、実際に車を持たずに、那須に住むことについて意見を訊くことにした。谷さんは、『マラッカ海峡』や直木賞候補になった『喜望峰』などの海洋冒険小説のほか、伝奇小説、時代小説など幅広い作家活動をしている人だ。
色川さんの来訪を喜んで迎えてくれた谷さんは、顔をしかめながら、車がないと那須に暮らしていくのは不可能に近いと忠告してくれた。
諦めのついた色川夫妻と編集長を乗せて、一路東京への帰路を急いだ。
それから間も無くのころ、1989年になるが、色川さんが一関に引っ越したという話を聞いた。一関(現在の瀬峰町)は、有名なジャズ喫茶店「ベイシー」があるところで、ジャズに造詣の深い色川さんが、那須を諦めて、一関を選んだのには「ベイシー」が関係しているのかもしれない。
近々、色川さんが一関に借りた家を訪ねたいと思っていたら、家の電話が鳴った。
なにか悪い知らせのような鳴り方だった。
受話器から、孝子さんの緊張した声が聞こえた。
「いま病院なんだけど、イケなくなったの」と覚えているが、ぼくも慌てていたから、それも定かではない。
とにかく、悪い知らせだった。
「すぐ行きます」
私は、そう言って慌ただしく家を出た。
栗原郡瀬峰町にある病院に駆けつけたが、玄関に立っていた地元の若い人が、色川さんはもう亡くなっていると言ったことを聞いてから頭が真っ白になってしまった。それからのことはうろ覚えになっている。ただ、地元の人が車を持ってきて、色川さんの遺体を運んでくれるという話で、その車を待ったことは覚えている。
着いた車は、地元の人が作業に使うための、小型のトラックだった。毛布に包まれた色川さんは、トラックの荷台に乗せられた。私は、荷台に横になっている色川さんの脇に座った。
黙って運転台に座った若い人は高速道路に入った。一関を目指すらしい。私は、風に吹かれながら、荷台に乗って高速を走るのは違反じゃないかと思った。荷台の上で揺れる色川さんを見ていて、勝負の最中、心臓麻痺で急逝する「出目徳」のことを思い出していた。和田誠さんが映画化した『麻雀放浪記』の中では、俳優の高品格が演じた「出目徳」は裸にされ、リヤカーに乗せられて、ドブの中に捨てられるんだっけな。
車は、すぐに一関のインターに来た。そこを降りるときも、荷台に乗っている私は、咎められることはなかった。
運転する若い人は、道を心得ているらしく、色川さんの借りているお宅に迷うことなく着いた。その報を聞いて、縁側から、作家たちや編集者たちの知った顔が飛び出してきた。
そうして、アッと言う間もなく、色川さんは畳敷の部屋に運ばれていった。
私は、荷台から降りて、小さな庭のようなところに立ち尽くしていたと思うが、それもはっきりしていない。
【著者プロフィール】
宮田 昭宏
Akihiro Miyata
国際基督教大学卒業後、1968年、講談社入社。小説誌「小説現代」編集部に配属。池波正太郎、山口瞳、野坂昭如、長部日出雄、田中小実昌などを担当。1974年に純文学誌「群像」編集部に異動。林京子『ギアマン・ビードロ』、吉行淳之介『夕暮れまで』、開高健『黄昏の力』、三浦哲郎『おろおろ草子』などに関わる。1979年「群像」新人賞に応募した村上春樹に出会う。1983年、文庫PR誌「イン☆ポケット」を創刊。安部譲二の処女小説「塀の中のプレイボール」を掲載。1985年、編集長として「小説現代」に戻り、常盤新平『遠いアメリカ』、阿部牧郎『それぞれの終楽章』の直木賞受賞に関わる。2016年から配信開始した『山口瞳 電子全集』では監修者を務める。

![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第26話 丸谷才一さんと『輝く日の宮』](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2024/12/secret-story_26_banar_t-e1734341179180.png)
![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第25話 挿絵画家のはなし](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2024/11/secret-story_25_banar_t-e1731410062147.png)
![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第24話 松本清張さんと『熱い絹』](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2024/10/secret-story_24_banar_t-e1728473891678.png)
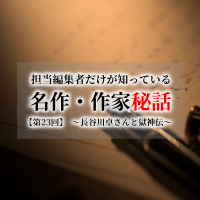
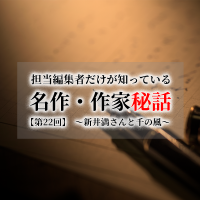
![連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第27話 色川さんと那須の土地](https://shosetsu-maru.com/wp-content/uploads/2025/02/secret-story_27_banar-600x315.png)