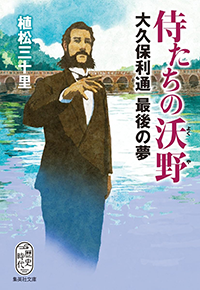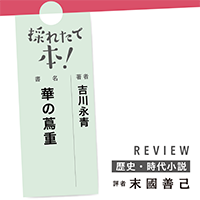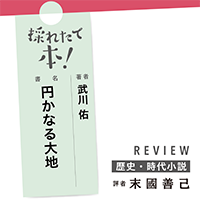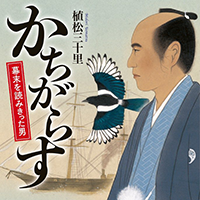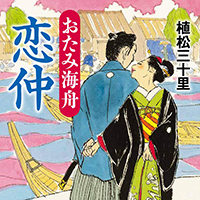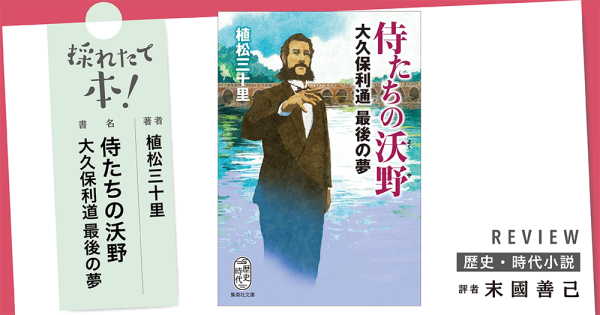採れたて本!【歴史・時代小説#27】
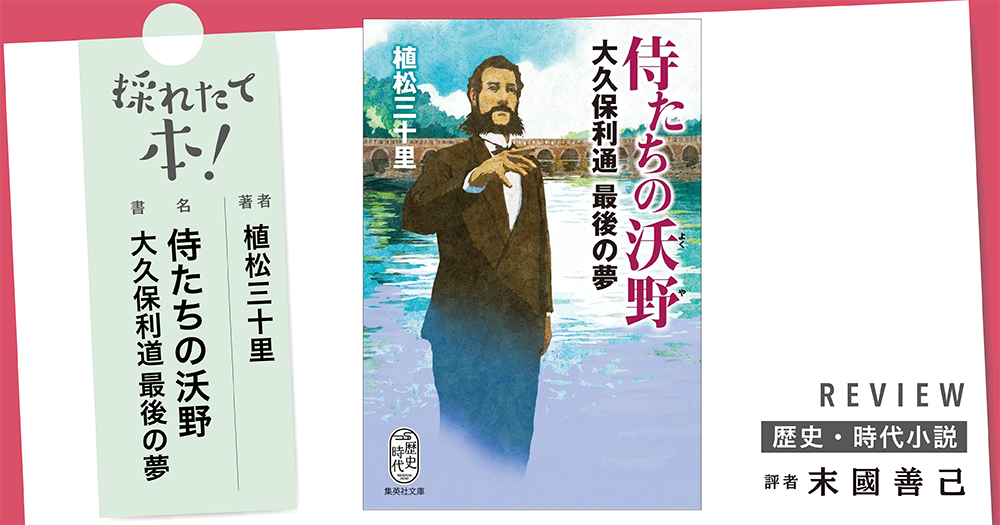
常磐炭田誕生の物語『燃えたぎる石』や『帝国ホテル建築物語』など、技術に着目した歴史小説を発表している植松三十里の新作は、明治初の国直轄の水利事業となった安積疏水建設を描いている。
豊前国金屋村(現在の大分県宇佐市)の庄屋の家に生まれた南一郎平は、父の遺志を継ぐため独学で測量、土木などを学び、川から高台の金屋村まで水路の建設を始める。明治維新前後に工費が尽きた南は、新政府から派遣された松方正義に陳情し、政府の援助で水路を完成させた。松方の誘いで内務省に入った南は、東北で大規模な新田開発を行いたい大久保利通内務卿に命じられ適地を探すため東北に向かう。南は、福島県と地域の豪商が開発し、移住者が養蚕中心の農業をしていた安積原野に目を付ける。安積原野は水が少ないものの、猪苗代湖から人工の水路(疏水)を引けば米も作れ豊かになる。
実は大久保も、安積原野での新田開発を考えていた。大久保にとって安積原野の開発は、元武士に農業という新しい仕事を与える、大規模な土木工事を日本人の手で完成させ世界に日本の実力を示す、フランス式のメートル法を普及させるなどの目的もあった。陣頭指揮を命じられた南は、現地に居を構える。
猪苗代湖の水は日橋川で会津へ流れていたが、東の郡山側の安積原野まで水路を造れば水が減るかもしれないとして、会津の農民が一揆も辞さない強硬姿勢で反対する。湖の東側も一枚岩ではなく、水路に近い地域と離れた地域では温度差があり、莫大な予算をどのように捻出するかも問題になる。賛成派と反対派が争い、費用対効果があるのかが議論されるところは現代の公共工事と同じといえる。農家出身の南が、反対派を粘り強く説得し、双方が納得できる落とし所を探ろうとする展開は理想の進め方であり、真に必要な公共工事とは何かも考えさせられる。
安積疏水の工事を後押ししていた大久保が暗殺されるが、南たちはその遺志を受け継ぎ工事の着工にこぎつける。だがフランスで土木技術を学び、蒸気機関で動くドリルやダイナマイトなどの最新機器を購入した山田寅吉が帰国するも巨大な工作機械を運ぶ方法を考える必要があったり、作業員が事故で亡くなり竜神の祟りとの噂が出たりと、困難が続く。
南は、薩摩出身で剛腕の開発責任者・奈良原繁、オランダ出身の技術者ファン・ドールン、長く留学し日本人を見下すところがある山田、金屋村の水路建設でも協力を得た眼鏡橋を造る職人集団・児島組といった異なる個性が能力を最大限発揮できる環境を整え、難しい工事、短い工期、予算不足などの難問を克服していく。裏方として安積疏水の工事を支えた南は、責任が重い、目立たない、異なる利害の間に入るので双方に恨まれる危険があるなどとして敬遠されがちな調整役の重要性を教えてくれるのである。
評者=末國善己