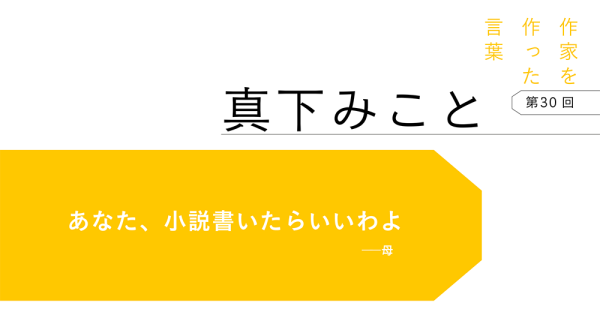作家を作った言葉〔第30回〕真下みこと
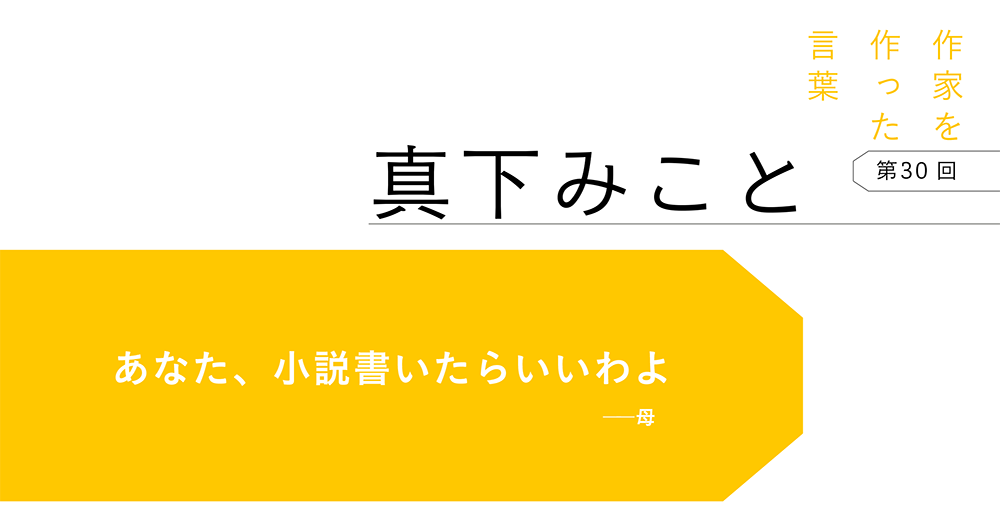
「嘘をついてはいけません」
最初にそのように言われたのがいつのことだったか、今ではよく覚えていない。大人たちに怒られているのは、大抵嘘をついた子どもだった。私は素直というか臆病な子だったので、とにかく嘘をついてはいけないのだと、怒られないように生きてきた。
中学生になった頃、夕食時に疲れた顔をした母が言った。
「面白い話をしてくれる?」
毎日働いていた母は多忙を極めており、食後はまた家で仕事をしていた。ゆっくり話を聞いてもらえるのは、夕食の時間だけだった。父は私たちが夕食を食べる時間には帰って来られず、食卓には私と母と弟がついた。私と弟は毎日学校であったことを話していたのだが、小中学生の話術には限界があり、きっと日々時間に追われている母には退屈だったのだろう。
それから私は毎日学校で何か面白いことがないかを探すことになった。しかし学校というのは基本的に勉強をする場所なので、毎日のように面白いことが起きるわけではない。悩んだ末、私はある種の嘘をつくことに決めた。面白いエピソードを完成させるため、そのエピソードに必要がないと判断した人はいなかったものとし、出来事の順番を入れ替えて再構成したのだ。
それまでも遊びで絵本を書いたり、友達を笑わせるためにギャグ漫画を書いたり、曲を作ったりはしていたが、それは完全なる趣味の創作で、嘘という感覚はなかった。しかしいるはずの友人をいないものとして語ったり、事実として起きた出来事の順番を入れ替えたりすることは、嘘と言って差し支えがないだろう。
そのようにして半分創作して作り上げた虚偽のエピソードを、私は毎日食卓でみんなに聞かせた。最初はぎこちなかったが、だんだんと話し方にも慣れてきて、ある日給食の時間に起こったエピソードを語ると、母は泣くほど笑い、こう言った。
「あなた、小説書いたらいいわよ」
学校での捏造エピソードを話すことと小説を書くことの関連性がわからなかった私は、その発言を流し、結局小説を書き始めたのはそれから八年ほど経った頃だった。母の発言も、このエッセイの依頼があり、何かないかなと考えていたところで思い出したものだ。
母のあの発言が、私にとっては嘘をついて大人に褒められた初めての経験だ。しかしそこで小説を書けと言ったということは、母は気づいていたのかもしれない。私が毎日のように、嘘をついていたのだと。
真下みこと(ました・みこと)
1997年埼玉県生まれ。2019年『#柚莉愛とかくれんぼ』で第61回メフィスト賞を受賞し、翌年デビュー。著書に『あさひは失敗しない』『茜さす日に嘘を隠して』『舞璃花の鬼ごっこ』『わたしの結び目』『かごいっぱいに詰め込んで』などがある。