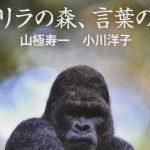小川洋子さん『サイレントシンガー』*PickUPインタビュー*

言葉を封印すると見えてくるもの
言葉から距離を置きたい人々を書いてきた
これまでも小川洋子さんは、決して表舞台に立つことなくひっそりと生きる人々の姿を掬い上げてきた。
「私はずっと、人間が作りだした言葉というものから、ちょっと距離を置きたい人を書いていますね。『博士の愛した数式』なら数字ではいくらでも表現できるけれど言葉を使っての社会参加はできない人、『猫を抱いて象と泳ぐ』ならチェスを指している間は無言でいられる人、『ことり』は小鳥としか喋れない人……。言葉を受け止めきれずに不自由さを感じている人を書き続けてきた結果、無言という究極の状態にたどり着いたという感じです」
という新作『サイレントシンガー』は、沈黙を愛する人々に寄り添った、不思議な歌声を持つ一人の女性、リリカの物語である。
「出発点はシンガーです。前から売れっ子歌手というより、そういう人の陰に隠れている人に興味がありました。たとえば誰かのコンサートに行っても、私はバックコーラスの人が気になってしまって。ああいう人は、いつか自分がセンターに行きたいと思っているのか、あるいはコーラスとしての技術を極めたいと思っているのか。気になっているうちに、仮歌歌手という人がいるのを知ったんです」

仮歌とは、有名歌手等がレコーディングする際に、どんなふうに歌ったらいいかディレクターたちのイメージをより鮮明に伝えるための見本ともいえる歌のことである。
「仮歌専門の方に取材をしたのですが、その方はデビューしたい気持ちはまったくなくて、仮歌の世界が心地いいとおっしゃっていました。それで、表現者であっても自分の個性や主張は押し出さない、むしろ自分を出したくないという人は実はたくさんいるんじゃないか、と。それに、今は自分の表現を一瞬にして世界中に発信できる道具をみんなが持っている世の中ですが、私は主張したくないんだ、という人もいるはずだという確信があります。そこで、言葉を持っていない、進化する前の人間に戻りたいというような、究極の無言を貫きたい人の居場所として、〝アカシアの野辺〟というものが浮かびました」
沈黙を愛する人々が集まる野辺
本作の主な舞台となる〝アカシアの野辺〟のはじまりは、〝内気な人の会〟と称するほんの数人のグループが敷地を金網で囲い、小川のほとりを開墾して畑を耕し、動物を飼い、沈黙を愛し、指言葉を使って暮らしはじめたもの。仲間は少しずつ増えていき、やがて彼らが住む場所は〝アカシアの野辺〟と名付けられたのである。
「〝内気な人の会〟って実際にあるんですよ。ずいぶん前ですけれど、私の小説に何か親しみを感じたのか、その会の方からお手紙をもらったことがあるんです。だから想像力だけで書いたわけではないんです。それと、修道院などでは実際に指言葉が使われているんですよね。北海道のトラピスト修道院の写真集を見ると、無言が写っている。なので、アカシアの野辺は宗教的なものとは無関係ですけれど、こういうコミュニティはわりとどこかにあるんじゃないかと私は思っているんです」
SNSなどで世界中の人と繫がることができ、それゆえ疲弊することもある昨今だからこそ、沈黙して暮らすことにはある種、憧れを抱いてしまう。
「私は一人で本を読んでいるだけで充分満足なので、そこまで誰かと繫がる必要があるのかという気がするんですよね。あるいは、たった一人、信頼できて、分かってくれて、正論で反論しない友達が一人いてくれれば、それでいい、という気がします」
ああ、だから野辺の会員たちは、森に〝自分のための木〟を持っているのか、と腑に落ちる。どうしても無言で魂を慰められない心持ちになった時、彼らはこっそりとその木の下にたち、言葉で喋りかけるという。
「私の知っている人で、ストレスが溜まった時に街路樹に抱き着くっていう人がいるんです(笑)。これも、空想だけではなくて実際にいる人のことなんです」
心くすぐるエピソードの数々は、どこから着想を得るのか
アカシアの野辺の敷地に隣接する家で、彼らの雑用係として働く祖母にリリカは育てられた。野辺の人々の子守歌を聴いて育った彼女は、彼らが羊毛を刈る際の『羊のための毛刈り歌』や、毎日夕方5時に役場から流れる『家路』を自分でも歌うようになった。
「ものを喋らない集団の人たちも、赤ん坊の泣き声と歌だけは静寂を乱さないと認めている、ということですね。同じ単語でも、喋り言葉の時とメロディーやリズムにのせて歌う時とでは、伝わり方が違いますよね。歌のほうが感情に訴えてくるというか、肉体に沁み込んで理論を超越するところがある。会話などで言葉の意味を理解するのは脳の理論的な働きによるものですが、歌声を聴くのは肉体的な体験になるように思います」

ある時役場の青年が、いつも流している『家路』を、リリカの歌声に差し替えたいと、録音の依頼にやってくる。その後、リリカにはさまざな歌の仕事が舞い込んでくる。玩具メーカーの商品〝ポピーちゃん人形〟の歌、水族館のアシカショーで披露される、アシカのジョーの歌声(ジョーが歌にあわせて口をパクパクさせる)等々、そして仮歌。どれも、歌い主が表に出ることのない仕事である。リリカは町に出掛けてはそうした仕事をこなし、野辺に帰る日々を送るようになる。
「自分が何者かを主張しない歌を歌う女の子が成長していく、ということは最初に決めていました。リリカは野辺に引きこもっている人々の居場所と町の現実的な世界との通り道となり、歌うことによって野辺の人たちに新鮮な空気を届け、同時に野辺にこもった陰鬱なものをかきだす役目を果たしているんでしょうね」
リリカは祖母の後を継いで、野辺の人々が作った野菜やお菓子や毛糸類の販売所の店番もしている。ある時から彼女は、店の常連である、有料道路の料金所で働く青年と親しくなっていく。彼の趣味は文学者たちの未発表作品発見の記事を作り、スクラップブックに貼り付けていくこと。
「ある意味、書き言葉の海に没入している青年です。極端なところまでいっているという意味では、野辺の人たちと似たもの同士なんです」
この偽の記事の内容がなんとも楽しい。カフカの未発表作品が意外なところから掘り返されたり、エミリ・ディキンスンの詩片が意外なところに隠されていたり……。
「あれは全部自分のオリジナルで、考えている時がいちばん楽しかったです(笑)」
そんな噓記事以外にも、小川さんらしい、心くすぐるエピソードや品々が作品を彩る。野辺の人々が首から下げている気象管ガラス、迷子になった男の子のために祖母が作った人形の友だち、そんな人形たちが並べられた人形公園、角が絡まった2頭の羊の顚末、ゼニガメの放生会……。個人的には、アカシアの野辺での〝さようなら〟の指言葉に心つかまれた。閉じた両方の瞼を左手の親指と人差し指で押さえるのが〝さようなら〟の指言葉。目を閉じなければ、野辺の人とはさようならはできない、というものだ。
「この指言葉は実際にあって、でも本当は違う意味なんです。書きながら実際に自分で指言葉をやってみた時に、これがさようならの意味だとすると去っていく相手の姿が見えないなと思って」

たびたび繰り返される「完全」と「不完全」という表現も心に残る。祖母いわく「人間は、完全を求めちゃいけない生きものなのさ」「野辺の人たちは、完全なる不完全を目指している」。たとえば野辺の販売所で売っているお菓子には、ひとつだけ違う形、つまり小さな不完全がしのばされている。
「ピノっていうアイスクリームは、ひとつだけ違う形のものが入っていたりするらしいですね。一個だけのはぐれものは、人間の集団の中では〝あの人変わっている〟といっていじめられたり排除されたりするけれど、見方を変えれば、ラッキーなものになる。そのイメージでした。野辺の人たちは社会に出たら不完全な人々かもしれないけれど、人間があるべきひとつの理想的で完全な姿を体現しようとしている人たちじゃないかな、というイメージもありました」
まさかのピノきっかけ。ピノしかり〝内気な人の会〟しかり指言葉しかり、小川さんは実在するものから着想を得ることも多い。以前うかがったもので忘れがたいのは、『猫を抱いて象と泳ぐ』の主人公、リトル・アリョーヒンの唇に産毛が生えている、という設定のきっかけ。
「ああ、あれは政治家の方が皮膚を喉に移植したらそこに毛が生えた、という実際の記事がヒントになったんですよね。不思議なことって、もうすでに世の中にあるんですよ。でもそうした不思議に気づかずに通り過ぎる人は多い。不思議だなとか、全然役にも立たないけれど面白いなとか、知りたいなと思えることって、やっぱり無言でいないとキャッチできないんです。美術館なんかでみんな無言でいるのは、そうでないとキャッチできないものがあるからでしょうね。お芝居を観る時だってみんなその間はずっと黙っている。なにか本質的な感受性を揺さぶられようとしたら、自分の言葉を封印しないと何も入ってこない。今、劇場へ行くと、1000人2000人の人がスマホを切って、3時間も黙ってじっとひとつの舞台を観ていますよね。舞台が人気なのは、現代人にとって異質な体験だからかもしれませんね」
ミュージカルにはまったから生まれた作品
小川さんも、舞台にはよく足を運んでいるという。
「ミュージカルにはまってしまって。シンガーに興味を持ったのも、なぜ私はミュージカルを観ている時にこんなにうっとりしてしまうのかという、その不思議がスタートだったんです。音楽は空気の振動という物理的な現象なのに、それが鼓膜を振動させて感情という形のないものになっていくのは、小説家に小説を書かせるほどの想像力をかき立てることなんです。それがきっかけで『サイレントシンガー』や『耳に棲むもの』といった小説が書けたので、ミュージカルと出会ってよかったなと思っています」
現在は、帝国劇場を舞台にした「劇場という名の星座」という小説を「すばる」で連載している。
「ミュージカルが好きだと公言していたら依頼がきたんです。建て替えのために今年2月で休館した帝国劇場の元支配人の方が、文学で帝国劇場の歴史を残しておきたいとおっしゃっていて、その相談を受けた編集者が私を推薦してくだったんです。取材で帝劇の裏の裏まで連れていってもらえて、もう本当に感謝感謝です(笑)」

数学、チェス、ハダカデバネズミ(エッセイ『とにかく散歩いたしましょう』で詳しく書いている)ほかもろもろ、そして今回の帝国劇場……。小川さんは好きなものをとことん追求するタイプでもある。
「きっと、どんな作家も、書く対象に愛を注がないと書けないですよ。作家には推し活できる素養がないと(笑)。ただ、推し活がきっかけでも、自分の中の回路を通って作品として出てきた時には、最初の推しが何だったか見当がつかないくらい遠く旅立っていないといけない、とは思います」
自作の、ひっそりと人生を送っている主人公たちについても、
「私はそういう人を推したくなるんでしょうね。この人は放っておいたらどこか世界の淵から暗闇に去っていきそうだから、私がちょっと待ちなさいと言って引き上げて、背中をさすってあげて、御迷惑じゃなければ残したいことを私が書記として文章に書いておきます、という感じですね。あるいは、何も喋らないまま去った人も化石になって残っているので、その化石の中に凝縮されている、その人の生きた世界を自分が発掘して読み解く、みたいな感じでもあります。そういう感触で書ける時のほうがうまくいきます」
では次作の「劇場という名の星座」のように、取材して書くという執筆作業の時はどのような感覚なのだろう。
「帝国劇場というのがまた魅力的な場所で、私の好みの人がたくさんいるんです。私がお金を払って観ているのは、完成された上澄みであって、その下に本当にサイレントな人々が黙々と働いている。『劇場という名の星座』というタイトルは、暗闇の中に輝いている星はいっぱいあって、それをひとつに結んだ形が劇場という星座だ、というイメージです。世界は広くて、自分が知らないところでもちゃんとそこで一心に働いている人がいる。そういう人によって世界が支えられていると思うと、とても安心します」
小川洋子(おがわ・ようこ)
1962年岡山県生まれ。1988年「揚羽蝶が壊れる時」で海燕新人文学賞を受賞。1991年「妊娠カレンダー」で芥川賞、2004年『博士の愛した数式』で読売文学賞と本屋大賞、『ブラフマンの埋葬』で泉鏡花文学賞、2006年『ミーナの行進』で谷崎潤一郎賞を受賞。その他の著書に『やさしい訴え』『ホテル・アイリス』『沈黙博物館』『アンネ・フランクの記憶』『薬指の標本』『夜明けの縁をさ迷う人々』『猫を抱いて象と泳ぐ』等。