君嶋彼方『君の顔では泣けない』
諦めた先の人生
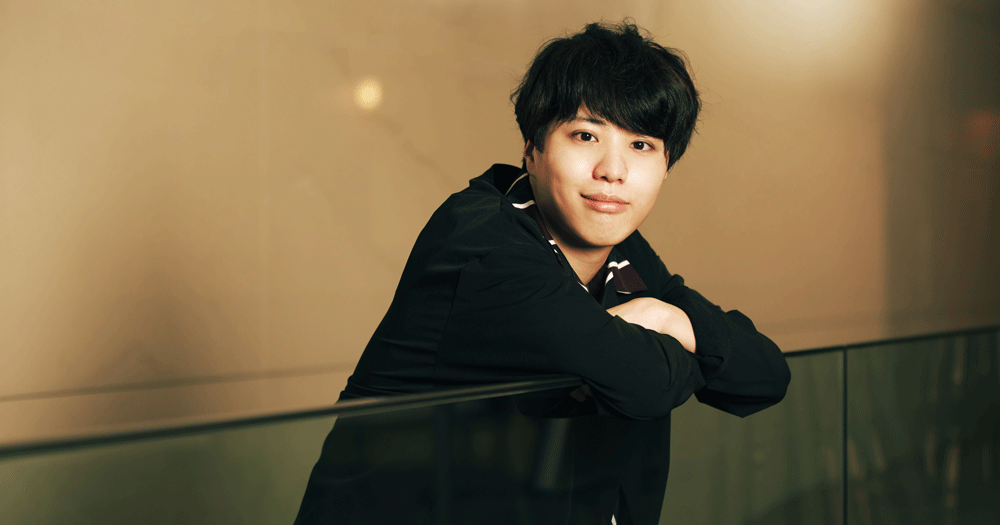
第一二回小説 野性時代新人賞を受賞した君嶋彼方の『君の顔では泣けない』は、いわゆる「男女入れ替わりもの」だ。しかし、定番のラブコメ路線には進まない。入れ替わってしまった男女の心情を透徹したリアリズムで描き出していく。そこには当該ジャンルに対する批評意識とエンターテインメントの作り手としての「逃げない」矜持があった。
心情描写こそ小説にとっての見せ場
七月の第三土曜日、東京に暮らす三〇歳のまなみは夫と三歳になる愛娘を家に残して、東京近郊の故郷へと一人で帰省する。駅で待ち合わせた人物は、陸という名前の同い年の青年だ。馴染みの喫茶店に足を運び、互いの近況を報告し合ううちに、まなみの一人称に「俺」が混じり出す。そして、決定的な文章が現れる。
〈十五年前。俺たちの体は入れ替わった。そして十五年。今に至るまで、一度も体は元に戻っていない〉
この文章の凄みは、女性の体に入った男性がセックスも妊娠も出産も全て経験した、という衝撃が書かずとも伝わってくるところにある。年齢設定も絶妙だ。
「男だった期間と女になってからの期間がイコールになる、という年齢設定にしたかったんです。キリがいいかなと思って直感で一五歳と三〇歳を選んだんですが、一〇歳と二〇歳、二〇歳と四〇歳では、自分が本当に書きたいと思う話にはならなかった気がします。一五歳だからこそ、入れ替わったことで家族や友人ともう会えない、自分が自分だと認めてもらえないといった不安を強烈なものとして書くことができた。それに三〇歳だからこそ、元にはきっともう戻らないと諦めた先でどうするか、という人生の選択まで書くことができたんです」
衝撃のオープニングシークエンスの後、時計の針は高校一年生の夏、「入れ替わり」当日の朝へと巻き戻る。まなみの体と入れ替わった陸は、初めて体験する生理の痛みに戸惑い、すすり泣いていた──。「男女入れ替わりもの」の最新形である『君の顔では泣けない』は、冒頭から同ジャンルのお約束を心地いいくらい破っていく。
「新海誠監督の『君の名は。』(二〇一六年)のずっと前から、それこそ平安時代の『とりかへばや物語』の頃から、男女の入れ替わりの物語は表現され続けてきました。そこに自分が挑戦するなら、これまでなかったようなものを目指したかった。そう考えた時に、過去の作品に対して抱いた違和感は手がかりになるなと思ったんです。例えば、女性の体に入った男子がまず最初にすることと言えば、自分の胸を揉むことですよね。でも、一時間後ぐらいだったらもしかしたらあるかもしれないですけど(笑)、〝初手でやるかな?〟と。まずはパニックになるだろう、と思ったんです。なおかつ、生理だったら泣いてしまうくらいのショックを受けるんじゃないかな、と……。この作品は話の展開が二転三転するようなタイプのものではないし、ある意味冒頭でネタバラシもしてしまっている。だからこそ、入れ替わり後の一つ一つのシチュエーション、そしてその心情描写は丁寧に書かなければいけない。この小説にとっての見せ場はそこだ、と意識していました」
入れ替わったら、絶望恋愛ではなく、同志愛
二人の男女が入れ替わったまま戻らないという設定に関しても、吟味を重ねたと言う。
「パッと浮かんだ設定だったんですが、同じような設定の作品があるかは絶対に知っておかなければいけないと思い、ネットで調べました。男女が入れ替わったまま長い時間を過ごすという設定の作品もあるにはあったものの、そのお話はラブストーリーだったんです。それは僕の書きたいことではなかったので、だったら堂々と書けるなと思いました」
実のところ、このジャンルはラブストーリー、なおかつラブコメ路線に進んでいくのが定番なのだ。
「そこが一番、僕にとって不思議だなと感じる点だったんです。自分が〝入れ替わり〟をリアルに想像したら、そこにある感情は絶望だったし、そこからどんなに想像を膨らませていっても、相手を──結局のところ自分の顔と体を好きになって恋をする、という感覚はどうしても出てこなかった。入れ替わった男女の心情を自分なりにリアルに書くならば、恋愛ではなく、同志愛を書くべきだと思いました。僕自身のもともとの好みも出ている気がしますね。入れ替わりものじゃなくても、恋愛感情とは違う男女の関係を描いている作品が好きなんです。例えば、僕が小説を書くようになったきっかけは山本文緒さんの作品を読んだことなんですが、『恋愛中毒』(一九九八年)の最後で描かれる男女の関係はうまく言葉にできません。でも、恋愛以上の強い繋がりがある。そこを自分も目指したかった」
物語の要所に据えたのは女性の人生ゆえの分岐点
物語は、一五歳の夏から時を刻む過去パートと、三〇歳の七月第三土曜日の一日を描く現在パートがスイッチしていく形式だ。
先へ進むにつれて、二人は一五年の間にどんな人生を歩むこととなったのか、どんな困難を乗り越えてきたのかという「謎」が、少しずつ明らかなものとなっていく。ただし、視点はスイッチしない。
著者は辻村深月との対談で、「日常で生活していく中で、相手の気持ちって絶対分からないじゃないですか。いくら小説とはいえそこを分からせてしまうのは、面白みもなくなるし、陸とまなみの結びつきの意味合いがちょっと変わってきちゃうんじゃないかなと思ったんです」と語っていた(「カドブン」より)。では、視点人物に陸を選んだのはなぜだったのだろう。
「物語としての面白みというか、広がりがあるのはそっちだなと思ったんです。女性には、妊娠や出産といった女性ならではの大きなイベントがありますよね。でも、男性の場合は、人生の分岐点と言えるようなイベントを設定しづらかった」
女性の人生における大イベントを、男性の作家が綴るのは相当難易度が高かったはずなのだ。しかし本作は、読者の間で「書き手は女性なのでは?」と囁かれるほど、ジェンダー描写に違和感がない。
「違う性別の体を持った人生を、微に入り細を穿ち書かなければいけないというのは確かにプレッシャーではありましたが、逃げずに書かなければ意味がないなと思っていました。とにかく自分が女の人の体になったと想像して、想像してと筆を走らせていったんですが、初体験のシーンはどうしても想像だけでは埋めきれなかった。そこは勇気を出して、妻にヒアリングしました。そういう話を聞くのは恋人であっても難しい気がするし、血の繋がった家族ならなおさら難しい。妻と結婚していなかったら、この小説を書き上げることはできなかったと思います」
ものすごく遠い存在でも他人の中には自分がいる
本作の最大の特徴は、特殊な設定とは対照的に、描かれた一つ一つのエピソードには誰しもの人生で起こりうる、感じうる普遍性が宿っている点にある。例えば、成人後に地元で開かれた高校の同窓会に出席するシーンで、陸は「こっち来ると、ちゃんとできなかったあの頃を思い出して、嫌になるんだよ」と言う。陸にとっての「ちゃんとできなかった」は、上手にまなみを演じ切ることができず、いつか元に戻った時のまなみの人生を損なってしまった……という後悔を指すが、違う意味にも聞こえる。
「僕は同窓会があっても絶対に行きたくないんですが(笑)、その理由は、今はそれなりに順風満帆でも、その場に行ったら当時の教室のことをどうしても思い出してしまうから。まさに〝ちゃんとできなかったあの頃を思い出して、嫌になる〟という言葉に尽きるかなと思います」
特殊な状況設定だからこそ出てきたように思われる言葉は、実は作家の人生と紐づいているのだ。そして、読み手の人生にも。
〈俺は色んな人たちに生かされてきて、今どうにかここにいることができている〉
入れ替わり後の人生に絶望し何度ももう無理だと諦めかけた陸が、三〇歳になった現実をしみじみと噛み締めながら心の中でつぶやいた言葉だ。だが──。
「それは僕自身が普段からずっと思っていることでもあるんです。いつか小説で使いたいなと思っていた言葉なんですが、この作品で、こういう形で落としこむことができてよかったと思っています。たとえ自分からものすごく遠い存在の他人を書いたとしても完全に他人ということはない。自分の感情というものはどこかしらで、絶対に入ってくる。他人の心を想像しながら書く楽しさと、自分はこういうことを思っているんだということを書く楽しさを、絡めていく醍醐味を味わえたのがこの小説だったんです」
高校一年の坂平陸は、同級生の水村まなみともつれるようにプールに落ちたことで体が入れ替わる。家族、友人など人間関係がリセットしてしまう。同作では生活に戸惑う十五歳と、新たな生き方を受け容れた三〇歳の陸が交互に展開される。青春小説の爽やかさを持ちながらも、「性」にまつわる違和感を正面から描き切った渾身作。
君嶋彼方(きみじま・かなた)
1989年東京都出身。2021年、「水平線は回転する」で第12回小説 野性時代新人賞を受賞。同作を改題した『君の顔では泣けない』でデビュー。選考にあたっては選考委員の辻村深月さんが「この作品を推すために選考会に臨もうと、読み終わった瞬間、強く心に決めました」と激賞。
(写真撮影/黒石あみ 文・取材/吉田大助)
〈「STORY BOX」2021年12月号掲載〉


