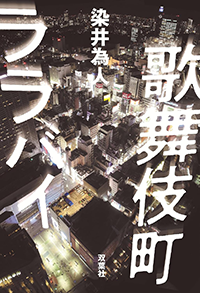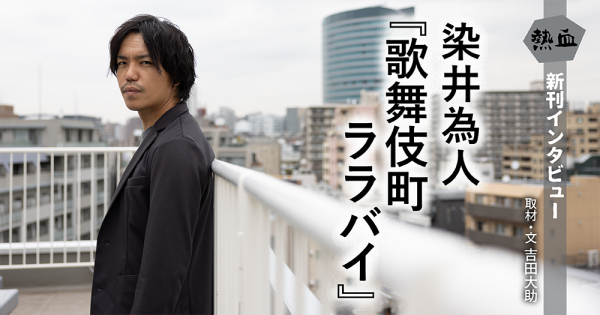染井為人『歌舞伎町ララバイ』◆熱血新刊インタビュー◆
やりすぎ、ではなく
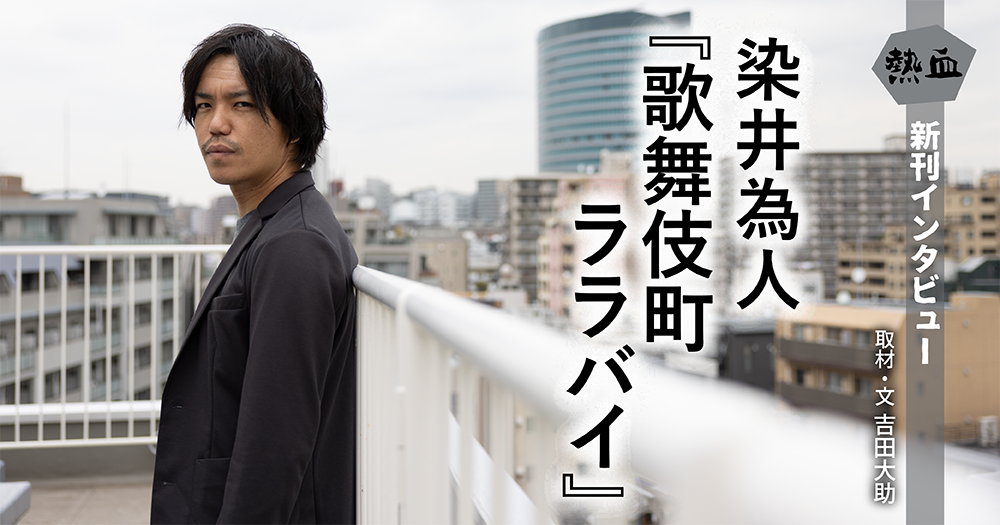
物語の出発点は、場所への興味だった。日本一、東洋一の歓楽街として知られる、新宿・歌舞伎町だ。
「もう20年くらい前になるんですが、初めて歌舞伎町へ行った頃のことはよく覚えています。当時は、見るからにヤクザだという人たちがいっぱい歩いていたんですよね。でも、周りの普通の人たちは特に怖がっている感じはない。女装している人や奇抜な格好をしている人もいっぱいいて、田舎の繁華街だとしたら彼らは目立つんだろうけど、歌舞伎町だといろんな種類の人がいすぎて気にならないんです。他人なんて気にしないという街の雰囲気に、居心地の良さを感じていました」
だが、ここ数年で街の雰囲気は変わってきている。
「もうヤクザっぽい人は見かけないですよね。ヤクザと入れ替わるように台頭してきた半グレと呼ばれる人たちは一般人の中に紛れている。これは今の社会全体の傾向ですが、犯罪が見えづらくなっているんです。一見すごく健全な、安全な街になったように見えて、実際はそうじゃないんじゃないか。〝昔のほうがまだ良かったんじゃないか?〟と」
取材も兼ねて歌舞伎町をすみずみまで歩いてみると、いくつもの衝撃が作家の胸に訪れた。
「道に立ちんぼの女の子たちがずらっと並んでいて、自分より年配のサラリーマンたちが、品定めするような顔つきでウロウロしている。しかも、目と鼻の先に警察官がいるんです。にもかかわらず平然とそういうことが行われていて、〝ここは日本だよな?〟とショックを受けました。トー横キッズ(※歌舞伎町・新宿東宝ビルの周辺の広場や路地裏でたむろする若者たち)のことも以前から気になっていたんですが、明らかに10代の子達が歌舞伎町の一角に集まっているという光景は、どこか得体の知れなさを感じました。そのすぐ近くには、48階建てのギラギラした歌舞伎町タワーがそびえている」
「路上でたむろしている若者たちと、歌舞伎町タワーの高層階にいるような大人たち、という対比に気付いたことも収穫でした」。そして、物語の想像力が大きく動いた。
「世の中で話題になったものって、必ずそれを利用しようとする人たちが出てきますよね。トー横キッズもメディアを通して存在が一気に広まった結果、その子たちを利用しようとする悪い大人たちがいっぱい出てきて、連日ニュースになっている。この構図を引っ繰り返す、というかぶち壊すような物語を書いてみたら面白いかもしれないと思ったんです」
唯一のルールは、「登場人物の感情に寄り添って書くこと」
物語は歌舞伎町タワーが建設中の、2019年10月から始まる。語り手は、トー横キッズの一人である15歳の少女・七瀬だ。言動のはしばしから自我の強さを感じさせる彼女は、中学を卒業直後、生まれ故郷の群馬を捨ててこの街へとやって来た。
「歌舞伎町やトー横キッズに関する資料を読み込んでいったところで、最初の1ページだけ、何も決めずに書いちゃったんです。〈七瀬にとって歌舞伎町は安息の地だ。(中略)なによりこの猥雑さがありがたかった。雑念を掻き消してくれるからだ。生まれてきた意味などといったくだらない考えに囚われなくて済む。それはまちがって生まれてきてしまった者にとって幸せなことだ〉。その辺りの文章を書いたことで、七瀬のキャラクターが突然立ち上がってきたんです」
七瀬は、4つ年上の〝ホス狂い〟の少女・愛莉衣の手ほどきを受けパパ活で稼いでいたが、今は別のしのぎを持っている。男の誘いに乗ったふりをしてぼったくり店に連れて行き、店からキックバックをもらう「ガールキャッチ」だ。しかし、ハメた相手が悪く、歌舞伎町一帯を取り仕切るヤクザの若頭に呼び出されてしまい──。普通だったら恐怖や不安を感じるところだろうが、このヒロインのリアクションは違う。「くそダル」。その一言に、七瀬の人間性が凝縮されている。
「僕もその四文字を書いた時、〝この子、面白い!〟と思いました。こんな時ですら冷めているというか、とんでもない肝の据わり方をしている(笑)。無鉄砲さは危うさでもあるんですが、頭は切れるし情に厚い。七瀬ちゃんの魅力に、僕自身が強烈に惹きつけられていきました」
トー横キッズのリーダー的存在となるユタカや、下っ端ヤクザの颯太。ガーナ人のドラッグディーラー・コディや、ゴールデン街のスナック「きらり」のママ・サチ。「恵まれない若者を救済し、悪い大人たちから守ること」を目的に活動しているPYPという団体の大人たち……。七瀬の日常生活の描写を通じて歌舞伎町の風景が活写されていった先で、物語は大きく動く。愛莉衣がオーバードーズで路上死してしまったのだ。その裏には、さまざまな人間の悪意があった。
「たぶん七瀬ちゃんにとって、愛莉衣ちゃんはまぶしすぎる存在だったんです。自分と似たようなつらい境遇にいたはずなのに素直で、自分の感情をストレートに出せる彼女がまぶしすぎて、腹が立つんですよね。でも、失ってみて、尊い存在だったと気づく。そんな彼女を死に追いやった人間がいたと知ってしまったら、七瀬は絶対に許せないだろうなと思うんです。僕は、小説を書くうえでのルールが一つあるんです。それは、登場人物の感情に寄り添って書くということです」
一番エンタメっぽく感じるところは、リアルなんです
第二部では時間軸が大きくジャンプし、語り口も多視点群像形式へと変貌を遂げる。社会派テイストが強かった物語の色合いもガラッと変わって、ネタバレすれすれの表現をするならば……「痛快リベンジストーリー」となるのだ。
「第一部では基本的な登場人物を出して、歌舞伎町の現実であったり、それぞれの背景にあるものを見せていく。後半にあたる第二部で、一気に仕掛けたいと思っていました」
「登場人物たちは自分の命を狙って近づいてくるのが誰かは分からないんだけれども、読者は分かっている」。物語と読者が結ぶ、うしろ暗い共犯関係がなんとも魅力的だ。
「歌舞伎町の今をそのまま反映させるような書き方であれば、もっとじっとり暗い物語になったはずなんです。でも、それは僕が書くべきものではないなと思ったんですよね。後半はがっつりエンタメ色を入れて、やりすぎだと思われるぐらいの展開もOKにしました。そうすることで、〝利用する者と利用される者〟という、歌舞伎町だけでなく今の日本社会のあらゆる場所に蔓延している構図をぶち壊したかった」
〝やりすぎ〟は、間違いなく本作の魅力だ。
「歌舞伎町の中でも、ゴールデン街ってまた特殊じゃないですか。人とすれ違うのも大変な狭いエリアに、飲み屋が密集していますよね。あの迷路のような不思議な感じを活かして、一度入ったら一生出られないような、ヘンな館を作ってみました。そこに魔女みたいな存在が一人いて……と。あそこは、やりすぎだったかもしれません(笑)」
一方で、やりすぎだと感じるかもしれないエピソードは、そうではないのかもしれない。等身大の現実と地続きかもしれない。
「ギリギリのラインを突きたかったんです。例えば、この話には政治家も出てくるんですが、政治家周りのエピソードって10年前だったらリアリティがなかったと思うんですよ。でも、日本でも元総理が銃撃されましたし、うさん臭い人物がどんどん政治家になっていく傾向が、国内外で一気に加速した。今のこの時代は何でもアリだから、ここで書いたことがまったく起きないよねとはならないんじゃないか」
エンタメ色を出すためのフィクションだと思われたところは、実はリアル。いかに今という時代が、善悪の境界線が壊れているかを象徴するエピソードだ。歌舞伎町で暗躍する殺し屋の存在も、リアルに基づいている。
「僕がいろいろな資料に当たった中で、一番怖いと思ったのは外国人が請け負う殺しの仕事です。彼らは外国からヒットマンを呼び寄せて、仕事をさせた後ですぐ帰国させる。そうすると、警察も捜査のしようがないんです。何も知らない人からするとあそこが一番エンタメっぽく感じるんじゃないかと思うんですが、リアルなんです」
振り返ってみれば染井為人という作家は、壊れた善悪の境界線を書き続けてきた。作家がこの街で物語を生み出したのは、必然だったのだ。
中学卒業と同時に親元から飛び出し歌舞伎町にたどり着いた15歳の少女・七瀬。わずか15年の人生で絶望を味わい、すべてをあきらめている七瀬にとって、歌舞伎町は唯一、心安らげる場所だった。トー横広場で仲間とダベり、危ないバイトに手を出していくうち、歌舞伎町の闇社会や家出少女たちを食い物にしようとする大人たちとも関わっていく。そして事件は起きた──。社会派サスペンスの新鋭が描く衝撃の復讐劇。
染井為人(そめい・ためひと)
1983年千葉県生まれ。芸能マネージャー、演劇プロデューサーなどを経て、2017年「悪い夏」で横溝正史ミステリ大賞優秀賞を受賞し、同作でデビュー。4作目となる『正体』は亀梨和也が主演しWOWOWで連続テレビドラマ化、横浜流星主演で映画化された。そのほかの著書に『正義の申し子』『震える天秤』『海神』などがある。