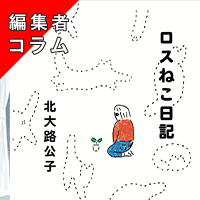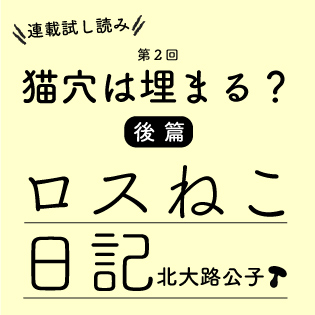ロスねこ日記 ◈ 北大路公子
インターネット、とりわけSNSを日々眺めていてつくづく思うのは、「世の中の人は猫を飼い過ぎではないか」ということであり、さらに「その猫を見せびらかし過ぎではないか」ということである。
実際、SNS界を覗くと、至るところに猫がいる。寝て起きて寝て遊んで食べておすましして寝て寝てと、おもに寝ている姿が多いが、常に誰かが猫の画像をアップしているのだ。
右を見ても猫。左を見ても猫。
これが我々の生きる二十一世紀である。インターネットは社会のさまざまな側面に光を当てたが、「人は隙あらば自分ちの猫を自慢したがる生き物である」との真実もまた明るみに出した。
まったく、これだけのスピードで通信技術が進み、なおかつ見知らぬ人からこれだけ飼い猫自慢をされる未来が来るとは思わなかった。
しかし、誤解しないでもらいたいのだが、私は人々の猫自慢を責めているわけではない。むしろ逆だ。猫はいい。家にいれば誰だって自慢したくなる。できることなら、私だってそうしたい。嬉しい時も悲しい時も寂しい時もお腹がすいた時も叱られた時も眠い時も大好きな稀勢の里が勝った時も負けた時も、とにかく猫を愛で、撫で、心を癒やし、写真を撮り、自慢し、「おりこうさんのふわふわちゃんでちゅねー」と赤ちゃん言葉で逐一SNSにアップして、皆から「化け猫キモばばあ」と呼ばれて遠巻きにされたいのだ。されたいのだが、でもされない。なぜなら猫を飼っていないからだ。
生活に猫が足りていないことは、わかっていた。飼い猫が死んで十五年近く、私の生活からはすっかり猫の気配が消えてしまった。
もちろん社会人の嗜みとして、心の中に常に猫はいる。皆もそうだろうと思う。誰にも見えない猫だが、今ではすっかり友達だ。いつだって私に寄り添い、笑い、辛い時は慰め、疲れた夜には風呂の一つも沸かしてくれて、晩酌の相手もばっちり務め、愚痴にはにゃあにゃあと相槌をうち、いざとなったら借金にも応じてくれそうなところまで成長した。だが、その猫とのやりとりをSNSで自慢したところで、別の意味の「化け猫キモばばあ」となるだけであろう。
私の心にぽっかり空いた猫の穴。脳内猫や他人の猫写真では埋め切れないその穴を、私は長く抱えて暮らしていた。そんなある日のこと、担当編集者のK嬢が言った。
「何かを育ててみてはどうでしょう」
よほど空虚な生活をしているように見えたのだろうか。あるいは事あるごとに、「本当はうちの死んだ猫が世界で一番かわいいのだが、他の人はうちの猫を知らないので、自分の猫が一番かわいいと思っている。気の毒なことであり、幸せなことでもある」など聞かされるのに飽き飽きしたのだろうか。
しかし残念ながら、我が家には今後、時間と人手が抜群にかかりそうな老親が二人いて、何かを育てるといっても、これ以上生き物を増やすのは難しい。もし二人と一匹が同時に病に倒れたらと考えただけで、気が遠くなる。私は非常に器の小さな人間なのだ。
「そういう事情なので、このお話はなかったことに……」
おずおずと断りの言葉を述べると、K嬢が思いがけない提案をした。
「動物じゃなくて植物はどうですか」
「植物?」
その考えはなかった。なかったが、「生活の潤い」という点から考えると、まんざら悪い話ではないかもしれない。緑のある暮らしは心を豊かにするともっぱらの評判であるし、花は無口であるけれども人の愛情を感じ取ることができるとも聞く。優しい言葉をかけるときれいに咲くなどという、一歩間違えば得体の知れない水やらなにやらを買わされそうな話もある。それくらい奥ゆかしくかつ繊細なのだろう。私にぴったりといえる。
ただ問題は、私が園芸方面に一切興味がないことだ。興味がないので経験もない。猫のように「あらあらめんこちゃんでちゅねー」と愛情をもって育てられるかどうか、まったくわからないのである。
「大丈夫かなあ」
「大丈夫ですよ!」
K嬢はなぜか自信満々だ。
確かに私の場合、母が俗にいう「みどりのゆび」の持ち主である。さほど熱心に世話をしている風には見えないのに、あっという間に緑を繁らせたり、花を咲かせたりするのだ。私にもその血が流れていると考えれば、ものが花だけに、一気に才能が開花する可能性もある。不安材料としては、同じ親から生まれた妹が以前、「どんな植物も私にかかれば枯れてしまう……」としょんぼりしているのを目撃してしまったことだが、しかし、もしかすると私は赤ん坊の時に誘拐されたどこぞの国の王女かもしれず、そうすると妹とは血が繋がっていないから大丈夫、と思わせておいて、同時に母とも他人ということになり、一体どこに活路を見出だせばいいのかわからないのである。何を言っているのか。
とにかく自分が種から育てた鉢植えに、ある日、可憐な花が一輪咲く。その儚げな花びらを見つめる私の胸が、徐々にあたたかなもので満たされていく。そう、猫穴が再び愛で埋まっていくのだ。
「やってみようかな」
K嬢に言うと、「いいと思います!」と私以上に乗り気になっている。
「では手始めに椎茸はどうでしょう」
「え?」
「そういう栽培キットが売っているので、育てやすいと思います」
「花は……?」
「美味しいですし」
「食べるの……?」
いや、椎茸だから当然食べるのだろうが、その場合、猫の穴を埋めるべく育てた椎茸を食べてしまうというのは、愛する猫を食べることにはならないのだろうか。というか、食べた後にはまた穴が空くのではないのだろうか。ゴールはどこにあるのだろうか。
「えーとですね、椎茸だけではなく、さまざまなものを育て美味しく食べることによって、最終的には死んだ猫への思いの昇華というか成仏的なところを目指すのです」
なるほど。丹精込めて育てた椎茸その他を食することで私は猫と同化し、その生命を永遠に自分の中に取り込むということか。取り込みたいかどうかは別にして。
(「STORY BOX」2018年1月号掲載)
*第1回後篇は、3月5日にアップ予定です