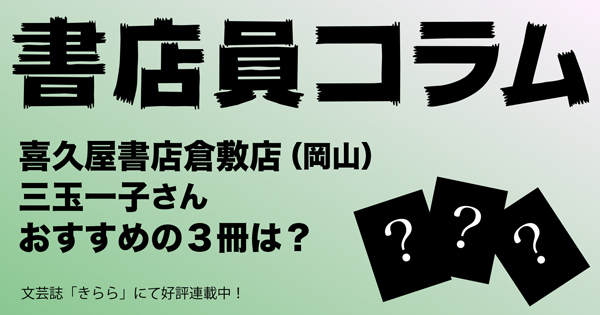つめたい空気の中で読む静けさと陰りに満ちた本たち
秋の気配が見え隠れしだす夏の終わり頃、暑さが苦手な私は一刻も早く涼しさを掴まえようとして、静けさや陰りに満ちた小説を手に取りがちだ。現実世界では出勤時はまだまだ汗だくでも、小説の中の風景を思い浮かべるだけで頭と心がひんやりと静けさに包まれる。
母親と二人暮らしのオスカルは学校でいじめにあう孤独な少年。ある日、隣にエリという少女が引っ越してきて二人は次第に心を通わせるが、彼女の周囲で全身の血を抜かれた遺体が発見される恐ろしい事件が起こる。ヨン・アイヴィデ・リンドクヴィストの『モールス』はスウェーデンの凍える大地での残酷な事件の描写と、少年とヴァンパイアの純愛という奇妙な物語展開に引き付けられる。

アーナルデュル・インドリダソンによる『湿地』はアイスランド発のミステリ。北の湿地にあるアパートで老人が殺害された。老人の机の引き出しから見つかった古い写真。それは1968年、4歳で亡くなった少女の墓を撮影したものだった。犯罪捜査官・エーレンデュルが老人と少女の関係を追ううち残酷で陰惨な結末が明らかになっていく。この作品では始終雨交じりの冷たい風が吹き荒れている。アイスランドの首都・レイキャヴィクの荒涼とした風景と寒々しい空気に読み手も包まれる。けっして爽快な読後ではないがページをめくる手を止められない。

カズオ・イシグロの近未来的小説『わたしを離さないで』は「提供者」と呼ばれる人々の世話をしている介護人のキャシーによる語りと回想で物語が進む。キャシーについても、「提供者」とはどういう人々であるかについても物語の中盤まで知らされない。キャシーや友人たちが幼い頃育った「ヘールシャム」という寄宿学校での日々も何か普通とは違う違和感を抱かせながらも、抑制の効いた語り口で綴られ謎めいている。淡々とした語り口調が物語の結末の衝撃度をより強いものにしていて、また子供時代の記憶を一層切ないものにしている。読み進めるのが次第に苦しくなるが、読み終えた後は命について、人生について、様々な思いと感情を巡らしてしまう。

ひんやりとした空気のなかで、そっと静かに物語の奥へ足を踏み入れてみてはどうだろう。