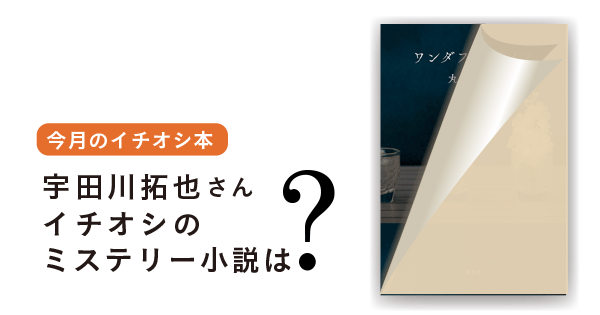今月のイチオシ本【ミステリー小説】
『ワンダフル・ライフ』
丸山正樹
それが、現実──。
ままならない日々を、そう割り切って受け入れていく生き方も、ひとつの処世術といえるのかもしれない。けれどそうすることで、目を背け、距離を置き、冷遇しているなにかを忘れてないか。丸山正樹『ワンダフル・ライフ』は、複数のケースを提示し、ミステリの手法を用いて読み手に、その〝なにか〟の一端をのぞかせようとする作品だ。
物語は四つのパートからなり、「無力の王」と題された章では、頸髄損傷で寝たきりの妻を自宅介護する男の行き詰まった「やってられない」日常が描かれる。
「真昼の月」では、子供はつくらないという前提で結婚した設計士の男が、妻に一年だけの妊活を認めさせるも実らず、さらに自分が妻について何も知らなかったと痛感する出来事が。
「不肖の子」は、広告会社に勤め、上司と不倫関係にある女性が不義の子を身ごもり、ある人物のもとを訪れて、誰にも明かせなかった内なる思いを吐露する。
「仮面の恋」は、脳性麻痺の男が自らの障害を伏せ、ネットを通じて知り合った女子大生に会うため、介助ボランティアの青年に、ある策への協力を請う。
それぞれ容易には解決できない重い悩みを抱えた人間が登場し、実際の社会問題や事件を背景にして映し出される、タイトルの〝ワンダフル・ライフ〟とは程遠い状景。それは、飲食店で見掛けた障害者差別、社会にそぐわないものを排除しようとする世相、「お母さん、僕を殺さないで」という胸が圧し潰されるような切なる訴え──などのエピソードと相まって目を釘付けにする。そして一見バラバラな各章が、最後にひとつの像を結ぶとき、この結末が「それが、現実──」と嘯く物わかりのよさを気取った大勢の生き方と決して無関係ではないのだと思い知らされる。
また本作は、〝書くこと〟についての物語でもある。それで目の前の〝現実〟がたちどころに改善されるわけではない。だが、無力なれど試み、続けることからひとは目を逸らしてはならないのだと、著者の真摯な声が聞こえてくるようだ。
(文/宇田川拓也)
〈「STORY BOX」2021年3月号掲載〉