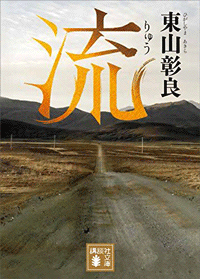SPECIAL対談 ◆ 加藤シゲアキ × 東山彰良

僕たちが信じる〝救済〟を書き続ける
『オルタネート』で第四二回吉川英治文学新人賞に輝き最も次回作が待たれる若手作家となった加藤シゲアキが、尊敬する作家として名前を挙げたのが、『流』で第一五三回直木賞を受賞した東山彰良だ。世代や作風は異なるものの、「旅」がテーマのエッセイ集を著作に持つなど、共通点も見て取れる。この日初対面となった二人が、小説の未来について語り合う。
東山作品の少年性 源泉にあるものは
加藤
僕が折に触れて「東山先生の作品が好きです」と言っていたことが、編集部から対談のオファーをいただくきっかけだったと思うんですが、今猛烈に恐縮しています。あのぉ……すごく好きです!
東山
光栄です(笑)。
加藤
東山さんの作品は強烈すぎて、他の本が読みたくなくなるぐらい放心するんです。最初に読んだのは、直木賞を受賞した『流』でした。選考委員の北方謙三さんが「二十年に一度の傑作」とおっしゃっていたじゃないですか。読んでみたら納得で、面白すぎて衝撃で。次に『僕が殺した人と僕を殺した人』を読んだらまたぶったまげて、一番新しい『怪物』を読んだら頭を抱えて……みたいな(笑)。
東山
その三作は僕のルーツである台湾を舞台にしているので、思い入れがあります。
加藤
僕は台湾の『牯嶺街(クーリンチェ)少年殺人事件』という映画が好きで、あの映画を観た時に「こういう小説が書きたい」と思ったんですが、「もうここに書かれているじゃん!」と東山さんの作品を読んで思ったんですよ。何が『クーリンチェ』を『クーリンチェ』たらしめているかと言うと、少年たちのイノセンスだったりピュアな部分。それが悲劇を生むわけなんですが、東山さんの作品の主人公にもそういった少年性を感じるんです。
東山
僕が書きたいものって、自分が子ども時代に出会った大人たちなんですよ。僕は五歳まで台湾にいたんですが、地域ぐるみで子どもを大事にしているようなコミュニティで育てられたんですね。周りの大人たちは結構口がうまくて、子どもをだまくらかして時に傷つけたりもするけれども、根本的なところでは大事に見守ってくれていた。自分にとってのそういう台湾の原風景を思い描きつつ書いているから、今加藤さんがおっしゃったような要素が出てくるのかもしれません。
加藤
子ども時代に見たものが、作家としてのルーツにあるんですね。
東山
五歳以前の記憶と日本へやって来た五歳以降の記憶が、自分の中ではっきり分かれているんです。五歳までの記憶が、楽しすぎたんでしょうね。要は、『男はつらいよ』の寅さんみたいな大人が周りにいっぱいいた。ピュアかどうかで言えば、寅さんはピュアですよね(笑)。
加藤
例えば『怪物』の主人公は現代の日本に暮らす小説家ですが、編集者の女性と恋に落ちて、相手にめちゃめちゃに翻弄される。そこから「愛と自由」について、ものすごく真面目に考え始めるじゃないですか。僕はサリンジャーが好きなんですが、『キャッチャー・イン・ザ・ライ』のホールデンに通ずる、「濁っていない感じ」がする。東山さんの作品の主人公は、少年だけではなくて大人も内面がピュアなんだと思うんです。あと、東山さんの作品を読むと声を出して笑います。
東山
それは嬉しい。
加藤
『怪物』は一番笑いましたね。ピュアとはちょっと違うかもしれないですけど、主人公が「宝があるかも」と思うと衝動的に動いてしまったり、進んじゃいけないって分かっていながら進んでいって後で猛烈に反省している姿に、めちゃくちゃ共感したんです。「自分じゃん!」と。そういう状態になると、主人公のモノローグに入ってくるビックリマーク一個でゲラゲラ笑えてしまう。そのビックリマーク、分かる、みたいな(笑)。
東山
そういうふうに言っていただけるのは、本当に嬉しいんですよ。というのも、自分が好きなタイプの小説って、栄養の部分がどこにあるかというと、ストーリーではなく地の文章だと思っているんです。誰かが昔言っていたんですけど、いい小説っていうのは、どこを開いても面白い。パッと開いたところの文章を読んで気に入ったら、それは自分にとっていい小説なんだ、と。例えば、小説を映像化しようとする時に、加藤さんがゲラゲラ笑った部分はたぶん、全部なくなっちゃうんですよ。映像としては生き残らないところが逆に、小説の面白いところだって僕は思っているんです。
加藤
東山さんの本、めっちゃ開きますよ。『流』も『僕が殺した~』も『怪物』も、本棚の一番手が届きやすい場所に置いてあるんです。マネをしたいわけではないんですけど、小説を書いている時に行き詰まったら本を開いて、「やっぱ小説はこうじゃなきゃな!」と。そこでアガる時もあれば、自分なんて……とテンションが下がる時もあるんですけど(笑)。
二人は最新作で戦争と向き合う
東山
加藤さんの『オルタネート』を拝読させてもらったんですが、すごく清々しくて、そして細かい表現を一つとっても、言葉を丁寧に選んで置いていってる感じがして、共感しました。僕には絶対書けないなと思ったんです。高校生の主人公が三人出てきて、それぞれのマッチングアプリとの関わり合い方が描かれていきますよね。僕はスマホも持っていないしSNSのことは何も分からないんですが、読んでいて気付きがあるんですよ。三人の視点がスイッチしていくから、一人に対して「別にその考え方でいけばいいんじゃない?」と思っても、もう一人の言動を見ちゃうと「あいつももう少し歩み寄れればいいのに」と意見が変わってきたり。おそらく最初から意図されていたと思うんですけど、三人のうちで自分は誰に似ているのか、と読み手が感情移入しやすい作りになっている。
加藤
そうですね。一つのツールを描く時に、そのツールに対していろいろな距離感を持った人がいたほうが立体的になるかなと思ったんです。逆に、三人の人間性の違いを際立たせるために一つのツールを使っている、という感覚もありました。
東山
その書き方がすごくよかったです。一番よかったのは、三人がそれぞれの場所で、それぞれのやり方で問題を乗り越えていくというか、自分なりの漂着点をちゃんと見つけていくところ。物語の中で、三人が無理に絡み合わなかったじゃないですか。
加藤
最後で絡み合うかなと思いながら書いていったんですが、絡み合わなかったんです(笑)。出会ったらいいなとは思いつつも、別に出会わなくてもいいかな、やっぱりこっちかな、と。
東山
今回『できることならスティードで』も読ませてもらったんですが、エッセイの合間に短い小説がいくつか挟まれていますよね。あれも、絡み合っているようで絡み合わない。二作とも、何かが起こっているようで、実は何も起こっていないとも言える。僕、そういう小説が好きなんですよ。
加藤
めちゃくちゃ嬉しいです。東山さんの作品で言えば、『どの口が愛を語るんだ』がそうですよね。あれも事件が起きていると言えば起きているんですけど、どの短編もそれこそ「どの口が愛を語るんだ」と思わされながら終わる。そうか、短編だと東山さんはこうなるのかと思った作品でした。
東山
純文学と大衆文学を分けるのって意味がないことだと思ってるんですが、あれは純文学の雑誌で発表したものを集めた本でした。『オルタネート』はかなりエンタメを意識した作品だったと思うんですが、純文学的なものというか、何も起こらないような小説へのご興味も加藤さんの中にあるんじゃないですか。
加藤
ありますね。本当はやりたいんですが、書く勇気がないんですよ。何か盛り込まないと、読者を掴めないんじゃないかって恐れが常にあるんです。
東山
いつか書いてみてほしいですね。映画で言うと、『パターソン』(ジム・ジャームッシュ監督)みたいな。
加藤
『パターソン』、大好きです!
東山
『できることならスティードで』の小説パートは、『パターソン』の匂いがしましたね。
加藤
実は、一〇月にようやく次の本が出るんです。今おっしゃっていただいた方向性ではなくて、ジャンルとしてはわりときっちりミステリーなんですが、戦争を書くというテーマを己に課したんです。書き上げる前に『怪物』を読んでいたら、筆が止まっちゃったかもしれない(笑)。マジックリアリズム的手法で戦争を描く、という発想は自分には全くなかった。
東山
僕がその書き方を選んだ理由は、真正面から戦争という題材とぶつかっていっても太刀打ちできないなと思ったからなんです。今「中央公論」で連載している小説(「邪行のビビウ」)も、架空の国の内戦の話。そこにはいろんな国の独裁者像であるとか、自分なりに考えた独裁者とは何なのかという答えを盛り込んでいるんですが、もっと力がついてきたら現実の戦争を正面から描きたいなと思っていますね。
加藤
戦争を真正面から描くことは、難しさもあると思うんですけど、向かう先は決まっているじゃないですか。書くべきことは一応決まっている、というか。マジックリアリズムで戦争を描くとなるとあまりにも自由度が高すぎて、そちらのほうが大変なのではと僕は思ってしまいます。
東山
加藤さんはどんなふうに戦争を描かれたんですか?
加藤
東山さんがルーツである台湾の歴史を掘り下げて『怪物』や『流』を書かれたように、僕も自分のルーツを掘り下げてみたんです。僕は広島で生まれているので広島の戦争についての話はたくさん知っているんですが、いや、戦争って日本全体で起きたことだよな、と。母親が秋田出身なので、秋田では戦争の時に何があったんだろうと調べてみたら、日本最後の空襲って秋田なんです。
東山
そうなんですね。知らなかった。
加藤
僕も知りませんでした。これは小説の序盤で出てくる情報なのでネタバレにはならないと思うんですけど、昭和二〇年八月一四日の午後一〇時から終戦当日の未明にかけて、秋田市で起きている。秋田の人たちは、「あと一日早く降伏してくれれば」と何度思ったか分からないですよね。祖父母が被災していたら、母は生まれていなかったかもしれない。そこの認識から戦争を書いていくことで、重心が乗っかっていく感覚がありました。広島のことも描き続けるべきだけど、他の地域について調べたり想像することも大切なことだなと思いましたね。
偽物という感覚は拭えないものか?
東山
編集部から事前にいただいた質問事項の中に、「小説を書くうえで譲れないものは?」とあったんです。結構真剣に考えたんですが、思い付かなくて。どうして思い付かないのかなと考えてみたら、僕は小説を書くうえで、何も譲ったことがない。
加藤
おおっ!!
東山
いや、かっこよさそうに聞こえるかもしれないですけど、僕の場合は幸か不幸か売り上げが出ない状態が長く続いたから、編集者もあんまり僕に無理を言わなかったんですよ。もしも「ここはこうしろ。こうすれば売れるんだから」と言ってきていたら、その時点で僕はイヤになっちゃっていたと思うんです。
加藤
それでも本を出し続けることができたわけですよね。
東山
売れてないのは知ってるけど出してくれるという人たちが運よく、途切れずに現れてくれたんです。編集者からの指摘に聞く耳を持たないというわけではないんです。むしろ逆で、指摘を受けたら全て箇条書きにして、長いこと向き合うんですよ。その中で受け入れられるもの、編集者が言っているほうが正しいと思うものを採用して、修正する場合は譲るんじゃなくって、自分が貪欲にそれを「取り入れた」って感覚になるんです。だから、譲ることはないんですよね。
加藤
なるほど。
東山
もしも自分を譲って妥協できるのがプロなんだとしたら、僕はプロではない。そもそも、僕は自分に対して偽物感があるんです。自分が作家だとは思えずここまでずっと来ている。
加藤
偽物感、めっちゃ分かります。僕は『ピンクとグレー』という最初の小説を書いた時に、書き方が分からなかったからどうしたかというと、小説家役を演じていたんです。僕の勝手なイメージで小説家っぽさを自分に課して、小説家ならこう書くだろう、小説家の言葉ってこんなふうだよね、と演じながら書いていったんですよね。今となっては演じている感覚はなくなっているんですが、落語家さんでプライベートでも落語家っぽくしゃべってる人がいるじゃないですか。それと同じで、僕も小説家を演じる感覚が体に染み付いてしまっただけなんだと思う。
東山
書類なんかを書く時に、職業欄がありますよね。何と書いているんですか?
加藤
「自営業」です(笑)。バレている時は「タレント」って書く時もありますけどね。「作家」とは書けない。
東山
全く同じです。僕も二足のわらじの時はずっと「大学非常勤講師」と書いていたんです。二〇一九年に大学の仕事を辞めちゃったので、「作家」って書くしかないんですけど、ものすごく抵抗があります。
加藤
僕は『オルタネート』で吉川英治文学新人賞をいただいて、ちょっと荷がおりたんですよ。アマチュア感覚からセミプロみたいな感覚になったんです。直木賞を取っても、偽物の感覚は拭えないものですか?
東山
全然拭えないですね。
加藤
直木賞を取っても無理なんだとしたら、僕も一生拭えない(笑)。
東山
ちなみに、ジャニーズ、というのは加藤さんのアイデンティティになっているものですか?
加藤
それが、なんでか分からないんですけど、自分のことをあんまりジャニーズだと思っていないんですよ。
東山
そこは興味があってぜひ聞きたいんですけど、「俺はジャニーズだ!」みたいな人もやっぱりいる?
加藤
います、います。ジャニーズであることを自分のアイデンティティにしている人はたくさんいて、それはそれでかっこいいなと思うんですけど、僕の場合は「そっかそっか、そういえばジャニーズだった」と思う瞬間が年に何回もありますね。それこそ小説を書いている時は、アイドルでいるよりも小説を書いている時間のほうが長いから、そういう時に現場へ行って衣装を渡されると、「なんでスパンコールを着るんだ?」みたいな。
東山
そうなるかも(笑)。
加藤
自分の感覚としては、なんでもやれるから僕はジャニーズに入ったんですよね。小説の仕事もやらせてくれたし、バラエティに出たり、歌だったりドラマだったりとか、いろんなことができるからいるだけなんですよ。なんなんでしょうね、自分。自分のことが一番分からないです。
東山
僕は台湾で生まれて日本で育ったので、よくアイデンティティのことを人に聞かれるんです。特に中国に留学していた時は、向こうの人は結構ズバッと聞いてくるんで、「自分のことを台湾人と思うのか、日本人と思うのか、それとも中国人と思うのか」と。でも、どこの人とも思えない部分があって、それこそ職業欄に「作家」って書くことができないのと同じように、ものすごく答えづらい。
加藤
あぁ、分かります。
東山
そのことに対してずっと気持ち悪い感覚があったんですけど、台湾にいる音楽をやってる友達とか、あるいは海外に長年住んでいる友達と話すと、おまえは何人だとか、おまえは何者だっていう話は別に出ないし、決めつけるようなこともしない。そういう生き方をしている人たちを見ていると、ある意味ではアイデンティティがないことがアイデンティティなんだ、という考え方もできるんだって思ったんですよね。僕は今そんな感覚なんです。
加藤
僕もその感覚、しっくりきます。
本との出会いは運命だからこそ
東山
もしも自分に十分な経済力があって、甲斐性があったら、僕はたぶん小説なんて書かずにずっと旅をしてると思うんです。それが叶わないから、小説を書いている。現実逃避なんですよね。そう考えると、好きなだけ旅をすることができるような環境になったら、つまり旅をして幸せになっちゃったら、もう小説は書かなくなるかもしれない。加藤さんは既にエンターテインメントの世界で活躍されていて、たくさん評価も受けているわけじゃないですか。その上でまだ小説を書くというエネルギーは、どんなところから来るんでしょうか。
加藤
例えばアイドルとしての活動をしていると、そこでは幸せのほうがたくさんあるんですけど、基本的には「誰かのため」なんですよね。このほうがきっとファンの人は盛り上がってくれるだろう、グループでやるならこういうことがいいだろう、関係者はきっとこういうのを求めているだろう、と。曲を作ったりもするんですけど、自分の好きなものというよりは、求められているものを作っている感覚が強いんです。だけど小説は、誰かに見せるものというよりは、自分のために、自分の好きなものを作りたい。誰かに見せるための活動の過程で溜まったモヤモヤしたものを、解消したい。基本的にはそういう原動力なんです。
東山
今のお話を僕に置き換えると、例えば家族からもらうものはたくさんあって、僕が幸せになるためには不可欠なんだけれども、思うように旅に出られないという枷にもなっている。そこで溜まっていった何かを、小説を書くことで少しずつ昇華させている。逆に、旅だけがあって、家族がいないのも考えられない。それはそれで幸せになれない。
加藤
書くこともそうだし、読むことで昇華される部分もあると思うんですよ。他の人の小説を読んで救われたなと感じたり、ラクになったりもするんです。ただ、多くの人が小説を書かなくても大丈夫なように、多くの人が本を読まなくても大丈夫だったりする。こういう仕事をしていると「本を読むことを勧めてください」とか言われることが多いんですけど、幸せだったら本なんか読まないんじゃないかなと思ってしまう。
東山
大賛成。本を読む人は、何かこじらせてますよね(笑)。
加藤
『怪物』でも近しいことが書いてありましたよね。本を読むことや書くことは孤独で、そうせずにいられないから書いたり読んだりする。でも、孤独から逃げる術を他に知っていたら、それで何も問題ないじゃないですか。僕らは本の魅力を知っていますけど、読まない人は読まないままでも幸せなんじゃないかな、無理して読まなくていいんじゃないかなと思うんです。
東山
おっしゃるとおりで、作家が「本を読め。本を読まなきゃダメだ」と言うのは、例えばプロ野球選手が「野球をやらないやつはつまんないやつだ」と言うのと一緒ですよね。我々は野球をやらなくても、楽しく生きているんですから。ただ、本に出会うべき人が出会えなかったら不幸だとは思うんです。本にはその人がこじらせているものをちょっとだけ解きほぐす力があると思うし、なんなら「こじらせたまんまでも悪くないよ」というメッセージも入っていたりする。本を読んだら救われる人が、正しい本に出会わなかったら残念なことだとは思う。
加藤
本との出会いって、運命的なものも大きいじゃないですか。「本を勧めてください」と言われても、「ごめん、無理。あなたのことそんな知らないし」みたいな。人と本を的確にマッチングするのはまず不可能だし、本との出会いは運命としか言いようがない。
東山
僕らから何か言えるとしたら、「とりあえず、何でもいいから読んでみてもいいんじゃない? もしかしたら運命の出会いになるかもしれないよ」ですかね。
加藤
少し付け加えるとしたら、「とりあえず、僕らの本はどう?」と(笑)。
対談終了後、東山のエッセイ集『Turn! Turn! Turn!』のオビの文章に目を留めた加藤が、かっこいいですねとつぶやいた。〈いつかは自分だけの一文に出会える。まずは求めよ。話はそれからだ〉。それは、収録されたエッセイの末尾の一節だった。
〈文学への信頼と書き続けることへの決意。けっきょく作家にできることはそれだけなのだ。私たちは物語の持つ救済力を信じている。すべての人に届く物語というものが存在しない以上、私たちは私たちの信じる救済を書き続けるしかない。作家によってその救済は諦めであったり、越境であったり、歴史にうずもれた叡智であったりする。私の書くものではあなたを救えないかもしれないけれど、作家は星の数ほどいる。諦めずに求め続ければ、いつかは自分だけの一文に出会える。まずは求めよ。話はそれからだ〉
まずは求めよ。そう。全てはそこから始まるのだ。
加藤シゲアキ(かとう・しげあき)
1987年生まれ。大阪府出身。青山学院大学法学部卒。NEWSのメンバーとして活動しながら、2012年『ピンクとグレー』で作家デビュー。21年、『オルタネート』で吉川英治文学新人賞、高校生直木賞を受賞。同作は直木賞候補にもなり話題に。他の小説に『閃光スクランブル』『傘をもたない蟻たちは』『チュベローズで待ってる AGE22・AGE32』など。エッセイ集に『できることならスティードで』がある。
東山彰良(ひがしやま・あきら)
1968年生まれ。台湾台北市出身。5歳の時に日本に移住。2003年、「このミステリーがすごい!」大賞銀賞・読者賞受賞の長編を改題した『逃亡作法 TURD ON THE RUN』でデビュー。09年『路傍』で大藪春彦賞、15年『流』で直木賞を受賞。16年『罪の終わり』で中央公論文芸賞、17年に『僕が殺した人と僕を殺した人』で織田作之助賞、読売文学賞、渡辺淳一文学賞を受賞。
(構成/吉田大助)
〈「STORY BOX」2023年9月号掲載〉