著者の窓 第15回 ◈ 東山彰良『怪物』
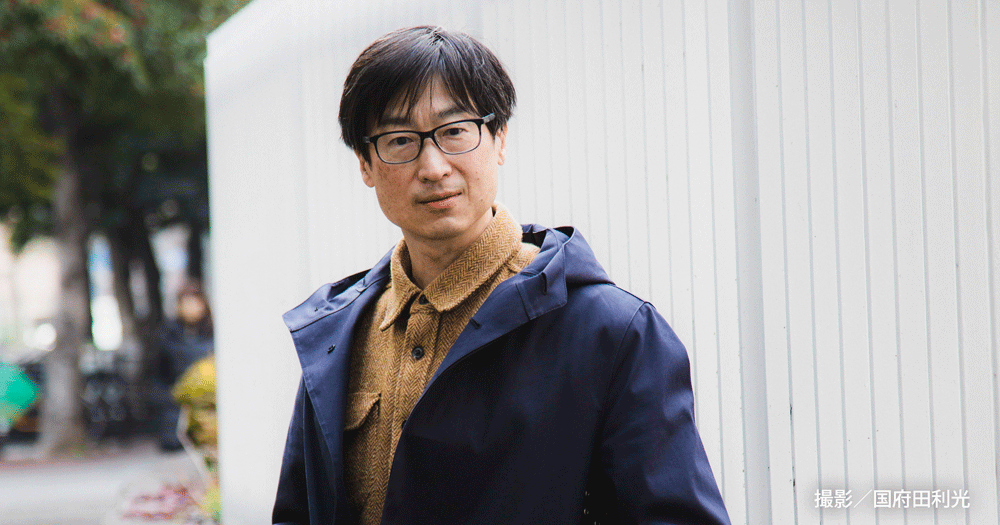
東山彰良さんの新作『怪物』(新潮社)は、日本・台湾・中国を舞台にした圧倒的スケールのエンターテインメント。出版社の女性社員との不倫関係に陥った、台湾出身の作家・柏山康平。彼の叔父で、台湾から大躍進政策時代の中国に飛行した王康平。二〇一六年と一九六二年、ふたつの物語は柏山の書いた小説『怪物』において重なり合います。愛と自由、虚構と現実。東山ワールドのテーマが凝縮した渾身の作について、お話をうかがいます。
男女の恋愛を書いてみたかった
──『怪物』は二〇二〇年から二一年にかけて『東京新聞』などに連載された長編小説です。現代の小説家・柏山康平と、毛沢東政権下の中国に墜落した台湾空軍のスパイ・鹿康平。二人の男の物語が共存する野心的なエンターテインメントですが、執筆の経緯を教えていただけますか。
この小説で第一に書きたかったのは男女の恋愛なんです。愛というテーマは短編では扱ってきましたが、長編で本格的に扱ったことはなかった。それに初挑戦してみたいというのが出発点でした。それとここ数年、歴史的な出来事をどうすれば現代のエンターテインメント小説に落とし込めるのかということをよく考えていて、この二つの問題をしばらく頭の中で同居させていたんですね。ピースがぴたっとはまったと感じたのは、父親と雑談していた時です。かつて台湾空軍に「黒蝙蝠中隊」と呼ばれる秘密の部隊があったことを知って、作品の全体像が見えてきました。
──一九五〇年代に設立された黒蝙蝠中隊は、中国大陸での偵察やアジテーションを任務とした部隊だそうですね。この史実のどこに反応されたのでしょう。
主人公の叔父が黒蝙蝠中隊にいたことにすれば、史実を無理なく作品に織り込めて、日本と台湾と中国を舞台にしたスケールの大きな作品が書けると思ったんです。しかも主人公を作家にすれば、史実をなぞるだけでなく、作中作の形でもっとはちゃめちゃな展開にすることもできる。設定として申し分ないと思いました。
主人公・柏山に自分の葛藤を投影して
──柏山康平は台北出身で、日本で活躍している小説家。叔父をモデルにした小説『怪物』によって国際的な評価を獲得した彼は、東山さんのプロフィールと重なる部分が多いですね。
ええ、自分自身をモデルにしたキャラクターです。もちろん編集者と不倫したり、そのせいでトラブルに巻き込まれたりという部分はフィクションですが(笑)、その過程で柏山が考えることは普段から考えていることと近いですね。たとえば彼は、自分が作家として偽物なんじゃないか、という感覚を抱いていますが、それは僕もデビュー以来ずっと思っていることです。二十年前に初めて書いた小説でデビューして、直木賞を受賞しても、まだ自分が本物の作家じゃないという気持ちがどこか拭えない。そうした葛藤を、柏山にストレートに仮託して書いています。

──柏山の叔父・王康平は、元黒蝙蝠中隊の隊員です。中国から奇跡の生還を果たした王康平の人生が、柏山に『怪物』を書かせることになりました。
王康平のモデルにあたるような叔父はいませんが、柏山の過去にはかなり自伝的な要素が入り交じっています。うちは父方も母方も大陸から台湾に渡ってきたいわゆる外省人で、陸軍中将だった母方の祖父をはじめとして、親戚には軍の関係者が多かった。祖父の体には銃で撃たれた傷跡がありました。僕自身もプロパガンダ教育を受けた世代で、大きくなったら兵隊さんになるんだ、と言って育ちました。よく分からないなりに戦争が身近なところにあるという感覚は、この作品に反映されていると思います。
──『怪物』が台湾でも翻訳出版されることになり、柏山は久しぶりに故国の土を踏みます。その旅の途中、同行した出版社社員・椎葉リサと一夜をともにした柏山。リサに夫がいることが分かった後も二人の関係は続き、柏山は愛について考えることになります。
自由とか孤独とか魂とか、そういう人が恥ずかしがって書かないようなテーマを臆面なく扱うのが好きなので、愛についても普段からよく考えているんです。自由よりも、愛はもっと曖昧で捉えどころがない。実際は愛じゃないものを、ごまかして愛に見せかけることもできますよね。愛の存在はどうすれば証明できるのか。ひと言では言いつくせないので、長い物語に託しました。
「大躍進政策」の惨禍を描いたわけ
──柏山の小説が大好きだと言いつつ、別の男性とも関係を持っていたリサ。彼女のようなキャラクターは、これまでの東山作品にはあまり登場していませんでしたね。
これまで僕が書いてきた女性は割と一面的で、気が強くて情に厚くて、というキャラクターが多かったですからね。今回はそれとは違った人物造型をするべきだと思っていました。誤解のないように言っておきますが、リサに具体的なモデルはいませんよ(笑)。柏山は僕がモデルでも、リサは架空の人物です。
──不倫関係を続ける柏山の前には、死亡した叔父の過去を知るという謎めいた女性・藤巻琴里が登場。台北にいるはずの従兄の幻を東京で見かけるなど、柏山の日常は少しずつ壊れていきます。
第一部は現実を書いているようで、柏山の見ている夢とも解釈できるんです。この小説が夢かもしれないというのは冒頭で宣言しているとおりです。第二部は柏山が失恋の痛手から立ち直って、現実に戻ってくるまでの物語。ただし彼にとっての現実とはフィクションの世界なので、結局彼は小説に戻ってくることになります。そうして書き上げられた作品が第三部の作中作『怪物』です。
──そんな柏山の物語と並行して、一九五〇年代末の中国に墜落した鹿康平の冒険譚が断片的に語られます。当時の中国は毛沢東が主導した「大躍進政策」によって、多くの人が飢えと暴力に苦しめられていました。
僕は大学院で中国経済を学んだので、大躍進政策についても多少知識があります。文化大革命や国共内戦、抗日戦争という大きな事件に挟まれてあまりスポットが当たることはありませんが、知れば知るほど悲惨な時代なんですね。文化大革命や抗日戦争については、すでに中国の作家たちが優れた作品をたくさん書いていますし、大躍進政策の時代と現代を融合させることで、僕なりの歴史ものが書けるんじゃないかと思いました。

──非科学的な政策によって、ばたばたと人の命が失われていく。怖い時代だなと思いました。
とはいえこの時代がどうしても書きたかったわけではないですし、批判的な意図も特にありません。人間性がむき出しになる極限状況としてこの時代を扱っているので、何ならゾンビのはびこる世界でもよかったんですよ。
──身分を隠して生きる鹿康平の運命を左右するのが、広東省の農村に君臨する蘇大方。〝怪物〟と呼ばれたこの男は、物語の中で強烈な存在感を放っています。
子供の頃、僕は中国の毛沢東を牙の生えた怪物のように思っていました。プロパガンダ教育によって、そんなイメージを植え付けられていたんです。後年、毛沢東の肖像画を見て、そのへんのおじさんと変わらないのでびっくりしました。この小説でもおとぎ話の怪物のように思えた蘇大方が、次第に絶対悪でないことが分かってくる、という書き方を心がけています。蘇大方は家族や近隣住民を守るために、怪物としての生き方を選んだ。それが鹿康平の人生と対立することになります。
現実とフィクションは影響を及ぼし合うもの
──中国で鹿康平と行動をともにするのがシャオという少女です。危険な状況の中で育ってゆく、二人の淡い関係も印象的でした。
この小説では愛というテーマを、さまざまなシチュエーションで反復させているんです。柏山とリサ、鹿康平とシャオ、あるいは離婚した柏山の両親もそうですね。それによって柏山の立っている分岐点を、より印象づけたいと考えました。
──鹿康平はどのように蘇大方のもとを逃れ、台湾に帰ってきたのか。語られることがない歴史の空白を作中作『怪物』は語り直します。面白いのはその内容が、柏山の心境を受けて変化していくことです。
この作品を一言で表現するなら「失恋した作家が加筆修正をする話」(笑)。柏山の心境の変化と『怪物』に施された加筆修正が、響き合うような構成にしたいと思っていました。現実と物語が影響を及ぼし合うというのは、作家としてはごく自然な感覚なんです。僕を取り巻いている現実は書いている物語に影響しますし、書いたり読んだりした物語は実人生に影響を与える。日常的に起こっていることなので、作中作をこのように扱うのが一番しっくりきたんですね。
──さまざまな葛藤を経て、柏山は愛についてひとつの答えを手にします。その結果、自分が本来いるべき場所に戻ってくる。力強く、感動的なシーンです。
この答えは事前に用意していたものではなく、推敲している間にふっと浮かんできたもの。格好つけた言い方をするなら、作者が作品に教わったということになるでしょうか。これが愛についての普遍的な答えではないかもしれないけど、柏山にとっては正しい答えなのだろうなと思います。
魂が弱らない限りは、自由な小説を書き続けたい
──第三部に置かれているのは、加筆修正を施された『怪物』の途中部分。疾走感のある鹿康平の物語から、迷いを断ち切った柏山の心情が浮かんできました。
終わり方をどうするかは迷いましたし、編集者さんとも相談しました。作中作をもっと前に置いて、柏山が立ち直るシーンで終わるという案も考えたんですが、今の形にしてよかったと思います。作品に広がりが出ましたから。

──忘れてはいけない歴史を取り込みながら、圧倒的に面白いエンターテインメントを作り上げる。フィクションでしかできない方法で歴史に対峙する、東山さんの覚悟のようなものも感じました。
ありがとうございます。小説の存在意義ってどこにあるんだろう、ということをよく考えるんですが、その答えのひとつに「戦争」というキーワードがある気がするんですね。といっても戦争をそのまま描くのではなく、かつて起こった悲惨な出来事を、我々にとって他人事じゃない物語として描き出す。それが小説の役目のひとつじゃないのかなと。史実を書くといってもNHKのドキュメンタリー番組のようにするのではなく、あくまでエンターテインメントの要素として扱うのが、自分の仕事だと思っています。
──過去と現在が入り交じり、作中作と現実が影響を及ぼし合う。どこに向かっていくのか予想がつかない小説そのものが、自由というテーマを体現しているようにも感じました。
いつも自分でもどこに漂着するか分からないまま書いているので、そういう勢いが生まれているのかもしれません。小説を書く時に気をつけていることは、決して物語を無理に終わらせようとしないこと。物語が自然に終わる地点まで、伴走するような気持ちで書いています。僕の大好きなチャールズ・ブコウスキーは「魂が弱ってくると形式が出てくる」と言っています。自分の魂がまだ弱っていないことを証明するために、これからも自由な作品を書いていきたいです。
東山彰良(ひがしやま・あきら)
1968年台湾台北市生まれ。9歳の時に家族で福岡県に移住。2003年、「このミステリーがすごい!」大賞銀賞・読者賞受賞の長編を改題した『逃亡作法 TURD ON THE RUN』でデビュー。09年『路傍』で大藪春彦賞、15年『流』で直木賞、16年『罪の終わり』で中央公論文芸賞を受賞。17年から18年にかけて『僕が殺した人と僕を殺した人』で、織田作之助賞、読売文学賞、渡辺淳一文学賞を受賞する。他に『夜汐』『どの口が愛を語るんだ』など著書多数。

(インタビュー/朝宮運河 取材中写真/松田麻樹)
〈「本の窓」2022年5月号掲載〉







