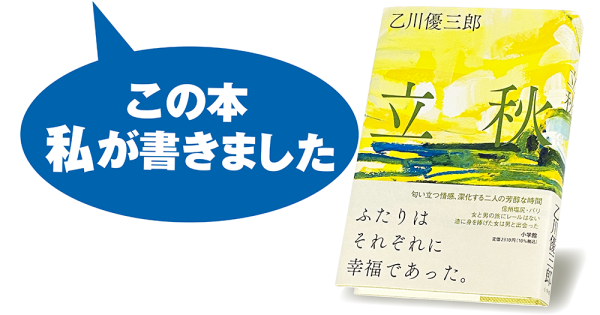乙川優三郎『立秋』
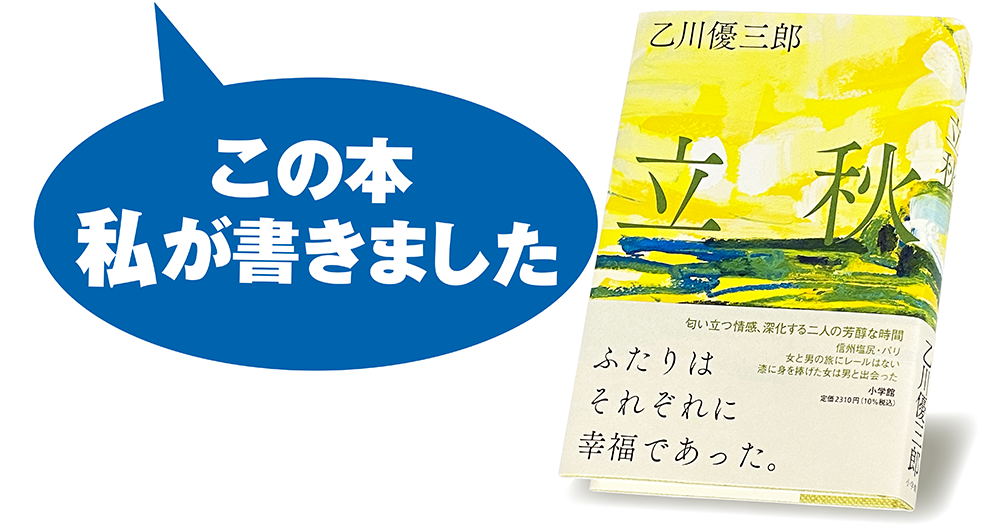
小説の中のリアル
いわゆるやくざの親分らしい人の家で、父とその人が花札をするのを見ていたことがある。なにもない30畳ほどの和室の中央、床の間に日本刀、私は小学生。その日、父は負けたと思う。勝っていたら、どこかで豪遊したはずだから。
叔父が訪ねてきて、白鞘の日本刀を振りまわしたことがある。父が金を与えないためであった。暴れはじめた叔父に父は棒切れで立ち向かい、なんとか追い払った。兄弟のすることかと私は思ったが、真剣の怖さを思い知り、なにも言えなかった。それから60余年を経た今でも、銃より怖いと思っている。
そうしたことを小説の中で書くと、信じてもらえないが、常識では考えられないことが世の中にはたくさんあると思う。私は自分の経験から考えられることを書くので、およそ非常識な物語になることが多い。今どきこんな人はいないという意見をよく聞くが、そういう人を見たことがないから、いない、と決めつける人たちは、ではなにを知っているのかと疑いたくなる。マルコスの非道を書いたときも、本当ですかあ、と鼻で笑う人がいたが、戒厳令下のフィリピンに住んでいた私は、その怖さを多少なりと知っている。頭だけで生きている人には見えないリアルというものがあって、文章でなんとか伝えようと試みるのが小説かもしれない。
病院の待合室で、それは美しい日本語を話すご婦人を見かけたことがある。見た目はごく普通の人だが、とにかく美しい言葉遣いに惚れ惚れした。こういう人も小説の中に出てくると、そんな人はいないということになってしまうような気がする。しかしリアルを捨てたくはないので、私は書くことにしている。その結果、おとぎ話として笑われる。
小説世界の中の男と女は、より自由でいいと考えている。その生き方に私は私の知るリアルを重ねる。「立秋」のふたりは平均的な常識人ではないが、こういう人たちはいると確信している。
乙川優三郎(おとかわ・ゆうざぶろう)
1953年東京都生れ。96年『藪燕』でオール讀物新人賞を受賞。97年『霧の橋』で時代小説大賞を、2001年『五年の梅』で山本周五郎賞、02年『生きる』で直木三十五賞、04年『武家用心集』で中山義秀文学賞、13年『脊梁山脈』で大佛次郎賞、16年『太陽は気を失う』で芸術選奨文部科学大臣賞、17年『ロゴスの市』で島清恋愛文学賞を受賞。著書に『トワイライト・シャッフル』『R.S.ヴィラセニョール』『ある日 失わずにすむもの』『二十五年後の読書』『この地上において私たちを満足させるもの』『地先』『ナインストーリーズ』『あの春がゆき この夏がきて』など多数