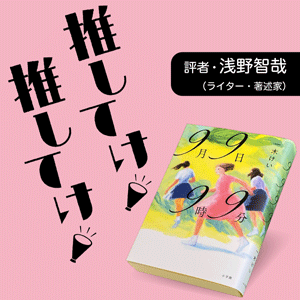一木けい『嵐の中で踊れ』◆熱血新刊インタビュー◆
恋には謎が必要

人生がガラッと変わる一晩の物語。青春小説の定番と言える設定だが、それをこう書くか、と驚かされた。避難所に指定された中学校、というシチュエーション選びが素晴らしい。
「私がまだバンコクに住んでいた時に、東京にいる妹からLINEで〝台風が来るから避難しろって連絡が入ったんだけど、けいちゃんだったらどうする?〟と相談されたんです。 〝私だったら避難するよ〟と伝えたら、妹は家族で避難所に行くことになったんですね。そうしたら、私が心配しないように気にかけてくれたのか、LINE で避難所のいろいろな写真を送ってくれたんです。子供たちは楽しそうに走り回っていて、お母さんたちは集まってワイワイしていて、お父さんたちはそれぞれの陣地で憔悴しきった顔をしている(笑)。このシチューションが妙に気になったんです」
その瞬間、一気に想像が膨らんでいった。
「意識に引っかかる話を聞くと、〝私だったらどうかな?〟と考えちゃうんです。会いたくない人に会うことになったらイヤだな、避難所からは逃げられないしなと思ったし、もしも自分が中学生だったら、家族と一緒に避難なんかしたくないですね。〝お父さんのこと見られたくない!〟って、思春期の女の子だったら思う気がするんです」
避難所にいたくない理由を指折り考えていくことで、物語の大枠が決まっていった。登場人物たちが、会いたくなかった相手と再会してしまうという物語だ。
好きな相手には謎めいていてほしい
9月のある夜、台風が近づいているという警報を受け、地域の人々が避難所に指定された中学校の体育館に集まった。物語は多視点群像形式で、語り手をバトンタッチしながら進んでいく。バトンを受けた1人目の語り手は、夫とは長らく不仲で、9歳になる息子・蓮太を連れて避難した主婦の詩伊だ。彼女は15歳年下の青年と恋をして、2年前に別れた過去を持っていた。2人目の語り手となる高校1年生の厳は、同級生の虹に片思い中だ。3人目の語り手は、四面四角な性格が子供たちにも疎まれている43歳の銀行マン、日出樹。そんな彼も秘密を抱えていて……。
この3人が会いたくないと思っている人物は、誰か? 恋の相手だ。
「編集者さんからは、甘酸っぱいものを、というご依頼をいただいていたんです。それもあってまず生まれたキャラクターは、高校生の厳と虹ちゃんでした。ただ、編集さんとお互いの恋の黒歴史を話していたら、やっぱり中年も入れとくかってことになりまして(笑)。群像劇に挑戦したかったんですよね。群像劇にするならいろんな年代を語り手にしたほうが面白いから、10代、20代、30代、40代というふうにキャラクターたちの年齢をバラけさせることにしたんです」
高校生の厳は〈この恋を、どうやったら諦められるんだろう?〉と呻吟しているが、おじさん街道まっしぐらの日出樹も〈恋。あの忌まわしくも呪わしい感情〉という鬱屈を抱えている。年齢は違えど、恋という「嵐」に振り回されるのは一緒。
「ただ、厳は未来もあるしウブなので、〝行けー!〟と思いながら書いていましたが、日出樹に対しては〝逃げろ!〟という感じだったかもしれません(苦笑)。日出樹は、書いたことがないタイプの人を書いてみたかったんですよね。真面目すぎる彼にどんな人を組み合わせたら楽しいかなと想像したら、商店街クラッシャーだなと思って、性的に奔放な海果子が出てきたんです」
恋の甘酸っぱさを表現しながら、もしかしたらそれ以上に、苦々しさにフォーカスを当てたのは何故だったのだろう?
「そもそもが恋って、そういうものだよねという気持ちが自分の中にあるんだと思います。楽しいことばかりではないですよね。でも、楽しくないことが楽しい。例えば、自分は相手から1日に LINE を5通欲しいと思っていたとして、3通しか来ないとしますよね。それってもどかしいし、苦しいんですよ。でも、届かない2通があるからこそ、もっと知りたいなとか、今何しているのかなと思って会いたくなる」
その心境の言語化が、本作に限らずこれまでさまざまな恋を描いてきた、一木けいらしかった。
「恋には、謎が必要なんです。好きな相手には謎めいていてほしい。謎がなくなると、魅力もなくなっちゃうんですよ。だから、詩伊の元カレの山内は、書いている私もそうだし読者さんもきっとそうだと思うんですが、最初は魅力的なんですよね。でも、詩伊に対する感情をドバーッと出した瞬間、急に普通の男に見えてくる(笑)。そういう瞬間を書けたのは、いろいろな語り手を出した群像劇にしたからだったかなと思っています」
小説を書くことになったのは、偶然の出会い
もう一人の語り手である中学1年生の小梅は、音楽ユーチューバー「よあじん」に心酔している。この日、「よあじん」が自分の街に来ているかもしれないことに気づいて……。
「恋ではない、推しへの愛も書きたいなと思っていました。〝その感情って何なんだろう?〟という疑問が、小説の種になることが多いんです」
実は、小梅が会いたくない人物は、家族以外の全員だ。彼女は他人の視線を恐れ、家の外では常にマスクをしている。
「私の娘も、コロナ禍が明けてからも外したくないと言っていた時期が長かったんですよね。ずっとマスク姿の顔しか知らないのに、今さら外せないと言って、先生に外せって言われた体育祭では、顔を隠しながら踊ったりしていた。もっと深刻な事例なども調べているうちに、一番健やかでハッピーでいてほしい子供たち世代が、コロナ禍で受けた影響の大きさを実感しました。〝お願い。元気でいてね〟という思いを込めて、小梅ちゃんの話を書いたんです」
それぞれの葛藤を抱えた登場人物たちの運命は、台風の夜に絡み合う。そして、度合いには大小があるが、己の人生を変化させることとなる。ストーリーを事前に組み立てることはしなかったそうだが、「朝になったらこの話は終わるというゴールが見えていたから、その気楽さみたいなものはあったかもしれません」。自然発生的に生まれた展開や会話に、身を委ねるようにして書いていったそうだ。
「ノリとフィーリングでお話を作っていったので、後から辻褄を合わせるのが大変でした。例えばある人がある人を見て〝どうしてここにいるんだ!? 〟と衝撃を受けたシーンを書いたら、校閲さんから〝すでにその前のシーンで見ているのでは?〟というご指摘をいただいて、〝その通りだ!〟と。基本的に体育館のワンシチュエーションなので、人物の配置とか動線とかがすごく重要になってくるんです。改めて振り返ってみると、今まで挑戦したことがない要素をたくさん盛り込んだ作品でした」
小説の最終盤で、こんな文章が登場する。それは、それぞれの登場人物たちのドラマを丁寧に積み上げていったからこそ、辿り着けた一文だ。〈もしかすると、予測不能な場において、人は他者と通じ合い、自分の新たな側面に気づくのかもしれない〉。
「偶然の出会いってすごく大切で、人生を変えるものだと思っています。私が小説を書くことになったのも、偶然道ばたで一回だけ出会った女の子がきっかけだったんです。大学生の時にチラシまきのバイトをしていて、彼女もチラシまきのバイトをしていて、集合住宅のポストの前で一緒になったんです。すごい暗くて寒い日で、彼女は日本人じゃない女の子だったんですけど、ものすごくきれいな声と顔で、自分は今こういうことが楽しくてこういうことには困っていて……といっぱいお話をしてくれて。会ったのはそれ一回なんですけれども、あの子に出会ってなかったら私は書いていなかったかもしれません。その子の魅力を言葉で表現してみたかったというのが、私が小説を書きたいと思ったきっかけなんです」
登場人物たちが、本人も気が付いていないような魅力を書くこと。書き手がそんな思いで書いているからこそ、読者もまた自己と他者への探究心が搔き立てられるのだ。
「美醜ではなくて、魅力的な人を書きたいんですよ。これからも小説を書くことで、素敵って思う人はどうして素敵なんだろうかと、そのことを探究していきたいんです」
一木けい(いちき・けい)
1979年、福岡県生まれ。2016年、「女による女のためのR‐18文学賞」読者賞を受賞。デビュー作『1ミリの後悔もない、はずがない』が話題となる。他の著書に『愛を知らない』『全部ゆるせたらいいのに』『9月9日9時9分』『彼女がそれも愛と呼ぶなら』『結論それなの、愛』『彼女たちが隠したかったこと』がある。