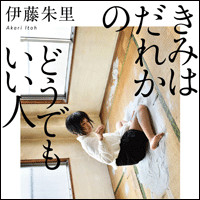伊藤朱里『きみはだれかのどうでもいい人』

同じ景色を、違う目で(または聞けなかった声に寄せて)
子供の頃、親戚に連れられミュージカル「エリザベート」を見に行った。有名な作品なので詳細は割愛するが、タイトルロールであるオーストリア皇后の前に最初の敵として立ちはだかるのが、皇太后、つまり姑のゾフィーだ。彼女は自由を愛し束縛を嫌うエリザベートを新婚初夜の翌朝五時に叩き起こし、「乗馬はするな」「歯を磨け」「自分を殺し皇后らしくしろ」と古く厳しいしきたりで雁字搦めにする。エリザベートがその美貌を利用して発言権を得そうになると、それを阻止すべく皇帝、つまり自分の息子に娼婦をけしかけさえする。幼かった私には「嫌なババア(汚い言葉で恐縮です)」という印象しかない人物だった。
約十年後、大人になった私は自分で「エリザベート」の再演版を見に行った。すると、昔はなかったはずのシーンが追加されていた。老いた皇太后がついに息子である皇帝から背を向けられ、死の間際、孤独に胸の内を吐露するのだ。「義務を忘れた者は滅びてしまうのよ」「優しさより厳しさを 心殺して務めたわ」──人はだれも、時代や社会の流れと無縁でいることはできない。その中で自分なりに生き抜こうとする、ただそれだけで、新しい価値観を築こうとする者を追い詰めてしまうこともある。当然、逆もあるだろう。皇后より「私」個人でありたい、というごく現代的な願いを抱えたエリザベートの存在が、ゾフィーがあれだけ守ろうとした帝国を破滅へと導いた(かもしれない)ように。
彼女とて、悪役になるために生まれたのではない。自分の時代を懸命に生きた一人の人間だった。昔はその場面がカットされていたとはいえ、そして子供だったとはいえ、いや子供だったからこそ、そんな簡単なことにさえ言(歌)われるまで気づかなかったかつての自分を私は恥じた。その後も何度か観劇したが、たぶんその場面では毎回のように泣いていた。
『きみはだれかのどうでもいい人』を書き終えたとき、そんなことを思い出した。この作品には、それぞれ立場も年齢も違う複数の女たちが出てくる。現実はミュージカルとは違うから、他人が胸に秘めた本音を歌で知ることはできない。小説の読み方など自由であるべきだが、強いて言えば、本来なら聞けないはずの声に耳を傾ける、もしくはそういう声が存在するかもしれないということに思いを馳せる一助に、本作が少しでもなれたらと思う。
あの二度目の観劇もちょうど十年前になる。この夏「エリザベート」はまた再演されたが、チケットが激戦だったこと、そして私が今作の推敲の只中だったこともあって、残念ながら見に行くことはかなわなかった。十年前の舞台でタイトルロールのエリザベートを演じていた女優の涼風真世さんは、今回の再演版ではゾフィーを演じたらしい。ぜひ一度、今の私のこの目で見て、この耳で聴いてみたかった。