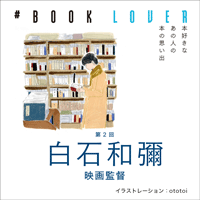物語のつくりかた 第19回 白石和彌さん(映画監督)
新しい作品の制作に取り掛かる時は、自分の中に「これを撮りたい!」と思える衝動を、まず見つけなければなりません。それがなければ気持ちが入った映画にはならないですし、場合によってはオファーをお断りせざるを得ないこともあります。
たとえば昨年公開された『凪待ち』に関して言えば、ただただ落ちていく一方の人間を描くのではなく、もう一度人生を歩み直す姿にスポットを当てたいという衝動が最初にありました。
きっかけになったのは二〇一六年公開の『日本で一番悪い奴ら』です。この作品は現実の事件が題材で、覚せい剤使用で逮捕された北海道警察の刑事をモデルに、警察組織内の悪を描き出したものですが、その元刑事の方とは今でも交流があるんです。逮捕、そして九年の服役を経て生じた考え方の変化など、いろんな話を聞くうちに自分の中でも様々な発見がありました。落ちたところから何かを得て再生していく人間の姿に強い関心を持ったんです。
その点、『凪待ち』で主役を演じていただいた香取慎吾さんは、ちょうどSMAPを解散して人生の転機に直面している時期で、『凪待ち』で描くテーマに通ずる局面にありました。実際に香取さんと細かい話をしたわけではありませんが、そうした背景は自然と演技にも表れていたように思います。
脚本を作り込んでいく作業というのは、自分自身と対話を重ねることでもあります。登場人物の言動ひとつひとつに対し、「本当はこういう行動はとらないのではないか」、「自分だったらどうするだろうか」などと、自問自答しながら世界観を突き詰めていくんです。
それに加えて『凪待ち』では、震災後の石巻市を舞台としているため、事前に地元の漁師さんたちの話を聞いてまわることから始めました。やはり震災はデリケートな題材ですから、フィクションとはいえ、嘘をついていい部分とそうでない部分があります。作品の中に出てくる「津波で全部駄目になったのではなく、津波が来たことで海が新しくなり、新しい生命がそこで育まれたんだ」というセリフは、実際に現地で耳にしたものでした。これは当事者でなければ言えない言葉ですよね。
倫理観を超える瞬間 生まれる快感を描く
僕が撮る映画はどうしてもバイオレンスシーンが注目されがちですが、これは決して最初から狙っていたわけではありません。やはり師事していた若松孝二監督の影響が大きいでしょう。助監督をやらせていただいた作品も、ほとんどがVシネマでした。だから当時は、撮影が終わるといつも血糊まみれの状態で……。そのままスタッフと朝まで飲み明かすものだから、帰り道に必ずお巡りさんから職質を受けるんです(笑)。「いや、これ映画なんですよ」といくら言っても、酔っぱらいの言い訳としか思われないから、なかなか帰らせてくれなくて苦労したのを覚えています。
そんなことばかりだったから、自分が監督として独り立ちした暁には、もう暴力的な映画は撮りたくないとすら思っていたんです。ところが、『凶悪』(二〇一三年)を撮った時に、自分の中にそういうDNAが組み込まれていることを、はっきりと自覚させられました。登場人物が、観る側の倫理観を超えていく瞬間にある種の快感があり、それこそが自分が求める物語なのだと気づかされたのです。
倫理観の先へどこまで行けるかというのは、もはやチキンレースのようなもの。僕は他の創り手よりも少し先へ行く勇気を、若松監督の現場で身につけたのだと思います。
ただ、暴力にもいろいろあります。バイオレンスアクションそのものが売りになるエンターテインメントもあれば、暴力が痛々しく見えてしまう物語もある。その描き方の違いについては慎重に考えるようにしています。たとえば『凪待ち』の場合は、暴力シーンを楽しんでもらう物語ではなく、"自分に跳ね返ってくる暴力"を描きました。
一方で、死体などをどこまでリアルに見せるか、という点も考えなければなりません。『孤狼の血』は最初から、暴力も死体もなるべく全部見せようという方針で撮った映画でした。
そもそも僕は、行き過ぎた無菌状態で人が育つことに少し疑問があるんです。自分自身の幼少期を振り返ってみても、けっこう厳しい描写のある映像作品にも触れてきたと思いますし。だからといって、決して露悪的にやりたいわけではなく、あくまでストーリー上の流れで見せるべきところはしっかりと見せて、観客の気持ちをのせていきたいと考えています。その匙加減については、今もまだ試行錯誤の途中ですね。

iPhoneで撮影した『麻雀放浪記2020』
『孤狼の血』は、柚月裕子さんの小説を原作とした作品です。原作があるものについては、どこまでアレンジするかという点も考えなければなりません。そこで大切なのは、原作へのリスペクトがあるかどうか、です。
そもそも一本の長編小説を二時間の映像に収めるのは無理があります。そこで様々なアレンジを加えることになりますが、原作に対するリスペクトがあれば世界観は守られるはずですし、原作者やファンの方にも納得してもらえるものになるでしょう。『孤狼の血』に関して言えば、柚月さん自身がおっしゃっていた、深作欣二監督や中島貞夫監督が撮っていたかつての実録ヤクザ映画の現代版というコンセプトに大いに共感していたので、その点は常に意識していました。
僕の作風というのはどうやら、意識せずとも自然と画面に緊張感が生まれ、どこか昭和の臭いが漂ってしまうようです。『孤狼の血』のような作品ではそれがうまくハマってくれました。結果的に、原作者の方と良い関係を育める作品になったのは、僕にとってもすごく嬉しいことですね。
ただ、時にはもっとポップに撮りたい作品もあります。そこで『麻雀放浪記2020』では、全編をiPhoneで撮影する試みを行ないました。
面白いもので、映画というのはカメラそのものの質量が画面に影響を与えます。たとえば通常の大きなカメラで撮る場合、被写体の手前にあるものが邪魔になり、それを排除してアングルを設定し直さなければならないようなことがよくあります。しかしiPhoneなら、それを手にしたカメラマンが自由に動けるので、状況を変えることなく即座に狙ったままの絵が撮れる。映画においてこれは大きな違いで、この試みは僕にとっても貴重な経験になりました。
本当のことを言えば、僕は助監督時代からずっと、自分は映画監督には向いていないと思っていました。むしろ、監督なんてなるものじゃないとすら思っていました(笑)。というのも、僕の下積み時代はとくに、映画監督はエキセントリックな人ばかりで、とても自分のような普通の人間に務まる職業ではないと感じたからです。
たとえば屋外での撮影中、カメラの後ろのスペースが足りないからと、夜中の三時に隣の民家のドアを叩き、「あとで直すんで、壁に穴を開けていいですか?」と言ったりする。そんな無茶苦茶なエピソードが、ほんとうにたくさん残っているんですよ。
これは自分にはできないなと痛感していたのですが、一方で「自分のほうがいい映画が撮れるんじゃないか」と思うような作品に出会うこともあります。そんな気持ちが原動力になって、こうしてたくさんの映画を撮らせてもらえるようになりました。
実は三十代で作れたのはデビュー作と『凶悪』の二本だけで、そういう意味では「やり忘れたこと」がすごくあるような気がしているんです。それをなんとか取り戻したいと模索してきました。
それに「白石さんとこの作品を作りたい」というオファーをもらった時に、「これは」と思ってしまったら、性格的に、もう他人には渡したくない(笑)。それも原動力になっていると思います。
白石和彌(しらいし・かずや)
1974年北海道生まれ。中村幻児監督主催の映像塾に参加。以降、若松孝二監督に師事し、フリーの演出部として活動。2010年『ロストパラダイス・イン・トーキョー』で長編監督デビュー。13年『凶悪』で第38回報知映画賞監督賞、第37回日本アカデミー賞優秀監督賞・優秀脚本賞など数々の映画賞を受賞。主な監督作品に『日本で一番悪い奴ら』『彼女がその名を知らない鳥たち』『孤狼の血』『麻雀放浪記2020』『凪待ち』などがある。
Q&A
1. 夜型? 朝型?
朝型です。新聞奨学生だったので、毎朝4時に起きていた生活の名残ですね。人よりちょっと早めに起きて、メールチェックなどの作業にあてています。
2. オフの過ごし方は?
映画を観ていることが多いですね(笑)。あるいは、近所をぶらぶら歩きながら写真を撮ることも。これもロケハンに近いかもしれませんが。
3. ストレス解消法は?
サウナと料理。とくに料理は昔からけっこうやるんです。子どもが生まれた時はまだ映画の仕事が少なかったので、離乳食づくりもやってました。
4. 仕事上の必需品は?
iPhoneでしょう。ついにこれで映画を一本撮ってしまったくらいですし。それから、最近はiPadも活用していて、作業のペーパーレス化を進めています。
5. もし今この仕事をしていなかったら、どんな仕事をしていたと思いますか?
考えたこともなかったですが、居酒屋とかで普通に働いていたかもしれませんね。あと、農業にも興味があります。菅原文太さんのように、引退後に就農するのはちょっと憧れますね。
6. 理想の10年後は?
それはやはり、まだ映画を撮り続けていたいですよね。時代劇にも挑戦したいし、海外での撮影もやってみたい。簡単なことではありませんが、そのためには10年後も仕事をもらえるように頑張らなければなりません。