【生誕100周年】「酔っ払うことがわたしの仕事だった」チャールズ・ブコウスキーのおすすめ作品5選

酒、女、競馬、そして書くことを愛した米国の作家チャールズ・ブコウスキー。49歳で作家に専念するようになるまであらゆる職を転々として放浪し、働きながら創作し続けた彼の生涯は破天荒そのものでした。今回はどこか人生の悲哀を感じさせる、チャールズ・ブコウスキーの作品を5つ紹介します。
【愛された無頼作家・チャールズ・ブコウスキー】
酒や女、競馬をとことん愛した無頼作家としていまもなおカルト的人気を誇る米国の作家チャールズ・ブコウスキー。1920年に生まれ、今年で生誕100周年を迎える彼は、大恐慌や世界大戦、冷戦など激動する世界情勢のなかにあって、生涯変わることなく「本物の無頼漢」として貫いた自らの生き方を、詩や小説の題材へと反映させました。
競馬場に毎日のように通い、酒場でしこたま飲んだくれては、女とファックする……。
そんな破天荒な日々をそのまま書き綴ったのです。
大学中退後、あらゆる職を転々とし、放浪と酒浸りによる穀潰しの日々を送っていたブコウスキーは作品を通して、社会への怒りや哀しみを、人間の愛と狂気を、ありのままの乾いた詩情でもって描くことで自身の文学を確立し、数多くの熱狂的なファンを生み出しました。
晩年になってようやく作家一本の道で食べられるようになるまで、まさに波乱万丈の人生を送り続けていた彼が、亡くなるまでに残した詩集や小説の数は50以上にものぼります。死後に創刊された作品を含めればなんとその数100冊以上とも。
醜くも温かい、痛くも優しい、そんなチャールズ・ブコウスキーの作品を紹介します。
【伝説的カルト作家による30の短編集『町でいちばんの美女』】
『町でいちばんの美女』は短いもので5,6ページ、長くても20ページ未満の30の物語で構成される、ブコウスキーの代表作ともいえる短編集です。
この短編集にはいかにもぶっとんだ、フィクションであろう作品もありますが、ほとんどが彼自身の体験がかなり反映された「酒、女、競馬に溺れる」人々が登場する短編で構成されています。
そして、それらほとんどの物語に共通して暴力や性愛のシーン、下品な表現などがこれでもかというぐらい詰め込まれているのが、ブコウスキー文学の特徴。
なかには過激な性犯罪や殺人を、異様に乾いた文体で、まるであたりまえのように描写した物語もあります。

https://www.amazon.co.jp/dp/4102129111/
表題作『町でいちばんの美女』は、キャスという名前の町でいちばんの美女と荒廃した生活を送る、町でいちばんのブ男である「私」の話です。
キャスは繊細で情熱的である一方、自傷癖を抱えており、ことあるごとに目の下に針を刺したり、ガラスで首を切りつけたりしては、「これでもきれいか」と尋ねます。
「お前みたいにいい女はこの世にいないんだ」と言って抱きしめると、キャスは声を殺して泣くのでした。
ある夜、キャスと出会った私は、キャスを自分の部屋へと誘います。
「彼女のキスは細やかで烈しい。私はしゃにむに躰をまさぐって上に乗った。熱く引き締まっていた。長く続けたいので、ゆっくり始めた。彼女は私の眼をまっすぐ見つめた。
(略)
そのあと、終えて服を着た彼女を、昨夜のバーまで車で送った。彼女は忘れがたかった。」(「町でいちばんの美女」より)
彼女に夢中になった私は幾度となくキャスと体を重ねるようになります。それから二人は束の間の幸福な日々を送りますが、冷たく、哀しい知らせが私のもとに突然届きます……。
表題作以外にも暴力描写の激しい『レイモン・ヴァスケス殺し』や、くすっと笑える『おえらい作家たち』など、合計30編の哀しみとユーモアに満ちた短編が収録されています。
伝説的カルト作家による名短編集『町でいちばんの美女』。チャールズ・ブコウスキーを初めて手にする方にもおすすめです。
【日常を異常な観察眼で切り取った34の名短編集『ありきたりの狂気の物語』】
『ありきたりの狂気の物語』は『町でいちばんの美女』の姉妹編です。元々この2冊は1つの冊子にまとめられていました。
したがってこの短編集にもブコウスキー作品に共通の題材「酒や女、競馬」をもとに人生の悲しみや絶望が描かれています。
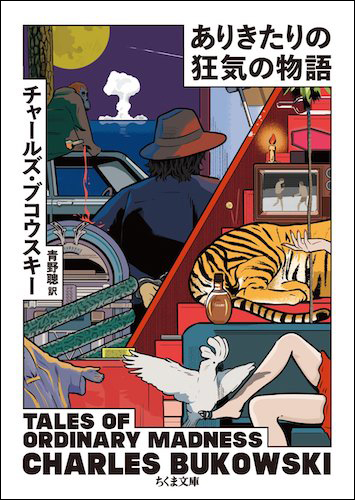
https://www.amazon.co.jp/dp/4480434607/
『狂った生き物』は失業して部屋からも追い出された「私」が、水を飲ませてもらうため緑色の三階建ての家を訪れたことをきっかけに、キャロルという女と私が奇妙で淫靡な交際をし始める物語です。
その緑の家ではキャロルが「自由動物園」と称し、キツネ、オオカミ、サル、虎、ピューマ、蛇など……、ありとあらゆる動物を飼っていました。
水を飲ませてもらったあと、その家にそのまま泊まることになった私。なかなか寝付けないでいた私は、キャロルと蛇が官能的な性交にふけっているところを目撃します。
「「ここの動物たちをほんとうに愛してたんだね」
「そうよ、全員、どの種類のどの一匹も」と彼女はいった。
(略)
大きく開かれた目には、恐れも、疑いもなかった。来るものは拒まず、去るものは追わずという目だった。動物的であり、そして人間的だった。」(『ありきたりの狂気の物語』「狂った生きもの」より)
3日目にして私はキャロルと初めて性交をします。
その後彼女は妊娠し、私と結婚しますが、悲劇は突如として二人を襲います……。
「私は病院の一階で待った。思えばなにもかもが妙だった。私がドヤ街を出てあの家へ歩いていったことから、すべてははじまった。愛と苦しみ。その闘いは、愛の方が勝っていたが、苦しみはまだ終わっていなかった。」(『ありきたりの狂気の物語』「狂った生きもの」より)
まさにブコウスキーらしい奇天烈なストーリー。目もくらむラストに注目です。
他にも、なぜか酔いどれの「私」が結婚式の付添人を務めることになる「禅式結婚式」など、彼の奇異な才能を堪能できる作品が満載です。
人間の狂気や、愛と哀しみを鋭い感性で表現した著者の代表的短編集。
ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。
【老いていっそう破天荒に生きた、ブコウスキーの痛快日記『死をポケットに入れて』】
1994年3月9日に生涯を閉じることとなったブコウスキーが、1991年8月から1993年2月まで、まさに死の直前まで書いていた日記をまとめた『死をポケットに入れて』。
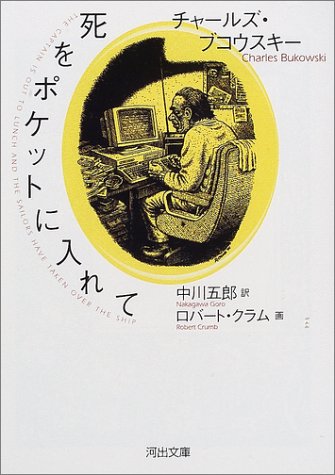
https://www.amazon.co.jp/dp/4309462189/
「日記」とはいうものの、ブコウスキーはこの著作でいわゆる世間一般でいうところの日記の書き方、つまり「その日に起こった出来事を感想とともに書き記す」ことだけにとどまらず、そこから死や文学など、いろいろな事柄について想いを馳せていきます。
「わたしは死を左のポケットに入れて持ち歩いている。そいつを取り出して、話しかけてみる。「やあ、ベイビー、どうしてる? いつわたしのもとにやってきてくれるのかな? ちゃんと心構えしておくからね」
(略)
何が恐ろしいのかといえば、死ではなく、みんなが生きる人生そのもの、あるいは天寿を全うしてその死を迎えられないということだ。みんなは自分たち自身の人生をありがたがることもなく、小便をひっかけている。」(『死をポケットに入れて』より)
周囲が寝静まった深夜、2階の書斎で愛用していたMacの画面に浮かび上がる省察の数々……、死についてや、書くことについて、敬愛する作家と詩人について、退屈なハリウッドについて、人生について。はたまた自らをインタビュアーと偽って自宅を訪れる熱狂的なファンとのやり取りについて面白おかしく語ったかと思えば、爪を切ることについて滔々と語ってみたりと、それらユニークな文章の数々は「日記」というよりも、ブコウスキーが長きに渡って作家として培ってきた洞察力が光るエッセイであると言えます。
この日記集は「93年2月27日12:56AM」付けで書かれた日記を最後に終わります。それは「真の芸術の価値はどこにあるか」という省察に始まり、最後には「シェイクスピアを嫌いだと言う権利はあなたにはない」と手紙を寄せてきた男に対する、ユニークな叫びで終わります。
「多くの若者たちがわたしの言うことを信じて、シェイクスピアをわざわざ読むことさえしなくなってしまうだろう。そんなことをする権利はわたしにはない。そういったことを綿々と書き綴っていた。返事は書かなかった。しかしわたしは逃げも隠れもせずに、いつでもここにいる。
てめえなんかくそくらえ、この野郎め。それにわたしはトルストイだって嫌いだ!」(『死をポケットに入れて』より)
ライトな読み口で何度となく読み返したくなる1冊です。
【全く予測不能かつ強烈な異色探偵小説『パルプ』】
自伝的要素が濃い作品がほとんどのブコウスキーが手掛けた、「怪作」と名高い異色の探偵小説『パルプ』。
物語は仕事にあぶれ、酒と女に取り憑かれた史上最低の探偵ニック・ビレーンのもとに「死の貴婦人」と名乗る謎の女が訪れるところから始まります。後に「死神」であることがわかるこの謎の女は、ブコウスキーが実際に敬愛していた死んだはずのフランス人作家・セリーヌを探してほしいと依頼します。
「俺は奴の方にゆっくりと歩いていった。すぐそばまで行った。ぴったりくっつくと、何を読んでるかも見えた。トーマス・マン。『魔の山』。
奴は顔を上げて俺を見た。
「この男はモンダイを抱えてる」奴は本を持ち上げて言った。
「どんなモンダイ?」俺は訊いた。
「退屈がゲイジュツだと思ってる」
奴は本を棚に戻し、まるっきりセリーヌみたい感じでそこに立っていた。」(『パルプ』より)
荒唐無稽な冒頭から始まるこの小説。
言われるままとにかく調査を始めるニックですが、物語はより予測不能な展開へと入り組んでいきます。
バーや競馬場に入り浸り、ほとんどろくに仕事をしないニックのもとに、死神を始め浮気妻や赤い雀、宇宙人など奇怪な登場人物が入り乱れ、いくつもの厄介な事件が起こり始めるのです。
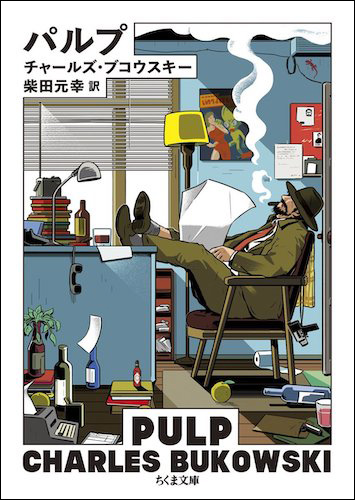
https://www.amazon.co.jp/dp/4480433473/
この小説はいくつもの奇妙な事件を解決する探偵の足跡を追う、純粋なエンタメ作品としても充分に楽しめます。
しかし、ブコウスキーが本筋のミステリと並んで描きたかったのは、だらしがなく厭世的なダメ探偵ニックが放つ、不愉快極まりない社会への怒りと諦めに満ちた人生哲学です。
「俺たちはさんざん待った。俺たちみんな、待つことが人を狂わせる大きな原因だってことくらい、医者は知らんのか?人はみな待って一生を過ごす。生きるために待ち、死ぬために待つ。
(略)
食べるために待ち、それからまた、食べるために待つ。頭のおかしい奴らと一緒に精神科の待合室で待ち、自分もやっぱりおかしいんだろうかと思案する。」(『パルプ』より)
「探偵小説」の衣を着ているようですが、あくまでどこまでもブコウスキー風の、強いメッセージ性に満ちた作品です。
【多感な青春時代を送った作者の自伝的小説『くそったれ! 少年時代』】
作者の分身と言えるヘンリー・チナスキーを主人公に、自身の体験が語られた自伝的小説『くそったれ! 少年時代』。
この小説は筆者のブコウスキー/主人公ヘンリーが幼い頃の最初の記憶を回想するシーンから始まり、小学校、中学校を経て高等学校を卒業するまでのおよそ20年間、つまり彼の幼少期、青年期の日々の記憶を追っていく物語となっています。
1944年、24歳の時に初めて小説を雑誌に発表したブコウスキーにとって、この作品は彼が作家になるまでの前日譚のようなものと言えます。
『町でいちばんの美女』など他の作品を読む限り、作家になってからのブコウスキーの人生はかなり波乱万丈であったように思われますが、それは彼の青春時代にも同じことが言えます。彼の青春はいわゆる「甘くほろ苦い」などというものではなく、むしろ「暗く、残酷で、暴力に満ちた」ものだったのです。
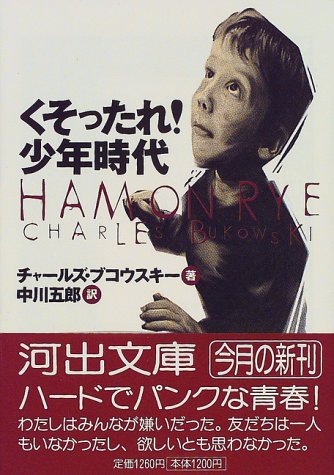
https://www.amazon.co.jp/dp/4309461913/
父親からの激しい虐待、学校の友人との不和、そして自身の容貌に対する強烈な劣等感……。
「裏の網戸の向こうで父の薔薇が花開いている。赤や白や黄色の薔薇で、どれも大きくて満開だった。陽はかなり落ちていたが、まだ完全に沈んでしまってはいず、顔を出している最後の部分が裏窓越しに姿を消していく。あの太陽だって父のものなんだと、わたしは思った。父の家の上で輝いているのだから、わたしには何の権利もない。わたしは彼の薔薇と同じだった。彼の所有物で、わたしのものではない……。」(『くそったれ! 少年時代』より)
大人への不信は募る一方で、友人ともうまくいかないチナスキー……。
あまりに多感な青年チナスキーの、くそったれな物語です。
【おわりに】
ブコウスキーの文章は、まったくてらいがなく、自ら書きたいと思ったことをありのままに書いていたため、一見すると暴力や露骨な性表現、絶望や虚無など「負のイメージ」によって満ちています。
しかしそんななかにも、時として垣間見える「人間の優しさや脆さ」の閃きこそが、ブコウスキー文学の特徴であり、魅力なのです。
初出:P+D MAGAZINE(2020/03/03)

