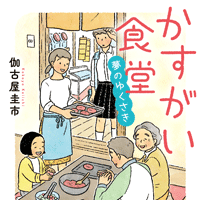思い出の味 ◈ 伽古屋圭市

この思い出は、夏の陽炎の向こう側にあるように、ひどくぼんやりとしている。
六、七歳前後のころだろうか、父に連れられて京都府北部にある舞鶴に行ったことが何度かある。いつも決まって夏のことだった。
父の目的はひたすら釣りをすることで、僕は日中、泊まっていた古い民家にほったらかしだった。たぶん民宿だろう。
海と、森しかない、本当に鄙びた場所で、僕は民家やその周辺で、ずっと遊んでいた。そんな小さな子をひとりでほっとくわけもないので、母か姉かは滞在していたはずだが、舞鶴での二人の記憶は不思議なほどにまるでない。
ある日、ひとりで森にいるとき、女の子に出会った。あまりに唐突すぎて恐縮だが、その前後の記憶がまるでないので、こう書くよりないのだ。
僕と同い年くらいの、小柄で、髪の長い女の子だった。おそらく短いながらも話をした。内容は、悲しいほどにまったく覚えていない。
そして女の子に、ラムネを貰った。
そのことだけは、はっきりと覚えている。白くて、丸く平たい形状をしていて、いまにも崩れてしまいそうな不恰好なラムネだった。そして驚くほどに甘いラムネだった。
口に入れるとほろほろと溶けてゆき、閉じ込められていた甘さが口いっぱいにひろがった。初めて味わうまろやかな甘さで、感動すると同時に、すぐに溶けて消えてしまう切なさも感じた。
なにもかもが曖昧な思い出なのに、不思議にラムネの味だけが、鮮明な記憶として残っている。
それからさまざまなラムネを食べてきたが、女の子に貰ったのと同じ味はおろか、似た味にも遭遇したことがない。それほどまでに特別な甘さだった。
きっと、幼少時の未熟な心が見せた錯誤なのだろう。
けれど、この記憶は幻想的な淡い風景に彩られていて、ひとりで遊んでいる少年に同情した森の妖精が特別なラムネを分けてくれたのではないかと、そんな甘い妄想も抱いてしまうのだ。