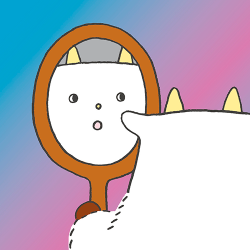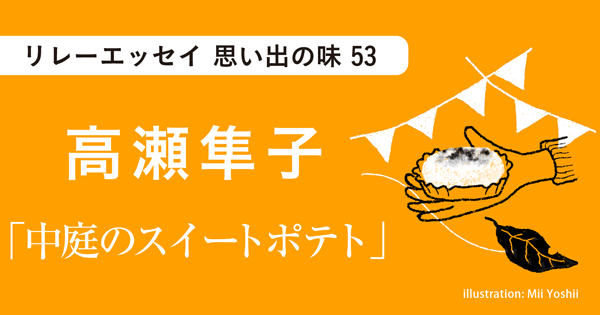思い出の味 ◈ 高瀬隼子
第53回
「中庭のスイートポテト」

十歳の頃だったと思う。小学校で祭りがあった。五、六年生が中庭で手作りの店を出し、下級生がお客さんになった。お店で使える通貨は葉っぱ。色がきれいだったり手のひらより大きかったりする、すてきな葉っぱを集めて持ってきた。一人五枚、という決まりだった。
ダンボールの迷路に入るのに一枚、草の汁で染めたハガキをもらうのに一枚、と葉っぱを渡していって、次に並んだのは甘いにおいのする、木箱のピンボールゲームの前だった。子どもが入れそうな大きさの木箱に輪ゴムのパチンコが付いていて、白いボールを飛ばす。ボールが決められたゴールに入ると、景品がもらえる。その景品が、スイートポテトだった。
もったりした黄色の、甘く、香ばしいにおいが、辺りいっぱいに漂っていた。葉っぱを一枚渡して、白いボールをパチンコで飛ばす。外れた。もう一枚葉っぱを渡す。外れた。最後の葉っぱも渡し、やはり外れた。ざんねんだったね、と言われて呆然と列から離れる。よっしゃあ! と叫ぶ声が聞こえて振り返ると、スイートポテトをもらっている子がいた。すぐさま頬張って、めっちゃうまいと言っていた。
祭り会場の中庭を出て、トイレに行くふりをして校舎に入った。最初はほんとうにトイレに行くつもりだったのだと思う。ただ、廊下を歩いている間にふと、この先の、校舎の反対側に大きな木があるなと思い付いた。トイレの前を素通りした。一人で外に出る。木の下に大きな葉っぱが落ちていた。六枚目。それは、友だちと公園や神社をまわって探した、とっておきの五枚とは違ったけれど、ちゃんと大きかった。
走って中庭に戻り、木箱のピンボールゲームの列に並んだ。パチンコで弾いた白いボールはまっすぐゴールに入った。ずるをしたとすぐに思った。おめでとう、と六年生から渡されたスイートポテトを、中庭で立ったまま食べた。十歳のわたしが一口で食べられるくらい小さかった。
あれが特別においしかったことを、妙に覚えている。甘くて仕方なかった。決して苦くはなかったのだ。
高瀬隼子(たかせ・じゅんこ)
1988年愛媛県生まれ。立命館大学文学部卒業。2019年「犬のかたちをしているもの」で第43回すばる文学賞を受賞、20年に同作で単行本デビュー。他の著書に『水たまりで息をする』がある。
〈「STORY BOX」2022年3月号掲載〉