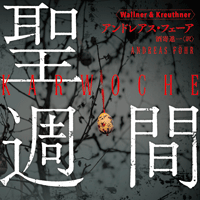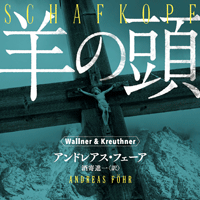翻訳者は語る 酒寄進一さん
ルネサンスの時代から「美」の象徴とされる「モナ・リザ」。一月に小学館文庫から発売予定の『モナ・リザ・ウイルス』は、この絵にまつわる謎を巡り、あらゆる「美」を破壊しようとするテロリストに神経美学者ヘレンが立ち向かう壮大で骨太なミステリーだ。このスピード感あふれる作品の翻訳を手掛けた酒寄進一さんに、翻訳の真髄を聞いた。
〈原書を読んで〉
「モナ・リザ」と言えば『ダ・ヴィンチ・コード』をはじめ題材として語り尽くされている印象があり、少し不安はありました。でも、読んだら非常に面白い。ルネサンスの時代と、ここ十年ほど注目されている神経美学、さらにルーヴル美術館だけでなく、プラド美術館所蔵「モナ・リザ」まで絡み合ってとても斬新です。舞台もアメリカ、メキシコ、ヨーロッパと多岐にわたる。登場する美術館や建物は図面などを取り寄せて調べました。その古さや狭さを具体的にイメージすることで、ただ「歩く」という動作でも、訳語の選び方に雰囲気が出る。本書を構成するモチーフのコンピュータウイルスやミツバチの生態についてもかなり細かく調べました。
〈翻訳の楽しみ〉
ごみごみした状態を「オイルサーディンの缶詰」に例える比喩がありました。でも日本の読者にはちょっとイメージがしづらい。そこで「芋を洗うような」と訳すこともできますが、全てを日本文化にアジャストしてしまっては外国文学を読む楽しみを奪ってしまう。その匙加減が一番難しくて面白いところですね。
本書では、サイドストーリー部分を訳すのも面白かった。特にキーマンの一人「異邦人」のキャラクターがじわじわと明らかになっていく過程は、あまり早くわかってもダメだし、わかりにくくてもダメ。補いすぎては興醒めですから。
読み合わせのメソッド
〈翻訳者になるまで〉
ドイツ語を学び始めたのは高校時代です。英語だけでは飽き足らず、フランス帰りの校長先生にフランス語を教えて欲しいとお願いしました。が、あっさり断られ、英語の先生にそのことをぼやいたところ、「じゃあドイツ語を教えよう」と。実は先生はドイツ文学好きだったんです。でも文法はほとんど教えてくれず、ひたすら詩を暗記させられたんですが(笑)。
次第にドイツ文学に興味を持ち、2年の時には課題の論文で夏目漱石『吾輩は猫である』とホフマン『牡猫ムルの人生観』の比較論を書いたんです。読み込むことや研究の面白さに目覚めました。
大学の推薦入試の面接ではドイツ語の詩をすらすら暗唱して見事合格(笑)。大学ではグリム童話を研究しました。卒業論文で三番目のばか息子をモチーフにした『熊の皮を着た男』などの童話について書いたんですが、大学の先輩で福武書店の編集者だった松居友さんと話していたら、『熊の皮を着た男』を翻訳したいと言う。論文を書いたくらいですから、作品について10分も20分も熱く語ったら、「じゃあ翻訳してくれないか」と(笑)。『くまおとこ』という絵本が僕のデビュー作品です。
〈意識すること〉
絵本の編集では、松居さんが実践していた独自のメソッドがありました。「読み合わせ」というもので、書き手と編集者が絵を見ながら何度も声に出して読む。するとピタッと絵に合った言葉が降ってくる感覚があるんです。ここ数年は刊行点数が増えてできなくなったのですが、それまでは長編作品も全て音読していました。そうしてリズムを整える。翻訳中の作品とリズムの合う音楽の助けも借ります。本書の場合にはノルウェーのアーティスト、Mari Boineを聞きながら訳しました。民族音楽とロックを融合させた音楽が、この物語にも合う。ルネサンス期のパートはその時代の音楽をBGMにして訳しました。だからそれぞれのパートで少しリズムが違うんじゃないかな。
漢字の使い方も作品によって変えています。児童書の経験があるから、漢字とひらがなとどちらが読みやすいか、全体のバランスを見ながら調整しています。
〈今後の野望〉
先般ヘッセの『デーミアン』を訳しました。17歳の時に読んだ作品に改めて向き合い、古典の読み直しをしたいなと。原文を読み直すと当時との感じ方の違いに驚きます。今の読者に求められるミステリーなどにも応えつつ、若い読者に古典をもういちど紹介し直したい。ドイツ文学を多くの方に知っていただくのが使命だと思っていますから。
(構成/奥田素子)