ピンク映画のこぼれ話/木全公彦『スクリーンの裾をめくってみれば 誰も知らない日本映画の裏面史』
独立系成人映画、つまりピンク映画のエピソードを中心に、日本の映画史を裏面から浮き彫りにする一冊を紹介します。
【ポスト・ブック・レビュー この人に訊け!】
与那原 恵【ノンフィクションライター】
スクリーンの裾をめくってみれば 誰も知らない日本映画の裏面史
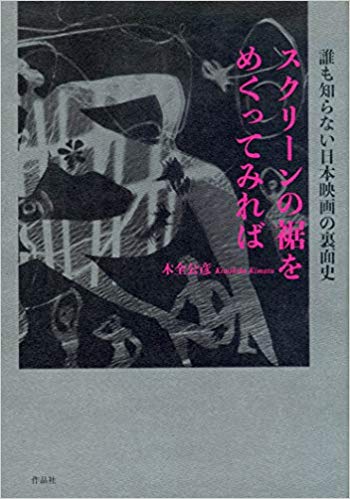
木全公彦 著
作品社
2000円+税
装丁/水崎真奈美(BOTANICA)
ピンク映画のエピソードを通して見る戦後日本の風景
ひとつのことを突きつめて、熱っぽく語る人の文章につよく魅せられる。映画評論家・ライター・DVDコーディネーターとして活躍する著者は、戦後日本映画のなかでも、主にピンク映画と呼ばれる独立系成人映画周辺をいきいきと浮かび上がらせる。
〈日頃から、映画史とは著名な監督や有名作だけで成立しているものではなく、無数の
日本にピンク映画が登場するのは、一九六二年の『肉体の市場』とされるが、それ以前、五〇年頃にはストリップやヌードを売り物にするエロ映画が製作されていた。さらには性教育映画、性病防止映画などが氾濫していったのは、教育的・啓蒙的映画という名目のもとに、観客が求めるエロを巧みに表現したからだ。実際、ストリップ劇場で映画上映と「実演」が行われ、摘発をくらってしまう。
しかし、そんなことにめげることもなく、あらゆる手段でエロ映画は上映されていく。あるアメリカ製短編エロ映画は、結核療養所から流出したものだったという一件や、米軍統治下にあった沖縄から「闇フィルム」が本土へと運ばれていたことなど、社会史としてもじつに興味深い。
当然のことながら、俳優や監督たちも一筋縄でいかない。俳優三國連太郎の初監督作品『台風』は、意欲的な企画として立ち上がったが、脚本は二転三転し、撮影も混乱をきわめるなど、「騒動」となった。また、長谷川和彦監督の幻のデビュー作は、低予算のロード・ムービー的ピンク映画だが、未完成に終わった。今では撮影フィルムの行方もわからない。
本書を通してよみがえってくるのは、すえた匂いのする場末の映画館の暗闇、上映が始まる瞬間のわくわくする気分である。
(週刊ポスト 2019年1.11号より)
初出:P+D MAGAZINE(2019/05/02)

