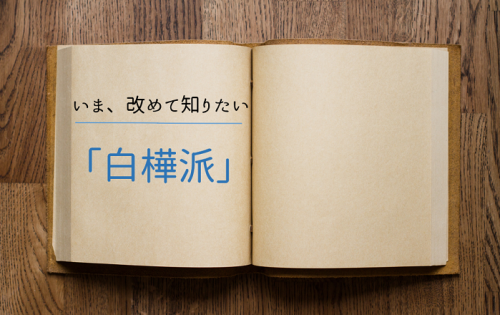【有島武郎、志賀直哉、武者小路実篤etc.】いま改めて知りたい「白樺派」
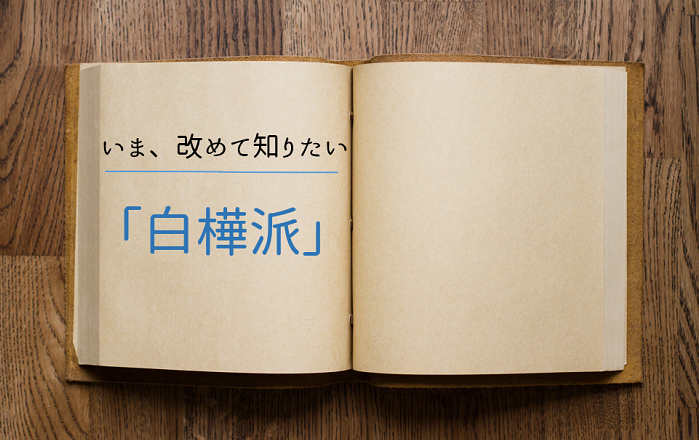
志賀直哉や有島武郎、武者小路実篤といった文豪たちを中心とする文学の潮流、「白樺派」。その成り立ちや理念、そして「白樺派」に属する作家たちの代表的な作品などについて解説します。
志賀直哉や有島武郎、武者小路実篤といった錚々たる文豪たちを中心とする文学の潮流、「白樺派」。国語の教科書で「白樺派」という言葉を聞いたことはあるけれど、その成り立ちや代表的な作品は知らない……、という方が多いのではないでしょうか?
今回は、「白樺派」が生まれた背景やその理念・作風、後世に与えた影響などとともに、白樺派の中心的な作家の代表作を3作品ご紹介します。
「白樺派」とは?
そもそも「白樺派」という名前は、1910年に刊行された同人誌「白樺」に由来しています。学習院中等科で親しかった武者小路実篤と志賀直哉が中心となり、有島武郎や里見
「白樺」には大正デモクラシーの影響を受けた自由かつ個人主義的な空気があり、掲載される作品の多くもそのような空気を色濃く反映したものでした。特に白樺派の中心人物であった武者小路実篤や志賀直哉、有島武郎は、私有財産を否定し非暴力主義を貫いたロシアの小説家・トルストイの文学に傾倒し、その思想の影響を強く受けていました。
武者小路実篤自身が「白樺」に所属するメンバーを“食うに困らなかった”と形容したこともあるように、「白樺」に見られる自由主義・理想主義は時として“楽観的”、“社会意識の欠如”と受け取られることもありました。「白樺」は学習院の中では“遊惰の徒”(仕事もせずにぶらぶらと遊んでいる人)が作った雑誌として禁書になるという憂き目にも遭ったものの、多くの偉大な文学者を排出したとともに、芸術雑誌としてロダンやセザンヌ、ゴッホといった画家を日本に広く紹介する役割も果たしたのです。
……次の章からは、「白樺派」の中心人物であった小説家、武者小路実篤・有島武郎・志賀直哉の代表的な作品とそのあらすじ・読みどころをご紹介します。
武者小路実篤『友情』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/410105701X/
『友情』は、白樺派の中心人物であり、思想的な支柱でもあった武者小路実篤が1920年に発表した小説です。ストーリーはとてもシンプルで、杉子という聡明な女性に盲目的なまでの片思いをしている脚本家の男・野島が、小説家の親友・大宮にその女性を奪われてしまう──という筋書きです。
偏屈で異性慣れしていない主人公・野島の杉子への思い入れは、「杉」という文字を見るだけで杉子のことを連想してしまうほどに強烈なものでした。
新聞を見ても、雑誌を見ても、本を見ても、杉という字が目についた。そして目につくとはっとした。しかし彼はまだ殆んど杉子とは一言も言葉を交さなかった。
しかし、杉子は情熱的な愛の告白をしてきた大宮のほうに惹かれ、大宮は親友である野島に手紙を通じて謝罪しつつ、杉子と結婚します。本作の白眉は、事実を知った野島が大宮に対して怒りを覚えつつも、このような手紙を書くラストシーンです。
死んでも君達には同情してもらいたくない。僕は一人で耐える。そしてその淋しさから何かを生む。(中略)君よ、僕のことは心配しないでくれ、傷ついても僕は僕だ。
野島が大失恋ののちに選んだのは、クヨクヨと悩んだり大宮を恨み続けたりすることではなく、“淋しさから何かを生む”という前向きな生き方でした。
文芸評論家の亀井勝一郎は、本作について
恋愛によってより強く生きるものがあるように、失恋によってより強く成るものもある。むしろ逆境こそ生命の光栄だという高い誇りが『友情』の示す最後の言葉だ
──武者小路実篤『友情』解説より
と述べています。人間の本能的かつ自由な恋愛を肯定し、青春を輝かしいものとして嫌味なく描いた本作はまさに、自由主義的な理念を支柱とする白樺派の代表作とも言える小説です。
有島武郎『カインの末裔』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4003103645/
短編小説『カインの末裔』は、1917年に発表された有島武郎の代表作です。
本作の主人公は、仁右衛門という名の粗野で横暴な男。彼とその妻が開拓期の北海道にやってきて、小作農として働き始めるところから物語は始まります。
長い影を地にひいて、痩馬の手綱を取りながら、彼れは黙りこくって歩いた。大きな汚い風呂敷包と一緒に、
章魚 のように頭ばかり大きい赤坊をおぶった彼れの妻は、少し跛脚 をひきながら三、四間も離れてその跡からとぼとぼとついて行った。
仁右衛門は広い農場を手に入れることを目標によく働きましたが、不倫や博打、略奪などありとあらゆる村の禁忌を犯したことで、村中から白い目で見られていました。
そんなある日、仁右衛門の幼い子どもが突如発病し、帰宅した彼の目の前で命を落としてしまいます。その悲しい出来事に続くように、仁右衛門が草競馬に出場させた愛馬が事故で骨折してしまい、二度と競馬に出場できなくなったことに激昂した彼が自分の手で馬を殺してしまったことで、大切なものを一度に失います。
窮地に立たされた彼は村人たちを頼ろうとしますが、村中の家々から絶縁されていた彼にはもはや拠りどころにできる場所はひとつもありませんでした。仁右衛門と妻は、仕方なく村を出てゆきます。
大きな荷を背負った二人の姿はまろびがちに少しずつ動いて行った。共同墓地の下を通る時、妻は手を合せてそっちを拝みながら歩いた――わざとらしいほど高い声を挙げて泣きながら。二人がこの村に這入った時は一頭の馬も持っていた。一人の赤坊もいた。二人はそれらのものすら自然から奪い去られてしまったのだ。
物語は、すべてを奪われ、村を追われた仁右衛門夫婦が再び放浪の旅に出る──という救いのないシーンで幕を下ろすのです。
本作のタイトルである『カインの末裔』。カインとは、旧約聖書の登場人物であるアダムとイブの息子のことです。カインは農夫でしたが、アベルという羊飼いの弟とともに神への捧げものをした際、アベルの供物だけが神に受け入れられたことに嫉妬し、弟を殺してしまった人物として描かれています。
『カインの末裔』が発表された当時、文壇からは、悪人・仁右衛門の末路が“不徹底”である──といった批判が上がりました。しかし有島武郎はその1年後、文芸誌に「自己を描出したに外ならない『カインの末裔』」という題の自作解説を載せ、批判を一蹴します。
彼は人間と融和していく術に疎く、自然を征服して行く業に暗い。それにも拘らず彼は、そのディレンマのうちに在って生きねばならぬ激しい衝動に駆り立てられる
──有島武郎「自己を描出したに外ならない『カインの末裔』」より
有島は、野性的で社会との衝突を繰り返してばかりの仁右衛門というキャラクターに、自分自身やあらゆる人間の姿を重ねていました。キリスト教に深い関心を抱いていた有島は、人間は本来罪深い存在であり、人類は皆「カインの末裔」であるということを、本作を通じて説いたのです。
志賀直哉『城の崎にて』
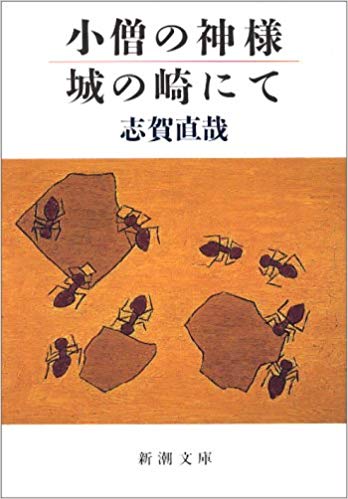
出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4101030057/
『城の崎にて』は、「小説の神様」と評された志賀直哉が1917年に発表した短編小説・随筆作品です。
山の手線の電車に跳飛ばされて怪我をした、その後養生に、一人で但馬の城崎温泉へ出掛けた。
という少々ショッキングな一文から始まる本作は、志賀直哉自身が1913年に同様の事故を経験し、城崎温泉で療養をしていた実際の経験に基づいています。事故以来どうも頭がはっきりとせず、話し相手もいないと語る志賀は、作中で散歩ばかりして1日を過ごしています。
療養中、志賀は蜂、鼠、いもりという3匹の生き物の死を偶然目にします。
或朝の事、自分は一疋蜂が玄関の屋根で死んで居るのを見つけた。足を腹の下にぴったりとつけ、触角はだらしなく顔へたれ下がっていた。他の蜂は一向に冷淡だった。
或所 迄来ると橋だの岸だのに人が立って何か川の中の物を見ながら騒いでいた。それは大きな鼠を川へなげ込んだのを見ているのだ。鼠は一生懸命に泳いで逃げようとする。鼠には首の所に7寸ばかりの魚串が刺し貫してあった。(中略)自分は鼠の最期を見る気がしなかった。
自分はいもりを驚かして水へ入れようと思った。(中略)自分はしゃがんだまま、わきの小鞠ほどの石を取り上げ、それを投げてやった。(中略)最初石が当たったとは思わなかった。いもりの反らした尾が自然に静かに下りてきた。すると肘を張ったようにして傾斜に堪えて、前へついていた両の前足の指が内へまくれ込むと、いもりは力なく前へのめってしまった。尾は全く石についた。もう動かない。いもりは死んでしまった。自分はとんだことをしたと思った。
志賀はこれらの生き物の運命を目の当たりにしたことで、自分が生き残ったことの“偶然性”を痛感します。そして、生きていることと死んでいることとの間に差はさほどないのではないか──という境地に至ります。
本作はとても短い作品ですが、私小説の代表作としても、名文としても名高い小説です。鼠の死を見届けようとしないところ、いもりを殺してしまったことに対する罪悪感などには志賀の人道主義的な面がよく表れており、生涯にわたって無宗教であった彼の死生観も窺うことのできる作品です。
おわりに
「白樺派」は学習院の卒業生たちを中心に興った潮流であったため、所属するメンバー同士の交流が長年にわたって続いたことも大きな特徴でした。たとえば、武者小路実篤は志賀直哉が88歳で亡くなる前年に、彼に宛ててこんな手紙を送っています。
この世に生きて君とあい
君と一緒に仕事した
自分の書きたいことを書いて来た
何年たつても君は君僕は僕
よき友達持って正直にものを言う
実にたのしい二人は友達
また、「白樺」の同人のひとりであった里見弴も、随筆の中にこんな言葉を残しています。
若い頃の親しい友達同士は、いくら逢っても、もうこれで逢い足りた、沢山だ、とはめったに思うものでないが、それにしても、『白樺』の仲間くらい、訪ねる、遊びに来る、誘い合わせてどこかへ一緒に行く、という風に、年がら年じゅう、誰かしらと顔を合わせていたのも少なかろう。
──里見弴『青春回顧』より
「白樺」に所属する作家たちの多くは、よき友人という関係性の中で互いに影響を与え合い、それぞれの作品に磨きをかけていました。白樺派は、同窓生を中心に生まれ広がっていったという、日本の文学史の中でも非常に稀有な派閥だったと言えるでしょう。
(※参考文献……阿部軍治『白樺派とトルストイ』、関川夏央『白樺たちの大正』)
初出:P+D MAGAZINE(2020/01/25)