「推してけ! 推してけ!」第33回 ◆『ハピネスエンディング株式会社』(トイアンナ・著)
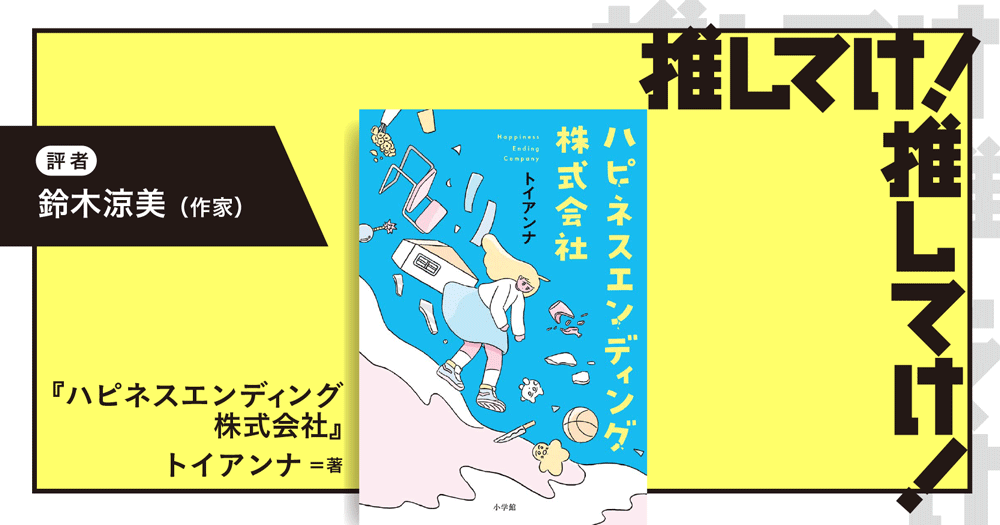
評者=鈴木涼美
(作家)
それが正当な手段でなくとも
非常識な行動が糾弾されるだけでなく、度を越して叩かれ炎上する様子を見ていると、時折思う。ここでは倫理的に正しいということが、誰かが生きることそれ自体よりも重要とされているようだ、と。誰かを愚かで不可解だと攻撃する正当性は、一体いつどこで何が基準に決められるのだろうか、と訝しんでしまう。自分の使用する物差しで他者の生を測るということがいかに残酷なことなのか、私たちは少なくとも意識的でなくてはならないのだ。その物差しは自分が生まれ育った環境によって、たまたまその形をしているだけなのかもしれないのだから。
ライターとして恋愛から婚活、キャリア形成まで、実質的なノウハウと機知に富んだ思考を伝授してきたトイアンナの新作小説は、ともすれば倫理的に問題あり、と判断されてしまいそうな方法でのサバイバルを扱う。登場するのは、親子関係に深刻な問題を抱えて生きてきた者たちだ。
物語の表題でもある「ハピネスエンディング株式会社」は主人公が長期インターンとして働くことになるベンチャー企業で、模擬葬儀、つまり「生きているうちにやる葬儀のリハーサル」を主要な業務としている。カウンセリングと称される打ち合わせを経て、実際に死んでいない人間の葬儀を取り仕切るのだが、現場は常に緊張感が高く、荒々しい。というのも依頼してくる者のほとんどが、親への復讐や因縁との訣別を目的としており、完璧な葬儀のために流れを確認したい、なんて牧歌的な依頼はほぼないからだ。
多くの〝常識的な〟人は、いくら嫌なことがあっても育ててくれた親を全否定するなんて間違っていると感じるかもしれない。怪我によるスポーツでの挫折はあったものの、特に問題のない家庭で育ち、特に問題のない大学生活を送る主人公は条件に惹かれてインターンに応募したものの、業務の説明を聞いて「生きてる親を模擬葬儀で殺してスッキリって、そんなひどいことを、やるなんて」と、とても〝常識的な〟反応を示す。しかし実際にやってくる、それぞれ自分とは違う環境で自分とは違う人生を歩んできた依頼主たちの姿を見て話を聞き、この業務に何かしら意味があるのではないかと思うようになる。
依頼主の恨みや傷はさまざまで、その多くが主人公の、あるいは読者である私自身の想像を超えている。学校でのいじめが相対的にマシに思えるほど酷い体罰を受け続けていたり、薬物依存の母親による性的虐待被害者だったり、新興宗教にのめり込んだ親に自慰行為を監視されたり。そのような親から未だに逃れられていない依頼主もいる。親子の問題を当事者の視点で描いた小説は数多あるが、親と何の問題もない主人公の視点で描かれるからこそ浮かび上がる痛ましさがある。
正当な手段で、例えば親との対話によって、アダルトチルドレンの回復論によって、専門家による入念な治療や第三者の介入によって、自分の人生を手繰り寄せられる人もいるとは思う。親との確執を抱えながら、自分の力で歩んできた人に模擬葬儀は、稚拙で愚かなロールプレイにしか見えないのかもしれない。児童虐待の被害者たち100人による「親への手紙」を収録した『日本一醜い親への手紙 そんな親なら捨てちゃえば?』(2017、Create Media編)が出版された時、親に対して攻撃的すぎると不快感を示す読者の声もあったという。反抗期を経た誰もが多少は経験する親とのすれ違いだからこそ、そこには中途半端な想像力が働き、「だからって……」と許容範囲を超えた非道徳的な行動には批判が集まりがちだ。
でもそれがどうした、とも思う。物語に登場する虐待当事者たちは、あらゆる事情から他の選択肢ではなく模擬葬儀を求めてやってくる。それは自分の命を守るためだけでなく、親の命や、あるいは現在の恋人や将来の自分の子供を守ることもある。主人公が思い至るように「被害者が、ずっと被害者でいるとは限らない」からだ。取材や執筆を通して、自分の生きる道の未だ定まっていない若者と対峙してきた著者だからこそ、時に社会一般の規範からはみ出したとしても、生き延びてほしいと願うのかもしれない。立派と言われる正攻法じゃなくても、死んだり殺したりするよりはずっといい、という助言のように私には読めた。
鈴木涼美(すずき・すずみ)
1983年生まれ。慶應大環境情報学部卒業。東大大学院を修了後、日本経済新聞社記者を経て2013年『「AV女優」の社会学』(青土社)で文筆家デビュー。小説『ギフテッド』『グレイスレス』(ともに文藝春秋)で芥川賞候補。新刊に『8cmヒールのニュースショー』(扶桑社)など。
〈「STORY BOX」2023年5月号掲載〉




