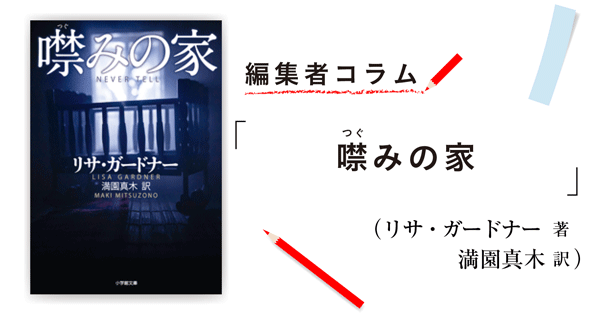◎編集者コラム◎ 『噤みの家』リサ・ガードナー 訳/満園真木
◎編集者コラム◎
『噤みの家』リサ・ガードナー 訳/満園真木

ボストン市警殺人課の部長刑事であり、一児の母でもあるD・D・ウォレン。超豪腕の彼女が活躍する、アメリカの大人気シリーズ第11作目(※短篇・中篇を除く)『噤(つぐ)みの家』をいよいよ日本の皆さまにお届けします。小学館文庫からは、長篇8作目『無痛の子』、9作目『棺の女』、10作目『完璧な家族』が好評発売中ですが、本作『噤みの家』では、472日間の壮絶な監禁からの生還者として『棺の女』に初登場し、あまりに強烈な印象を残したフローラ・デインのその後が描かれます。もちろん、新たな事件を描く抜群に面白いスリラー小説でもありますので、ミステリファンの皆さまにもぜひ手に取っていただきたいと思います!
今回は、かねてより本シリーズを強く推し続けてくださった文芸評論家の池上冬樹さんが解説を担当。熱い思いがこめられた名解説を一人でも多くの方にお読みいただきたく、ここに全文を掲載させていただきます。
解説
池上冬樹
いやあ面白い。やはり面白い。いったいこの複雑なストーリーはどこに向かうのか、どう結着をつけるのかといろいろ推理しながら読んでいたが、まったく違う方向にいくので、わくわくしてしまう。え? そういう風になるの? そういう展開なの? と驚き、同時に喜びながら、頁を繰ることになるからだ。リサ・ガードナーが優れた作家であるのはわかっていたけれど、相変わらず素晴らしく、世界的ベストセラー作家であることも納得だ。
何よりも傷つき、悩み苦しむ女性たちの声を、ここまで響かせることに驚きを感じる。リサ・ガードナーと同じく、暴力の被害者たる女性たちを熱く激しく描くカリン・スローターという作家もいて(『贖いのリミット』『グッド・ドーター』など必読。スローターもまた世界的な大ベストセラー作家だ)、凄まじくも切々たる慟哭を描くけれど、ガードナーは女性刑事D・D・ウォレンという子持ちの安定した家庭をもつ刑事を主人公の一人にしているので、スローターほどの息苦しさを免れている。それでも女性たちのどうしようもない悲しみは読者の胸を強くうつ。
リサ・ガードナーが一皮むけたのは、やはり『棺の女』だろう。誘拐・監禁をテーマにしたサスペンスは数多くあるが(小学館文庫から昨年出たロミー・ハウスマンの異色作『汚れなき子』も最近の収穫だ)、これは飛び抜けて強烈だった。
まず、D・D・ウォレンが駆けつけると、ガレージには黒焦げの男の死体がある。殺したのは、監禁されていた二十代の女性フローラ。彼女は七年前に誘拐され、一年以上も監禁されて解放された被害者だった。フローラは独自に異常犯罪者を狩っているのか?
刑事はフローラと失踪している女性たちの行方を追及し、フローラは監禁されていた過去と異常犯罪者との対決を物語る。生還者であることがいかに孤独で絶望的であるかを、監禁されていた四百七十二日の実態を少しずつみせることで明らかにしていく。唾棄すべき者たちに蹂躙されながらも、生き抜かざるをえない女性の悲しみと苦しみが読者の胸を激しくうつ。無垢な少女時代に憧れながらも、決して戻ることのできない現実をかみしめるラストには誰もが慟哭するだろう。これほど心を揺さぶる小説も久しぶりだった。誘拐監禁事件ものの名作になると思ったが、その思いはいまでも変わらない。
『棺の女』のあと、『棺の女』の前日譚『無痛の子』をはさんで、今年二月に『完璧な家族』が出た。家族四人が銃殺された事件をD・Dが追及する内容だが、眼をひくのは家族のうち、十三歳の次女と九歳の長男、母親および同居中の恋人が被害にあい、十六歳の長女ロクシーと犬二匹が行方不明であること。長女のロクシーが犯人なのか。それとも犯人から逃げているのかを、D・Dと、生還者たちで自警団を作っているフローラが追う。
長い監禁からの生還者であるフローラと、里親に預けられた先で酷い体験をしていたロクシー。ここでも迫害にあった女性たちの傷だらけの生き残りと死闘が描かれる。ずたぼろになった心と体を抱えた女性たちはどう生きるべきなのか。残虐きわまりない悲劇的な体験から一体何を見いだせというのか。優れたフーダニットとともに激烈なドラマが脈打っている。ひたぶるに己が傷を直視していかざるをえない者たちの、慟哭と叫びが激しく胸をうつ(ロクシーの手記の何と切ないことか!)。読む者の心を揺さぶる圧倒的な力強さと包容力がここにあるのだ。
そして本書『噤みの家』である。冒頭でもふれたようにとても面白いのだが、それは何よりも冒頭で読者を摑むからである。シリーズの読者に強烈な謎を提示するからだ。物語はまず、妊娠中の数学教師イーヴィが自宅に帰る場面から始まる。
イーヴィは玄関のドアが開いていることに気づく。不安にかられながら夫コンラッドの仕事部屋にいくと、夫は射殺されていた。夫の手には銃、机にはパソコンがあり、イーヴィは夫が見ていた画面を見て、衝動的に銃を手にとり、パソコンに銃弾を何発も撃ち込む。やがて駆けつけた警察にイーヴィは逮捕される。
事件の翌日、ボストン市警殺人課の部長刑事D・D・ウォレンは殺人現場へと向かう。D・Dはイーヴィを知っていた。十六年前、十六歳だったイーヴィは、有名な数学者でハーヴァード大学教授の父親を誤って殺していた。近くで不法侵入が多発していたので、父親がショットガンを買い、娘にそれを見せ、手にとらせていたときに銃が暴発して、至近距離から父親の胸を吹き飛ばした。悲劇的な事故として片づけられたが、同じような銃絡みの事件が二度も起きるだろうか。コンラッドは頭に一発、胸を二発撃たれていた。パソコンには十二発。いったい何を隠したいのか。警察はイーヴィが殺したと見る。
D・Dが現場の家を出ると、道路の向こうにフローラが待っていた。D・Dの新しい秘密情報提供者で、一月前の事件(『完璧な家族』)でも大いに力になってくれた。そのフローラがいう。ニュースで被害者コンラッドの写真を見た、わたしは彼を知っている、ジェイコブ・ネスと一緒に会ったことがあるというのだ。ジェイコブはフローラをさらい、一年四カ月にわたってレイプした男だ。六年前、FBIによるフローラ救出作戦の最中に死んだ。コンラッドは、誘拐犯ジェイコブと知り合いだったのか?
ここまでわずか三十八頁。思わず、おお!! と声が出てしまった。強烈な謎がいくつもあり、なおかつそれがジェイコブとつながるからだ。コンラッドを殺したのは誰なのか、イーヴィが隠そうとしていることは何なのか、コンラッドとジェイコブの関係は何なのか、そもそもコンラッドとは何者なのか? さらにもうひとつ、イーヴィは過去に本当に父親を誤って殺したのか? という疑問さえも前面に出てきて、いちだんと混迷が深まるからだ。深まる謎がそれぞれ追及されていき、三人の視点で少しずつ繙かれていくのだけれど、繙かれながらも中盤以降、ますますこみだしてきて、頁を繰る手に力が入る。真相が知りたくなり、途中で降りられなくなり、一気に最後まで読み通すことになる。
ごらんのように本書『噤みの家』は、『棺の女』『完璧な家族』と繋がっている。とくに『棺の女』と重なる部分があり、フローラを誘拐した犯人と事件の被害者が関係しているということで強く引き込まれていくのだが、もちろん前記二作を読んでいなくても大丈夫。いきなり本書から読んでも問題はない。本書でも、たびたび『棺の女』における悪党ジェイコブとの細部が詳しく語られるし、ミステリのプロットが実によくできているので、それだけでも十二分に読み応えがあるからだ。いくつもの謎が絡みだし、まったく予想もつかない方向へとむかう。ミステリ的昂奮はたいしたものである。
だがしかし、読者の心を摑むのは、ミステリ的昂奮と同時に事件関係者たち、とくにイーヴィとフローラの肖像だろう。なかでも怪物ジェイコブの犠牲者のフローラである。〝トラウマは精神的なものだとみんな思ってる〟が、トラウマは精神的なものだけではなく、〝生理学的なものでも〟あり、〝副腎疲労のせいで、ずっと戦闘モードのまま何日も抜けられないことがある。(略)燃えつきて、何日もベッドから起きあがれなくなる。/混みあったところではまともに機能できない。ラッシュ時の地下鉄には乗れない。ほかの人の体臭に耐えられない〟のだ。何故なら〝警戒心が高まりすぎ〟るからだ。〝ジェイコブはもう死んでいるのに。でもまだわたしの頭のなかにいる〟〝いまだにジェイコブの被害者に戻ってしまうことがある〟のだ。
そんな過去を忘れたいのに忘れられないフローラは、ジェイコブと関わりのある男が出てきたとき、事件捜査のために、過去の最悪の時間をもう一度思い出そうとする(この場面が緊張感にあふれて実に読ませる)。それにしても何という強さだろう。〝ジェイコブが最悪中の最悪のモンスターなら、それを生きのびたフローラはタフ中のタフだ〟とD・Dは見ているのだが、思いは複雑だ。というのも、〝D・Dの刑事の部分がフローラの強さを称賛するいっぽうで、D・Dの母親の部分はそれによって失われたものに胸が痛くなる〟からである。
そう、D・D・ウォレン・シリーズがいいのは、刑事の視点と母親の視点が生きている点である。物語においては、娘と母というサイド・ストーリーが大きく紡がれることになる。『棺の女』のラストでは、娘と母の感動的な、だがもう絶対に無垢な少女時代へとは戻れない現実を強く印象づけたが、本書では、もう一組の娘と母の関係が重ねられる。イーヴィと母親の複雑な関係だ。物語の興趣にふれるので曖昧に書くが、イーヴィもまた母親との関係で深く傷つく。だからこそラストシーンが読者の心を揺さぶるのである。こんなふうに人々はよりそい、傷ついた心をいやすのだと感得させられるからだ。『棺の女』のラストシーンを忘れられない読者には、ようやくフローラと母の関係に、ひとつの区切りがついたのではないかという思いもきざす。
〝わたしはもう隅に引っこんでいない。前に踏みだす。住んでいる世界の一員になる。たとえ怖くても。だって、人生は怖いけど、それでもほかに道はないのだから〟という文章が最後の最後に出てくるけれど、この〝人生は怖いけど、それでもほかに道はないのだから〟は、悲しくも厳しい現実認識だろう。人はそれでも前を見て歩いていかなくてはいけないことを、作者は感動的な場面とともに切々と訴える。
冒頭にも書いたが、とにかく面白い小説だ。謎解きがいくつもあり、実にスリリングな展開をたどる。でも、結末に至れば、作者の力強いメッセージに心がふるえることになる。慟哭にみちた人生でも生きるに値することがあることを真摯に謳いあげているからである。
作者が謝辞でいうように、まだ終わりではなく、続きがある。D・Dとともに、フローラたちの辛く悲しい惨憺たる人生に少しでも幸が多かりしことを願いながら、ずっと見守っていきたいと思う。
(いけがみ・ふゆき/文芸評論家)
──『噤みの家』担当者より