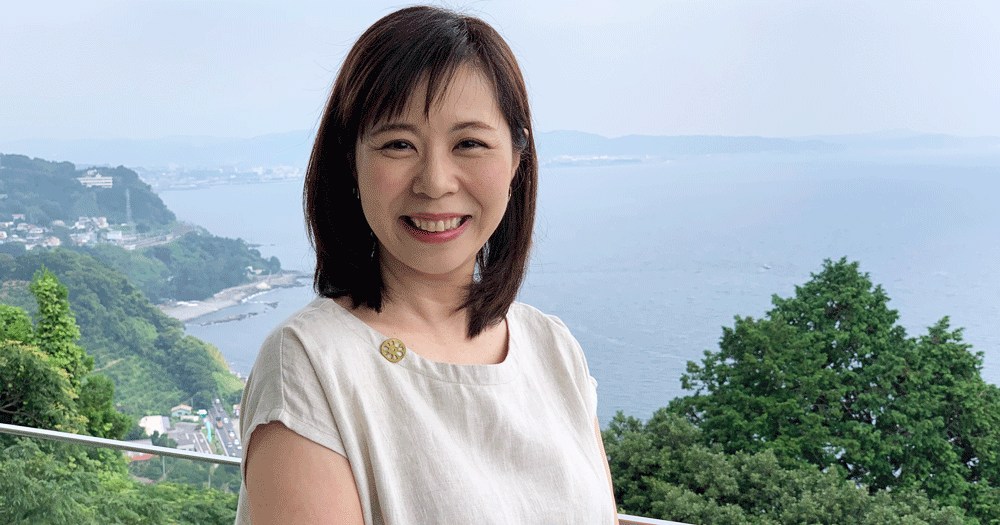椰月美智子さん『こんぱるいろ、彼方』
青春小説から恋愛小説、家族小説までさまざまなテイストで描く椰月美智子さん。新作『こんぱるいろ、彼方』で選んだテーマはベトナムからのボートピープル。なぜ、今、この題材を選んだのか。その経緯と、執筆にこめた思いを聞いた。
友達の友達がボートピープルだった
ある世代以上の人なら、「ボートピープル」と聞けば、人々があふれんばかりに乗った船が漂流しているニュース映像を思い浮かべるだろう。ベトナム戦争が終結した1975年以降、日本にもインドシナからたくさんの人々が船に乗って難民としてやってきた、その時の映像だ。椰月美智子さんの新作『こんぱるいろ、彼方』はそんなボートピープルとなった一家の女性三代の物語。
「四、五年前に地元の友達と買い物に行った時、偶然友達の知り合いが歩いてきたんです。友達がその人のことを可愛らしい名前で呼ぶのを聞いて、〝自分と同世代にしては珍しいな〟と思って。仮名でリオンさんとしますが、後から友達に〝リオンちゃんはボートピープルだったんだよ〟と聞いてびっくりして。小学校にあがる前くらいにベトナムから日本に来て、帰化したんだそうです。自分と同世代の人、しかも友達の友達という身近な人がボートピープルだったことが衝撃でした」
その時、これはぜひ小説に書いてみたいと思ったという。
「ボートピープルが遠い場所の物語ではなく、身近にいるということで、自分も無関係ではないと感じました。どういう状況で海をわたってきたのか、すごく知りたくなりました」
そこでさっそく、リオンさんに取材をお願いした。だが、
「彼女はベトナムにいたこともボートに乗ったことも憶えていないというんです。ベトナム語も話せないし、ベトナム戦争のことも詳しくない。子どもにも自分がベトナム人であることを伝えていない、とのことでした。バイト仲間だった友達によると、当時の彼女は自分がボートピープルであることもあっけらかんと話していたし、周囲も彼女をベトナムの名前で呼んでいたそうです。それが変わったのは、やっぱりお子さんができたことが大きいのかなと思いました。それで彼女のご家族を紹介してもらいました。リオンさんのお姉さんは当時のことを憶えているし、ベトナム語も話すし、彼女の子どもたちも親のルーツを知っている。姉妹でもそんなに違うことが意外でした」
そこから生まれたのが、女性三代の物語にするということ。
「戦争というと男性のものというイメージがありますよね。ベトナム戦争を描いた映画も『プラトーン』をはじめ、男性たちの話が多い。でも女の人たちも生活を守るために大変だったんだろうなと思って。その部分を書きたいと思いました。それに、生まれた時代がちょっと違うだけで、まったく違う人生になること、まったく違う感覚を持つことも書きたくて。それで母、娘、孫娘三世代の話にしようと思いました」
子どもには隠していた自分のルーツ
一九七三年生まれの真依子はサラリーマンの夫と大学生の娘の奈月、中学生の息子、賢人と暮らし、スーパーの総菜売り場で働く主婦。奈月から夏休みに友人と海外を旅行するためパスポートが取りたいと言われ、真依子は動揺する。実は彼女は五歳の頃にボートピープルとして家族で日本にやって来たベトナム人なのだが、そのことを子どもたちには伝えていなかったのだ。隠していた理由は、「いじめられると思ったから」。さまざまなルーツを持つ人々が多く暮らす国だったら、そんな感情は抱かないはずだ。彼女がそう思ってしまうのは、日本の排他性にあるのだろうと感じずにはいられない。
「私も、リオンさんの話を聞いた時、ベトナム人であることを隠そうとするのは日本だからだろうなと思いました。彼女は顔立ちが日本人と似ているので、言われなければ分からない。だからこそ隠しておこうという気持ちなんでしょうね」
日本の外国人差別の縮図だと感じるのは、真依子の勤務先のスーパーの総菜売り場。主任の男は日系三世のブラジル人、カルロスのことを馬鹿にし何かと言葉でいたぶるが、調理場の責任者は黙っている。パート仲間の女性が抗議してもなあなあにしてしまうだけ。真依子も主任には腹を立てているが、自分から意見する勇気はない。
「ベトナム人技能実習生に対する搾取の問題もありましたし、日本は島国だからか、いまだに差別する人、排他的な人が多いと感じます。真依子のスーパーで起きたことのように、いじめに発展することもある。差別する人だけじゃなくて、心の中で差別はいけないと思っているのに、その場さえ収まればいいと思って何も言わない人もいる。そのあたりも考えてもらいたいというか、自分が考えたいと思って書きました」
真依子は物事に積極的に関与しようとしないタイプだが、一方、娘の奈月は正義感が強く、公正に物事を見ようとする。
「真依子とは違うタイプにしようと思っていて。奈月のおかげで、みんなの意識が変わっていく。そういう存在です」
友人たちとの夏休みの旅行先をベトナムに決めた矢先、母親からその国の血を引くことを聞かされた奈月。ショックは受けるものの、ただ、彼女はそれを否定的にとらえはしないのが真依子とは対照的だ。実際、最近の若い人は、昔に比べ国籍やルーツで人を差別したり区別する意識は低いのではないか。
「そうだと思います。うちの子のクラスでも、フィリピン出身の親を持つ子とか多いんですが、国籍なんて誰もなんとも思っていなくて、それよりも性格がいいか悪いかといったことを言っていますね(笑)。私はリオンさんや真依子と同世代ですが、確かに私が小さい頃は外国の血を引く子は珍しがられていました。でも、今の子どもはそれほど気にしないと思います」
奈月が興味を持ったのは、その国の歴史について。一緒に旅する女友達二人にも事実を伝え、旅行ではホーチミンと、母親たちの出身地であるニャチャンを訪れることにする。
「私も二〇一八年にホーチミンとニャチャンに取材に行ってきました。ホーチミンは二十代の頃に一度訪ねたことがありますが、やはり今回行かないと分からないことがたくさんあって。ガイドの方にもいろいろ話を聞いたのですが、みなさんベトナム戦争に対してはその人なりの思いがありました。博物館に行くと目を覆いたくなるような戦時の写真がたくさん展示されている。事前に石川文洋さんや沢田教一さんの写真集も見ていたんですが、現地のじめっとした博物館で見るとまた違う感じがしました。クチトンネルにも拷問器具が置かれていて、アメリカ人観光客も多くて、どういう思いで見ているのかなと気になりました」
現地で椰月さん自身が感じたこと、見聞きしたことは、本書のなかに反映されている。また、作中、奈月の友人の一人が「無理」と言って見ようとしないのが印象的だ。
「見る人によって全然感覚が違うんだろうなと思います。見たくないという人も、ひどいから見られないという人もいれば、見世物にしちゃいけないという意識の人もいるだろうし、それを商売にしてお金を取っているのが許せない人もいると思う。いろんな思いが交錯しているんです。私は全部見たい、知りたいと思うほうですが(笑)」
また、真依子たち家族は南側のベトナム共和国にいた人間だ。北ベトナムが勝利を収めた後、南側の政府関係者や富裕層は財産を没収されるなど苦難を強いられ、それで逃げ出すこととなったわけだが、
「博物館などの展示、北側の目線なんですよね。こんなひどいことを南側にされた、という視点なので、南側の人間は複雑な思いで見ることになる。戦時中、北側を追い詰めた南側も、戦後は国を脱出せざるをえなくなるくらいひどい扱いを受けているんですね。やはり戦争は勝ち負け関係なく、全員が被害者だなと感じました」
複雑な立場で現地で見聞きし体験することを、奈月は真っすぐな心で受け止めていく。
生活が一変し国を脱出するまで
真依子の母、春恵のベトナム名はスアン。彼女のパートでは、幸福だったニャチャンの日々から、家族で脱出を決心するまでが描かれる。
「リオンさんのお母さんにもお話を聞いたんですけれど、口数が多い方ではなく、日本語もあまり話さない方で。ただ、自分たちが若い頃は戦争の影はほとんどなかったということを話されていたので、そこから想像を膨らませていきました。脱出の具体的な内容については中国系の男性の方に取材をしたので、それを参考にしました。話を聞いて、本当に大変だったんだな、って。北側の人が見張っているから怪しまれないように家族一緒に行動できないし、凪の日は見つかりやすいからあえて台風の日に出航しなければならない。それだけでも危険なのに、海に出た後は海賊がいる。それでも脱出しようとするほどひどい状況だったということですよね。私の子ども時代は食べ物に困ることもなかったし、幸せに生きてきました。でも近くの国ではまったく違ったことが起きていて、それで日本に来た方が大勢いる。その事実を改めて知ることができてよかったです」
実際の難民は、日本にたどり着いた後も苦労した人は多かっただろう。春恵(スアン)や真依子たち一家は裕福な家庭だったようだが、
「勤勉な方たちで、自分たちで生活しようと頑張ったようです。もちろん最初の頃は政府や支援団体のサポートもあっただろうし、難民の方みんなが彼らのようにうまくいったわけではなく、日本語がおぼえられなかった人もいただろうし、職が見つからなかった人もいたと思います。ただ、今、日本は難民をなかなか受け入れない国となっていますよね。当時と状況は変わっているかもしれないけれど、もう少しどうにかならないかと思ったり」
そう、本書を読むと、昨今の国内の難民や移民の事情についてもふと思いをめぐらす。
「そういうことを考えてほしくてカルロスのことなども入れました。もう、差別をしている時代じゃない、と思っています」
今後世界は変わっていく気がする
過去を見つめ、未来を見つめる内容となっている本作。「今、この時期に、本が出せてありがたいです」と椰月さん。感染症の影響で生活が一変した今、今後の小説執筆に変化はあるだろうか。
「令和になってから空気感が変わったという感覚があって。これからも思いがけないことがたくさんある気配を感じます。なにか、見えない世界が近づいてきた……と言うとこいつは何を言っているんだろうと思われそうですが(笑)、物質世界から人類が離れていく気がする。その感覚は、今後の自分の小説に反映されると思います」
小学館
▶︎ noteにて試し読み掲載中!