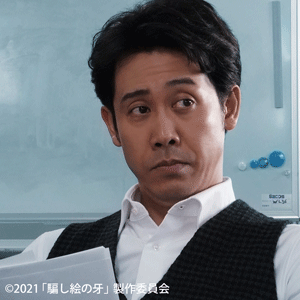塩田武士さん『歪んだ波紋』
グリコ・森永事件をモチーフにした『罪の声』が話題を呼び、出版界を舞台にした『騙し絵の牙』の映画化も決定。今注目の作家、塩田武士さんの新作『歪んだ波紋』は、情報発信のあり方とその受け取り方を問う社会派のエンターテインメントだ。
きっかけは小さな訂正記事
元神戸新聞の記者として、ジャーナリズムの世界に身をおいていた塩田武士さん。新作『歪んだ波紋』は、現役の新聞記者や元記者たちを主人公に、さまざまな"誤報"とその後を描く短篇集。だが、ネットニュースの存在も盛りこみつつ、最終的にはすべてが連なって現代の大きな闇が見えてくる作りだ。
「前段階として、もともと情報というものに対してすごく興味がありました。僕が社会派の作家として読んできた山崎豊子、松本清張が戦争を背負っているように読めるなか、現代作家は何を背負っているのかと考えた時、ひとつは情報ではないか、と思っていて。情報を軸にして考えたら、今の構造変化の説明がつくんじゃないか、という思いが根本にありました」
そんな思いを抱いてきた塩田さんが本作の着想を得たのは、『罪の声』のプロモーションでホテルに泊まっていた朝。
「部屋に朝刊が届いたので読んでいたら、囲み記事があったんです。市役所の臨時職員がゲームの世界大会で優勝したという記事は間違いでした、という内容でした。なんだと思ってよく読んだら、記者クラブで会見が開かれ"この人優勝しました"という話になって、記者たちは記事を書いた。でもその人がフェイスブックに載せていた世界大会の際に行ったレストランなどの写真が他から転載されたものだという指摘があって、嘘が分かったんですね。そこで聞いたことを信じて記事を書いてしまう記者クラブという古い制度と、SNSで一人の嘘が暴かれるという今日的な出来事と、その新旧の対比がすごく面白いと感じました。僕も記者時代に市役所詰めの時期がありましたが、その場にいたら間違いなくその誤報を書いていたと思う。この嘘をついた人はこの後どうなるんやろうと考えた時、誤報の先に真実が現れるんじゃないかという仮定ができていきました」
誤報ののちに見えてくる人間の真実
"誤報"と"後報"をモチーフに、五篇からならなる本作。冒頭の「黒い依頼」では近畿新報の記者が社内の特別チームから頼まれ、轢き逃げ事件を追い、思わぬ真実を知って愕然とする。
「まず、誤報と虚報は区別をつけなくてはいけないと考え、情報に悪意が介在しているとしたらどういうことか、というところから逆算して書きました。誤った情報を流すことは人の人生を狂わせもする、ということも書きたかった。それを書いてみて、では次は誤報と時効というのはどうだろうと」
続く「共犯者」では、定年を迎えた全国紙の元記者の相賀が、自殺したかつての同僚が遺した資料を見て、三十三年前に書かれた記事について記憶をたどる。
三本目の「ゼロの影」では全国紙、大日新聞の同僚と結婚した元記者の女性が、盗撮犯罪のもみ消しに気づく。
「これは誤報と沈黙について書いたもの。記者クラブが結託してひとつの事実を沈黙させてしまう。もう一方で、今の社会はSNSでもいろんな情報が飛び交っていて、炎上に対して沈黙したり相手にしなかったりすることは、間接的に相手を支持したことになる、という意味の沈黙についても考えました」
この主人公は社内結婚をしたために異動となり、そのため退職したという経緯がある。他の短篇でも感じるが、記者の世界はかなりの男社会という印象を受ける。
「男女比がまったく違いますからね。だからここでは差別組織を追いかけた女性記者が社内で差別に遭うという、内外ふたつの差別と対峙する姿を書きました」
四本目「Dの微笑」では近畿新報の支局のデスクが、あるテレビ番組の奇妙な点に気づく。
「僕は記者時代に五年くらいテレビ局担当をしていたんです。それとは別に、新刊のプロモーションで朝の情報番組にコメンテーターとして出演したことが一回あって。自分が取材していないことについて話す恐怖を味わい、ずっと手に汗握ってました。そうした、以前自分が見ていたもの、最近になって新たに見えたものを合わせて、誤報と娯楽について書きました」
最終話「歪んだ波紋」では、前四篇にもつながる、誤報と権力の構造が浮かび上がる。
「四篇をきっちり書き、最後の五本目で小説全体をまとめないといけないとなった時、権力というものが頭に浮かびました。基本的な三権、ウォッチドッグの第四の権力、そしてそれら全てをみんなで監視しますよという新たな"第五の権力"についても書かないといけないと思ったんです」
最終話まで行きついた時、気づいたことがあった。
「誤報を出してしまった彼らの過ちのもとは、ぜんぶ人間の弱さにあるんですよね」
自身も記者時代、記事の訂正を出したことは何度もあったという。
「こんなに誤報について語っているのを神戸新聞の知り合いが読んだら、"どの口が言うねん!"と言われます(笑)。菓子折り持って謝りに行ったこともあります。誤報を出した時って、一瞬ごまかそうとしてしまう。あさましいですよね。この本の中にも、誤報を訂正したくないという人の弱さが書かれていますが、自分が経験しているからリアリティが出たという。非常に格好悪いですね(笑)」
人間はどうしても間違える。その時に潔く認めて誤りを公表できるかどうか。しかしその一方で、あえて意図的に間違った情報を流布する人たちもいる。
「それはもう作家でもジャーナリストでもなく、ただの悪質な活動家じゃないかと思う。それで、五本目の『歪んだ波紋』では、それらのより大きな存在としての組織を出しました。社会派小説というのは現状の分析もしますが、未来予想図を提示するというのもひとつの役割だと思うんです。ここに書いたのは、将来できるかもしれないし、もしかしたらもうすでにあるかもしれない組織ですね。今は、真実でなくても"面白くて自分の役に立つニュース"という、今までになかったものが拡散しはじめている。例えば巨大企業数社が世界の個人情報を吸い上げて、自分たちの利益のために一見ニュース風なものを作って流しはじめたっておかしくない。『マスゴミ』といわれているレガシーメディアを攻撃して失墜させ、俺たちのほうが真実なんだと思わせる活動をはじめる組織が生まれる可能性だってあるんです」
ジャーナリズムの過渡期 本作では経済学者のシュンペンターが提唱した「創造的破壊」という言葉も用いられる。
「創造的破壊によって前進するという意味ですよね。マイナーチェンジではなくぺっしゃんこにすることで新しい価値観が進んでいくという。今は、情報というものによってあらゆる雛型が壊れ、これまであったものが通用しなくなったため、すべて新しくしていかなければならないという過渡期にいるんだと思います」
では、ジャーナリズムの社会の理想像はどこにあるか。
「いろいろ考えられますが、ひとつは、調査報道がもっと数多くできたらいいなということ。通信社と新聞社が役割分担して、通信社が速報を打ち、新聞社が分析を発信するという形も一つではないか、と。担当の枠組みで特ダネを競いあうなんて浅いし意味がなくなってきている。ウェブニュースなら出遅れても三十秒で追いつける。何新聞に抜かれたなどというコップの中の争いではなく、闇に埋もれている事実を調査して光を当てるのがジャーナリストの使命じゃないかと思います。それはもちろん、手間とお金がかかることですけれど。あとは、今はもう情報公開法は浸透してきていますけれど、公文書等の管理に関する法律は十年遅れてできている。ちゃんと公文書を残すということをもっと進めていかないと」
もちろん、個人の心掛けも大切だ。
「一人ひとりが自分なりのジャーナリズムを持つことが大事だと思います。というと硬く聞こえるかもしれませんが、人々が自分なりに情報の取捨選択をする、ということですよね。クリックする前に一呼吸するなど、情報に対して冷静になれたらいいですよね」
本作でも登場人物のみなが揺れ動く存在の中、信頼できるのは二本目の「共犯者」に登場する元新聞記者の相賀だ。コツコツと調査を続ける彼の姿は、後でも触れられる。
「相賀さんにはモデルがいます。元讀賣新聞記者の加藤譲さんという方で、"ミスター・グリコ森永事件"といわれた方ですね。もう七十歳近くですが、まだ取材を続けている。頭が下がります。そういう人物を書きたかったんです。ただ、相賀も、二本目の段階ではiPhoneが録音機になることも知らないし留守番電話を使いこなしていなかったために元同僚とすれ違ってしまう。でも最終話で出てきた時は最新のメディアにめちゃくちゃ詳しくなっている。その間に何があったのかを考えると、相賀の凄まじさが分かりますよね。いくつになっても学ぶ意志を持った、素敵な人です」
社会派であることを意識して
本作の各話のタイトルを見て「ゼロの影」から「ゼロの焦点」、「Dの微笑」から「Dの複合」など、松本清張作品を思い出した人もいるのではないか。
「影響を受けた短篇といえば、やっぱり松本清張なんですよね。短い中に悪意や疑心暗鬼にかられる人間の姿が描かれ、社会性もあり、なおかつ話が面白い。これらをすべて短篇で満たそうと思うと相当難しい。そうしたものを書きたいという気持ちもあり、意識してタイトルをつけました。実は僕にとって短篇ってハードルが高いんです。今回も一篇を書くのに二~三か月かかりました。でもその分、分解した時にピースの数が多いと思います」
また新たな挑戦を実現した塩田さん。現在は大泉洋さんをあて書きした『騙し絵の牙』が大泉さん主演で映画化の企画も進行中。
「『騙し絵の牙』のようなエンターテインメントのラインで新しいものを書きたいですし、『罪の声』『歪んだ波紋』に繋がる社会派も書いていきたい。ジャーナリズムは自分の大きなテーマでもあるんですが、今後は経済システムについて、自分なりの解釈で書いてみたいとも思っています」