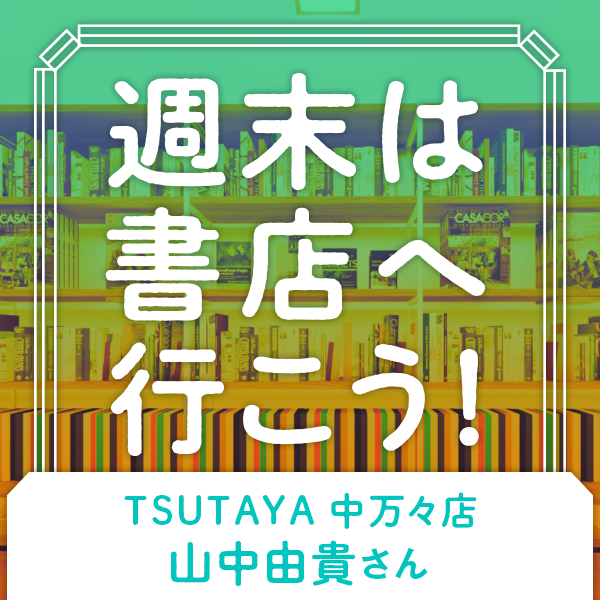藤谷 治さん『燃えよ、あんず』
うねりのある物語で読ませる作家、藤谷治さん。新作『燃えよ、あんず』は著者自身を彷彿させるオサムさんと、著者自身がかつて経営していたお店の客たちをめぐる物語。しかし自伝的作品ではなく、きっかけはまた別で……。
書店店主とある常連客の物語
「小説の中にいっぱい小説を詰め込む、ということをやってみたかったんです」
と、藤谷治さんは言う。新作『燃えよ、あんず』についてだ。
「それにはどうすればいいかということで、自分の持っている話から、久美ちゃんという人の話を引きずりだしました。誤解をおそれずに言えば、話はなんでもよかったんです。なぜなら、どんな小説でも、話がまわりはじめるとそこにいろんな人間が出てきているわけで、いろんな人間というのは、それぞれの事情をかかえていますよね。みんなが人生を引きずってここにいる。ここに五人の人間がいるとすれば、五個の事情がある。それを書けばいい。だから、どんなシチュエーションでもかまわなかったんです」
久美ちゃんというのは、藤谷治さんがかつて下北沢で経営していた書店〈フィクショネス〉の常連客のこと。そう、本作は実在した書店を舞台に、店主のオサムさんや妻の桃子さん、他の常連客たちが登場する。ただ、内容はまったくのフィクションだ。
「久美ちゃんはほぼ実在の人物ですが、二十年くらい会っていません。でも新しい小説を書き始めようと思った時、あの子はどうしているかな、幸せになっているといいなと思ったんですよね」
取次を通さずに買い切りの形で選りすぐった書籍を並べていた小さな書店〈フィクショネス〉。文学教室などイベントも開き、そこによく参加していた客の一人が、まだ二十代前半の久美ちゃんだ。彼女は結婚するが、事故で夫を亡くしてしまう。周囲が心配するなか、夫の家族と親しかった彼女は、彼らと一緒に暮らすと言って奈良へと越していく。
それから数十年。ある日、ふらりと久美ちゃんが店に顔を出す。彼女を連れてきたのは、常連客の一人、由良だ。陰気な美青年だった彼と久美ちゃんが一緒にいるのは意外だが、彼女は彼の紹介で職を見つけ、東京に戻ってきたというのだ。
「何が久美ちゃんにとっての幸せか、それは他人が決められることではないですよね。ただ、本人は明るく楽しく過ごしているつもりでも、実は哀しみの中に閉じこもっているという状態であるなら、そこからもう一歩先があるんじゃないかという思いがありました」
各章には、オサムさんの視点を通して見たその後の久美ちゃんをめぐる物語のほかに、由良の手記であったり、久美ちゃんの新たな恋物語であったりと、異なる"小説"が挿入されていく。その由良の手記のなかで、彼が久美ちゃんを呼び戻したのは善意ではなく、悪意めいた気持ちがあったことが明かされる。彼には、人が傷つく姿を見たいという欲求があり、わざわざ久美ちゃんに職を紹介したのも興味本位なところがある。
「僕のなかにも、由良のような奴がいる。僕のなかにこういう奴がいなかったら、僕は小説を書いていないと思う。人を操るのは不愉快だし、不幸になる姿を見るなんて耐えられない。でも、それなしでは生きられない。そんな濁った血が、いつも自分の身体の中をめぐっている気がする。それが、小説を書くことと関係がある気がします。本当はそういう自分を隠してニコニコと穏やかにしていたい。でもそうはいかない。本当に不思議ですよ」
ただし由良が職を紹介したことは、結果的に久美ちゃんを前向きな気持ちにさせている。善意の行動が芳しくない結果を招くことだってあるのが現実なのに、なんとも皮肉でコミカル。
「五十年以上生きてきて思うのは、人生とか人間って、ものすごく長いレンジで見たら勧善懲悪だということ。うまく説明できないんですけれど、人を蹴落としてのしあがった奴や、人の不幸が好きという奴は、知らないうちに消えているんですよ。だから、もしそういう人間が現れたとしても、それは一時的なノイズにすぎない。情けない言い方になるけれど"愛は勝つ"なんですよ(笑)。それは人間関係だけの話ではなくて、一人の人間の中でも言えることかもしれない。人は長いレンジで見ると、いい人になっていく。ただそうなった時に、かつて自分が取り返しのつかないことをした過去を思い出して、そこから苦しみが始まる。由良も、この先苦しむことになるでしょうね。だから、人はそもそも他人を嫌な気持ちにさせないほうがいいんですよ」
久美ちゃんがその後の人生をどう辿るか、何が起きるかはざっくりとは考えていたというが、
「書く前に一応、見取り図は書いていたんです。でも書き始めたら、自分を制御できるもんじゃない。しかも僕、これを執筆中に入院したこともあって、どうにも調子が出なかったんです。無理に書いても出来が悪い。焦点を合わせていくのに時間がかかりました」

この人に幸せになってほしい、と願う気持ち
久美ちゃんは明るく心優しいが、時にマイペースで事務作業が苦手。そんな彼女にも、やがて新たな出会いが訪れ、恋が育まれていく。しかし、そこで大きな問題が勃発。オサムさんや桃子さんはもちろん、店の常連客のピンキーやキタノも気にかけ、一肌脱ごうとする。ピンキーは大麻を密売している疑いがあるし、キタノは自分はロリコンだと広言するなど、なんだか癖のある連中だが、オサムさんや桃子さんを含め、みな心根は良い。
「彼らも自分では気づいていないし、あまりにダイレクトすぎて小説には直接書きませんでしたが、彼らは共通の気持ちを持っているんです。それは、自分にとって何の縁もない人だけれど、久美ちゃんを幸せにしたら自分も幸せになる、という気持ち。ゲン担ぎのような、理屈にならない気持ちです」
そうした気持ちは自分の中にもある、とも。
「たとえばランチを食べに行く時に『ビッグイシュー』を売っているホームレスを見かけたら、その人の前を素通りして贅沢なお店でお昼を食べることができない。素通りせずに一冊買って、ランチはちょっと安いものにしたとしても、できることをやったと満足できる。そんな気持ちは、実はみんなの中にあるんじゃないかと思うんです。それと同じで、みんな久美ちゃんの前を素通りできない。ただ、彼女のためなら何でもしてやろうと思っているのは桃子さんだけ。オサムさんはちょっと面倒くさがっている。キタノやピンキーは半分以上、面白がっているところがある」
だが、久美ちゃんが危機に直面した時、また由良が彼女の人生に顔を見せ、ある行動を起こす。そこから大騒動が展開していくことに。事の次第がオサムさんの語り口調で時にユーモラスに語られていくが、このオサムさん、ご自身を投影しているためか、愚痴っぽかったり、車のナビゲーションが下手だったりと、少々自虐的に書いているようにも思え、なんだか微笑ましい。
「人のために何かしてあげてるように見せて、いい人に思われるなんて本当に恥ずかしい!」
と言うのだから、やっぱりオサムさんは治さんなのだ。一方、桃子さんは相当な人格者。終盤、周囲の怒りを一瞬で鎮火させるような言葉を言う場面が素敵だ。
「普段はプリプリしていても、意外な瞬間にふわっと人を許して全部を受け入れてしまう人っていますよね。理詰めで全体的に考えた時に、断罪されてしかるべきという相手に対して、羽根布団でくるむようなことを言う人。人間の中には、そういう面もあるんですよ」
個性の強い人々が入り乱れて、なんともにぎやかに騒動の顛末が語られ、連載時のタイトルが『ぽんこつたち』だったのも納得。
「僕は単行本にする際もそのままのタイトルにするつもりでしたが、担当者に替えたほうがいいと言われて。悩んでいた頃に室生犀星の詩集を読み返していたら、このフレーズに出合ってしまって。それで、小説内にもこの詩が出てくるように、書き加えたんです」
がらりとテイストが変わって物語がぐっと締まるのは、最後の数十ページだ。そこで語られるのは、ある脇役の半生。
「当初は最後ではなく、物語の途中に挿入していたんです。でも当時の担当編集者が、"この部分は最後に載せましょう"と言ったんですよ」
というから編集者の慧眼、おそるべし。この部分があるからこそ、久美ちゃんはもちろん、ほかの人間全員にも、ひとつひとつの大切な人生があるのだと、最後の最後で実感させられる。
「一人一人が世界を背負っている、ということは、僕は大きなメッセージとして持っています。この部分の中心人物も"自分は世界を背負っている"と言いますが、これは『リア王』を上演する舞台のバックステージを描いた『ドレッサー』という芝居を意識したもの。三十年くらい前かな、三國連太郎と柄本明で三越劇場でその芝居を上演したことがあって。三國が演じるのはもう老いているけれどプライドだけは高い男。彼が『うるさい、俺はこれから全世界を背負って歩かなきゃならんのだ、このいまいましい全世界をな!』と言った記憶がある。それが耳に残っていて、この台詞を僕なりに解釈して作中に書きました。いろんな人間が、一人一人、世界を背負って歩いている。それを背負わないでいる奴は卑怯でずるいと思う」
大事なのは結末に至る過程
小説の中にさまざまな小説が組み込まれ、世界の複雑さを見せてくれる本作。藤谷さんが九月に刊行した『小説は君のためにある』は、若い人へ向けた文学案内。そのなかには、〈小説にとって、あらすじなんかどうだっていいのだ〉〈大事なのは結末に至る過程である……といえば平凡だけれど、実際そうだ。〉という言葉がある。
「たとえば推理小説だったら、事件が起こって最後に犯人が分かるというあらすじだってことは読む前から分かる。それでも人が新しい推理小説が出たらまた読むのは、そのあらすじでは説明できない趣向がいろいろあるから。その趣向こそ小説ですよ、と言いたいんです。『燃えよ、あんず』も、読者は久美ちゃんは最後にどうなるの? とは思うかもしれない。でもそこを重要と思わせないためにいろいろ工夫をしているんです。結末だけ分かればいい、という小説にはしていないはずなんです」
いってみれば、小説について書いたものとして、『小説は君のためにある』は理論篇、『燃えよ、あんず』は実践篇、と藤谷さん。
「今回『燃えよ、あんず』を書いて、小説というものが持っている特質と役割を僕自身が実感できたと思います」